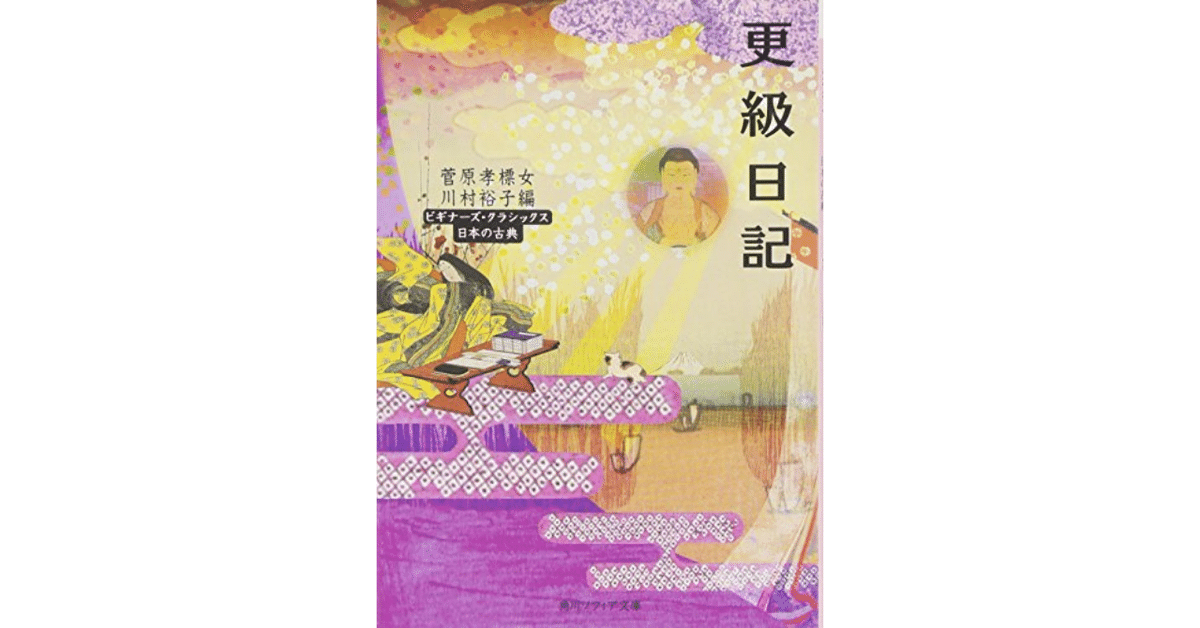
さらさらとエッセイを書く娘の日記
『更級日記 ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 』菅原孝標女 (著), 川村 裕子 (編集)(角川ソフィア文庫 86 ビギナーズ・クラシックス)
夢見る少女が大人になる。平安時代に生きた女性の一生。古典入門の決定版!
平安時代の女性の日記。父の任地である東国で育った作者は京に上り、ようやく手に入れた憧れの物語を読みふけった。女房として宮家へ出仕するものの、すぐに引退し結婚。夫は包容力も財力もある人だったが、20年に満たない結婚生活ののち、死別。その後は訪れる人もまれな寂しい生活を過ごす。13歳から40年におよぶ日記に描かれた、思いこがれた生活をついに手にすることのなかった一生が、今の世にも胸に迫る。
古典の日記文学はいろいろ見てきたが一番面白い日記ではないのかな。それは宮廷女官日記のようにお高くもないし、面倒な恋バナもなく、ごく中流(と言っても歌人としては一流の人だが)の千年前の『源氏物語』好き少女日記からお詣り(現世利益)より物語(空想物語)という旅日記へ、さらに結婚して宮中勤めかと思うとロマンスめいた出合いもあったけど主婦に目覚めたところで夫との別れ。そこから心を入れ替えて神仏に祈る日々。
「更科」というのは「姥捨山」のことで夫が亡くなった場所の名前だった(更科蕎麦の長野地方)。仏の願いよりも空想少女だったのが晩年は寺社巡りオバサンへというのが面白い。日記というが起伏に富んでいる物語風。翻訳も今風なアニメキャラ的な感じ。
塚本邦雄が当代きっての歌人というイメージで語っていた。菅原道真の五代目の娘であり、叔母が『蜻蛉日記』の藤原道長の母で勅撰和歌集にも載るぐらいの超有名歌人だが、そんなイメージは見事に裏切られた(一般的な夢見る少女から普通のオバサンへというパターン)。
それもエッセイの文才は清少納言に匹敵するのではないか。読ませどころがいろいろある。薬師如来像を作って、物語を読めますようにと祈ったり、その後は神仏よりも物語ばかり言っていた少女がオバサンになると180度変化していくのも面白い。
