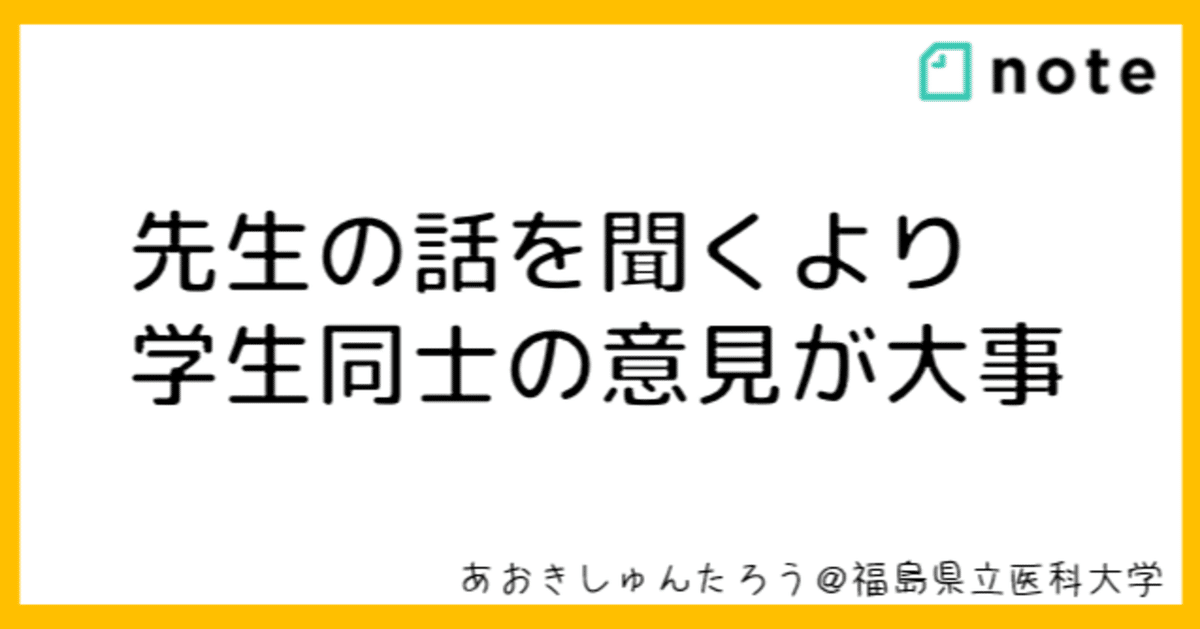
仲間の意見を聞くほうが、講師から教えられるよりもいいかもという話ーピア・インストラクションー
仲間の意見を聞くスタイルの学習のほうが、講師から話を聞くスタイルよりも学習効率がいいよというお話をします。
どもです、福島県立医科大学で医学教育にたずさわっていますあおきしゅんたろうです。
先日の記事では、「仲間とともに取り組む効果」について書かせていただきましたが、ディスカッションベースで、役割分担して、お互いに教えあいましょうという内容でしたね。
今日のテーマは同じように仲間同士の学習方法である「ピア・インストラクション」について解説します(参考文献はこちら)。
協働学習と同じように、仲間と学びあう方法ではあるのですが、こちらは「仲間の意見を聞くこと」が中心的な要素です。
ピア・インストラクションとは?

一般的なレクチャーですと、
講師 → 聴衆
という1方向設計なのですが、ピア・インストラクションは
講師 → (聴衆 ⇔ 聴衆)
というインタラクションを設計します。
講演会や授業って講師が話しまくるスタイルが一般的じゃないですか。そこの発想を180度転換します。
具体的に言うと、とあるテーマで講演をするときに、講師が話すんじゃなくて、聴衆に話を振りましょう。
例えば、餃子がテーマの講習だとすると
餃子は食べたことがありますか?(アンケート式の質問)
餃子のどんなところが好きですか?(コメントを求める質問)
を投げかけます。そして聴衆がアンケートや質問に答えるとともに、アンケート結果や回答をいっしょにみていきます。場合によっては、講師がコメントをしていきます。
そのあとで、聴衆同士のディスカッションをはさんで、さらに内容を深めていく場合もあります。あるいは、講師がさらに踏み込んで解説していく場合もあります。
みなさんももうすでに回答頂いた内容なので補足説明ですが、餃子の魅力は・・・・という感じで展開していくといいでしょう。
ピア・インストラクションのメリット
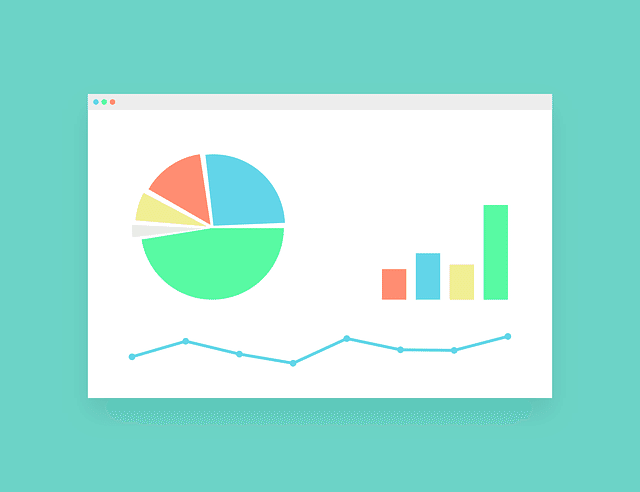
なぜこのような設計にするのか?というと、聴衆は、講師よりも聴衆同士のほうが親しみやすく、アドバイスをしてくれると認識しているためです。
講師と聴衆は立場も違えば年齢も違うことが多いのですが、聴衆同士だとそれが近くなります。たとえ話を聞くときも、じぶんから近い人の意見や考えを聞くほうが頭に入ってきやすいのです。
ピア・インストラクションをすることで、学習内容を深く理解することができるため、学習効果があがります。
協働学習と違って、グループを作る必要がないので、仲間同士のインストラクションを使いつつ、大規模な講演会や授業でも利用することができます。
ピア・インストラクションの準備
当初はクリッカーというPCにつなぐ機械を使って投票を行っていました。
最近では投票の閲覧は、いろいろなものが使えますよね。わたしは有料ではありますがMentimeterという機能を使わせていただいています。
ZOOMやTeamsなんかにも投票機能が付いていますので、そういう媒体を使うことも良いかもしれません。
あとは原始的な方法ですが挙手や色付きの紙をあげてもらう方法なんかも使えると思います。

いかがだったでしょうか?講演や授業がうまくいかないなというときに、結構な場合、講師の人が話しまくってしまうということがあると思います。
要所要所でいいので、ピア・インストラクションの発想を取り入れて、楽しめる研修会を設計してみませんか?
最後まで読んでいただいてありがとうございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
筆者 あおきしゅんたろうは福島県立医科大学で大学教員をしています。大学では医療コミュニケーションについての医学教育を担当しており、臨床心理士・公認心理師として認知行動療法を専門に活動しています。この記事は、所属機関を代表する意見ではなく、あくまで僕自身の考えや研究エビデンスを基に書いています。
そのほかのあおきの発する情報はこちらから、興味がある方はぜひご覧くださいませ。
Twitter @airibugfri note以外のあおき発信情報について更新してます。
Instagram @aokishuntaro あおきのメンタルヘルスの保ち方を紹介します(福島暮らしをたまーに紹介してます)。
YouTube ばっちこい心理学 心理学おたくの岩野とあおきがみなさんにわかりやすく心理学とメンタルヘルスについてのお話を伝えてます。
