
発達障害でも、独学で資格試験に一発合格する方法
【この記事は、約7分で読めます】
※ 本記事は発達障害当事者のみならず、資格試験を目指す社会人、そして受験や定期テストを控える学生も対象としています。
まずは、こちらをご覧ください。

先日、僕は情報セキュリティマネジメント試験に合格しました。
手前味噌ですが、見事過去こちらで公約した約束を果たしたわけです。
この試験は、国家試験です。
すなわち、国から認められた試験であります。
そして、僕はこの試験を独学で一発合格しました。
僕は社会人になってから数々の資格試験を受けてきましたが、その全てを独学で勉強し9割の勝率で一発合格しました。
費用をかけたと言えば、過去問・必要最低限のテキスト・試験代と試験会場までの交通費だけです。
実際今回の勉強も、受験料を合わせても1万円以下しか支払っていません。
なぜ少額の投資で、一発合格が実現できるのでしょう?
しかも僕、ハンデ持ちですよ(笑)
今回の記事では、発達障害であっても最小限の投資で最大の効果を上げて合格に導く方法をお教えします。
そしてこの方法は資格試験のみならず、学校のテストや人生を左右する受験にも応用が可能です。
どうぞ最後までお読みいただき、あなたの学びに活用できれば嬉しいです。
1.独学で資格試験に一発合格するための考え方
①音読を繰り返す
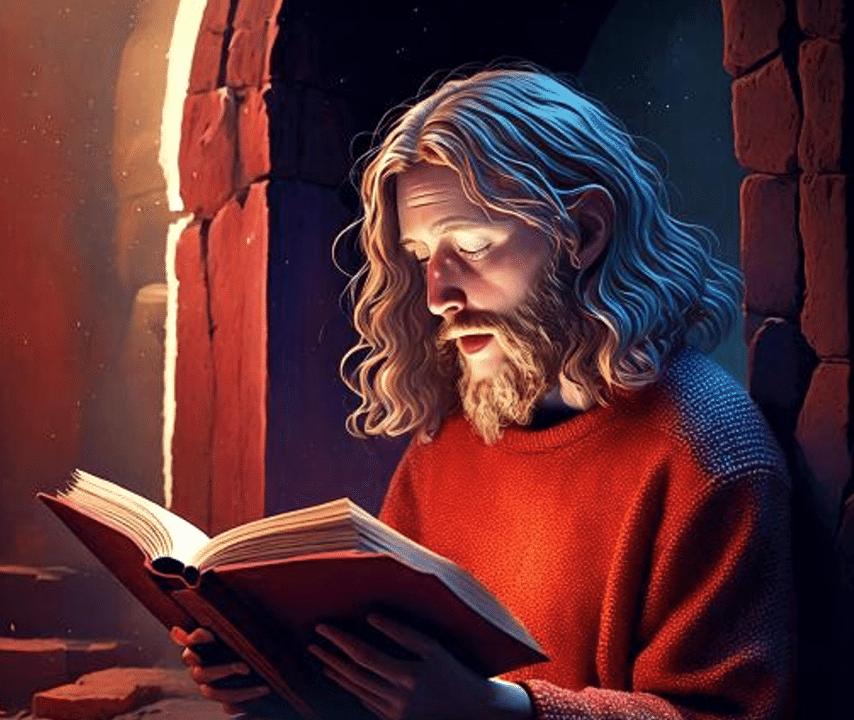
勉強をする上でまず大切なのは、音読を繰り返すことです。
なぜなら、音読によって「読む」「聞く」というインプットに加え「話す」「書く」というアウトプットが同時に実現できるからです。
大抵の方々は、「読む」「聞く」については日ごろ実践していると思います。
参考書やテキストを「読む」のは当たり前のようにやっているでしょう。
通勤・通学の行き帰りにYouTubeやポッドキャストなど通じて、「聞く」のも実践している方は実践しているかもしれません。
しかし、その先の「話す」「書く」についてはどうでしょうか。
参考書、声に出して読んでますか?
YouTubeやポッドキャストで聞いた内容、声に出してノートなりメモ帳なりに写してますか?
厳しい言い方ですが、ここで「話す」「書く」のアウトプットができないのであれば、あなたは合格への道が遠のくでしょう。
しかし、アウトプットを行えば学んだ内容が思い出せます。
同時に、記憶として定着できるまでの時間も半減できます。
これは、司法書士試験に一発合格し現在は試験講師として活躍されている松本雅典氏の言葉からも、明白です。
たとえば、資格試験の勉強をする場合、知識をいくら頭に詰め込んだところで、本番の試験で実際に思い出せないかぎり、点数はとれません。それゆえ、勉強では「思い出す機会を多く設ける」ことが重要なのだそう。
思い出す機会を多くつくるには、試験勉強をする人であれば「問題を解く」ことが適しているでしょう。試験とは関係なく、単に本を読んで勉強するだけの人なら、「思い出しながら紙に書き出す」「声に出しながら思い出す」など。さまざまなやり方で、アウトプットの機会は設けられるのです。
せっかく勉強に与えられる時間があるのなら、限られた中で最大の効果を上げたいでしょう。
ましてや社会人は学生と違い、働いている分勉強に充てる自由な時間も確保できません。
だから最小の時間で最大の効果を上げるべく、「音読」が重要になるのです。
※ 音読の重要性については、前回記事もご覧下さい。
音読は、勉強に限らず普段の仕事でもあなたの能力を最も引き出すのに重要です。
事実、その結果として僕は障害者雇用でも正社員に登用され6年以上勤務でき、資格試験も一発合格を達成しているのですから。
音読は効果が出るまで、時間はかかります。
しかし、効果が出てからは加速度が上がります。
ぜひとも、音読を継続しましょう。
②「読む」「聞く」「書く」「話す」の4つの車輪を回す

次に大切なのは、「読む」「聞く」「書く」「話す」の4つの車輪を常日頃意識して回す心がけです。
なぜなら、インプットとアウトプットを繰り返せばあなたの知識や理解の定着が早まるからです。
ここに、1台の車があるとします。
車は車輪が4つあって、かつ4つともまんべんなく回ることで前進します。
どれか一つ欠けても、偏って回しても車は進めません(三輪車は置いといて)。
つまり、4つのバランスを保てば学習速度が上がるのです。
今回の試験で言うと、それぞれの車輪は次のように例えられます。
ちなみにオンライン講座は、本試験を想定したものです(会社費用で捻出していただいたのは、助かったです)。
読む(インプット):オンライン講座でのテキストや用語集
聞く(インプット):オンライン講座の動画、過去問聞き流しのYouTube動画
書く(アウトプット):オンライン講座の動画をパソコンのメモ帳で要約
話す(アウトプット):テキスト・過去問の音読
勉強の際は、常にこれら4つの車輪をまんべんなく回しているかを意識して取り組みましょう。
スランプに陥ったり成績が伸びない時は、どこかの車輪が回っていない可能性があります。
③過去問は、最良の参考書である

どんな他の参考書よりも優れたテキストは、過去問に他なりません。
なぜなら、過去問は試験の傾向や頻出される問題などの分析ができるからです。
いわば、過去問が「こういう問題が本番に出てくるから、お前らしっかり対策しとけよ」とタネ明かしをしているのです。
これ以上、合格に直結した参考書はないでしょう。
過去問研究の重要性は、個別指導で多くの大学合格実績がある東京個別指導学院さんのコメントからも、明白です。
入試過去問題を解く目的は、受験校でどのような問題が出題されるかを知り、合格点までの距離(得点差)を知り、合格するために必要な課題をあぶり出して、演習を行い、合格点をとれるようにして、受験校に合格することです。
僕は、どんな試験でも勉強する前にまず最新の過去問を入手し、出題分析に当たります。
この項目でどれだけの時間をかけるか?
問題はどういう構成をしていて、出題者は何を意図して受験生に問いているのか?
どれまでの情報までインプット・アウトプットすれば良いのか?
その上で、計画を立てて勉強を始めます。
過去問は最低でも3年、最高で5年分は入手します。
3年未満では情報量が足らず、6年以上では出題者も代わって試験自体の質も変わるからです。
また、本番想定問題は絶対に解きません。
なぜなら、想定問題は本試験の出題者が作っているわけではなく、傾向や頻出問題の見極めを誤るからです。
これは資格試験を目指す人のみならず、受験生に向けてこそ声を大にして主張したいですね。
※ 話はそれますが、僕は受験生の方に間違っても大手予備校が出版している「共通テスト 予想問題集」のような本には目にすら触れて欲しくないと考えてます。
試験の作成者が、全国から派遣された大学教員なのか予備校講師なのかでは、試験の質に違いが生じるのは少し考えれば一目瞭然でしょう。
仕事でもスポーツでもゲームでも何でも、勝負に勝つためにはまず相手の戦略を知る。
戦略とはつまり、「情報」であり「知力」です。
より一つでも多く戦略を知るため、過去問研究を怠らないようにしましょう。
2.一発合格への具体的行動
①試験日までの戦略計画を立てる

まず、あなたが受けたい試験を具体的に、いつ受けるのかを決めるのが始まりです。
なぜなら、初めにゴールを決めればゴールから逆算して試験という「本番」までの戦略が立てられるからです。
特にこれは、社会人である方に留意していただきたい点です。
受験や学校のテストであれば、開催日から逆算して計画も立てやすいでしょう。
また僕が今回受けた情報セキュリティマネジメントのような月単位で開催されている試験は、「〇か月後に受験」と先にゴールを決めるのです。
その後、本番までのプランを立てます。
僕は今回の資格は9月の受験に向け、5月から進めました。
最初の2カ月は、オンライン研修で学んだ知識のインプット・アウトプット。
次の1カ月半は、過去問ネットからランダムに過去問を解く。
そして、最後の2週間で総仕上げに冊子の過去問を解くことですね。
ちなみに僕は、過去問研究にこちらのサイトを活用しました。
通勤の行き帰りや会社の昼休みに、他の選択肢が並んでいる理由も分析しながら解いていきました。
また、総仕上げはこの本を解きました。
こうした計画に忠実通りに従い、僕は試験に一発合格を達成したのです。
ゴールを初めに設定し、ゴールから逆算して計画を立てる。
これは試験のみならず仕事でも同じで、社会で活躍するのに必要なスキルなのです。
②スキマ時間を、捻出する

次に、スキマ時間を捻出し、その時間を試験勉強に充てることです。
なぜなら、こうした10分20分の些細な時間が試験の合否を大きく左右するからです。
また時間に限りがあるので、「覚えなきゃ!」「理解しなきゃ!」とメリハリもつきます。
あなたが自由に時間を使えるのは、いつでしょうか?
通勤・通学の移動中。
バスや電車が来るまでの待ち時間。
会社や学校の昼休み。
etc…
その間、あなたが何をして時間を過ごしているかを洗い出し、その時間を試験時間に変えるのです。
社会人の方にありがちですが、人は「時間がない」とついつい試験日を引き延ばしたり勉強時間を削ったりする傾向にあります。
僕からしたら、普段の仕事なら時間管理できてるのに、どうして勉強になったらできないのか不思議でたまりません。
苦言を呈せば、それはメタボの方が適切に体重管理してないのと同等なほど、自分に甘いと言わざるを得ません。
通勤の移動や休みの日に早起きなど、時間の捻出はいくらでもできます。
なぜ、それができないのでしょう?
僕はスキマ時間のおかげで、TOEIC830点も英検準一級一発合格も達成しました。
そうした時間の使い方を工夫して音読を継続すれば必ず身に着くのに、本当にもったいない。
スキマ時間を作る、勉強に充てる。
こうした積み重ねが、試験合格に近づいてくるのです。
③手元にいつも辞書を置く

分からない単語や専門用語があれば、すぐに辞書を引きます。
なぜなら辞書を引く習慣は、あなたが自ら問題を見つけ、調べて自分の意見を持つという能動的に学ぶ力が鍛えられるからです。
現代でしたら、ネットでググればいくらでも単語はものの1分で調べられます。
ちょっとでもひっかかる・分からない単語があったら、すぐに調べましょう。
ちなみに、僕は情報セキュリティマネジメント試験の勉強中、このサイトをよく利用してました。
https://wa3.i-3-i.info/index.html(「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典」)
※ 埋め込みが上手くいかず、文字直貼りで申し訳ありません。
そして、ネットに頼る以上に紙の辞書を推奨します。
なぜなら、調べる時間を敢えてかければ引く過程の中でも学び、使いこむ達成感が得られるからです。
これは、進研ゼミやこどもチャレンジで有名なベネッセでも、実証されている内容です。
僕は仕事でも、分からない言葉が出てきたらすぐ調べられるよう常にオンライン辞書サイトを表示させたままにしています。
さらに家では、紙の英英辞典と国語辞書を使っています。
紙の辞書を使えば周辺の言葉も目に入るし、単語の仲間も一覧できて一石二鳥だからです。
辞書をいつでもどこでも、引く習慣をつけましょう。
疑問に思い調べる姿勢は、仕事でも能動的な態度を示すのに重要な姿勢です。
④試験1週間前に、本番の予行練習を行う

そして、試験1週間前は本番を想定した環境で予行練習をします。
なぜなら、本番環境をシミュレーションできれば試験当日に落ち着いて問題に取り組めるからです。
僕は今回の試験で、次のようにシミュレーションしました。
過去問を購入し、試験と同じ時間で解く。
図書館の学習室(ブース付きなら尚良し)に向かう。
当日試験を受けるのと全く同じ行動をとる。
「1」によって、解くべき問題・捨て問の見極めや集中力をかけるメリハリの判断を見極めます。
「2」によって、移動時間中にやることの整理をつけます(メンタルのコンディション安定・どの分野を復習するかなど)。
可能であれば、会場の雰囲気や土地勘を身に着けるため、当日の試験会場に近い図書館が望ましいです。
そして「3」によって、本番でも練習と同じように行動すればOKなんだという自信がつきます。
具体的僕の場合は、次のようなものです。
本番に必要な持ち物(筆記用具・受験票・免許証など)を用意して出発する。
電車の移動中に、ポッドキャストを聞き流して出題内容の最終確認を行う。
必要な持ち物を会場の机上でどこに置くかを決めて、本番も同じようにセッティングする。
気合を入れるため、試験会場に入る前UCCのブラック缶コーヒーを買って一気に飲み干す。
このように「決まった所作」を行えば、心に余裕が生まれます。
万が一想定外の問題が出たとしても「ここまで手順通りにやってきた、だから他の解ける問題を先にをやって後回しにしよう」といった対処が可能になります。
練習は、本番のように。
本番は、練習のように。
予行練習をして、本番はゆとりを持って試験に臨みましょう。
まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以上で、試験に一発合格するための考え方と具体的行動をお伝えしました。
多くの社会人は「資格を取ったところで実務が伴っていなけりゃ意味がない」と資格を取得すること自体を軽視しています。
確かに実務が伴ってなければ成果が証明できないし、面接でのアピールにもなりません。
しかし、取得できる人間にはきちんと合格までの戦略を練り、行動を起こしています。
それは仕事においても、タイムマネジメントや優先順位の判断にもリンクしてきます。
実は、今回の記事だけではとてもお伝えできる情報量が足りません。
他の資格試験でも一発合格できた具体的行動、詳細な過去問研究方法など、まだまだ伝えたいことは盛りだくさんです。
試験シリーズは今後も、継続して発信してまいります。
どうぞ楽しみに待ってくださいね。
この記事をきっかけに、あなたが試験に合格し自ら将来の可能性を広げ人生を切り拓くヒントとなりますように。
いいなと思ったら応援しよう!

