
Baby, Its Embodiment and Identification
思い返してみれば、娘を産んでから最初の1ヶ月はとても大変で、しんどくて、それでいて特別な、不思議な1ヶ月だった。
こう書いてみてまず、「娘を産んでから」なんて言葉づかいをするようになったのも最近のことだな、とふと思った。あのときにはまだ「娘」とか「子どもを産んだ」とかそういう物言いさえ自分に馴染まなくて、むずがゆかった。
なんというか、出産というイベントは人生を大きく分断したように感じる。
「それまでの日々」と「それからの日々」。
現実の実物の赤ちゃんをこの手で育てる日々は紛れもなく、お腹の中で育てていた日々との連続の上にあるはずなのに、なにかが決定的に変わった。
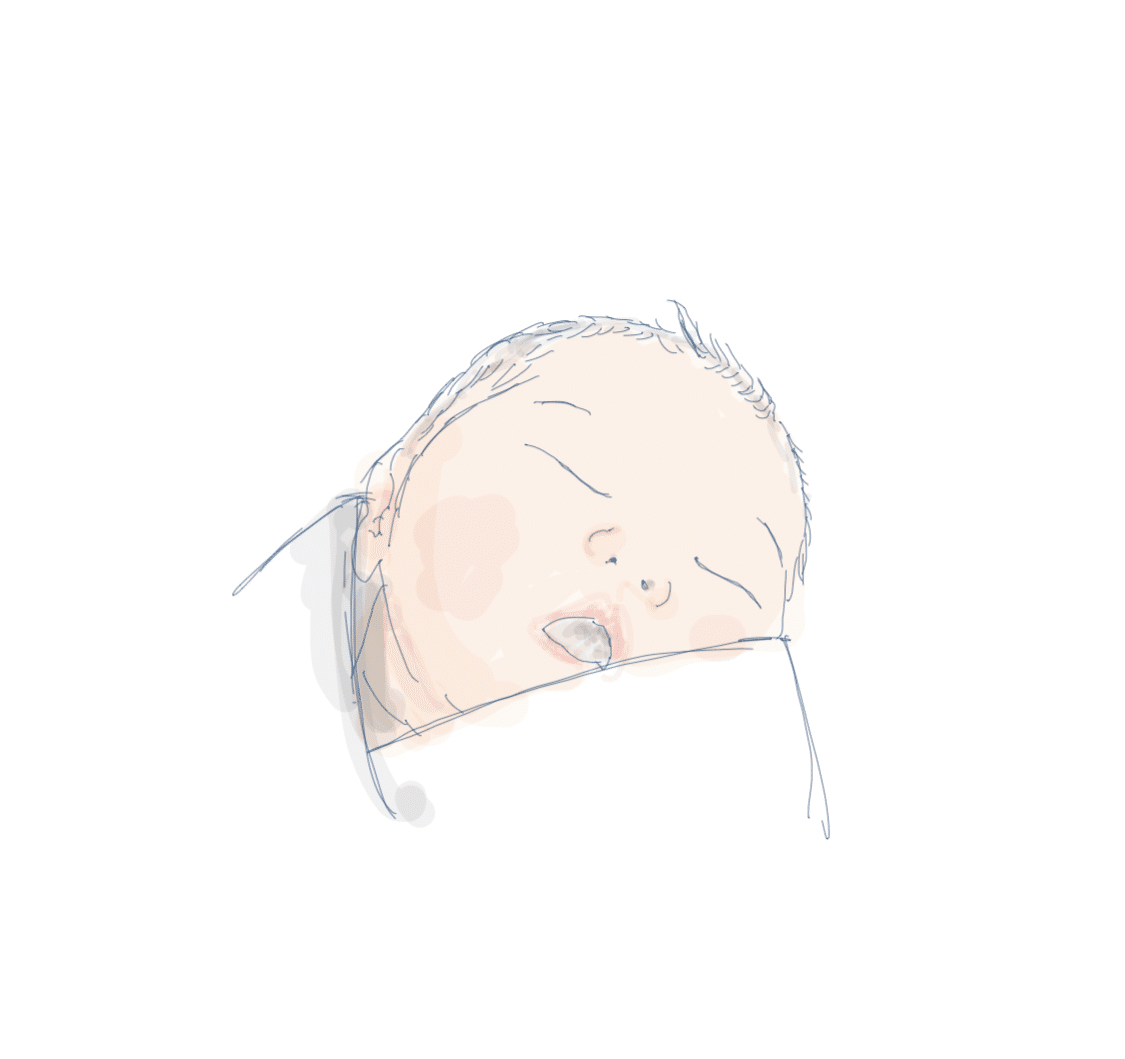
「それまでの日々」の中にいたときは、その日はいつ訪れるかわからない出産の日として認識されていた。対して「それからの日々」にいる今は、その日は娘を産んだ日であり、娘の誕生日となった。
うまくいえないけれど、出産の日と娘を産んだ日というのは、全く同じことを意味している全く同じ日を指すにもかかわらず、心象としては大きな隔たりがあるのだ。
「それまでの日々」においては、日に日に大きくなるお腹や、その中でモゾモゾ動く生命体が、確かに自分も赤ちゃんをもつ身なのだと教えてくれる現実的な証拠としてあった。だけど赤ちゃんがいるというのはどこか夢のようでふわふわと浮世離れしていた。
そういう感覚の中では、出産予定日とか実際の出産日というのは、どこまでも機械的な意味しか持ちえない。
女として、小さい頃から嫌というほど出産の痛みを脅され続けてきたわけで、噂に聞く恐怖の出産に自分もこれから立ち向かわなければならないという、そのXデーこそが出産というものだった。
それが、実際にXデーを迎えて出産を終えてみたらどうだろう。
Xデーまでのさまざまな日々のドラマも、心の機微も、全部全部セピア色に変わってまるで遠い昔のことのようだ。今と断絶した遠い昔。
喉元過ぎれば熱さ忘れるという諺がこれほどまでしっくりきたことはない。
そうでもしなければ、人は二人目三人目の子どもを産むことができないからだろうか。そうとしか思えない。
あれほど日常になっていた妊娠中のしんどさも、私なりに壮絶だった分娩体験も、どれも語りたいはずなのに、それ以上に強烈な印象を放つ日々が突如としてスタートした。
今や現実に人格を持ったミニチュアの人間がそこにいるのだ。
これまで想像するしかできなかった・・・いや、想像しようとしてもできなかった、自分のお腹の中にいた赤ちゃんの顔かたちと表情。壊れそうなほど小さな手足の指先。オギャーと泣く声。実体がなくまるで架空の存在だったその生命体が、人格を持った一人の人間として現実に体現された。

そしてその小さな小さな赤ちゃんと24時間片時も離れず、四苦八苦しながら一緒に過ごすうちに、その子の個性の輪郭が少しずつ少しずつ浮かび上がってきて、他の赤ちゃんと区別される、たった一人の我が子になっていったのだった。
娘が生まれた日、その病院はたまたま出産ラッシュで娘を含めて5人の赤ちゃんが生まれた。
同じ誕生日の5人の赤ちゃんは、男の子も女の子もみんな似たり寄ったりの顔立ちだった。赤ちゃんの連れ去りや間違い防止のために赤ちゃんの腕に「◯◯ベビー」と書かれたバンドが巻かれただけでなく(◯◯はママの名前)、足の裏にマジックペンで大きく名字が書かれていた。
つまりそれくらい、生まれてすぐの赤ちゃんは無個性だった。プロの助産師さんはもちろん、母親本人さえも我が子を他の子と区別するのは難しい。
だけど2ヶ月半経った今、私のお腹にいた赤ちゃんは「私の娘」と(まだどこかむずがゆさが残りながらも)それほど違和感なく口をつくようになった。それは他のどの赤ちゃんとも違う、人格のある一人の赤ちゃんになってきたからだ。
寝起きにふくれっ面をしながらうーんと伸びる仕草も、お地蔵さんのような顔をして泣きじゃくる顔も、少年漫画に出てきそうなギザギザの髪も、ご機嫌の時はくりくりキュルルンとした二重のきれいな瞳も、他の誰とも違う個性。

もしかして成長というのは、個性の輪郭が濃くなっていく過程を指すのだろうか。
その子の個性の片鱗を見つけるたびに、その子が他の誰でもない世界にたった一人の我が子だという証拠を見つけるようで、愛おしさが1つずつまた積み重なっていく。
