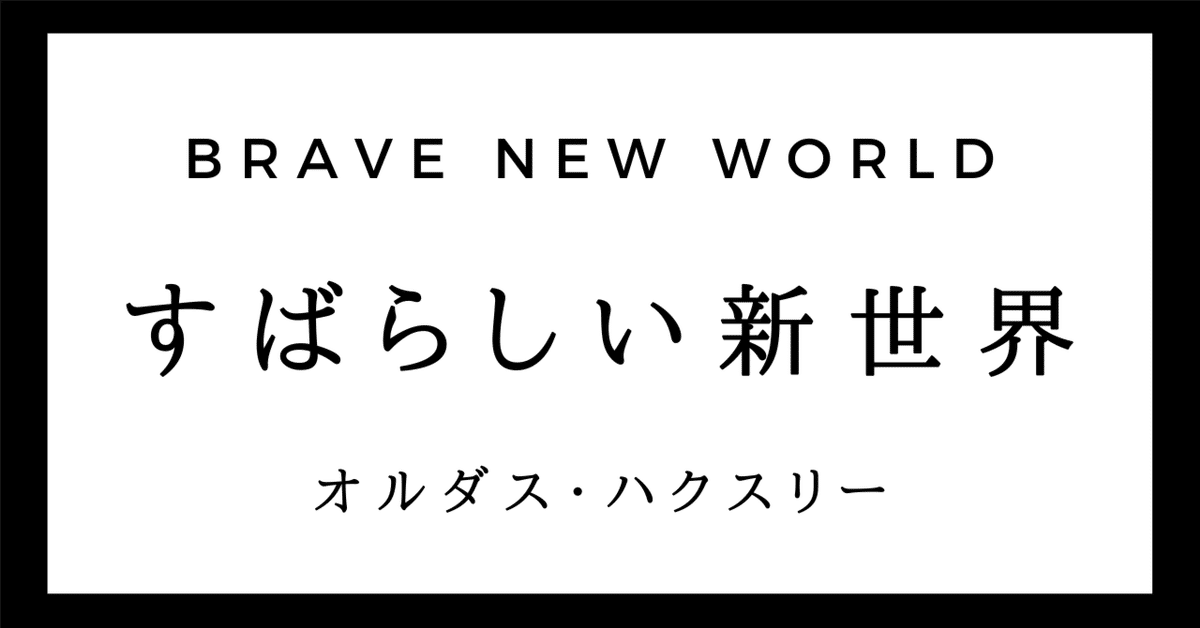
【小説】人間の終焉〜『すばらしい新世界』#7
「すばらしい新世界」(オルダス・ハクスリー/黒原敏行、光文社、2013)は、イギリスの作家オルダス・ハクスリー(1894~1963)が1932年に発表したディストピア小説です。原題「Brave New World」です。
出版から90年以上経った今でも、色褪せないディストピア小説の古典的名作となっています。
世界観
この世界はT型フォードが発売された西暦1908年を元年とするフォード紀元(AF)が使われ、フォードが神として崇められています。
AF141年(西暦2049年)の9年戦争を契機に、世界は破壊か統制かの選択を迫られ、当初は力による統制を行いましたが、各地で反発運動が起こり、最終的に、生化学的な条件づけによる統制へと世界は進みました。
そして、舞台はAF631年(西暦2540年)です。
この時代になると条件付けによる統制は、社会の隅々にまで行き渡り、「共同性(Community)、同一性(Identity)、安定性(Stability)」というモットーが徹底された社会となっています。
赤ちゃんは、母親から生まれるのではなく、科学的に管理された壜で、ボカノフスキー法と呼ばれる方法で効率よく多くの卵が孵化され、あらかじめ決められた社会階級(※上から順にアルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、エプシロンとなっている)に即した能力を持つように調整されます。思考も睡眠教育や刷り込みにより条件づけされ、その階級に即した(都合のいいい)考え方を持つようになります。
また、ソーマという多幸作用をもたらすドラッグを服用することで、不安や孤独というものを解消しており、誰もが幸せな社会が作られています。
あらすじ
「中央ロンドン孵化・条件づけセンター」に勤めているバーナードは、最も階級が高いアルファプラスにしては背が低く、壜に誤ってアルコールを入れられたため、発育不全になったのだと噂されていました。
ある日、バーナードはベータ階級のレーニナとのデートで、この文明社会と隔絶された野蛮人居留区へと旅行に出かけます。そこで二人は、もう文明社会には存在しないシェイクスピアを愛読している野蛮人のジョンと出会います。ジョンの生い立ちは、ロンドン(文明社会)からきた母親から生まれ、野蛮人居留区で育つという特殊なものでした。
そして、バーナードは、ジョンと母親をロンドンへ連れてきます。
ジョンはその珍しさからロンドンでの注目の的となり、様々なところへ引っ張りだこになりますが、同時に文明社会に対して違和感を感じはじめ、世界統括官のひとりのムスタファ・モンドと対峙するのでした。
見どころ
緻密な世界観
壜での出生、社会階級、ソーマといった幸福なドラッグといった社会システムやアイテムがうまく噛み合い、一見ユートピアな社会に住んでいると思わせるアイデアは、1932年に出版されたと思えない作品です。
ある一面から見たら、ユートピアで、まさに「すばらしい新世界」です。しかし、ある一面では、これほど人間性が失われた世界はないのではないでしょうか。
原題の「Brave New World」は、シェイクスピアの『テンペスト』のセリフからとられています。
テンペストの中では、人間性を賛美する意味で使われた「Brave New World」とこの作品のタイトルが対照的になって、私たちが讃えるべき世界とは何なのか、読者に突きつけているように感じます。
翻訳とはこういうことか!と思わせるレトリック
練り上げられた世界観の構成に一役を買っているのが、随所に散りばめられたレトリックです。
どこか聞いたことのある語感や、韻を踏んだ心地よさが、ストーリーに独特の世界観を印象付けます。
本文には何気なく登場するレトリックですが、原文では韻を踏んでいるところを翻訳にあたっては、どう翻訳するのかといった課題があります。
そういった翻訳の苦労や考え方が光文社古典文庫の訳者あとがきに記載されており、翻訳の苦労とプロの技を知ることができます。
例えば、以下のレトリックは原文の意味を壊さず、うまく日本語訳されているんだと感心します。
「うらむより一グラム」
(A gramme is better than a damn)
「個人の想いは社会の重荷」
(When the individual feels, the community reels)
海外小説を如何に日本人に伝えるか。ただ、翻訳しただけでは韻も踏めないし、その言葉から連想されるイメージが伝わらない。
海外小説は、翻訳者をみて買うのもありです。
世界統括官との白熱議論
この作品のハイライトは、野蛮人ジョンと世界統括官ムスタファ・モンドとの議論です。
ジョンは、愛読しているシェイクスピアを引用し、この社会の不自然さを説きますが、これがことごとくムスタファ・モンドから反論にあいます。読んでいる身としては、ジョンと同様に不自然さを感じているので、ジョンの主張と同じような考えになりますが、それが片っ端から否定されます。しかも、ムスタファ・モンドも全く古典文学に無理解な人間ではないです。逆にジョンよりも古典には詳しい始末です。
ムスタファ・モンドの反論には、隙がなく、これが本当に幸福な理想社会には思えないけど、無理矢理説得される。ある意味爽快なシーンです。
「快適さなんて欲しくない。欲しいのは神です。詩です。本物の危険です。自由です。美徳です。そして罪悪です。」
「要するにきみは」とムスタファ・モンドは言った。「不幸になる権利を要求しているわけだ」
「ああ、それでけっこう」ジョンは挑むように言った。「僕は不幸になる権利を要求しているんです」
ジョンの態度に多くの人は、共感するかと思います。そんな不自由な社会では、生きていけない。これはかりそめの幸福だ、と。
でも、ふと感じるのが、こう思っている自分が今の社会に満足しているから出る発言なのではないかという不安です。
本当に苦しんでいる人からしたら、不幸になる権利なんて欲しくない。と思うこともあるのではないのか。自由を求める自分の気持ちというのは、ある意味、特権階級的な考え方なのではないかと考えてしまいます。
単にこんな社会は嫌だねということで終わらせないSF(スペキュレイティブ・フィクション)の面白さが詰まった作品です。
