
綾辻行人『十角館の殺人』ワシントン・ポスト掲載レビュー
綾辻行人さんの代表作『十角館の殺人』の英訳版である The Decagon House Murders の出版を受けて、ワシントン・ポスト紙にレビューが掲載されました。それが2015年7月15日ということで、もう3年ほど前のことになるのですが、最近ふと思い立ち、探してみたところレビューの完訳が存在しなかった(あったらすみません)ので、訳してみることにしました。個人の趣味での翻訳なので、お読みになる際は、誤訳・文章の拙さをご理解いただいたうえで、あくまで参考程度にご覧ください。
なお、抄訳は講談社さんの特設ページ「綾辻行人の館」で読むことができます。
アガサ・クリスティを彷彿とさせる『十角館の殺人』
by マイケル・ディルダ
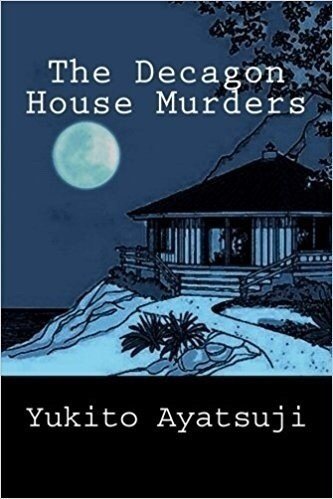
綾辻行人の『十角館の殺人』は、アガサ・クリスティあるいはジョン・ディクスン・カー流の、古典的なミスディレクションの作法に則った素晴らしいミステリだ。その魅力は、キャラクターの描写や、大都会での犯罪の描写にあるのではなく、とてつもなく複雑なプロットにある。読者は直感的あるいは感情的にではなく、知的にこの作品に向き合わねばならない。まるで手品を見ているときのように、我々は何が起こっているか、いかにして犯罪が為されたのか思いめぐらすのである。
村上春樹の作品群(それらは往々にして奇想天外であり、何かを発見する物語だ)を除けば、この作品は——恥ずかしながら——私が初めて読んだ、まとまった長さの日本のミステリということになる。とはいえこの作品は、いわゆる「本格」という活発な流派に属する作品なのだ。島田荘司が『十角館の殺人』の序文で書いているように、「本格」という用語は「オーソドックス」であること、「文学的なだけでなく、多かれ少なかれ、ゲームとしての側面を持つ探偵小説の形式に目を向けている」ことを意味する。島田は、ミステリ黄金時代の作家、S・S・ヴァン・ダインを引用しながら、「本格」は読者に「高度な論理的思考」を求める、とも書いている。
現代の日本のミステリを概説しよう。島田荘司は、フーダニットのフェア・プレイに準じた、20世紀初頭の西洋の巨匠たちが「本格」の型を提供したのだ、と説明する。だが、1950、60年代までには、犯罪小説への心理的なアプローチが支配的になった。そういった流れもあり、松本清張は「探偵小説において重要なのは、犯罪に至る動機と犯人の心理描写である」と述べた。その結果、「オーソドックス」なアプローチは軽んじられ、黙殺されたのだ——1981年に、島田荘司の傑作『占星術殺人事件』が出るまでは。
この作品の出版が呼び水となり、日本の若い作家たちは、それまでのミステリに新たな趣向を加え始めた。外界から隔絶された山荘や孤島といった、脱出手段のない、容疑者たちが閉じ込められたクローズド・サークルや、手がかりのフェアな提示、などだ。1974年に創設された京都大学推理小説研究会では、古典ミステリの研究が活発になり、そこは会員たちが多種多様な犯人当てに興じる場となった。そして多くの重要な新人作家を輩出することになるこの会から、綾辻行人が現れたのだ。彼が書いた作品が『十角館の殺人』だ。
この本は、浜辺にいる、名前が明かされていない人物のモノローグで幕を開ける。一人一人、順番に殺していかねばならない。ちょうどそう、英国のあの、高名な女流作家が構築したプロットのように——じわじわと一人ずつ。そうやって彼らに思い知らせてやるのだ。死というものの苦しみを、悲しみを、痛みを、恐怖を。後になるまで読者は気づかないが、この情感に満ちた文章の中に、キーとなるものが存在する。もちろん、文章中でほのめかされているのは、アガサ・クリスティの『そして誰もいなくなった』である。
物語は、軽妙で機知に富んだ始まり方をする。大学の推理小説研究会に属する7人の会員たちは、本土と連絡の取れない孤島で1週間を過ごすことになる。彼らは本名ではなく、エラリイ、アガサ、カー、オルツィ、ルルウ、ヴァン、ポウ、といった、敬愛すべき西洋のミステリ作家たちの名前を名乗る。一見すると他愛もない遊びに思えるが、綾辻はこれを巧みに用いるのだ。
推理小説研究会の面々が島に上陸すると、読者は島の歴史と2つの主な建築物について知ることになる。1つは、今となっては焼けて駄目になってしまった青屋敷、そしてもう1つが十角館だ。この館は、10ある壁面が各部屋を囲んでおり、10ある同一の扉が真ん中のホールに向かって開くようになっている。扉の1つは玄関ホールへ、もう1つは厨房へ、そして3つ目は洗面所へと続く。残りの扉は寝室へと続いており、会員たちは各々部屋を選ぶ。数多の古典ミステリに倣い、読者には島の地図と十角館の見取り図が与えられる。
初日。1986年3月26日の夜は何も起こらない。
その間、本土では推理小説研究会の現役会員と、かつての会員の2人が匿名の手紙を受け取る。どちらの手紙にも「お前たちが殺した千織は、私の娘だった」と書かれていた。千織は推理小説研究会の会員だったが、1年前の新年会の席で、急性アルコール中毒を起こして亡くなっていたのだ。封筒に記されていた名前は、中村青司。彼は島にある2つの建物を建てた建築家で、半年前に不可解な状況で死を遂げていた。彼とその妻、そして2人の使用人の死体が、青屋敷の焼け跡から見つかったが、妻の左手は切断されていた。その事件は未解決のままだ。
ここから綾辻は、島での出来事と本土での調査を交互に描く。本土では、島田という年上の男に助けられながら、2人の学生が告発文の意味を調査する。一方、島では、十角館にいる会員たちが目覚め、厨房のテーブルの上に7枚のプレートがあるのを発見する。プレートにはそれぞれ文字が刻まれており、「第一の被害者」「第二の被害者」と続く中、最後の2枚には「探偵」「殺人犯人」と記されていた。それからまもなくして、推理小説マニアたちは、一人また一人と死んでいく。
もし仮にこの小説を厳粛な社会文書のように取ると、その死亡者の数に読者は思わず、ぎょっとするはずだ。しかし綾辻は読者に、被害者たちに対するいかなる重々しい感情も抱かせはしない。被害者たちは型にはまった人物なのだ。聡明で冷めたところのあるエラリイ。会員たちの中でも、自信に満ちた美女であるアガサ。恥ずかしがり屋で、引っ込み思案でありながらも、千織に信頼されていたオルツィ。エラリイを嫌い、オルツィに言い寄ったことのあるカー。風邪をひいているヴァン。医学部のポウ。眼鏡をかけたオタクとして描かれているルルウ。この中の誰が犯人なのか? あるいは他に犯人がいるのか?
ウォン・ホーリンによる英訳は読みやすく、登場人物たちの会話を含む短いパラグラフの連なりによって、物語はどんどん進んでいく。多くの抜け目ない読者も、最後に明かされる真相には驚くことだろう。そしてエピローグでは、さらなる展開が読者を待ち受けている。
この『十角館の殺人』については、あまり多くを語るまい。だが、これだけは言っておこう。この作品は、密室の謎や不可能犯罪、黄金時代の「読者への挑戦状」が好きな方たちにとって、大いなる喜びをもたらすものとなるだろう。また、出版元である Locked Room International は、密室物の巨匠、ジョン・ディクスン・カーに影響を受けたフランスの現代作家、ポール・アルテの作品や、今は亡きデレック・スミスによる古典犯罪小説を3編収録した(感嘆すべき「悪魔を呼び起こせ」も収録されている)オムニバスを出している。さらには、この出版社は、他にも日本のミステリを出しているのである。さらなる「本格」を発見するのが楽しみでしょうがない。私としてはまず、島田荘司の『占星術殺人事件』を手に入れるつもりだ。まだまだ、夏は残されている。
——2015年7月15日 マイケル・ディルダ
以上が、ワシントン・ポストに掲載されたレビューの全訳になります。こうして通読してみると、このレビューは、かつての日本における「本格」の扱いや、新本格の作家たちがよく用いる設定(山荘、孤島などのクローズド・サークル)、京都大学推理小説研究会の存在などにしっかりと目を配ったうえで、ネタバレをせずに『十角館の殺人』を紹介し、賞賛する素晴らしい仕事であると分かります。
現在では、島田荘司さんの『占星術殺人事件』が The Tokyo Zodiac Murders の題で、有栖川有栖さんの『孤島パズル』が The Moai Island Puzzle の題で英訳され、出版されているようなので、ますます海外で「本格」が受容されやすくなっているといえるでしょう。2017年は、新本格ミステリ30周年のメモリアル・イヤーということで、国内では大変な盛り上がりようでしたが、こういった熱が海を超え、海外でも新たに「本格」ムーブメントが起こればいいなと、一ファンとして思います。
参考
・The Washington Post:http://wpo.st/EBpQ0
・綾辻行人の館:http://kodanshabunko.com/ayatsuji/overseas.html
・Locked Room International:http://lockedroominternational.com/
#綾辻行人 #十角館の殺人 #十角館 #館 #小説 #ミステリ #ミステリー小説 #本格ミステリ #新本格 #島田荘司 #有栖川有栖 #レビュー #翻訳
