
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』その3~誤訳、珍訳、抜け、誤解
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を読んで、えいごを学ぼう!
想定は4回でしたが、ことの他ふるわないのでwここはすっとばして、イッキに最終回&ツッコミ編への予告とします。
今回はブルーパー編
つまり、つっこみです
とりあえず「抜け」を見つけちゃいました。
Technically the carrier was named the People's Liberation Army Navy
Gansu. Why their navy has "Army" in its name I'll never know.
Regardless,people stopped calling it that and started calling it Stratt's Vat. Despite objections from the sailors aboard, the name stuck. We wandered around the South China Sea, never getting too close to land.
正式には、空母の艦名は〈中国人民解放軍海軍・甘粛〉だった。にもかかわらず、みんなその名で呼ぶのをやめて、〈ストラットのタンク〉と呼びはじめていた。水兵たちは異議を唱えたが、その名は定着した。ぼくらはけっして陸地に近づきすぎないようにしなから、南シナ海周辺をさまよっていた。
何も問題はないようにみえますが、
Why their navy has "Army" in its name I'll never know. の一行がスッポリ抜けちゃってます。
ちなみにこの一行をよけずに訳すなら
空母の艦名は〈中国人民解放軍海軍(The People's Liberation Army Navy)・甘粛〉だった。(なぜ海軍の名前の中に陸軍という語が入っているのかについてぼくは知る由もない)
といったかんじでしょうか。
とりあえず大筋に影響はありませんが、だからといって勝手にスキップしてもいいものでしょうか?
コレはたまたま見つけただけなのでがっつり探したらまだまだ他にもあるかもしれません。
ARMYは元々陸海空問わず「軍」そのもののことも指すのでトゲアリトゲナシトゲトゲのような後付け累積型ネーミングのごとく扱うのは不当ともいえますが、理系な主人公のキャラづけなのか、中国を揶揄しているのか作者の意図については知る由もありません。
「ARMY=軍隊」或いは「ARMY=志を共にする集団」という語彙がマニアやインテリだけのトリビアではないことはエルヴィス・コステロの「Oliver's Army」という曲名やBTSのファンがなによりの証拠です。
さて
「抜け」の次はコレ
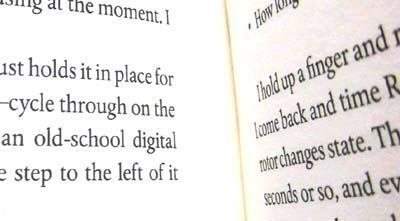
Like an old-school digital clock back home.
昔、学校にあったデジタル時計のようだ。
これ誤訳です。
old-school はむかしの学校などではありません。
「オールドスクール」はもはやカタカナ語として、定着しており、「黎明期の、初期型の、ひと昔前の」といった意味で、元々はヒップホップやファッションの世界で使われてたものが多ジャンルにも広がりをみせました。モノに使う場合はVintageとかOld fashionedが類語でしょうか。
少なくとも「old-school」のように、ハイフンを見たらなにかしらあると気付くのがプロというものではないでしょうか。
ここは作者にもひとつツッコミたいことがあります。なつかしのデジタルクロックは、なつかしの自動車や自転車の積算距離メーターのような「ローター式」はあり得ません。
なぜなら「ローター式」ではそのサイズに収まりきりません。卓上型、または枕元型のなつかしクロックに採用されていたのは、空港や駅の案内などでもお馴染みのパタパタ式(Flap Display)です。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」にパニソニックのものが映りこんでいたことが日本では話題になりました。端の秒針に相当する部分だけはローター式です。
さてさて
読んでいて日本語がおかしい場合はほぼ誤訳だというのを聞いたことがあります。なるほど、たとえ翻訳者が原書を理解していたとしても、訳文が日本語として成立していなければ、その翻訳は失敗ですから、そういえるでしょうね。
The hull robot reaches out with some seriously telescoping arms.
船体ロボットが、まさに入れ子式としか思えないアームを何本か、こっちに向かってのばしてくる。
「まさに入れ子式としか思えない」って何?
telescoping というのは望遠鏡や三段式警棒や梯子車の梯子のハシゴのように伸縮式だということです。ここはシンプルに「伸縮式のアームを伸ばしてきた」と記述すればすむはなしでは?読者に対して語彙力のマウントをとりたかったのでしょうか?
Along another wall was a bookshelf full of specimen jars of animal parts in formaldehyde.
壁沿いにはホルムアルデヒド漬けの動物の身体の一部の標本がびっしり並んだ本棚。
まぁホルムアルデヒドだなんてこの学校にいたら子供たちがシックハウス症候群になりそうです。ホルムアルデヒドの水溶液はホルマリンといい、日本には「ホルマリン漬け」という、時には比喩表現などにも用いられる由緒正しいことばがあるのです。
よく翻訳力は日本語力だといいますが、ここまでくると日本語の語彙力というより常識力の問題といえます。
The handles certainly aren’t connected by any mechanical means. Must be an adhesive.
ハンドルはなにか機械的な方法で取り付けられたわけではない。接着したのにちかいない。
この文も日本語としてヘンです。
mechanicalなので「機械的」としたのかもしれませんが、日本語で機械的といういと、対象の事情にかかわらず一律に対処するとか、右から左と流れ作業的に処理するといった意味ですが、英語のmechanical connectionはボルトやリベットやネジなどの手段で2つの物体をつなぐことで、接着剤などで接合する方法は含まないというわけです。
だからこのmechanicalを機械的に機械的と訳するのは誤りなのです。
さて、この本ではやたらと「どうどう」という言葉がでてきますが、これもほとんど意味不明です。私はこの言葉は馬に対して使われている場面以外ほとんど知りません。稀に血の気の多い輩をなだめるのに冗談めかして使うことはありますが。
警報が鳴り響く。耳が痛くなるような甲高い音だ。
「どうどう、どうどう!」と声をかけ、あわててパネルをスキャンして。"接近警報ミュート"と書かれたボタンを見つける。それを押すと、警報音が止まった。
ぼくらが親戚同士? いったいどういう—
「ああ! つまり……どうどう!」これはみっちり考えなくてはならない。
「少し時間がかかると思う」とぼくはいった。「相互作用を見る必要が—|どうどう《、、、、》!」
うとうとしかけて……。
「どうどう!」ガバッと起き上がる。「ビートルズだ!」
或いは流行語大賞でも狙っているのでしょうか?
さらにもうひとつ
この翻訳者は果たして作者の意図を理解しているのか?
と疑いたくなるような一節、
Rocky’s actual name is a sequence of notes—he told it to me once
ロッキーのほんとうの名前は一連の音だ
置きにいったのでしょうか?
意味的には間違ってはいないのですが、そんなん言ったら人類の言葉だって、犬やカラスの鳴き声だって「一連の音」じゃん~てなことになってしまいます。
ここでいうsequenceはおそらく音楽のフレーズのことです。
ネット上に「What's the difference between a musical phrase and a sequence?」なんて質問があるのを目にすれば、sequenceという語を皆がどんなニュアンスで理解しているのか想像がつくでしょう。
データサイエンスの台頭でシーケンサーでググると、ゲノム解析などが上位に出てくるかもしれませんが、DTM用の打ち込みソフトというのは基本的にシーケンサーソフトです。音楽方面ではいまや当たり前すぎてシーケンサーという言葉を意識すらしてないかもですが、ほんのひと昔前にはシーケンサーという名の単体のキカイが売られていました。
現在でも例えばフィギュアスケートの演技なんかも、シークエンスの集まりだったりするので、アンテナを伸ばしていればデータサイエンス以外のエンタメよりのシークエンスにいくらでも出会えるはずです。
さいわいなことにロッキーは音楽的な和音で話す。
などというくだりもありましたし、当作のオーディオブック版におけるエイリアンの会話部分はメロディアスになっているらしいとの情報をコメント欄にお寄せいただきました。
今回のツッコミに意味はあるのか?ただ信者の神経を逆なでしてるだけで誰にも利はないのではないか?と思うかもしれませんが、そうは思いません。なぜならこのしくじりの中に日本のダメな部分の縮図があるからです。
最もシンプルなポイントは「チェック体制」、これはトヨタの米国におけるリコール問題にも通じます。この事件に関する日本での報道は完全に「大本営発表」と化しているのでまずそこが大問題なのですが、裁判ではトヨタのソフトウェア開発において、チェック体制がなかったことが問題視されました。
翻って「ヘイルメアリー」では恐らく翻訳者の3割ほどの英語力の方がチェック役だったとしても、たとえば「怠け者のスクリーン」が「待機画面」だと気づいてあげられたでしょうし、SFを扱う編集部には複数人いるであろう、宇宙オタクが目を通せば、「クレスト」よりも「ミッションパッチ」や「ミッションロゴ」の方がより日本のオタクには通じますよなどとアドバイスもできたでしょう。
いや、英語力0の学生に日本語のゲラを読ませただけでも多くの不具合は発見できたでしょう。
そもそもの問題として、ホンヤクものは日本語がヘンなのは当たり前という慣例から改めなければならないでしょうし、今あげたミスの8割はチェック体制以前の翻訳者の意識の問題ではないでしょうか。
このゆるさは危機管理の予算はケチるという日本の大問題、たとえばみずほやauの不具合問題などとも地続きです。
さて、今回は次投稿への予告も兼ねると冒頭で言いましたが、次投稿つっこみ編のテーマは今つらつらと並べたことは一切カンケーありませんw
「プロジェクト・ヘイル・メアリー」そのもの、つまり作者のウィアーへのツッコミです。「プロジェクト・ヘイル・メアリー」についてなにかしら読みたいなどと言う人々は皆、信者でしょうから共感ゼロかもしれませんが…
