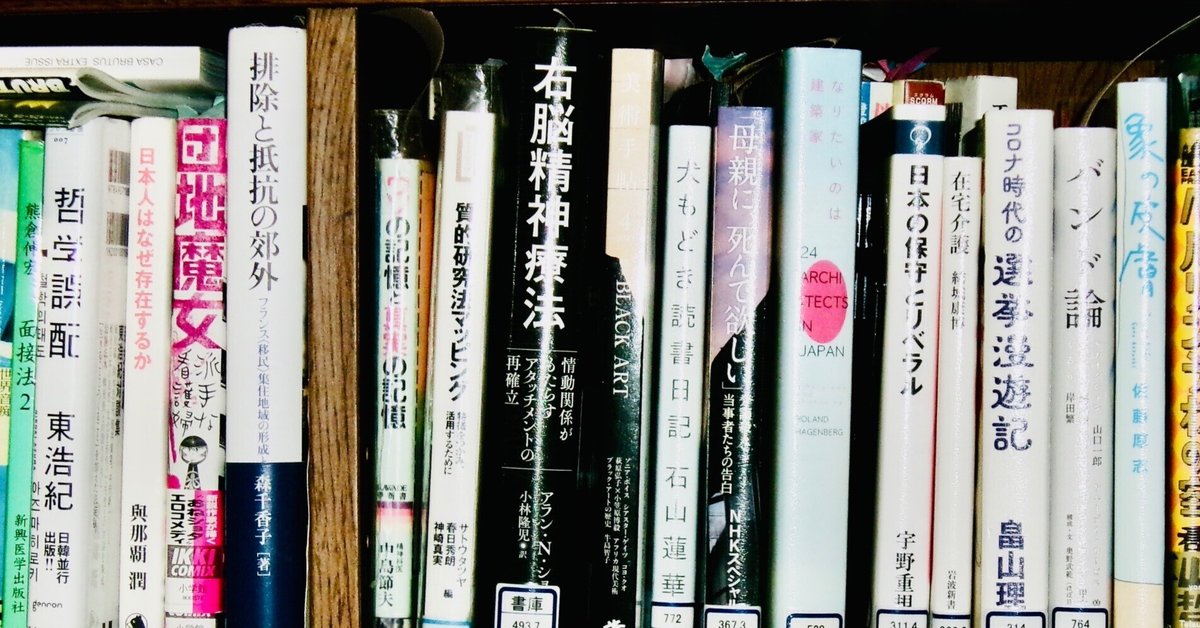
読書感想 『嫌いなら呼ぶなよ』 綿矢りさ 「折り目正しい“闇”」
とても恥ずかしい話だけど、だいぶ長い間、「わたや」ではなく「めんや」だと思っていた。
2004年、19歳で芥川賞受賞、同時受賞が、20歳の金原ひとみだった。そのことは、ニュースとして覚えている。
勝手な個人的な事情だけど、その頃は、仕事も辞めて介護に専念していて、しかも、その家族の症状が悪くなっている頃で、自分は社会から断絶し、そこから落っこちている状況だと思っていたので、そういうニュースはまぶしすぎて、怖いくらいだった。
そのせいか、その後、中年になってから、本を読む習慣がついたのに、綿矢りさの作品を読めなかった。初めて読んだのは、『大地のゲーム』だった。ある批評家が、震災後の小説、と評していたからで、読んだのは2016年だった。とても遅い読者だけど、芥川賞受賞から、10年以上経っても、こうした鋭く生々しい描写がある作品を書く作家だったのかと思い、新鮮だった。
その後、金原ひとみの作品も読むようになり、『アンソーシャルディスタンス』では、コロナ禍でも、その時だけしか感じられないことも書こうとしていて、なんだかすごいとも思った。
二人とも、20冊弱の作品を発表しているから、コンスタントに作品を書き続けていることになるのだろうと思う。とても若い時に注目を浴びる大変さは、想像しかできないけれど、それで、その後のキャリアが困難になった実例は、メディアを通してに過ぎないが、少なからず見てきた記憶があるから、早い栄光の怖さもあるのに、こうして二人ともが生き残っているのは、とても珍しい例だと思うようになった。
2004年の芥川賞のときは、若くて華やかな作家を2人同時受賞させることで、より話題を作ろうとしているのでは、と屈折した見方をしていたのだけど、実は、才能のある作家の未来もつくるために、意識的に同時受賞をさせ、その注目を分散させた、という戦略があったのかもしれない。
その後の二人の作家の実績の蓄積を見ると、そんなことまで思うようになった。
『嫌いなら呼ぶなよ』 綿矢りさ
どうして、この作品を読もうと思ったのかは覚えていないけれど、それでも、申し訳ないのだけど、今回も図書館で借りようと思って、予約をしてから、しばらく待ったから、読みたい人は多かったはずだ。
赤地に青の水玉。目をひく装丁だった。
扉に、こうした言葉。
知らない人から嫌われるのは、
あなたが素晴らしい証拠。
―― パリス・ヒルトン
現在のSNSが盛んになった時代には、ごく一般的に、この言葉が大事になってきているのかもしれないけれど、考えたら、綿矢りさは、すでに20年近く、こうした言葉が実感としてわかる年月を過ごしてきたのだろうから、そういう意味でも、人とは質の違う体験をしながら、作品を書き続けてきた作家なのだと改めて思う。
自分は、人から、どう見られているのか。
自分が、どう思われたいのか。
自分を、どう思いたいのか。
この書籍は、4つの短編から出来上がっているけれど、どれも、自意識が過剰になりがちな現代だからこそ、生じるような“闇”を描いているように思った。
眼帯のミニーマウス
自分の見た目にコンプレックスがあり、ただ、それだけが理由ではないようだけど、整形をしたのが主人公だった。その上、整形したことを、同じ会社に勤める人に話をしたことで、「整形いじり」の毎日が始まってしまった。
私のプライドは一風変わってて、自分の立場や権利を正論で勝ち取るぐらいなら、ぼろくそ言われている方がましなのだ。怒ったり泣いたりは美学に反する。怒りは古い油の臭いがする。胸やけするドーナツを二、三個揚げ終わったあとのような、肋骨の内の油釜。自分の花道に散らかるゲロやゴミは片付けずに踏んづけてのしのし歩いてやる。プライドの十センチハイヒールはいてるから足汚れない大丈夫。
ウケる。ウケる。傷ついたってしょうがないから、とりあえずウケとく。とりあえずみんな楽しそうだからよかった、私の整形いじっているとき、放牧されて窮屈な小屋から脱出してアルプス山脈の草原で元気に跳ね回る子やぎの群れぐらい嬉しそうだったもん。職場の仲間たちの、あんな無邪気な笑顔を引き出せて幸せ。って思えるわけもない。
プライバシーの問題だからさすがにもう少しそっとしといてくれると思ってたけど、連日みんな全力でいじってきた。整形キャラとして定着しそうな勢いだ。自分はそんなヤワじゃないと思ってたけど、中学のころみんなにハブられたトラウマまで思い出す始末であまりよく眠れなかった。
それから、その「整形いじり」はエスカレートもするが、そこから、注目を浴びること。匿名性を守ること。そういう矛盾した要素を両立させるような方向へ、主人公は進んでいくのだけど、見た目に関しては、21世紀になって、不自然なほど重視されるようになった空気感が、あちこちから、あふれていた。
神田タ
ユーチューバーの(主に)ファンについての話。
と単純化し過ぎてはいけないのだけど、ユーチューバーのことは、今はテレビにも出ているから、それほど興味もなくて申し訳ないのだけど、それでも、どういう人たちがいるのかを、一部とはいえ、認識するようになったのに比べて、どんな人が熱心なファンなのかについては、ほとんど意識もしていなかったことに気がついた。
繁忙期でピリピリしがちなときでも態度を変えない私は、ムードメーカーとして常に職場の空気を清浄化し、癒し系バイトちゃんの名をほしいままにしていた。しゃべり方がゆっくりしているだけで、どうして人は安心するのだろう。その間に脳がすごい勢いで回転していることもあるのに。
そうした冷静な知性の持ち主が、それほど人気のないユーチューバーに、だんだん意識もせずに、のめり込んでいく。
彼らが視聴者を欲していて、自己顕示欲を満たしたくて、でも見知らぬ大勢の人間を相手にしていることへの独特の警戒と不安が、強い照明で白飛びした画面に映る彼らの表情から伝わってくるのを見るのが好きだ。まだ視聴者の少ないチャンネルの固定視聴者になり、激励したり批判したり、温と冷の私のコメントに翻弄されている主の動揺が見てとれると、支配欲さえ満たされる。
コロナのせいで、レジャー施設もショッピングモールも軒並み休業するようになってからは、私はおうち時間のほとんどを神田の動画を見ることに費やした。
あくまでも、どこかで自分の方が上、というような気持ちを味わいたい、ということなのかもしれない、などと思わせるような主人公は、本人が思った以上に、自分の気持ちそのものを注ぎ込んでいくような作業を続けてしまう。
すごい悪口を書いたコメントを見ると、対抗心が湧いてきて、自分ももっと書いて目立ちたくなった。練りに練った辛辣なコメントを書き込んで送信ボタンを押すとき、身体中の毛細血管、特に脳の血管に興奮で血がグワっと流れるのを感じる。どこか裏の掲示板で陰口を叩くのと違って、本人が見ているかもしれない、いや必ず見ているに違いない場所に堂々と批判的なコメントを書くのは、本当に興奮、いや勇気が要った。
そうしているうちに、自分では正義感のようなものから発している言語のはずが、あるきっかけで、悪質なストーカーのように受け取られていることを知り、さらに、行動は本人が想像していなかった方向へ、やはり進んでいくのだけど、気持ちのあっという間の上下も含めて、薄い怖さがあった。
嫌いなら呼ぶなよ
表題作。
物語の構造は、とてもオーソドックスなはずだった。妻の親友の夫婦の家に招かれ、そこで、小規模なパーティーが開かれた。それほど気乗りがしないが、出かけた主人公の男性は、当初は、ごく平凡な人かと思わせていたのだけど、それが、本来の目的である主人公の「不倫」をめぐっての「裁判」のような状況になってから、不気味なほどの軽い内面が、読者にむき出しに伝わるようになってくる。
何かが開いた感じはした。
例えば、探偵まで雇って撮影された、不倫相手と手を繋いでいる写真を見せられた時の反応。
違う、そこじゃない。この角度からの写真はただでさえ苦手なのに、顔が動いているときに撮られて顎の辺りがぶれているせいで、僕の顔が1.5倍は顔デカに見えている。真上からの光源のせいで星野さんもとんでもないブスに写ってるけど、現物はここまでほうれい線深くないぞ。
「そうだったんですね。本当に気づいてませんでした。隠し撮りまでされていたとは」
落ち込んでも仕方ない、探偵はカメラマンじゃないからしょうがない。それに僕と星野さんは確かに仲良さそうに手を繋いで街を歩いているが、浮気現場の証拠としてはそれほど決定的な写真ではない。
さらに、さまざまに責められるのだけど、その時、本人の心はそこにはいない。
現実逃避したくなると、僕は誰かにインタビューされている体で、頭のなかで話し始めるくせがある。インタビュアーは僕にとても興味があり、僕のプライバシーについてなら無限に情報を得たがっていて、熱心に質問をくり出し続ける。僕は穏やかに彼女の質問に丁寧に答えていく。
『素敵なパートナーがいるにもかかわらず浮気をなさった霜月さんにお伺いしたいのですが、既婚者でありながらそこまでモテる理由とは一体何なのでしょうか?』
そこから、さらにしばらく自己愛に満ちた妄想が続くのだけど、この「裁判」の最中に、こうしたことを考えられるのは、気持ち悪いを通り越して、そのタフさに驚くような思いにもなれるし、さらに、決定的な写真を見せられて、それでも、なんとかしようとする主人公に、妻が少し悲鳴のように言葉を投げかける。
「なんでまだ許してもらえると信じきってるの?その図太さが恐い。あなたの本性を暴きたい、殻を割りたいと思ってたけど、つるんとして目も鼻もないムキゆでタマゴみたいな顔が出てきそうで不気味なの。明るすぎる闇っていうか」
「楓、僕にはそんな詩的な表現、もったいないよ」
ここからさらに、主人公は、不気味だけど、あまり深みのない思考を、さらに繰り出し続けていくのだけど、そうした矛盾を、とんでもなく強い自己肯定感で支えているらしいのがわかり、主人公の内面で、見えないものがないはずなのに、やっぱり少し怖い。
老は害で、若も輩
作家とライターが揉めて、それをメールでやりとりしながらも、「Cc」にずっといた編集者が、いつ間にか、そこに参戦することになる話。
もう新しいメディアではないけれど、それでも、そういえば、1対1の戦いのはずが、微妙にオープンになることによって、客観的になるのではなく、かえって、揉め方が面倒くさくなる。それは、なかなか、ここまでのトラブルまで行かないとしても、今も、どこかで行われている戦いのように思えた。
それほど多くの小説を読んでいないので、それこそ浅い推測なのだけど、このツールを使っての揉め事を、こうして鮮やかに作品化した人は他に知らない。
折り目正しい闇
4編を読み終えて、とても上品な作品だという印象が残った。
明るすぎる闇。という表現が小説の中にもあったのだけど、登場人物に深さがないせいかもしれないが、全体として、それよりも、とても折り目正しい闇、というように思えた。
それは、闇の表現にも崩れが少なく、押し付けがましくなく、描写が隅から隅まで正確で、だからいろいろなことがクリアに見えてしまったせいだと思う。
唐突な例えかもしれないが、どんな歌でも一度聴いたら歌える、という伝説をもつ美空ひばりのように、綿矢りさは、どんなことでも書けるのではないか。そんな、小説の技術の高さについて、改めて、いろいろなことを考えさせられる作品だった。
(こちら↓は、電子書籍版です)。
(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。
#推薦図書 #読書感想文 #嫌いなら呼ぶなよ
#綿矢りさ #芥川賞 #金原ひとみ #同時受賞
#小説 #作家 #技術 #毎日投稿
#最年少受賞
いいなと思ったら応援しよう!

