
伊川津貝塚 有髯土偶 91:変成帯と石
愛知県新城市(しんしろし)富栄茶屋貝津(とみさかちゃやがいつ)の大當峯神社(おおとうみねじんじゃ)から鳳来寺山の麓にある鳳来寺山自然科学博物館に向かいました。そこには新城市長篠向林(ながしのむかいばやし)に現れた中央構造線の掘削断面が移築展示されているからです。「露頭」とは野外に地層や岩石が露出している場所のことですが、中央構造線では外帯(がいたい:太平洋側)特有の岩石と内帯(ないたい:大陸側)特有の岩石が衝突して露出している場所が存在するのです。
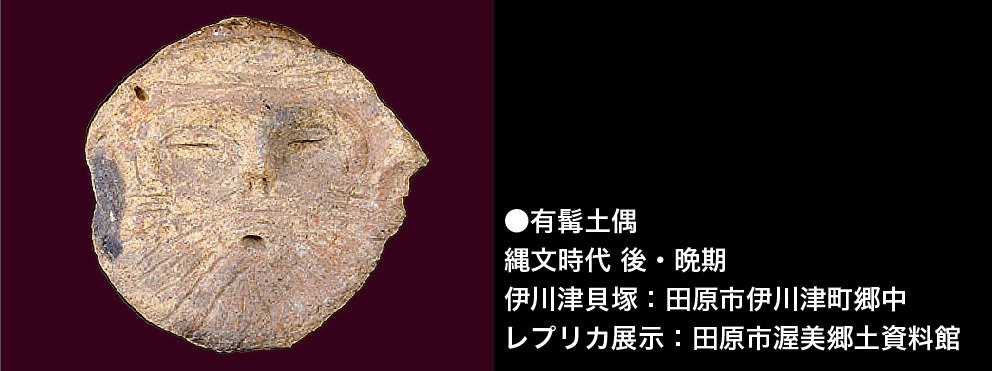



富栄茶屋貝津の大當峯神社前から北に登る舗装路、富坂設楽線(とみさかしだらせん)を5.3kmほどたどると右手に分岐する県道441号線があり、その入り口左右には対になった巨大でモダンな常夜灯が設置されていた。
それが真言宗五智教団の煙巌山 鳳来寺の表参道登口だった。
常夜灯の間を抜け、東に向かって表参道(441号線)を登って行くと、900m以内の左手が鳳来寺山自然科学博物館の敷地になっており、駐車場があった。
駐車場に沿って北に入って行くと、深い谷に架かった橋の向こう側に明るい桜色を基調にした正面に二階に上がる階段のある3階建ての建物があった。

階段を2階に上がると、入館受付のあるロビーがあって、そのロビーの壁に中央構造線の露頭が組み込まれていたが、それは最後に観ることにして、まずは目に付いたものから観て行くことにした。
3階に上がる階段脇にJ形の奇妙なものが展示されていた。

それは「流紋岩の球顆(きゅうか)」という名称で石灰で何かを包んであるような形体をしていた。
産地は「新城市副川」とある。
「副川」という川で出土したものかと思ったのだが、「副川」という川があるわけではなく、「副川」は内帯の海老川沿いに位置する地名だった。
案内プレートには以下のようにあった。
奥三河地方で見られる流紋岩にはしばしば球状の物体(球顆)が含まれている。マグマの冷却末期にできた構造で、中に空隙をもつことが多い。空隙にケイ酸分に富んだ熱水が入ったことで、 中からオパールや玉髄(ぎょくずい:石英)が見つかることが多い。
この隣には以下の「球顆」とその中から出てきた「玉髄」がセットで展示されていたが、この玉髄は見た感じでは石英には見えなかった。

隣のJ形の物体は複数の球顆が連なってできているものらしい。
ロビーにつながっている展示室に入ると、新城市で採集されたコケなどの植物や昆虫などが展示されていた。
最初に目に留まったのは以下の「ヒメコクサゴケ」だった。

コケは50種類以上採集して育てていたことがあるが、ヒメコクサゴケは珍しいものではなく、どこでもよく見られるコケだ。
下記写真のように枝を伸ばすのだが、これはそれを解りやすく展示したもので、実際に野外で枝を伸ばしているように見えるものでもなく、石の表面を覆った塊にしか見えないので、こんな展示の仕方があるんだなと目に留まった。
19種類のどんぐりが並べて展示されていた。

目立って大きなドングリはナラガシワとクヌギで、ブナとウバメガシの果実はドングリには見えないが、ナラガシワととブナは同じブナ科だ。
秋田県以南の日本列島に分布するナラガシワとクヌギのどんぐりは縄文人にとっても食べでのある主食にされた、どんぐりだったと思われ、縄文時代中期~晩期の縄文遺跡からよく出土しているが、ナラガシワに関しては縄文時代後期にナラ枯れが発生し、被害が拡大したことが確認されている。
このナラ枯れは現代でも1980年代から目立っているという。
縄文時代中期~晩期には関東平野に広く分布していたというが、現在は関東平野でも殆ど見られなくなっているという。
愛知県でもナラガシワは絶滅危惧種IB類に分類されている。
絶滅危惧種はIA類とIB類に分類されているが、IA類の方が危険度は高い。
一方、クヌギは 成長が早いこともあって、食用だけではなく、縄文時代中期から建築用資材や燃料としても利用され、日本人には現代でも親しまれている樹木だ。
下記写真は果実を守る殻斗(かくと)を付けたナラガシワのドングリ。

縄文人になった気分で見ると美味しそうだ!
下記写真はアベマキのどんぐり。

ナラガシワのドングリの一般的なイメージの殻斗と、アベマキのどんぐりのような鱗状の殻斗が、どんぐりを代表する2種類の殻斗だ。
続いて目に留まったのが下記のイオウイロハシリグモの標本だった。

イオウイロハシリグモは網を張らずに獲物を捕らえる種のなかで、もっともよく見られるクモだという。
ただ、体色に変異が多いのが特徴であることから、昔からそれぞれの体色や斑紋から、それぞれが別種だと誤解されてきたたクモだという。
展示されているイオウイロハシリグモは身体の両側に白線を持っているが、この白線がないものもいて、見かけで同種とは思えないのはよく解る。
しかも、白線を持っているイオウイロハシリグモも、いくつものタイプがあるうえに、白線以外の斑紋を持ったイオウイロハシリグモもいるという。
上記写真の手書きのネームプレートには「(スジボケ型)」とあるが、これは白線がボケているタイプのイオウイロハシリグモということなのだろう。
展示されているイオウイロハシリグモは以下の記事にしてある乳岩で採取されたものだが、日本列島では北海道〜九州の全域、そして薩南諸島まで分布しているという。
別の展示室に移動すると、中央構造線の内帯と外帯に分けて岩が展示されている場所があった。
まずは日本最大の広域変成帯である、外帯(太平洋側)に位置する三波川変成帯(さんばがわへんせいたい)で産出した緑色片岩が目に留まった。

三波川変成帯は海洋プレートに圧力を受けた1億年くらい前の地層が高圧を受けてできた以下の岩石が主になっているという。
・緑色片岩
・黒色片岩
・蛇紋岩
一方、内帯(大陸側)に位置する領家変成帯(りょうけへんせいたい)で産出した岩石の中で目に留まったのが以下の片麻岩(へんまがん)だった。

目に留まった理由は一目瞭然だ。
濃色の部分と薄色の部分が層状に重なった片麻状組織を持つ岩石であることから「片麻岩」と名付けられている。
領家変成帯の岩石はやはり1億年くらい前の堆積岩が高温で変質した岩石や花崗岩の仲間でできているという。
以下の6種類の岩石が領家変成帯で主に見られる岩石だ。
・片麻岩 ・花崗岩
・石英片岩 ・閃緑岩
・雲母片岩 ・はんれい岩
(この項、続く)
◼️◼️◼️◼️
変成前の岩石は変成時の温度によって、以下のような3種類の変成岩に変成します。
・結晶片岩=変成時に比較的低温で、変成があまり進まなかった岩石
・片麻岩=変成時の条件が比較的高温で、変成が進んだ岩石
・片岩=変成時の条件があまりにも高温の作用を受けた岩石
