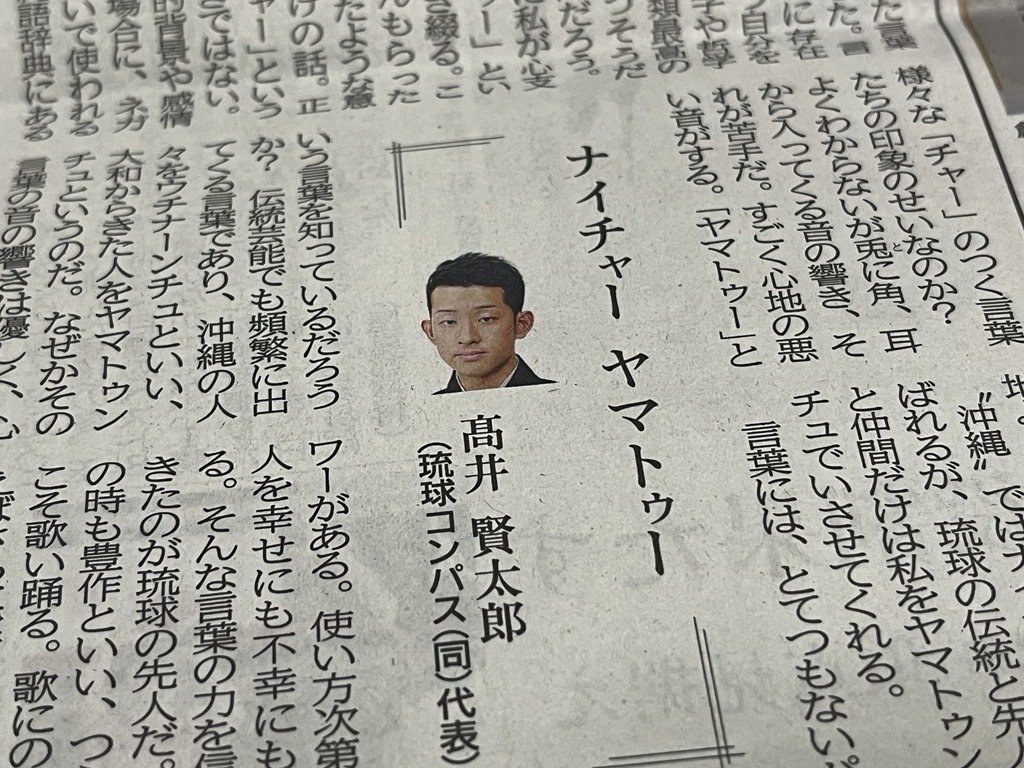琉球新報 落ち穂「ナイチャーヤマトゥー」#10
これまで私がもらった言葉と想いを書き綴ってきた。言葉はいつも記憶の中に存在し、困難に立ち向かう自分を導いてくれる。言語学や哲学の分野で「言葉は人類最高の発明だ」なんて言うそうだが、きっとそうなんだろう。
本コラムの最後に私が心支えられた「ヤマトゥー」という言葉について書き綴る。
これまでにたくさんもらった「ナイチャー」と似たような意味だが、ここだけの話。正直、私は「ナイチャー」という言葉があまり好きではない。
歴史的、文化的背景や感情的な要素が絡む場合に、ネガティブな意味合いで使われるからか?沖縄語辞典にある様々な「チャー」のつく言葉たちの印象のせいなのか?よくわからないが
兎に角、耳から入ってくる音の響き、それが苦手だ。すごく心地の悪い音がする。
「ヤマトゥー」という言葉を知っているだろうか?
伝統芸能でも頻繁に出てくる言葉であり、沖縄の人々をウチナーンチュといい、大和からきた人をヤマトゥンチュというのだ。なぜかその言葉の音の響きは優しく、心地よく、あたたかい。
現代の"沖縄"ではナイチャーと呼ばれるが、琉球の伝統と先人と仲間だけは私をヤマトゥンチュでいさせてくれる。
言葉には、とてつもないパワーがある。使い方次第で、人を幸せにも不幸にもできる。そんな言葉の力を信じてきたのが琉球の先人だ。
不作の時も豊作といい、つらい時こそ歌い踊る。歌にのせて歌えばさらに霊力が高まるとされた地域の芸能を見ればわかる通り、言葉のパワーで心豊かに生きていた。
そして、アジアの中心に位置し様々な文化や人が行き交ったこの島は、多様な文化と人を受け入れ、独自の価値を育んできた。
ハタチでこの伝統に出会って、10年が経つ。やっと沖縄の”お”が分かったようで分かっていない。
そんな私もいつかはナイチャーじゃなくてヤマトゥーになれるだろうか...というのは、もはやどうでもいい。
今、この島の空気を吸っている。一緒に伝統をつなごうと言ってくれる仲間がいる。琉球の伝統と共にある私の人生は最高に幸せで最高に楽しい。
琉球新報 落ち穂 髙井賢太郎「ナイチャーヤマトゥー」 より