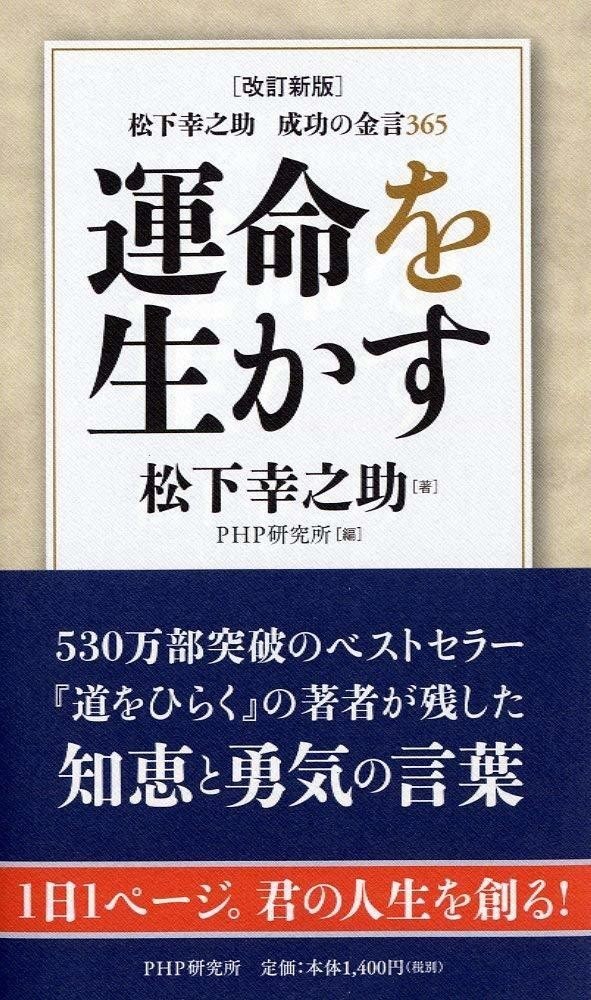松下幸之助と『経営の技法』#3
「法と経営学」の観点から、松下幸之助を読み解いてみます。
テキストは、「運命を生かす」(PHP研究所)。日めくりカレンダーのように、一日一言紹介されています。その一言ずつを、該当する日付ごとに、読み解いていきます。
1.2/18の金言
他人の庭の花が赤く見えることもあるが、それは心の迷い。この世に楽なことなどない。
2.2/18の概要
松下幸之助氏は、以下のように話しています。
コツコツまじめにやっているのは自分だけ、人はみな濡れ手で粟、と思えてきて、自分も何か一つと思いがちだが、そうは世間は許さない。楽なことなどはない。
3.経営者へのメッセージ
安易に流されることを戒めています。
経営的には、ここでの最後の部分、すなわち「一歩一歩地道に積み重ねてきた着実な成果」という言葉が重要でしょう。言わば、「見えざる資産」の重要性です。
すなわち、まともな蓄積もないまま事業だけ拡大しても、いずれパンクします。見えざる資産の重要性は、『ゼミナール 経営学入門』でも詳細に検証されていることです。
リスク管理的には、自分自身の経営判断として、安易な手法のリスクに気づくこと(リスクコントロール能力)と、実際にそうならないように自制すること(リスクコントロール能力)が重要である、と整理できます。
さらに、これらのことを会社組織に実行させることも、重要な「内部統制」の問題です。
すなわち、経営的には、会社の各従業員が安易な方法に流れないように統制しなければなりません。さらに、会社組織自身=各従業員が、安易な方法の危険に気づき、安易に流れないようにコントロールできるようにしなければなりません。
4.株主へのメッセージ
さらに、ガバナンス上のコントロールとして、株主によるコントロールも期待されるべきです。
すなわち、株主や、これに代わって経営者をチェックする社外取締役、監査役などは、安易な方法を選択しようとする経営者を戒めなければいけません。
5.おわりに
このように見れば、最近ではすっかり定着したものの見方ですが、短期的に、ときに四半期ごとに、結果を求めるアメリカ型の会社法ではなく、中長期的な成長に投資できる日本型経営の利点に関わる話とも評価できます。
すなわち、中長期的な成長に投資できる、と言われる日本型の経営であっても、実際に成果が出なくても辛抱強く地道に取り組むことの難しさが指摘されているのです。国際的な競争により、短期的な成果も以前より強く求められるようになった現在に比べれば、松下幸之助氏の時代は、よりじっくりと経営に取り組めたはずですが、それでも、浮足立つ気持ちをコントロールしなければならない、と話しているのです。
このことから、短期的な成果が以前よりも強く求められる現代では、浮足立つ気持ちのコントロールは、氏の発言当時よりも一層、その重要性が増しているはずです。