
超動くマンカラ(11)~2次元マンカラは、いつ生まれた?(その1の補足(+β))
前回のnoteはこちら。
前々回の記事の訂正と補足でした。
今回は、さらにまた補足「スタッキング」について書きます。
スタッキングを使用した最初期のボードゲーム
前回の記事を書いた前後に、Kanare_Abstractさんが興味深い記事を書きました。
この中で紹介されている、アブストラクトゲームの1つに、目がいきました。
1930年に発表された『Tricolor』です。
全く知らず、お初です。
前々回紹介した『Intermedium』が1977年ですので、40年以上も前のゲームです。
このゲームにはスタッキングのルールがあります。
さらに、Boardgamegeekでの説明には、面白い情報が書かれていました。
【Descriptionより引用】
It is one of the oldest stacking games (older are just Tower of Hanoi, Lasca and Bashni).
【翻訳】
これは最も古いスタッキングゲームの1つです(古いのはハノイの塔、ラスカ、バシュニだけです)。
意外にも、最初期のスタッキングを含んだゲームがわかってしまいました。
◆『Tower Of Hanoi(ハノイの塔)』
このゲームは、Boardgamegeekには登録されておりませんので、Wikipediaをごらんください。
『ハノイの塔』は、フランスの数学者エドゥアール・リュカさんが考え、1883年にゲームを販売しました。
ゲームというかパズル(ソリティア)として扱われています。
ちなみに、リュカさんは「超動くマンカラ」の番外編「マンカラ一人勝ち問題」でも、非常に深く関わりのあるナイスガイです。
もう1つの追加情報。
「ハノイの塔」をベースにしたアブストラクトゲーム『Varanasi(バラナシ)』もあります。
中島雅弘さんが考案したゲームで、Nestorgamesでも販売していました。
◆『Laska(ラスカ)』
1911年に、チェスの世界チャンピオンでもあったEmanuel Lasker(エマニュエル・ラスカー)さんが、考案したボードゲームです。
Nestorgamesでも販売していました。
このゲームのベース、インスパイアの元になったのが『Bashni(バシュニ)』になります。
◆『Bashni(バシュニ)』
1885年以前に、すでにロシアで遊ばれていたと思われます。
『バシュニ』については、以前記事にしたことのある「Abstract Game」で、紹介だけでなく手筋研究も含めて数号(1、3、7、9、11、15、16号)にわたり書かれています。
あ、『ラスカ』も11号でかかれています。
さらに元祖のボードゲーム?
どうやら、スタッキングは19世紀ごろに生まれたゲームメカ二クスではないかと思われます。
…いや、すみません。
私、そう思ってないのです。
もっとさかのぼってしまいます。
しかも、古典も古典、伝統も伝統のスタンダードボードゲームです。
日本人も世界チャンピオンになったことのあるゲーム、

バックギャモンです。
いやいやいや、まてまてまて。
コマを積み重ねていないじゃないか。
ごもっともです。
しかしですね、ゲーム盤を垂直に立ててみましょう。
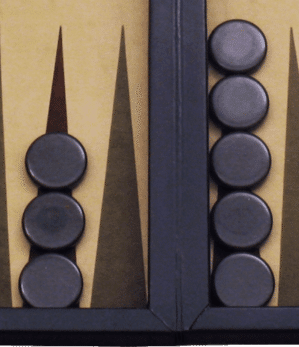
ほらね、平らに積み重なっているでしょ。
バックギャモンのマスは、コマを複数置くデザインとなっているので、物理的に上下に置いていないだけで、ルールとしてはスタッキングとして十分に扱える、と考えました。
バックギャモンのルールを確認すると、
・敵のコマ1個だけのマス:
自分のコマを同じマスに入ることができて、敵のコマを盤外から追い出す(キャプチャー)ことができる(非防御状態と攻撃)。
・敵のコマ2個以上のマス:
自分のコマを同じマスに入ることができない(防御状態)。
と、マスの中のコマの個数でルールが変わってきます。
これは、スタッキングのメカニクスと同様の扱いです。
バックギャモンの攻撃・防御ルールを活かしたボードゲームも、たくさんあります。
アブストラクトゲームの1例として、Nestorgamesでも販売されていた『Murus Gallicus(ミュルス・ガリカス)』です。
『FILLIT(フィリット)』を考案したラディアスリーの、アブストラクトゲーム紹介動画『アブな世界』でも取り上げています。
アブストラクトゲーム以外でも、バックギャモンぽいものがあります。
その1例が『Qwixx Duel(クウィックス・デュエル)』です。
ベースとなったのは、ロール・アンド・ライトの『Qwixx(クウィックス)』
です。
『クウィックス・デュエル』は、紙をペンではなく、ゲーム盤とコマをつかいますが、コマの置き方と攻撃・防御はバックギャモンのルールを上手にあしらっています。
そういえば、この記事の数日前に、テンデイズゲームズのタナカマさんがこんなツイートをしていましたね。
完全に見過ごしていたけど、クイックスデュエル、ダイスゲームだけどちゃんと二人用ならではの押し引きがあって面白い!最高に好み。 pic.twitter.com/Enxvb8Gqkk
— タナカ マコト (@tanakama) June 27, 2022
完全に見過ごしていたけど、クイックスデュエル、ダイスゲームだけどちゃんと二人用ならではの押し引きがあって面白い!最高に好み。
締め
ということで、補足の+β……って、これ補足?でした。
次回はちゃんと本編に戻る予定ですが、書いているひとがちゃんとしていないので、本当に予定です。
では。
