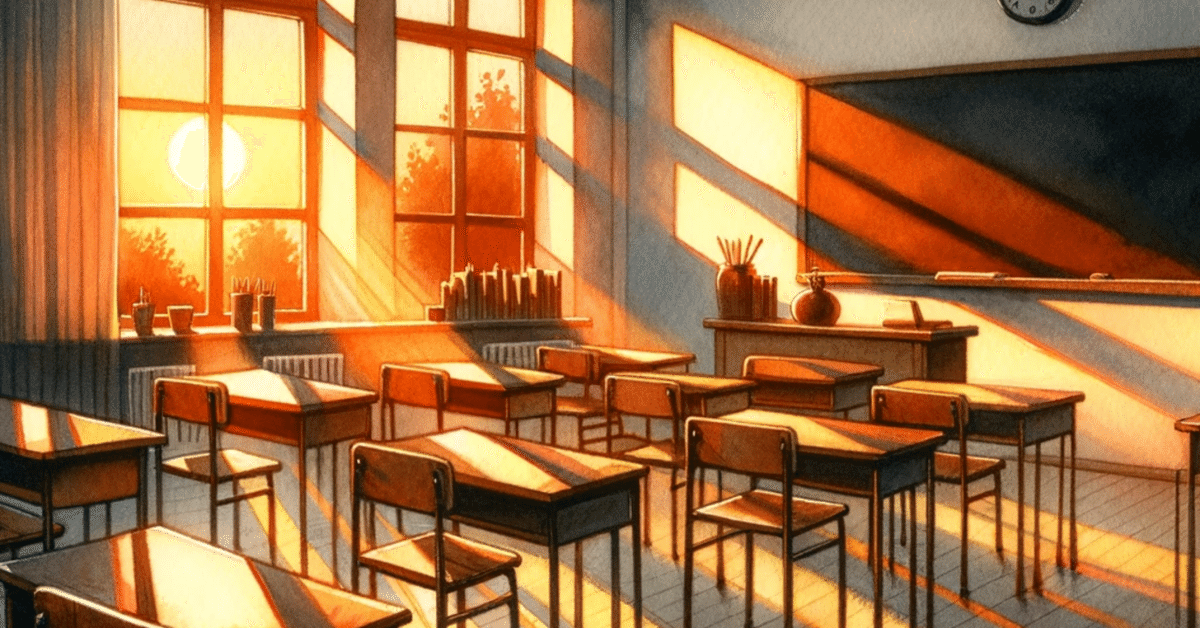
短編小説『青春、消息不明』
「実は、この前の文化祭の時から、俺お前のこと好きだったんだ。付き合ってください!」
「ごめんなさい!私なんか悟君にはもったいないと思うの。悟君にはもっと良い人がいるはず。だから私たちはずっと友達でいましょう?」
「そんなことないよ。俺はお前が好きなんだ!」
「ごめんなさい」
川上悟(かわかみさとる)、16歳。人生4回目の失恋だ。
通う生徒の男女割合が均等であるという理由で高校を選択し、経験はなかったが爽やかなイメージを抱かれるだろうという想定でサッカー部に所属し、楽器が出来ればギャップに惹かれるだろうという魂胆でピアノを練習しだした悟は、現在の高校生活に何を求めているのだろうか。
そう、"青春" である。
果たしてわざわざ行間を開けてまで『そう、"青春" である』などと溜める必要があったのか、これほどまでに分かりやすく青春を追い求める高校生が、まだこの日本に残っていた。
悟は入学以来、すでに3回の告白を、見事失敗に終わらせてきた。詳細は控えるが、3回とも勝機があるとは言えなかった。彼女がいなければ青春は成立しないという、なんとも哀れな危機感によって突き動かされた彼は、これといった戦略もなく、気になった異性にアプローチし続けた。
もちろんそんな空虚な恋愛は実を結ぶことなく、11月に入り4度目のチャレンジを迎えることとなった。改めて、今回の告白の模様を見てみよう。
「実は、この前の文化祭の時から、俺お前のこと好きだったんだ。付き合ってください!」
「ごめんなさい!私なんか悟君にはもったいないと思うの。悟君にはもっと良い人がいるはず。だから私たちはずっと友達でいましょう?」
「そんなことないよ。俺はお前が好きなんだ!」
「ごめんなさい」
どうやら先月行われた文化祭で一緒に構内を見て回り、その際に会話を交わしたらしい。所謂デートという過程を経ず、当たって砕けろの精神を垂れ流していた頃から成長し、なんとか二人で過ごす時間を設けることを覚えたようである。
しかしこれまでと同様、ひどい有様であることに変わりはない。
どうすればここまでテンプレート化したやり取りを繰り広げられるのか。悟は、「良い人が他にいるはずであるため自分たちは友達同士の関係を保とう」という、今後気まずい間柄にならないように配慮された、やんわりとした主張によって断られた。
失恋の場面が描かれる現代の小説において二度と登場しないだろうと思われるような会話が、本日ここ1年3組の教室に再現された。もはや才能であろう。何万回も擦られたシチュエーションを、自身の恋愛で現実にしてしまう、悟の才能であろう。
またもや掴み損ねた異性の背中を見送り、教室の窓から差し込む夕日に顔を赤らめた悟は、涙の一粒も落とさずにとぼとぼと学校を後にした。
「またダメだったな」
悟の失恋直後の落ち込み具合は、その回数を重ねるごとに浅くなりつつある。泣き崩れ、1日部屋から出てこないこともあった彼。この日は驚くべきことに、家までの1.5キロメートル程の道のりを歩いているうちに、ケロッと気持ちを回復させてしまった。
道中の公園で営業していた、サンドイッチを打っているキッチンカーに立ち寄った彼は、フルーツと生クリームがたっぷりと挟まったものを購入し、家に着くころには食べてしまっているという立ち直りぶりであった。
「ただいまー」
「おかえり。ちょっと遅かったじゃない。今日は部活ない日だったよねえ。なんかあったの?」
「ちょっと残って課題してたんだ。今日ご飯は?」
「今日は鮭焼いておひたしでもしようかな。ばあちゃんまたほうれん草持ってきてくれたから。あとは朝のお味噌汁かな」
「なんかもうちょっとないの?あんま魚食いたくないんだけど」
「今日は鮭で決まり。明日生姜焼きとかにしよ。先に風呂入っちゃいなさい」
「うん…」
川上由美子、42歳。悟の母親である。
この日由美子は悟が振られて帰ってきたことを完全に把握していた。
「あれ、そのお店って…」
由美子がそうつぶやく前に、悟はサンドイッチのフィルムをキッチン脇のごみ箱に捨て、足早に2階の自分の部屋へ消えた。
悟の第2回目の作戦はラブレターだった。徹夜で書き上げた恋文を、受け取ってさえもらえないという惨敗を経験した悟は、サンドイッチのごみと一緒にそのラブレターを捨てた。
由美子は妙に小奇麗な装飾のされた封筒と、生クリームのついたフィルムが同時に悟の手から捨てられる様子を横目で見て、「ああ、これは典型的なやけ食いだな」と、息子の心中を一寸の狂いもなく察した。
そんなふうにして悟の失恋は、第3回、そして本日の第4回も、由美子にはお見通しとなった。今回はただ小腹を埋めるために食べたサンドイッチであったわけだが、それでも由美子の読みに間違いはなかった。
そんなことを知りもしない悟は、自分の部屋に入りドアを閉めると、制服をベッドの上に脱ぎ捨て、椅子に勢いよく腰かけた。
そして深呼吸しながらいったん頭の中を空っぽにしたのち、今日の夕方、2人だけの空間となった教室を思い返してみた。
(なぜあんなことになったんだろう。イベントの後は付き合える可能性が高いって書いてあったのに。)
現代のような情報社会において、俗に言う"恋愛テクニック"なるものを発信するインフルエンサーが、その数を計り知れないほど存在している。
悟は片っ端から情報を取り入れ、実践できそうなものを即日決行してきた。「イベントの後は告白成功率が上がる」という女性アイドルの言葉を信じ切っていた彼にとって、今回の失敗は予想を大きく裏切る結果となった。
(もうネットの動画は全部見てしまった。これ以上俺に足りないテクニックはないはずじゃないか。リフティングも100回以上続けられるようになったし、ピアノも上手くなってきた。普通なら向こうから俺にアプローチしてきたっていいはずじゃないか。なぜいつも俺が話しかけて向こうから降られなくちゃならないんだ。
もう11月だ。陽太は6月に一人と付き合って、別れて、今はまた新しい彼女がいると言っていた。いよいよヤバくなってきた。どうすれば理想の青春を手に入れられるんだ。)
悟は一瞬考えることを止め、椅子に座ったまま回転した。デスクのペン立てから、夕日が沈みつつある窓に視線が映り、漫画がぎっしり詰まった本棚、制服が横たわるベッド、入ってきたときのドアと来て、再びデスクに戻ってきた。
悟はまた考える。
(そもそも青春ってなんなんだ?俺がやってきたことは本当に青春を謳歌するための努力だったのか?
俺にとって青春は思想の恋愛をすることだ。そのために色々やってきたんだ。ただ、なんだこの感じ。もし今日付き合えていたとしても理想の恋愛は実現していたんだろうか。俺はあいつのことが本当に好きだったのだろうか。)
悟は浮かび続ける青春、恋愛に関する疑問を、答えを出さないまま放置することにし、部屋着をテキトーにとって1階に降りていきシャワーを浴びた。
体の汗は流せたが、頭の中にこびりついた汚れを落とすには至らなかった。
その後キッチンに行った悟は、その晩するはずだった鮭を焼くときの臭いがないことに気が付いた。
「悟、もうお風呂入ったの?」
「母さん、今日の夜って鮭じゃなったの?」
「そうしようと思ってたんだけどねえ。冷蔵庫の中にもう使わないといけないひき肉があったから、今日は思い切ってハンバーグにしたのよ。悟ハンバーグ好きだったでしょ?」
「う、うん」
当然由美子の気遣いと知りもしない悟は、予想外のご馳走をガツガツと食した。デミグラスソースの味が口いっぱいに広がる。
「おいしい?」
「うん」
「もう高校生になって半年も経ったんだねえ。もうとっくに慣れたと思うけど。なんか楽しいことあった?」
「うん、まあ」
「そう、よかった」
由美子は悟の食いっぷりを見てそれほど落ち込んでいないことを見抜いた。あとは少し夜風に当たら去ればそれで済むだろうという、悟の単純な性
格を考慮したうえで、
「そうだ、悟。夜ごはん食べちゃったらお遣い行ってきてくれない?明日のお弁当と夜の分なんだけど」と提案した。
ちょうどそんな気分だった悟は、
「………おう、わかった」と口答えせずに母親の要求に応じた。
悟は夜ご飯を食べ終わり、手にはエコバックを、ポケットには由美子からもらった1000円札の入った財布を携帯し、家の外へと足を踏み出した。
住宅街の夜の静けさが彼を迎えた。遠くの街灯がほのかに光り、家々の間からは猫の気配や、遠くから漏れ聞こえてくる家族の笑い声が聞こえてきた。アスファルトの道を進むと、夜風が彼の体を包み込み、心地よい涼しさとともに頬をくすぐった。悟は深呼吸をし、その感覚を全身で感じ取りながらスーパーへの道のりを歩いた。
悟は家とスーパーの中間地点の辺りでふと立ち止まった。人の気配を感じたのだった。
住宅街にポツンと出現した空き地。1本だけ生えている大きな木が街灯の光を遮断し、奥のほうが暗闇となっていた。悟はその闇を凝視していたが、いよいよ気になって空き地に足を踏み入れた。
「こんなところで何をしてるんだ?」
声がした。
暗闇に目が慣れてくるにつれて、木の下から徐々に人の姿を捉えることができた。20代後半くらいの男が、コンクリートブロックの上に座っていた。
悟は少し戸惑いながら答えた。
「あ、いえ…なんとなくこちらの方に気が向いて」
「へえ、そうか。僕と…だいたい同じだね」
男の瞳が月明かりに照らされてかすかに光った。表情までは読み取れずにいた。
「あなたはこんなところで何をしているんですか?」
「だから言ったじゃないか。君と同じように、なんとなく静かなところで考え事をしてたのさ」
「そうだったんですね。……あの、少しお話させていただいてもいいですか?」
悟は初めて出会ったはずの男に心を許し始めていた。正体不明の親近感に包まれ、「この男になら何でも打ち明けられる」とさえ思った。
「あの、実は俺恋愛で悩んでて」
「恋愛………君は今何歳なんだい?」
「16です」
「高校…1年生?」
「はいそうです」
「そっか。それで?」
「それで、恋愛のことなんですけど、俺今日気になってた人に振られてしまったんです。今日が初めてじゃなくて、今まで3回失敗してきたんです。俺、高校入って、女子と付き合うために色々やってきたんですよ。でもなんかずっとうまくいかなくて」
「君は女の子と付き合って何がしたいの?」
「そりゃ色々やりたいことはありますよ。というか、そもそも何がしたいとか考える以前に、付き合わなきゃ意味ないじゃないですか。俺、どうしたらいいんでしょう」
「君、何か履き違えている気がするね」
「えっ………?」
悟は、それまで優しかった男の語気が急に強くなったため、少し後ずさった。
「ちょっと腰を下ろすんだ」
「はい……」
悟はこれから何を言われるのか不安になりながらも、男の言葉を全力で受け止めるつもりでいた。
「君にとって恋愛ってどういうものなんだい?」
「それは………あっ、そうだ、青春ですよ!俺、青春を求めて高校に入ったんです。理想の青春を手に入れるには、理想の恋愛をしなくちゃいけないんです」
「なるほどね…やはり君は少し勘違いをしているようだ。ちゃんと聴いてくれるかい?」
「はい!」
男はコンクリートブロックから降り、少し姿勢を変え、地面に足を組んで楽に座った。
「そもそも僕は『恋愛』という言葉自体が気に食わないんだ」
「えっ?どういうことですか?」
「君は今日振られた女の子に、最初どんなことを思った?」
「え、なんか、好きだなー、みたいな」
「その前は?」
「その前?」
「その人のことをもっと知ってみたいとは思わなかったかい?まさか名前すら知らない相手に告白したわけじゃないんだろう?」
「あっ、はい。思いました」
「恋愛って難しく考えがちだけど、結局3つくらいしかすることってないんだよ」
「3つ、ですか?」
「そうだ、3つだ。今僕が言ったように『相手のことを知りたいと思う』のが一つ目、そして君が言った『相手のことが好きになる』のが2つ目だ」
「じゃあ、3つ目は…」
「『楽しむこと』さ」
「楽しむ?楽しむって……そんなことで良いんですか?」
「順を追って説明しよう」
男の口調はさらに真剣になった。夜の静寂の中に、ピンと張り詰めたような緊張感が生まれ、悟は息を呑んでゆっくりと3回まばたきをした。
「さっき『恋愛』って言葉が気に食わないって言ったろう。一緒に過ごす男女の関係なんてとてもシンプルで、『知り、好きになり、楽しむ』という、これもさっき言った3つのみで良いと思うんだ。これ以上の装飾を施すと、逆にロマンチックさのかけらもないほど醜い概念になってしまう。
知って好きになるまでの段階を、どこかの頭の悪い誰かが、最も脳死的で、そして冷酷に、『ああ、ロマンチックだな』、などと軽い気持ちで、最も簡略化した言葉を用いて言い換えたのが『恋』だ。
そして、楽しむ気持ちを、これまた頭の悪い誰かが、『そういえばこんな言葉もあるのではないか』と、全く洗練されていない言い分で、大雑把に、荒削りな言葉で、これまた脳死的な言葉を用いて言い換えたのが『愛』。
極めつけは、もう救いようのないほど頭のイカれた誰かが、この一連の流れのことを、『ああ、なら合わせてしまえばいいのでは』と、目も当てられぬほどの残酷な考えで持って、生み出された可哀想な言葉が、現在の『恋愛』として日本にはびこっているんだ」
「はあ?なんですかいきなり。そんなこと、言わなくてもいいじゃないですか!」
悟は思わず反論した。
「じゃあ順を追って説明していこう。
まずはその人のことを知りたいと思う。この段階で、身長が高いとか、顔が整っているとか、勉強ができるとか、料理ができるとか、性格が優しいとか云々の、その人の、まるで雨の日にできた水溜りほどの浅い部分だけが目につくようであれば、その人との恋愛関係を結びたいと思う権利すらない。その人について、深海の光が届かなくなる部分まで知ろうという、愚直なまでに強い思いがない限り、恋愛のスターラインに立てすらしない。
そして、知っていくうちにその人のことが好きだと認識する。
自分がその人のことが本当に好きだと確認するためには、相手が、双方の人生を棒に振るような大犯罪を犯したり、自分の親族に想像を絶するような罵詈雑言を浴びせたり、極めつけは、相手が自分を殺そうとしているとしても、それでも自分はその人を許せるかというところだ。
その人の何もかもを許してしまうほどの心持ちが好きというもので、それがなぜ許せてしまうのかということは別に重要なことではない。そして、それができないかもしれないと思ったら、残念ながら、その人に感じたささやかなトキメキは、単なる性欲だ。その人との関係は、良くてその欲を処理し合うだけの関係で終わるだろう。本当に好きであればその想いを相手に伝え、いよいよ3つ目に移るんだ」
悟はもう喋らなかった。
「最後に、楽しむことだ。
楽しむというのは、一緒になった二人を取り巻く状況がどう転ぼうとも、そしてその状況に対応できても、対応できなくても、極論、どちらかが、記憶喪失で何もかもの思い出を放棄したり、はたまたどちらかが、絶対に目覚めることがない植物状態に陥ったりしても、それでも諦めることなく、その人のことを念頭に置いて力強く日々を生き抜いて行けるという、固い意志のことなんだ。その意志がない者は、完全に意気消沈したり、別れた瞬間に他の人に助けを求めたりする。そして、そうなってしまう者は、それまでの時間を全く楽しんではいなかった。楽しんでいなかったということは、実はその人のことを全く好きではなかったのであり、知りたくもなかったということなんだ。
君の言う恋愛は、この一連の流れを全く意識されることなく、ただ淡々と、「ずっと好き同士でいたい」とか、「距離が離れても心は繋がっている」とか、「付き合ったから、もっと君のことを知ってみたい」とか、「一緒にいなくても好きであることに変わりはない」とか、「二人で一生生き抜いていく」とか、順番がバラバラだったり、とぎれとぎれだったり、支離滅裂だったりな言葉達が日々吐き捨てられるような、現在の、所々が腐敗した不純な恋愛のことを言うんだろう。
そんなことじゃ理想の恋愛、理想の青春なんて手に入れられるわけがないじゃないか」
男は立ち上がり、空っぽになった悟を一瞥して歩き出した。
「今夜はいっぱい話せて楽しかったね。またいつでもおいでよ。フルーツサンド、安くしとくからさ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
