
散歩と雑学と読書ノート

最近一か月ほどの間で、散歩の途中に私は3回ソーレ君に出会った。ソーレ君というのはソーレと鳴くカラスのことである。6~7年ほど前に家内に教えられて我が家の近くでその鳴き声を聞いて以来、私はずっとソーレ君の声を聞くことを楽しみにしている。ソーレ君は私と家内にとってのアイドルである。そのソーレ君に関して少し書かせていただきたい。
まず、以前に勤務していた病院の広報誌に書いたソーレ君の記事を引用させていただくことにする。
★ 「カラスの常識」 柴田佳秀 子どもの未来社 2007,2
最近、また我が家の近くに、「ソーレ、ソーレ」と鳴くカラスが出没している。何度も確認しているので、カラスに間違いない。カラスがどう鳴こうと、カラスの勝手かもしれないが、この常識から逸脱した鳴き声がどうにも気になって、私は「カラスの常識」という本を買ってみた。それによると、カラスの鳴き声には30通り以上もあり、その鳴き声の意味も少しは分かっているという。「カアーカアー」と大きく鳴くのは警戒を表わし、「カカカカ」で仲間が集まるという。またカラスはオームのように人の声を真似することができるのだそうだ。そう言われれば確かに以前、「あほーあほー」と鳴くカラスがいたことを思い出した。コケコッコーと鳴くカラスの報告もあるという。ソーレと鳴いても騒ぐことではなさそうだ。
ところで、鳥の歌声と人間の言葉の進化を関連づけて研究している岡ノ谷一夫先生によると、新しい音声を学習できるのは、鳥とクジラと人間だけだろうとのことである。
ともあれ、私はソーレと鳴く彼(彼女?)の声を聞くと、すこし心が高揚し、元気になれるのである。ソーレ!
(H27,4)

私がソーレ君の声を聞いたことがあるのは、我が家から歩いて3~40分程度の距離を半径にした円に収まる範囲内で、主に街中である。
元気で生きている様子なので、余計なおせっかいながら、私はソーレと鳴くことで他のカラスからいじめにあったり、無視(シカト)されたりしないのだろうか、そもそも他のカラスとの対話はどのようにしているのだろうか、ソーレ君はカラス語がわかっているのだろうか、それともカアーと鳴くこともできるのだろうか等といろいろな心配をしたり疑問を感じたりしている。
以前にソーレ君がつがいと思われるカラスと電線に並んで、ソーレと叫んでいるところを見つけて、ソーレ君が孤独な生活を送っているのではないことを知ってほっとした気分を味わった。だからと言って先に述べた心配や疑問が完全に解消されたわけではない。むしろどうやってつがいのカラスと知り合ったのだろう、どうやってつがいとコミュニケーションを図っているのだろうと相変わらず余計な心配や疑問を深めている。
カラスの生活の基本は夫婦(つがい)だそうで、ねぐらの森に帰る時も二羽ずつ帰るのがカラスの常識だそうだ。ついでに、ねぐらには童謡に歌われるような「かわいい七つの子」が待っているのではなく子育ての巣は別なところに作っている。成鳥のねぐらは特定の森で、東京都心には明治神宮など三か所しかないという。ねぐらの森では時には一万羽近くのカラスが大集団で寝るのだそうだが、何故そうするのかは分かっていないようだ、
***
「読書ノート」
「おしゃべりな脳の研究
内言・聴声・対話的思考」チャールズ・ファニーハフ、 2022、みすず書房
私がカラスの鳴き声に関心を持つのは、精神科医としてずっと人間の声や対話能力に関心を持ってきたことが影響しているからだと言ってもよい。
今回取り上げる本は、ひとの「声」が脳の中でいかに多彩な活動をしているかを示す研究の報告である。筆者はイギリスのダラム大学心理学教授、専門は発達心理学である。脳内で自分と話す内言や幻聴(本書では聴声とも訳されている)などを研究してそれらを思考や意識と関連づける試みをしたり、ヴィゴツキーの「対話的思考」との関連性を考察している。
内言に関する科学的な研究が急速に進展しだしたのは最近のことである。
本書では、通常の内言をはじめ、子供が普通の会話である外言の体験から私的発話(ひとりごと)の時期を経て内言を発達させていく過程やスポーツ選手のセルフトーク、ろう者の内言、小説家の創作場面やその小説を黙読している場合など脳の中で自分や他の「声」が入り乱れてどのように活動しているか興味深い記述がなされている。
内言を脳の中の声と表現するのはヴィゴツキーやバフチンの影響と思われる。私はバフチンが好きで内言としての声に関心を持ち、特にその対話性を重視して考えてみていたので、本書の主張には馴染みやすさを感じている。しかし、本書のなかで、本来は音声の伴わない内言を声と表現することで、この場合は音声を伴っているのだろうかと紛らわしく感じる記述も見られるのが気になった。
それとは別に、もっとはっきりと、内言が音声化して明らかに音声を伴うが病的とは見なせない声(聴声)を体験する報告があると本書では述べられている。私はこの内言の音声化に強く興味を感じている。その機序がどうなっているのか、その声が自分の声と同じなのか違うのかと言ったことに関心がある。
聴声には正常とみなせるものと病的なものとがある。正常と主張される代表的なものに、ヒヤリング・ヴォイシズ・ムーブメントの参加者の体験がある。本書によると体験している聴声を内言に由来しているという見方をすることに当事者からはあまり賛同を得られず、トラウマ的な記憶に関連しているという主張がみられるとのことである。
病的なものとみなされている代表的なものに統合失調症の幻聴(聴声)がある。本著で触れられているように、幻聴を内言に由来しているという見方を導入して考えてみることは極めて有意義なことである。特に幻聴の脳内機構に関しては不明な部分が多いので、内言ネットワークの脳内機構をめぐる研究は重要な手掛かりになるかもしれない。
幻聴がいわば出所を誤認された内言だとしても、以下のような疑問がただちに生じる。
先にも述べたように、内言がどうして音声化してしまうのか、また幻聴の内容には内言とは思われない奇異なものが含まれることがあるがそれをどう考え位置づけるのか、幻聴の体験をしながら、正常な内言も体験しているのが普通である、その差異はどこから来るのか、さらに記憶との関連に関してももうすこし説明が必要であろう。
今日の内言や幻聴に関する研究では、PETやfMRIなどの脳画像が重要な役割を果たしている。
著者はそのような研究の中で、特に通常の言語は左脳のブローカ野やウェルニッケ野が関連して生じるが、幻聴体験者では右脳の言語関連領域の活性化がみられるという研究があることに注目している。また内言ネットワークではウェルニッケ野の活性が弱まるのだが幻聴体験者では弱まらなかったことやまた幻聴体験者では補足運動野の活性をみると内言体験者よりも反応が弱かったことに注目している。補足運動野は自己が行った行為をモニタリングしている。その活性が弱いことは幻聴が自己ではなく他者の言語行為と受け止められることに関係しているかもしれない。
通常の内言の特徴として筆者は対話的、凝縮、他者、評価的の4項目を挙げている。
対話的というのは、「自分の内言は異なる視点どうしの会話の形をとっている」と感じる度合いと関連している。凝縮というのは、内言の声が意味の圧縮されたものとして体験されたり、文が省略されたものとして体験される場合で、そのために内言は通常の発話の10倍近く早く心をよぎるという意見を述べる人もいる。もちろん完全な形の(外言と同じような)文による会話として体験されることもある。他者というのは内言にほかの人の声が出てくる場合で、少数派(ある研究では回答の約四分の一であった)ではある。「頭の中で、ほかの人の声が自分にうるさく小言を言うのが聞こえる」と述べる人がいたという。評価的としたのは、内言には自分のしていることを評価してやる気を高めることがあると答える度合いに関連している。
以上の内言の特徴は、統合失調症の幻聴を考えようとする際に極めて示唆的である。
***
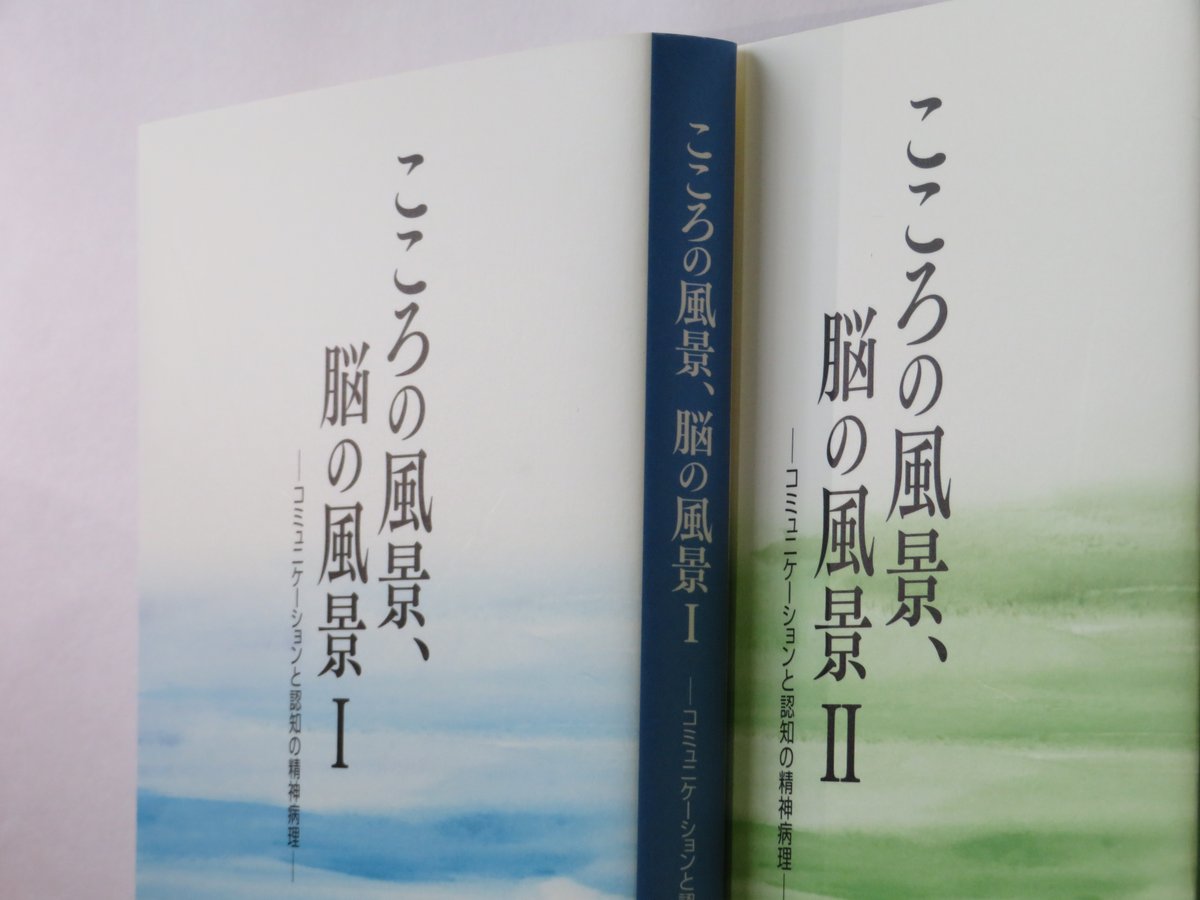
「こころの風景、脳の風景―コミュニケーションと認知の精神病理―Ⅰ、Ⅱ」より
今回から3回に分けて「幻覚をめぐる覚書ー知覚もつれー」を掲載させていただこうと思う。この論文は私にとっては大切なもので力を入れて書いたつもりだが、論考が不十分で未熟なてんも多く、今回変更や加筆を試みたが不満足なままである。内容も専門的すぎる上に、最近は専門家もあまり関心を示さない領域のものである。専門誌に投稿したものでもないので、独りよがりのものになっている可能性が高い、読みずらいものだが、お読みいただき、ご批判いただけたら幸いである。
幻覚をめぐる覚書―知覚もつれー (1)
1.はじめに
アンリ・エーは大著「幻覚」の序言を次のように書き始めている。
「著者が精神医学に接し始めた当初から、知覚の奇跡を顕すあの神秘的なもの、すなわち幻覚に魅了されてしまった。精神病理学の要となっているのがこの幻覚である。なぜなら、精神医学の知が答えるべき問題のすべてが秩序づけられているのは、この幻覚に準拠することによってなのであるから」
自分をアンリ・エーに重ね合わせるのは、なんとも恐れ多いことだが、私も幻覚に魅了された精神科医の一人である。私は以前、砂川市立病院誌(砂医誌)に同僚と、統合失調症やアルコール依存症およびレビー小体型認知症の幻覚に関連した論文を三篇投稿した。この覚書では、それぞれの論文に記載した幻覚の集計結果と、いくつかの問題提起をまとめて記載しておきたい。さらにこれまで幻覚をめぐってなされてきた議論を少し振り返りながら、幻覚の脳内機序を含め、私なりの幻覚に関する考えを覚書として書かせてもらおうと思う。
2.幻覚をめぐる問題点の所在
幻覚をめぐって私が関心を持った問題点をここであらかじめ簡単に述べておきたい。私は二つの点をめぐって考えてみた。近年幻覚を妄想よりに解釈したり、非知覚的な要素が強調される傾向がみられるが、できる限り幻覚を知覚よりの現象と理解して考えてみようと試みたことが一つである。もう一つは幻覚が対象なき知覚ではなく、その対象が脳内で作られ、それが外部に定位されると考えてみようとしたことである。
幻覚(特に言語性幻聴)を思考由来と捉える見方が現在は主流であると言ってもよいだろう。幻覚は知覚よりも思考に近いもの、つまり妄想に近いものと見られている。ここではその代表的な論考として中安信夫が「分裂病症候群」の中で述べている「背景思考の聴覚化」という見方を取り上げさせていただきたい。
中安は、自らが広範囲な統合失調症状を思考由来と考える根拠を次のようにドイツや、フランスでの理論的な展開に見いだしている。まずドイツ記述学派のシュレーダーが感覚性を幻覚の一時的標識から外して、自己所属感の障害によって生じた無縁性(他者所属性)に着目し、幻声(幻聴)を始め、自動思考、考想化声、思考奪取、作為体験などを共通の無縁的な思考に由来するとしたこと。またフランス精神医学では、感覚性が乏しく、そのぶん言語の領域に近い精神幻覚が精神感覚幻覚より重視されて、付随意的で非論理的にうごめく意識下の内的思考が意識化されて、幻声をはじめとする統合失調症の症状を顕現するとしたことを取りあげている。また幻覚の発生論として自動症が注目された。そして、その一つの極にクレランボーの精神自動症があることを中安は指摘している。中安はさらにフランス学派に影響された、西丸四方の「背景的思考の前景化」という考えに同調して「背景思考の聴覚化」という理論を提出したことを述べている。
私はこの思考由来という認識を必ずしも否定しようとは思わない。特に「背景思考」や「無縁的な思考」を内言に結びつけて検討してみたいと最近は考えている。もっとも、内言が何処まで思考なのかという問題はあるかもしれない。いずれにせよ、私は幻覚を思考よりとするよりは、知覚よりの現象としてまず捉えておきたいと考えている。中安の議論で言うと背景思考よりは聴覚化という現象にウエイトをおいてみておきたいと思う。このことは、幻覚という現象を考えてみるうえで特別強調するまでもない常識的な前提であると私は思っている。
幻覚を知覚よりに理解すると述べたが、この際の知覚は普通の知覚とは必ずしも同じではない。たとえば普通よりも強い強度を持ったものとして知覚されたり、幻聴の場合は音声が不明瞭であったり、言葉が凝縮されていて意味だけが過剰に知覚されるなど、普通とは少し異なる性質を帯びて知覚している場合がみられることを指摘しておきたい。もちろん普通の知覚と同じだと述べる患者が結構いることも併記しておきたい。
幻覚の定義で「対象なき知覚」という簡潔な定義がある。妄想よりの幻覚の理解では批判的に受けとめられる定義であるが、私は不十分だが悪くない定義だと思う。
「対象なき知覚」を念頭におきながら、私は一つの仮説として、知覚すべき対象がないのではなく対象は脳の中で作られていると考えてみた。つまり対象は外部にはないが脳内で作られるのだと理解するのである。この理解そのものはさほど無理のあるものとは思えない。しかしその際に患者の脳内に作られた幻覚が実際には脳の外部に知覚されてしまうのはなぜかという疑問が生じる。患者が幻覚を少なくとも一種の知覚性を帯びて、幻覚の対象を作った脳のその場ではない外部に成立していると体験していることは、私には幻覚を思考よりの妄想的な体験だとする見方との差異を何より明らかに示すものだと思う。なお患者の中で、幻聴が頭の中で聞こえると述べることがあるがその際の頭の中というのは漠然としていて脳神経系の特定の部位を、例えば言語野を指示するものではないことはいうまでもない。
普通の知覚においても、特に聴覚や視覚のようないわゆる遠隔知覚は、外部からの感覚刺激がいったん脳内で処理されたあと、実際の知覚は外部の刺激発生源にほぼ瞬時に定位され成立する。その際に起きている現象を考えてみると奇妙なことに、脳から外部へのはたきかけがなされたという確たる証拠は見だせない。身体の内部での知覚もこのてんは同じである。この現象を脳科学の先人、チャールズ・シェリントンは投影性(projicience )と呼んだ。しかし、シェリントン以来その現象を科学的にどう解釈し理解するかに関する説得力のある説明はまったくなされてこなかった。この現象をどう捉えるかは、感覚刺激の発生源でもない身体の外部や内部に定位して体験される幻覚をどう考察すかという課題にとっても重要な事柄である。
ただし、一つの可能性として幻覚に関してはそれが外部に位置づけられるというのは、患者の抱く妄想あるいは錯覚だとする見方があるかもしれない。それならば幻覚を思考由来というよりも思考そのものとする認識が成立するかもしれない。しかし、それは患者の報告をあまりに無視した言い方だと私は思うし、かりにそうだと仮定してもその妄想的な外部性と通常の外部知覚の違いををどう理解するか説明する必要は残るだろう。何よりも通常の外部知覚の脳科学的説明は問題として残ったままである。通常の知覚という現象は脳の処理されたその場で成立したり、脳の中に思考として閉じ込められたりしていない。外部に成立する通常の知覚も妄想なのだろうか。このてんは後ほどまた触れてみたい。
私はこの脳から外部へと向けられる作用が不明なままにほぼ瞬時に成立する投影という知覚現象を、いささか大げさだが、量子論でいう「量子もつれ」という現象になぞらえて、「知覚もつれ」というメタファーで呼んでおきたいと思う。その具体的な説明は「知覚もつれ」とした節で幻覚(特に幻聴と幻視)成立の脳内機構と合わせて少しふれてみようと思う。しかし難しい問題なので、今述べたような問題提起以上の考察はなかなか困難である。私は仮説的な説明をすこし試みてみたが奇異に感じられるだけかもしれない。しかしこの問題は脳科学の中であえて言えば、クオリアと同様に重要なハードプロブレムと言えるだろうと私は考えている。
3.幻覚をめぐるこれまでの私の論文のまとめ
ここでは、私がこれまで書いてきた幻覚をめぐる論文の主な内容をのべておきたい。なお幻聴を幻声と記載してあるときもあるが同じものと理解していただきたい。
(1)幻聴に関して
「幻聴に関する臨床的研究」(砂医誌、1999年)の中での主な結果と考察部分を多少補足しながら記しておきたい。
対象は、50名の患者で、男性24名(平均年齢38.6歳)、女性26名(平均年齢46.6歳)である。2名のアルコール依存症と2名の覚醒剤中毒以外は統合失調症圏内の患者で、私が主治医としてすべての患者に関りを持っていて、直接確認できた幻聴の体験に関して集計したものである。病気の経過年数は1年から40年以上で、私が主治医であった期間も3か月から18年にわたっている。なおアルコール依存症と覚醒剤中毒の患者の幻聴は統合失調症の幻聴と鑑別が困難なものであった。しかしこの小論では統合失調症の特徴を述べる際の数字は()内に記入したものとして受け止めていただきたい。ただし4名の数値を加えてみても統合失調症の特徴に関しては差異がないとみなしてよいものであった。
集計の項目は幻声の空間定位、幻声の主、幻声との対話性、幻声の内容面に関することである。
空間定位では身体の中とした者が20(18)名(頭の中が16名)、身体外が30(26)名(耳元が21名、近くからが10名、遠くからが19名)両方からが14(12)名であった。また身体から遠ざかるほど幻声の切迫感も減弱するようであった。この空間定位に関しては頭の中を含めて、耳の中、腹、胸部など身体の中からといういわば域外幻覚が意外と多くみられた。また、遠くから聞こえるという訴えのなかに、聴覚的に見て本来は聞き取れないと思われる域外幻覚があった。今回は極端なものはなかったが以前に私は、何キロも上空から声が聞こえるとか、スイスの産婦人科の医師の屋根裏部屋からマグナカルタと聞こえたと妄想的な認識が加わっていると考えられる域外幻覚を述べる患者に出会ったことがある。
ところで、1996年に、われわれと同様な幻覚の集計報告がなされた。
T.Nayami&AS Dauidによるもので、100例(うち61例が統合失調症)の患者からの三か月以内の幻聴に関する半構成的面接による調査である。その報告によると、38%が身体内部からの域外幻覚で、身体外部が49%その両方が12%であった。やはり域外幻覚が多くみられている。なお頭の場合は前頭部の中央に聞こえるとするものが多かったというが、我々の集計ではそこまで特定して聞き出せてはいなかった。
幻声の主では、自分の声が2名、知人の声が19(17)名で未知の声が27(24)名、その両方が10(8)名であった。また男の声36(33)名、女の声27(25)名、その両方25(23)名で、男性の声がやや多い傾向であった。先に触れた、T・Nayamiらの集計でも男性の声のほうが多かったとされている。なお物音にまじって聴こえるが5名いた。自分の声としたものが2名と少なかったが、思考化声のように自己の声で聞こえるのが当然かと思われる幻声も他者性を帯びていて、幻聴の声は他者性を帯びたものであると言われることを支持する結果であった。それにしてもなぜ他者性なのだろうか。また統合失調症では未知の声が一般的と考えられているが知人の声も意外と多くみられた。また知人と未知の声の両方を体験したとするものが10(8)名いた。統合失調症は未知の声の幻聴が主だとすることには私は少し疑問を感じている。
声との対話可能性に関しては、声と直接対話するが32(29)名、声同志の対話が20(16)名、その両方ともが19(16)名で、声同志の対話のみとしたものは1(0)名(覚醒剤中毒)だけであった。明らかに幻声と直接会話するケースが多くみられた。なお対話にならないが17名であった。
この対話性に関連して、1982年に中山や柏瀬によって、シュナイダーの一級症状のなかの「問答式の幻聴」が、日本では「患者に話しかけ、患者に応答する幻聴」と理解されているが、欧米では「声同志が話し合っている幻聴」と解釈されているという指摘がなされた。その後、翻訳の問題も含めて少し論争が繰り広げられた。論争の結果に関して私はしっかりと把握できていないが、結論としては声同志が話し合うという認識の方が優勢であったかと思う。シュナイダーの記載や翻訳の問題からは少し距離をおいてみておきたいのだが、私は今回の集計から、両方のパターンがあるとみるべきだと考える。しかし集計結果から見て、患者に話しかける幻聴の方が明らかに優位に多く体験されるものだろうと私は理解している。なお、あくまでも私の印象に過ぎないが、声同志が話し合っている幻聴は症状性及び器質性の精神病に多く見られるのではないかと思う。
内容に関して把握できた限りで、音楽が聞こえるが5名、思考化声が10名で、自分の行為を批評したり命令する内容が27名と半数以上に見られた。また良い内容が8名に対し悪い内容としたものが26名と多かった。思考化声が10名にみられたが、もし思考が幻聴の由来であるならばもう少し多くても良いのではあるまいか。もちろん思考と幻聴の関連を否定するものではない。ただし思考の範疇をどう捉えるかをふくめて「思考と言語」の関連はもう少し検討してみる必要があると思う。このてんは、後でも少し触れてみたい。なお幻聴が書き言葉で聞こえるとしたものは今回はみられなかったがもともと極めてまれで、ほとんどが話し言葉であることは、何故だろうかという疑問と共に特記しておいてよいことと私は考える。
(2)幻視に関して
次に幻視についてふれておきたい。私はアルコール依存症とレビー小体型認知症の幻視に注目している。特にその両者で幻視の内容上の違いがありそうだということに関心をもった。
まず「アルコール症患者の離脱症候に関する臨床的研究」(砂医誌、1986)では、アルコール依存症の離脱期に見られる幻覚について述べている。離脱期とした中には振戦せん妄以外の状態も含めている。ここでは30名の患者から聞き取った幻覚の体験を類型化したものを述べてみる。
幻視や錯視では、虫や動物が15名と半数の患者に出現していた。人物が見えるとしたものが9名、ある光景がパノラマのように見えたものが8名、その他(車など)3名であった。また幻聴や錯聴では人の声が13名、音楽が3名、その他(電話の音、車の音、動物の声)が5名であった。また幻臭が2名、体感幻覚が3名にみられた。
通常、アルコール依存症でみられる幻覚は、鮮やかな幻視が中心で、多くは虫や動物の幻視であると述べられるのが教科書的である。また幻聴に関しては、離脱期の初期に見られることがあるが多くはないこと、またアルコール幻覚症では幻聴が主体で、統合失調症との鑑別が困難なケースもあるといわれる。今回の我々の集計でも確かに幻視が多かったが、幻聴も13名と思いのほか多くの患者が体験していることが分かった。しかし、この幻聴の体験は、短い言葉であったり、複数の人の声がするといった程度で、長く続いてもいないし幻視のように鮮やかで複雑なものではなかった。やはり教科書的な記載どおり、離脱期の幻覚の中核は幻視であり、しかも虫や動物の幻視が多くみられた。しかし、人物の幻視も9名にみられており、振戦せん妄の最中に幻聴が生じることもあるなど、アルコール症の離脱期の幻覚はなかなか多彩である。
次に「レヴィー小体型認知症と幻覚」(砂医誌、2005)に関して簡単にふれておきたい。今回のわれわれの報告は5症例という少ない症例数なので、断定的なことはまったく述べられないが、この病では鮮やかで、しかも長く続く幻視が多く、虫や動物の幻視もみられるが、特に人物の幻視が中心なのだろうというのが本書に載せた「レビー小体型認知症と幻覚」のなかでの、私の見通しであった。
この論文には付記として、近年の報告では私の見通しどおり、明らかに人物の幻視が多いとされていることにふれた。ここでもそれを付記しておく。
アルコール依存症の離脱期と比較することは、意識レベルの違いもあり、的確ではないかもしれないが、私は両方の病では、幻視で見えてくるものに、虫、動物と人物との間に頻度の違いがあることに関心がある。細かい話であるかもしれないが、病の脳内での障害のあり方に違いがあると言えるのではあるまいか。このてんに関しては、後でもう一度ふれてみる予定である。
付記
レヴィ小体型認知症の幻視をめぐっての近年の報告では、筆者が予想した通り、幻視の内容は人物であることが圧倒的に多く、アルコール依存症との差異があるものと思われる。
①「Brain and Nerve」第70巻、第8号、2018年8月、西尾慶之「レヴィ小体型認知症の視覚障害と錯知覚」の中での記載を引用させてもらう(P892~893)
DLBの幻視の内容は圧倒的に人が多く、80%以上の患者において認められる。…幻の人物の像が隅々にわたって明瞭であることは稀で、顔がはっきり見えなかったり、脚がみえなかったりすることが多い。…患者は幻の人物について「知らない人」「おそらく近所の人」といった暖味な叙述をする場合が多い。幻の人物は無言である場合が多いが、20~40%の患者は幻視の人物が「話をする」と報告する。動物や物体を内容とする幻視も比較的多く、それぞれ40%、20%程度の患者において認められる。…DLBの幻視は無治療であれば年単位で繰り返し出現する
(アルコール依存症や中脳幻覚症やてんかんなど他の疾患による幻覚症候群では数分から数日せいぜい一ヶ月程度で消滅する点に大きな違いがある)
②「レビー小体型認知症」井関栄三/編著(2014年発行)より改変して引用(P26)
(表3の中で145名の患者が示した精神症状の出現頻度を人数(%)で示している、表中の幻覚および関連症状の項目をここでは引用させてもらう。ここでの資料でも人物の幻視が圧倒的に多く、アルコール依存症の振戦せん妄の虫や動物の多さとは対照的である)
人物の幻視 92名(66.9%)
動物・虫の幻視 44名(30.3%)
物体の幻視 35名(24.1%)
要素的幻視 10名( 6.9%)
実体的意識性 40名(27.6%)
幻聴 9名( 6.2%)
体感幻覚 3名( 2.1%)
3.これまでの幻覚論をめぐって
(1)エスキロールの幻覚論について
現代的な幻覚についての考察の出発点は、エスキロールの幻覚論にある。アンリ―-・エーはそのように指摘し、つねにそこに立ち戻ってみることをすすめている。ここではまずエスキロールの書いた「幻覚」論の中から、いくつかの文を引用してみる。
「ある人物がある感覚を実際に知覚しているという内的確信を持ち、その時この感覚を引き起こす適当な外的対象が彼の諸感覚の射程内に存在しない場合、この人物は幻覚状態にある」
「幻覚の現象は、デリーㇽにある人が諸感覚を、発病以前に知覚していたと同じようには、そして他の人々がそれを知覚するのと同じようには知覚しない場合に起こること錯覚には少しも似ていない。…幻覚においては、感覚も知覚も存在せず夢や夢遊病におけると同様であり、したがって外的対象が諸感覚に作用することはないのである。」
「幻覚とは、デリーㇽの一症状にすぎず…」
(以上は濱中らによるエスキロールの「幻覚」の訳、次の文は大橋博司の論文「19世紀以降における幻覚概念」より引用)
「幻覚においてはすべてが脳内で生じる。幻覚は、記憶が感覚の介入なしに再生される心像、観念に実在性、現実性を与える……。錯覚においては逆に、神経末端の感覚性が変化し、減弱し、倒錯する」(文中に挿入されたフランス語は省略した)
エスキロールは、幻覚を脳内で生じるものであるとし、ある人物がある感覚を実際に知覚していると確信していて、その感覚を引き起こす外的な対象が存在しない場合にその人は幻覚状態にあるとすると述べ、それは錯覚とはまったく異なるものであると述べている。また幻覚は発病以前の知覚と同じようには知覚されないとしているが、このことで「対象なき知覚」という認識を否定するものだはないと私はうけとめたい。
ところで大橋は「対象なき知覚」という言葉をエスキロールの「幻覚」の項には発見できない。バールに由来されるともいわれるが、エーによるとそれよりもずっと遡るものとしているという。なおエーは「知覚すべき対象なき知覚」という言い方を用いている。
エスキロールは幻覚をデリールの一症状としている。このデリール(Delire)という言葉は、多義的で、妄想と訳されることもあり、大橋は先に引用した論文の中で「幻覚とは本来「妄想」delireなのである。彼(エスキロール)にとってはhallucinatonとdelireとは同義語とも言えよう」と述べている。しかし、私はそのてんには違和感を覚える。次に述べる影山の説明をうけてこの場合の「デリール」は「精神病」としておきたいと思う。
エーの「幻覚」Ⅰの中の訳注で影山はデリーㇽの原義がラテン語の「溝から外れた状態」であり、後に転じて常軌を逸した、狂気、理性の狂い一般を指すようになったものである。と述べ、日本語の概念としては「精神病」に一番近いとしている。影山はピネル、エスキロールの時代のデリーㇽは、現代における用語法の古層をなすもので、意識障害発見以前の精神病の本質と見なされ、時には精神病と同義でもあった、としている。
以上のことからエスキロールのいう幻覚を精神病の一症状と常識的にとらえておいたうえで、妄想よりに幻覚を見るか、知覚よりに幻覚を見るか、妄想から幻覚が生じるとみるか、幻覚から二次的に妄想が生じるとみるか、妄想のない幻覚をどう位置づけるかなどを考察してみる必要があるのではないかと私は考える。
(2)我が国の幻覚論
1998年に加藤敏、小林聡之,が「幻覚の精神病理学の動向」という総説を臨床精神医学(7月号)に書いている。そのなかで、加藤らは、現象学的精神医学で幻覚が単独で話題になることは少ないが、近年生物学的精神医学において幻覚が統合失調症の格好のターゲットにされていると述べている。2000年代になってもその動向は継続されていると思われる。加藤らの論文以来、あくまでも私の知る限り、まとまった幻覚の総論は書かれていない。幻覚の精神病理学的な記述はすでに完成されているとみなされているせいだろうか。しかし私は幻覚の問題が精神病理学的な意味においてもまだ解決済みとは思えれないので、この拙論を書いている。
幻覚という現象は生物学的精神医学と精神病理学的精神医学が共同して研究していくことが可能な恰好の領域だと私は思う。
その意味で、2008年に出版された「精神医学対話」という優れた書物の中で、「幻覚」をめぐって、生物学的視点から福田正人が精神病理学的視点から小林聡之が担当してなされた対話的な論考は極めて興味深いものであった。
ここでは小林の論文を取り上げて、特に幻聴の知覚性に関して触れておきたい。なお福田の論文は後ほど触れさせてもらう予定である。
小林の論文のタイトルは「幻覚―このハイパーリアルなものー」である。小林は、ヤスパースが知覚の性格を帯びたものを真正幻覚と呼び、表象性を帯びたものを、仮性幻覚ないし偽幻覚としたことを批判して、それは表象が現実的でないという予断が働いた分類だとしている。ほんらい知覚と表象は簡単に区別できるものではなく幻覚には知覚体験と同時に表象としての体験があると小林は述べている。
さらに、ヤスパースの分類に対して、Goldsteinが、幻覚の実在性の確信によって分類すべきだとしていることを取り上げる。実在判断ならば、「声が聞こえている」ことよりも「(声が聞こえている)と思い込んでいること」の方が問題となり、声が聞こえていると思うことこそが幻覚体験の確信になってしまう、そうすると幻覚が妄想に回収されてしまうと述べる。そしてむしろ、“患者は幻覚が実在するものと信じ込んでいる”という命題が、いささか正鵠を失しているというべきであるとしている。
そのうえで、小林は安永の次の言葉を引用する「幻覚の現実性は真の知覚とはまた別次元の『より高い』現実性であるかのようにみえる」。つまり幻覚の現実性はハイパーリアルなものといえるものである。
私はこの安永の見方を肯定したいと思う。しかし、それが幻覚から知覚性を消去するものではないだろうと捉えておきたいと思う。安永は彼のパターン理論に表象と知覚をあてはめて、幻覚を論じている。パターン的理解では、表象はA面、知覚はB面で両者を分離できないものであるが、表象がより重視され,幻覚は表象に由来すると安永はしている。
小林は単純な幻覚の知覚論に対しては疑義を述べる、たとえば患者が数秒しか幻聴を聞いていないのに、幻聴の内容を問うと随分と長い報告をする場合があり、音だけでなく意味をうけとっているように思われる例があるというのである。私はこの場合は聞こえた声の内容とそれに関連して思い浮かんだことやあるいは妄想との区別をきちんとせずに報告しているからではないかと思う。短い時間でも知覚された幻聴はあり、それに伴って思考は動く。その際には幻聴はそれを媒介にした妄想と地続きであるとみるべきだろう。必ずしも不思議ではないように思う。一を聞いて100を知るということわざもある。知覚とそれに伴う思考(知覚的思い)に関しては次の項で触れてみたい。
小林はさらに聴覚や視覚以外の感覚モダリティの幻覚のとらえ方の問題、ハイパーリアルな幻覚はみな五感に収まりきらない域外幻覚とみるべきだということ、あるいは言語と幻覚について、幻覚を「運動なき知覚」というヴァイゼッカーの説に関してなど興味深い指摘をいろいろおこなっている。
4.知覚をどうとらえるか
私は知覚を重視した幻覚論を考えて見るうえで、知覚をどうとらえるかに関して一定の知見を持つ必要性を感じている。ここでは私が関心を持った、大森荘蔵やメルロポンティなどの哲学的視点からの知覚論を中心に触れさせていただきたい。
われわれは、日常生活で覚醒して動き回っている時には、外部からの色や形や音や匂いや味や皮膚への刺激やさらに身体内部からの感覚刺激に取り囲まれそれらを知覚する。哲学者の大森荘蔵は知覚することで出現する一定のまとまりのある現象を知覚風景とよぶ。大森は知覚として現れる現象を「立ち現われ」と表現した。ある風景を直接知覚している場合も、映像で見ている場合も、それをあとで思い出している場合でも、あるいは幻覚や夢で現れる場合でも、風景は同じ資格で立ち現れるとした。
そうした彼の考えは立ち現れ一元論とも呼ばれる。また、知覚されると同時にその対象が呼び起こす感情やさまざまな思考(観念)を、大森は「知覚的思い」とよんだ。さらに大森の重要な指摘として「重ね書き」がある。それは日常言語での知覚の描写と、たとえば電磁波や音波などが脳内に影響を与えて知覚が成立するというような自然科学的描写とは、「重ね書き」が可能で同格のものと理解しようという考えである。これは、たとえば幻覚について語る患者の言葉と、fMRIでの映像を「重ね書き」という概念で同一の現象を見ているのだという認識である。こういうとやや奇異な印象を持たれるかもしれないが、脳科学の世界では、このことは言わば、暗黙の前提として研究されている。
以上のような認識のもとで、大森は幻覚について次のように述べている。
「(たとえば)コップの知覚像を物理的コップの知覚像(物体―体制)と呼ぶか、また電磁場の像(場―体制)と呼ぶかは単なる言葉の問題で、それ以上の意義は見当たらない(括弧内の言葉は筆者による)……通常、『コップは見えるが電磁場は直接見ることができない』というが、この区別は単に知覚命題の体制の区別であり、それ以上のものではない」「幻覚を他の知覚と区別しようとして、幻覚の或る位置に何も物理的過程がないことを言うのであれば、鏡の中の像は幻覚となる。また、幻覚像の位置に、物体―体制を持つ知覚命題集合が当てはまらぬというのであれば、電磁場もまた幻覚と同様である」「幻覚は『対象なき知覚』ではない。鏡に映るコップの像が対象を持つのであれば、幻覚は大脳の中に立派に対象を持っているわけである。」「幻覚は知覚と同じ身分を持っている、幻覚を主観的というならば、すべての知覚が主観的である。……歯痛が歯の損傷状態を知らせるように、幻覚は脳の異常状態を知らせることになるだろう」。
私はこのような大森の認識に多少違和感を持つところもある。たとえば精神科医としては通常の知覚と幻覚が同じ身分を持っているとだけ言ってすますわけにはいかない。しかし「幻覚は大脳の中に立派に対象を持っている」という認識には共感する。大森は多分直感的にそう感じたのであろうが、私もすでに何度も述べたように「大脳が幻覚の対象をつくるのだ」という仮説的な認識のもとで幻覚を考えてみている。
その幻覚が仮に妄想や思考やあるいは表象に由来するものであったとしても、知覚的な対象が脳内でつくられて存在するから幻覚は知覚されるのであると私は考える。
そうだとすると幻覚の知覚的な対象が脳内でどのように作られるのだろうかと我々は問わなければならない。その点に関しては、詳細に触れる余裕がないが、私はカオス理論でいう、奇形的なアトラクターが脳内に出現して幻覚が生じるというシュピイツアーなどの論じていることが今のところ最も可能性のある手掛かりと考える。
ここで知覚をどうとらえるかをもう少し考えておくために、大森の述べる「知覚一元論」や「知覚的思い」を補足することにもなると思われる、ヒュームやマッハ、メルローポンティの知覚論などに触れておきたい。はじめにヒュームに関してみておこう。
人間の心に現れるすべての知覚を、ディヴィド・ヒュームは「人生論」のなかで、二種類に分けて論じている。「印象」と「観念」である。そして次のように言う。
「これら二つの間の相違は、それらが心に働きかけ、思考もしくは意識の内容となるときの勢いと生気との程度の違いにある。きわめて勢いよく、激しくて入り込む知覚を印象と名づけてもさしつかえなかろう。そして私は、心に初めて現れるときの感覚、情念、感動のすべてをこの名称で包括することにする。また、観念という言葉で、思考や推論の勢いのないこれらの心像を示すことにする」「印象と観念との間には、勢いとか活気の程度を除くと、ほかのどんな点でも著しい類似があるとうことである。一方はいわば他方の映像であるようにみえる。したがって、心のすべての知覚は二重になっており、印象としても観念としても現れるのである」
「すなわち、人間とは、思いもつかぬ速さでつぎつぎと継起し、たえず変化し、動き続けるさまざまな知覚の束あるいは集合にほかならぬということである」
木田元によると、カント哲学から物自体を引き去ればヒュームの現象主義になると言われるが、そのことに気がついた、若きマッハは,「私の自我をもふくめた世界は関連しあった感覚の、集団である。ただ、自我においてはいっそう強く連関しあっているだけだ、と思えた」と述べている。そしてのちに、感性的要素一元論を形成する。それは、次のような主張である。
「物体は色、音、熱、圧力、空間、時間などのこれ以上還元できない感覚の諸要素の結合から成っている。物体が感覚を生み出すのでなく、要素複合体が物体を形づくるのであり、かえって、物体とはみな要素複合体に対する思想上の記号に過ぎない」
私は、大森の知覚をめぐる理論をヒュームやマッハの知覚論に類似した要素をもっているものと考えている。おそらくこうした知覚論に関して専門的にはいろいろと批判的な意見が提出されているものと思われるが、この拙論で考えている幻覚の見方は、おおむね、ヒュームやマッハ、そして大森の知覚論に強く影響されているものである。
次にベルクソン、サルトル、メルロポンティ、ドゥルーズの知覚論にすこし触れておきたい。ベルクソンが「物質と記憶」で展開した「イマージュ(イメージ)」をめぐる議論は知覚をめぐる議論に対しても今なお影響を与え続けている。サルトルやメルロポンティやドゥルーズの知覚をめぐる論考もまたベルクソンの影響とそれとの格闘の上に築かれている。彼の影響はメイヤースにまで及んでいると言われている。ベルクソンに関しては後でまた触れる予定でいる。
サルトルは「想像力」でベルグソンのイマージュに対する疑問を展開しながら議論を進めている。またドゥルーズはすぐれた知覚論でもある、「シネマ」で、ベルクソンのイマージュと格闘しながらシネマにおける「運動イメージ」と「時間イメージ」に関して興味深い考察を展開している。周知のとおり、彼はヒュームの影響も受けている。
メルロポンティは知覚論を自らの哲学の主要な課題として展開している。ここでは私の関心事と関連させて、メルロポンティの知覚論のごく一部であるが触れておきたい。もちろんこれは哲学には素人の私が、日本の哲学者の解説なども手掛かりにして理解したことなので、あるいは間違いがあるかもしれない。
メルロポンティの「知覚の哲学 ラジオ講演1948年」の訳者である菅野の解説によると、メルロポンティは知覚をあらゆる経験の原型とみなした、さらに知覚をいわば沈黙の言語にほかならないともみなし、黙して語らない経験の意味を現象学は純粋な表現へともたらすべきだとして、言語論的な転回を企てもした。さらに言語的記述のみならず、絵画や音楽もまた場合によっては言語に優る知覚的経験の表現であるとした。
また遺稿「見えるものと見えないもの」において、見えるものは「知覚(自然)」であり、見えないものは、その知覚をめぐる「思考」であり「意味(言語)」であるとしている。そしてその両者は矛盾することのない切り離すことのできない一体のものとみなした。私の認識に間違いがなければその一体化をもたらすもの、あるいは架橋するものをメルロポンティは「肉(身体)」という概念で表現し、そこにキアスマ(交叉、絡み合い)という性格を付与している。それは自己や他者や自然(世界)とのあいだで、身体を介してなされるコミニケションの基盤をなすものである。同時にメルロポンティはこの現象に意識の源泉を見ようとしていたようである。
メルロポンティは「肉」という概念を次のように述べている。
「これは客観的な身体でもなければ、心によって己のものと考えられた身体(デカルト)でもなく、それは感じられるものと感じるものという二重の意味で感覚的なものなのである。……私の肉そのものが感覚的なものの一つでありながら、他のすべての感覚的なものの記入がおこなわれる場所なのである」 「知覚することー動くことの含み合いは思考―言語の含み合いである。ー肉とはこの円環の全体のことであって、単に空間―時間的に固体化されたこのものへの内属ではない」「私の身体が世界(それも一個の知覚されたものである)と同じ肉でできている……私の身体のこの肉が世界によって分かちもたれており、世界はそれを反映し、世界がそれを蚕食し、それが世界を蚕食している(感じられるものが主観性の極点であると同時に物質性の極点でもある)」
メルロポンティの述べる、「知覚」とその「思考-意味」の一体という見かたは、この小論で考えてみている幻覚論において、幻覚を知覚よりに見るか、思考よりに見るかという認識の違いが生じていることに重ね合わせて考えてみるとなかなか示唆的である。私は幻覚論において、この二つの見かたは切り離すべきではなく一体化したものとしてとらえておくことが必要だと考える。またメルロポンティのこの「見えるものと見えないもの」は、大森の「知覚と知覚的思い」とその認識を共有していると私には思える。
なお、「知覚」とその「思考-意味」の一体化といったがもちろんその両者がまったく同じものではない。その両者の間でのキアスム(絡み合い)あるいはループが問題になるのはそのためである。また思考しきれない知覚、つまり言語化ないし表現化しえない知覚もあると思われるが、どう見るべきだろうか。さらに知覚は感情や情動を生み出す源泉でもあると思うがそれをどうとらえるべきだろう。この辺の現象に関してはその脳内機序を含めてまだまだ謎だらけである。
私の聞きとりや認識に間違いがなければ、患者は幻覚の体験のさいに、決してその場で意識的に考えたり思いついたわけではない、「意味」や場合によっては知覚的な「表象」あるいは「イメージ」をいわば受動的に体験することがある。時にはそれだけが強圧的に「知覚」される。さらに「不安」を含めた様々な感情を「知覚」する。
私はここで説明を抜きにして、唐突だが、知覚に絡んでくる「意味」と「感情、情動」をそれぞれひとつの感覚モダリティとして,五感の系列の一つに追加して考えてみることを提案しておきたい。
次回は幻覚の脳内機序について考えてみたい。 (つづく)
