
公転する太陽──山田尚子『きみの色』における惑星とポエジーについて
※本記事はネタバレを含みます。
“太陽” としてのトツ子
『きみの色』は、トツ子が “太陽” であることが明らかになるまでの物語だ。
「もし自分の色が見えるのなら、それはどんな色なんだろう?」
そう問うたトツ子は、物語の終盤、てのひらを太陽に透かし、自らの色が “朱” 色であること、すなわち、自らが太陽と同じ色であることを “発見” する──。
*
“太陽” は恒星である。恒星は自らが光を放つ。トツ子はいつも誰かの “色” を求めるけれど、“光” がなければ “色” もない。照らしていたのはいつもトツ子だったのだ。
また “太陽” は、ひとつの系の中心である。きみやルイに “引かれて” 日々を生きていると思っていたトツ子はその実、きみやルイを “引き寄せ” てもいたのだ。

“公転” するきみとルイ
あるいは “太陽” は、周りの星々を “引き寄せ”、“公転” させる。
実際トツ子が、きみやルイを “引き寄せ”、“公転” させていたように。

というのは物理的な意味でも、比喩的な意味でもそうだ。トツ子はきみを古書店から物理的に引き出し、自らが住む寮へと “引き寄せ” るし、おとなしそうなルイは、トツ子たちが来れば思い切り、ぐるぐる “回り” ながらはしゃぐ。
あるいはトツ子は、2人の人生を “好転” させた。学校を辞めたことを言い出せなかったきみには、祖母と話すきっかけを与え、音楽が好きだと打ち明けられなかったルイには、ライブへ親を招く勇気を与えた。
「変えるべきものを変える勇気」を与える “光” (太陽=神)とは、ほかならぬトツ子自身だったのだ。
回転する “惑星” たち
それに “太陽” は、1つ2つの星だけを回転させるしかないほど無力ではない。そのエネルギーはもっと強力だ。
だからこの映画でも、“太陽” たるトツ子によって回転するのは、きみやルイだけでない。ほかのキャラクターたちはもちろん、周りの事物たちですら、自由自在に回転する。

きみがテンポキープに使っていたニュートンのゆりかごが、振り子時計の振り子が、地球儀が、あるいは天ぷら蕎麦のお盆さえ、このアニメでは “回転” する。
あるいは “回転” はしていなかったとしても、ニュートンのゆりかごからのマッチカット[1]で映ったミニトマトや3人が食べたアイスクリームのカップ、古書店のライトや熟していないオリーブの実など、“惑星” のモチーフがそこかしこに散りばめられたいた。

これほど執拗なまでに繰り返されるモチーフはしたがって、否が応でも観客の注意を引くが、とはいえそれらは映像や物語において、なにか重要な役割を果たすとは、必ずしもかぎらない。
ではいったい、こうしたモチーフは何のためにあるのか。それはもうほとんど、自由連想のようなものなのではないか──?
いや、そうなのだ。それは実際、自由連想でしかないのだ。そこには球体ということ以外、意味連関や必然性といった法則・秩序はいっさいないのだ。むしろその自由連想的な連関こそ、このアニメーション映画の真骨頂ではないか。
すなわち、一見まったく無関係に思える球体のモチーフが、球体というだけで連想的に結びついてしまうこと、まったく関係がなかったはずのその “天体” たちが、ほんの束の間、軌道を一にするような奇跡こそが、このアニメーション映画の核心なのではないか。
星の友情
いささか唐突だが、それこそ筆者がこの映画から自由連想的に思い浮かべたニーチェの一節を読んでもらいたい。
星の友情
かつてわれわれは友人同士であったが、いまや疎遠となってしまった。しかしそれは当然のことであり、われわれはそれを恥ずかしいことのように隠し立てしたり、誤魔化したりしようとは思わない。
われわれは、それぞれが自らの目的と航路をもつ二艘(にそう)の船なのだ。われわれはこれからもすれ違うことはあるだろうし、これまでもそうだったように、一緒に祝祭をあげることもあるだろう。
──そんなとき、この堂々たる二艘の船は、同じ港に、同じ陽光を浴びながら休息し、まるですでに目的に到達し、同じ目的を目指していたかのように見えたかもしれない。
しかしやがて、われわれの任務がもつ抗いえない力がわれわれをまたしても引き離し、別々の太陽の下へ、別々の海域へと送り出し、もはや二度と相まみえることもないかもしれない。
──仮に出会うことがあっても、互いに相手が誰だか分からないだろう。別々の海洋と太陽がわれわれをすっかり変えてしまうからだ!
私にはこれが、トツ子ときみ、ルイの関係性を描写したものだとしか思えない。
実のところルイは一艘の船に揺られて最後に旅立つわけだが、さておき、この「星の友情」のように、まったく交わらないはずだった星々の軌道がちょうど調和する一瞬に、トツ子・きみ・ルイの3人はバンドを組んだ。
こういう奇跡的な世界を、山田尚子監督はずっと切り取ってきた。『けいおん!』では二度と戻ることはない青春を、『たまこラブストーリー』では人が恋に落ちる一瞬を、『リズと青い鳥』では本来的にはそりが合わないはずの2人の少女の奇跡的調和を、『平家物語』では盛者必衰の理を、それぞれ輝かしい一瞬の煌めきを伴って描いてきた。
『きみの色』も例に漏れない。それは “奇跡” でしかないのだから、『きみの色』に大きくストレスがかかるような不和や性の匂いといった “現実” が前面には──あくまで「前面には」である──出てこないことは必然である[3]。
それは10代の(あるいは人間の) “リアル” を欠いているということなのではまったくなく、煩わしい苦悩も、一筋縄ではいかない性の悩みもひとまず措いて──その象徴としてに、“楽園” に登場するリンゴ=知恵の木の実は欠けることはない──、大人たちにとっては軽くとも、当人たちにとっては重大な思春期の葛藤を、いったん何の衒いもなく引き受けることができる “奇跡” を、別様の “リアリティ” として── “リアル” と “リアリティ” は違う[4]──意図的に選択して描いているからなのだ。
だからこの映画の主題は “色” などではない。大事なのは、“色” が “音” と同じ “波” という要素で繋がっていること、本来 “色” で表現できないはずの人間が、その “色” で同じ “色” をもつほかの事物と連関してしまうことなのだ。
この、繋がりようがないものが繋がってしまうような “奇跡” こそが、このアニメーション映画の主題なのだ。
“公転” する “太陽”
だからこのアニメーション映画においては、“太陽” すら “公転” する[5]。
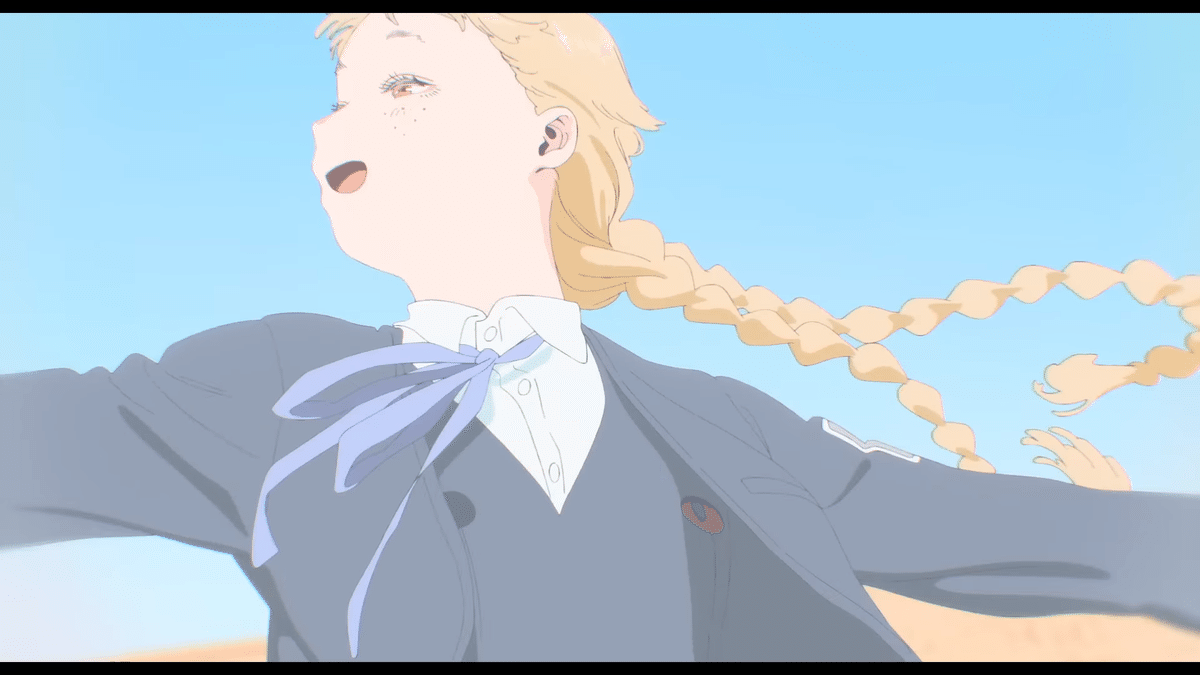
くるくる回ってきらきらと──。
言うまでもなく、その “奇跡” の頂点こそ、最後にトツ子が “楽園” で踊り舞うシーンだ(図5)。
全身を陽の照らされたトツ子の彩色はワントーン明るく[6]、光に包まれ空を舞う姿はやはり、光を、エネルギーを他者に分け合える “太陽” にふさわしい。
水金地火木土天アーメン/きのうのごはんはあったかソーメン──。
すべてのリズムを軽やかに、滑らかに踊り渡ってしまうトツ子はだから、言葉や文法の自然な結びつきから解き放たれ、無関係な名詞同士を結ぶ “奇跡” を謳う。「水金地火木土天」と来たら「アーメン」と繋げてよいのだし、「きのうのごはんはあったかソーメン」なのだ。
あるべき秩序を破ったこの言語使用はだから、「バターの馬」という羅列が許されるような言葉、ポエジー(詩)の言葉にほかならない。
ポエジーの “宇宙”
山田尚子監督が『きみの色』で描いたのは、このポエジーの世界だ。
関係がなかったはずの3人が、トツ子の口をついて出た一言により連関し、関係のないはずの事物たちが、“惑星” のモチーフで繋がる。回転しそうもない人物が回転し、動かないはずの “太陽” が ”公転” する——。
『きみの色』が描くのは、そういうポエジーの “宇宙” なのだ。
だから本当にあるのは “光” だけだ。トツ子は “太陽” でありながら、実のところ三原色の一端も担っている。だから3人が集まれば、“白” になる。“光” になる。
そういう自由連想的な “奇跡” が、“輝き” がそこに煌めいていた。
“光” があった。
おわりに:太陽といっしょになった海
太陽は夜に出会えない。
一度分かたれた星々が、また出会えるとはかぎらない[7]。「別々の海洋と太陽がわれわれをすっかり変えてしまう」のだから。
とすればむしろ、海が太陽と交わる一瞬こそ、やはり “奇跡” だったのではないか。
ランボーの詩(ポエジー)は、その “奇跡” をこそ、“永遠” だと詠っていたはずだ。
見つけだすことができたんだ。
何をだい? 永遠さ。
それは、太陽と
いっしょになった海なんだ。
筆者はこの “奇跡=永遠” を、以下のショットに見た。

雪の朝、トツ子は独り、海と地平と太陽と直列に連なる。
きっとこの合宿のこと、その朝のことを、トツ子は将来何度も想い返すことになるだろう。
そのときトツ子は、宝物を愛でるように、この3人が調和していた奇跡を想い、変えることのできないこの思い出を、静穏に受け入れるのだろう。
──と考えて、同じ思い出を私も生きていたことに気づく。
とすればこれは私たちの “光” だ。私たちの “色” だ。
「もし自分の色が見えるのなら、それはどんな色なんだろう?」
スクリーンに手をかざすまでもなく、私たちの生に彩が加えられたことを、私たちは “発見” したのだった。
p.s.
蛇足と分かっていながら、つけ加えざるを得ないことがある。
依田伸隆のことだ。むろん、「予告編ディレクター」だからといって、その個人名だけに、プロモーションビデオのすべてが帰せられるわけではない。
けれどほかに代表する名前がないし、何より、直観的に依田の仕事だと思うので、代表して依田の名を借り、依田が制作したと思しき『きみの色』のPVについて補足したい。
まずはこれを見てほしい(正確には以下は「スペシャルムービー」だが、「プロモーションビデオ」の一環ではあるだろう)。
ここには『きみの色』のすべてがある。
いや、それは言い過ぎだとしても、少なくとも『きみの色』のエッセンスは凝縮されている。これでもかという回転運動のカットの連続が、“惑星” のモチーフをこれみよがしに連関させる編集が、そのことを物語っている。
あるいは最後はご丁寧に、『ユーフォ』をはじめとする京アニ作品などで見たことのある、鳥のモチーフを生かした編集をも丁寧に差し挟む。

連関しないはずのものを連関させるこの仕事はだから、本作の真髄を、本作自体を用いて返した “本歌取り” 、あるいは、山田尚子監督の仕事を十二分に理解したある種の批評行為と言ってもよいかもしれない。
たとえば「映画『天気の子』スペシャル予報」で発揮されたような依田の才が、ここにも生かされているように思われ、そしてその手腕が、見事に山田尚子監督のポエジーとそれこそ連関したと思われ、筆者はいたく感動した。
定かではないとはいえ、依田伸隆とこのPVを、『きみの色』と同じ箱に入れ、変わらないものとして大切にしたい。
註
[1]本来は時間も場所も異なる、連続しない2つの場面を、共通の動作や似た被写体でつなぐ編集技法のこと。
[2]F・ニーチェ『喜ばしき知恵』村井則夫訳、河出文庫、2012年、288-289頁。なお、ここに記した改行や送り仮名は、読みやすいように引用者が加えたものである。
[3]実のところ、「ストレスがかかるような不和や性の匂い」がまったくないわけではぜんぜんない。きみやルイの家庭は、よく考えなくともかなり「不和」を感じるし、きみやルイから性の匂いを感じ取れる描写もいくらか差し挟まれている。ただそのような要素は絶妙な具合で “脱色” された “風” に描かれてはいる。しかし個人的にはぜんぜん “脱色” されたと感じることはできず、きみがルイを “見つける” 序盤の古書店のシーンからバンドを結成したあたりで、トツ子のことを考え、きみのことを考え、さらにルイのことを考え、勝手に辛くなっていた。ただ、そういう “色” はひとまず前面に出てこないように意図的につくっている、と見なすほうが穏当ではあるだろう。ルイについても、かなり思うところがあり、いろいろと書き連ねたいところもあるのだが、トツ子はトツ子として、きみはきみとして、ルイはルイとして、そういう人がそこに存在するのだということは念を押して強調しておきたい。
[4]これについては以下の記事を参照されたい。
[5]念のため付け加えれば、太陽は実際のところ観測する系を変えて、たとえば銀河系を外から観測すれば、太陽は銀河系の “中心” を基点に回っているのだから、その意味では現実においても太陽は “公転” していると言い得る(外から観測すれば太陽が動いていること自体はトツ子が授業のなかで見るビデオのなかでも描写されている)。しかしここで謂いたいのはむしろ、「太陽が太陽系においてなお公転する」というような、不可能な事態を可能にさせる、詩の力、ポエジーの跳躍のことである。一見して不可能に思えるこの “奇跡” をこの映画はずっと描いているのであり、このポエジーのエネルギーをこそ、トツ子は体現しているのだ。
[6]劇場販売パンフレットにおける色彩設計・小針裕子のスタッフインタビューを参照。
[7]小説版『きみの色』にはほんの少しプロローグがあり、その後の関係性が少しは継続することがほのめかされる。
参考文献等
Arthur Rimbaud, «Une saison en enfer »(Page:Rimbaud - Une saison en enfer.djvu/35 - Wikisource)(『地獄の季節』小林秀雄訳、岩波文庫、1970年。)
F・ニーチェ『喜ばしき知恵』村井則夫訳、河出文庫、2012年。
佐野晶(「きみの色」製作委員会原作)『小説 きみの色』宝島社文庫、2024年。
※画像の引用はすべて映画『きみの色』の以下のプロモーションビデオに拠り、権利はすべて「©2024「きみの色」製作委員会」に帰する。
・「【8/30(金)公開】「きみの色」スペシャルPV」(https://www.youtube.com/watch?v=POJL0ZQJDvg)
・「『きみの色』主題歌入り予告【主題歌 Mr.Children「in the pocket」】/8月30日(金)公開」(https://www.youtube.com/watch?v=F5FN0-p-sxI)
・「映画『きみの色』主題歌 Mr.Children「in the pocket」スペシャルムービー」(https://www.youtube.com/watch?v=ZGvDTx2rf80)
・「『きみの色』予告①/8月30日金公開」(https://www.youtube.com/watch?v=ewBr5DCJZv8)
※本記事は筆者による下記ブログからの転載です。
