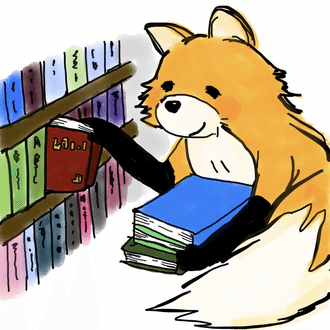“落語のやさしさに甘えたい”《マガジン“新書沼にようこそ” vol.13》
『江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか?』/田中優子
「土手エ歩ッてて、財布拾っちゃったンだヨ」
「何だってそんなドジなことするンでイ」(『三方一両損』より)
金は貯めない。その日のうちに使い切る。ましてや落ちてる金を拾うなんて
ーー金離れがよく、物事に執着しない「江戸っ子」の美学は、どのように育まれたのか?
落語に息づく人々の暮らしをひもとけば、現代人が忘れてしまった、まっとうな「しあわせ」が見えてくる。江戸の社会・文化を渉猟し、現代への明敏な批判としてよみがえらせてきた気鋭の江戸学者が世に問う、初めての本格的「落語論」。
うちのツレアイが落語好きなもので、私も少しずつ興味を持つようになりました。
地方なりに独演会聴きに行ったこともあります。
(故・柳家小三治師匠聴いたのとあるのは財産だと思ってます)
落語って、そのままでも笑えたり、じわっときたりするけれど、多分こういうこと知っているともっと面白いというのが、こちらの一冊。
逆に日常生活の中や昔からのしきたりが、残っているのも落語の中ですね。
それを知ると、ご飯と味噌汁食べて、「日本人でよかったなぁ」としみじみする感覚にも似た安堵が浮かびます。
落語の元ネタがイソップ物語であるものもあるそうです。
悪人ばかり出てくる話を善人ばかり出てくる話に転換したのが、日本の翻案であった。
善人はどこか抜けている。おかしい。面白い。しかし気持ちいい。「こんなふうに生きてみたい」と思わせるのだ。何かを禁じられるより、気持ちいい手本を見せられるほうが、私たちはそちらの方向に向きやすいのではないだろうか。それを生き方の美意識、と言ってもいいだろう。
この「決して劣等感をもたない」「自分の存在意義を絶対に疑わない」という人物像が、落語の価値を高めている。聴く側が「ああ、こんなふうに生きていてもいいんだ」と思えるからである。その笑いは「ほっとする」笑いであって、決して粗忽者を馬鹿にする笑いではない。
落語は、抜けている与太郎にも、使えない若旦那にも、お騒がせな粗忽者にも優しい。
もちろん江戸時代の方がよかったとかいうつもりはないけれど、「闇バイト」やら「ロマンス詐欺」やら、心が荒むニュースが多い昨今、こういう「性善説」を手本として見せられて、人も捨てたもんじゃないなと思える瞬間も欲しいなと思うのです。
落語について知りたければ、こちらが比較的わかりやすかったです。
ちなみに今回の本の内容とは関係ないのですが、小学館101新書のデザイン好きです。あの国民的アイドル彷彿とさせてくれるので(どこかで明記されているのかもしれないけれど)。
なんか色んな面白いこと教えてくれる感じがするのです。
テレレレッテレ〜
「落語でわかる江戸時代〜!」(のぶドラ派)
的な。
ちなみに見出し画像変更しました。
全く同じものはみつからなかったのですが、こんな感じのブックカバーです(これもいいな↓)。
↓
中身は読書ノート。
またいずれ紹介させていただきます!
最後までご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ素敵な読書生活を👋📚
いいなと思ったら応援しよう!