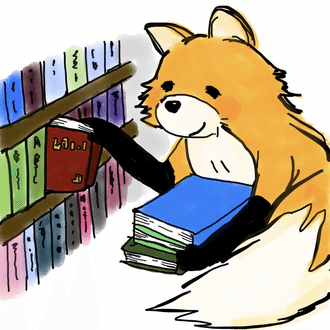“謎だらけだからこそ”《マガジン“新書沼にようこそ” vol.21》
『赤ちゃんはなぜ父親に似るのか』/竹内薫
「妊婦脳はホルモンシャワーのせい?」「出産に立ち会えば父親の自覚が生まれる?」科学知識を武器に、初子育てに立ち向かう著者。果たして子育てはサイエンスで楽になるのか!?知識欲が旺盛でも頭でっかちになりがちな新米パパが、ママのベストパートナーとなるにはどうすればいいのか。自身の体験を交えつつ、妊娠・出産・育児にまつわる科学研究から「赤ちゃんの不思議」を描く、ユーモアあふれる一冊。
サイエンスライターの著者。
代表作はこちらでしょうか(今読んでるところ)。
妊娠、出産、育児からまで、父親視点の奮闘が描かれる一冊。
妊娠、出産、育児と、私とツレアイが経験したことがない話なので、ただひたすらに驚き、同時に生命を生み出すという奇跡に頭が下がるばかりです。
もはや身の回りの妊婦さんや、それを経て母になった方たちを拝みたくなる。
自分たちもこうやって(むしろ◯十年は前なわけでさらに大変!)産んでもらったと思ったら、もう実家のある方向に足を向けて寝られません。
これね、特に男性、プレパパには読んで欲しいと思いました。
長い引用になってしまうけれど紹介させて下さい。
妊娠や子育てが、睡眠不足や仕事の中断や、その他もろもろ、精神をマイナス方向へと誘い、物忘れやイライラ感につながり、しまいには、「全てがうまくいっていない」という錯覚に陥るらしい。これは、そばにいるイクメン見習いにとってもストレスの種になる。妻が忘れたものを探索し、妻の口から飛び出るイライラをことごとく受け止め、必死に慰め、ひたすら謝り、(出産後は)子どもとの間を仲裁するのは、聖人レベルの徳を持つ人間でないと不可能だ。オレのような、ごく普通の人間は、どこかでいっぱいいっぱいになってしまい、「なんでそんなに怒鳴ってんの!」という具合に応酬してしまう。
そんな修羅場を経験したオレは、あるとき、発想を変えることにした。妻が物忘れをしたり、突然キレたりするのは不可避な出来事であり、それなりの科学的な理由が存在する。実際、子を宿し、出産し、授乳し、といった生活サイクルの変化には、ホルモンの変化という医学的かつ客観的な変化が伴っている。妻に罪はない。悪いのはホルモンなのだ。
もう1箇所。
妊娠中に女性の体を支配するホルモンは、妊娠を継続させ出産に備えるために、ストレスに対する反応を鈍くさせます。それはつまり、外界からの刺激全般に対する反応が鈍くなるということ。常に頭がぼーっとしている、と感じる人も多い。日付や時間感覚が曖昧になり、物事の段取りがうまく組めなくなるので、仕事効率が悪くなる人もいる。これは体がお産に向けて準備しているのであって、能力が下がったわけではありません。
ですから、職場などで妊娠中の女性に対して「何、ぼーっとしているんだ!」などと叱責するのは、いいことではない。ましてやダンナさんがそういう言葉をかけてはいけないし、それを責めてはいけない。化学物質が体を駆け巡っていて、体がそういう変化をしているのだと割り切るべきです。
妊娠、出産はしていないけれど、ホルモンバランスによって体が変わると言うのはわかるので、それがもっともっと激しく起こるとしたら……。
もう大変なんて言葉では言い尽くせないことまでは想像できるのです。
月々訪れるホルモンバランスに支配されてしまう女性の方々、そしてその周りの人々、女性の体の中でこういうことが起きているのだと思うと、優しくしたくなるのではないかと。
タイトルの「赤ちゃんはなぜ父親に似るのか」の答えについて、一部引用。
生まれた子が自分に似ている、この事実により、父親は生まれてきた子を聞違いなく自分の子であると認識し、愛着を持つようになる。これは進化の不思議です。
十月十日、お腹の中で育て、産めば間違いなく自分の子である母親とは違い、DNA鑑定でもしないと自分の子である確定はできない父親。
少しでもその苦悩を癒すべく、人はちゃんと進化してきてるんですね。
著者は男性ではありますが、妻からの生の声が結構反映されていると思うので、そういう意味では、これから子供を持つ人たちには必読書と言っていいかもと思う次第。
出産育児漫画色々ありますが、今回紹介の本と合わせておすすめしたいのはこちら
↓
いや、本当に妊娠出産ってすごいです。
全ての母、そしてそれを支える父に尊敬と感謝したいと思います。
最後までご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ素敵な読書生活を👋📚
いいなと思ったら応援しよう!