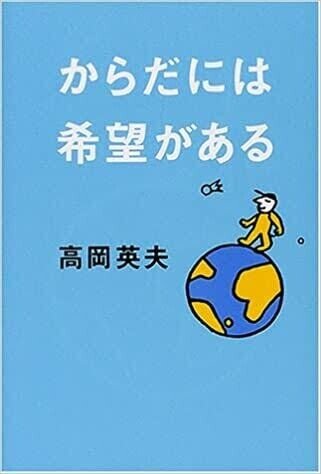「からだには希望がある」⑺
<私にとってこの本はどんな本か?>
私は小学校高学年の時、バスケをやってきました。あの頃「マイケル・ジョーダンになれる」と本気で思ってやってました。
結果はマイケルジョーダンになるどころか、中1の秋で、早々に脱落してしまいましたが😢
この本は、私にとっては希望と可能性が見える本、さすがにマイケルジョーダンになれるとは書いていませんが、その方向性、どっちの方向に行けば、その可能性が見えてくるのか?開けてくるのか?という「方角」の一つが書かれている本。
一流選手と私たちの違い。或いは、スポーツ以外のどんな分野においても、「すごいな」と感じる人と私たちの差、才能と言ったらそれまで。
私は冒頭でも話したように、つながっていると思っていて、それの「架け橋」の1つが書いてあると私が感じている本です。
なぜ好きなのか?
1番の肝は「脱力」にあるという点がものすごく惹かれる。一般的に言われる「力」の逆。つまり、ガタイとかフィジカルとか関係ない世界、そこにものすごく惹かれる。誰でも可能性があるというか。
現代の方向性とは真逆というか、例えるなら、スイカに塩をかけることによって、逆に甘さが増す、というか。
「力を入れるのではなく抜く」「力を付けるのではなく、抜き方を練習する」
前にプロジェクトXで柔道無差別級の上村春樹さんのことがやっていて、「音が違う」と
イチローも筋トレは逆に身体のセンサーを鈍くさせてしまうと、
天動説ではなくて、実は地動説が正しいのだよ、みたいな所がものすごく夢、希望、可能性を感じて、興奮します。
❸出会い
元々「トレーニング」とか「脱力」っていうのには興味・関心が強くて、そんな中で自然と出会ったという感じ。
▶️1番の元になっているのは、「インナーゲーム」という本で、これは母親が倉庫を整理していた時に偶然あった本で。
あそこから、始まった気がします、今思えば。「自身の能力」の引き出し方、今の言葉で言えば「フロー」や「ゾーン」
➡️私の体験談だと「フットサル」感覚脳モード(感じないようにするのではなく、感じて、感じてその上で、鈍感になる、感じられる量増やす)
➡️でも今思えば、逆にそこから、「野性」をコントロールし始めようとしてしまったかな?「うまくやろう」に傾きし過ぎてしまったかな?「ブサイクさ・泥臭さ・良い意味での強引さ」という私の「良さ・スパイク」を丸くしてしまったかな?
父親は、「昭和の男」がピッタリな「野性的・本能的・感情豊かな」な生き方しているように感じられる。
昔は、そんな父親を毛嫌いしてきたけど、実は1番見習うべき人だったなって気が付いた
まさしくこの本で語られている「からだには希望がある」という「未知のもの、眠っている潜在能力」を開いて、「快適に生きる」ということが実際にできるのではないかなと思っています。
「ゆる」を別な言葉に言い換えると「脱力法」有名なのは「自律訓練法」意識のコントロールで脱力していく「静的な方法」
❷身体意識
→「意識」だから、自覚次第でいくらでも変えられる。170㌢の大人の身長を伸ばすことは出来ないけれど、意識なら、いくらでも変えられる。だから「身体意識」身体を開発するんだけれど、本質は「意識」を開発していく。
ヨガに近い面もあると思いますが。あくまでも「ゆる体操」は運動能力の向上のため、日常生活をより「快適に過ごすため」の手段だと受け止めてます。
❶「美味しいビール注ぐ人」も「書道の達人」も全て本質は同じ「身体感覚」が深く開発されている
→「感じられている人」「センス」が深い人
→「上手い人」「強い人」(深い人)
→小学校2年生の時、書初め大会、どう見ても私の方が上手いと感じた、形はよかった。しかし、賞をもらったのは友達の方だった。「?」今でも覚えているということは「?」が深かったんだと思う。
→「キレイさ、上手さ」はスキル、「字の勢い、惹きつける力」は「人間性・その人自身」だったんだなって今は思う。
気が付くと、私はいつも「うまくやろう、良くなろう、綺麗にスマートに」とか意識してる自分がいる、無意識のレベルで。
意識の量、エネルギーの量、そのためには「好きなこと、楽しいこと、快いこと」ではないと無理だと思っていて
「得意・特性」を「好き」になれてる人は最強→ないものねだり
「スキル・センス」(技術・感覚)
「人間性・特性」つまりセンスを深める、開発するって、上部じゃない感じがあって「本質」みたいな感覚があって、私は好き