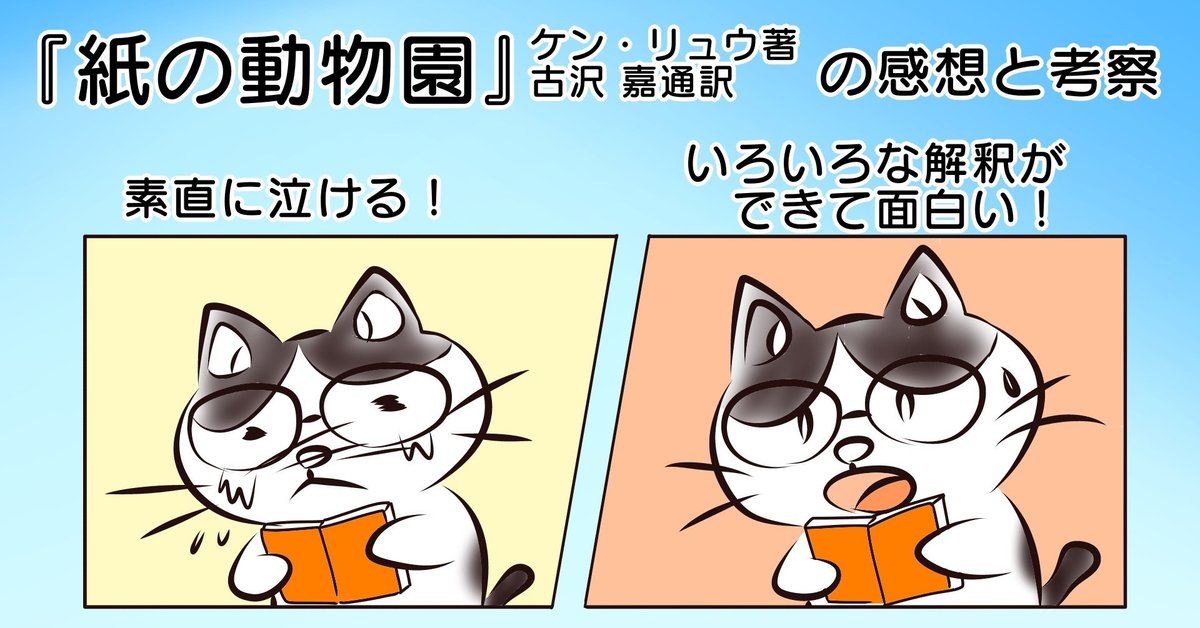
『紙の動物園』考察! 感動の親子愛の裏に無数の解釈がある?
1・前置き –この感想はネタバレを含みます!
ケン・リュウ著、古沢嘉通訳の 『紙の動物園』の感想&考察です。
この作品は、足立区立舎人図書館と共同で行ったオンライン読書会第1回(2020年9月22日開催)で参加者の方から紹介されたことで手に取りました。
SFファンなら誰もが知るヒューゴー賞とネビュラ賞の短編部門賞を取っているので、期待感を持って読みましたが、期待を裏切らない良い作品でした。
なお、この記事はがっつりネタバレを含みます。親子愛への感動だけでなく、いくつか感じた疑問を私なりに解釈したいからです。そのためネタバレ無しで読みたい方は、ここで読むのをやめて、『紙の動物園』を読んでからこの記事に戻ってきていただけると嬉しいです。
2・一見シンプルな親子愛の物語! だがSF好きにとって気になるポイントが…
本作は一見とてもシンプルな親子の愛情物語です。
主人公は自分を深く愛してくれた母親を偏見と虚栄心から遠ざけてしまい、母の死の瞬間にすら悲しむことができなかった男性です。その彼が、ある時亡き母の手紙を読んでいくつかの事実と母の想いを知り、深く涙する、というのが話のアウトラインです。
正直言ってこの親子関係だけで十分泣けます。
しかし、SF好きにとって気になるのは、老虎(ラオフー)を始めとする折り紙の動物が動くことの解釈です。
親子の愛情物語だけに着目すると、折り紙の動物が動くことは話に深みを与えるアイテムにしか見えません。
しかし、SF好きとして読後に気になってしまうポイントがあります。
母の「魔法」で動いていたはずの老虎が、母の死後にも動くことを考えると複数の解釈が成り立つのです。
次の項目で、解釈のバリエーションを深堀りしていきます。
3・老虎(ラオフー)が動く理由の解釈で物語の味わいが変わる?!
ここで議題にしたいのは、折り紙の動物を動かせるのは母親だけなのか、あるいは主人公にもその力があるのか、という点です。
これによって物語の解釈は大きく変わるので、まず解釈の可能性を列挙してみましょう。
① 紙の動物が動くのは単なるイメージや比喩表現
② 折り紙の動物を動かせるのは母親だけ
③ 主人公は「魔法」を後天的に受け継いでいる
④ 主人公は「魔法」を遺伝的に受け継いでいる
可能性としては上記の4つだと思います。以降で一つずつ検証します。
① 紙の動物が動くのは単なるイメージや比喩表現
この考え方はあまりにも味気ないし、作中で具体的に折り紙の動物が動く表現が多数あることから、まずこの解釈は「無い」と考えて良いでしょう。
無理にこの説を「アリ」とした場合、近所の少年のフィギュア(スターウォーズのオビ=ワン・ケノービ!)を老虎が壊すシーンは事実ではなく、想像の産物ということになります。
とすると、主人公がフィギュアを壊したのに、実は動かない老虎のせいにしている、のでしょうか?
Σ(・□・;)
これでは感動の物語が、スティーブンキング的なサイコホラーになってしまいますね💦
さすがにこの説は考えすぎ&ムリな解釈だと思います( ´∀` ;)
と、言うわけで①はナシです。
② 折り紙の動物を動かせるのは母親だけ
この解釈は恐らく主人公自身と読者がラストシーン直前まで持っている感覚ではないでしょうか?
この説を採用すれば、母の死後「魔法」が解けているはずなのに老虎が動くのは、死者を弔う「睛明節」という特別な日だから、という解釈が成り立ちます。
つまり、母が死に際に語った「睛明節」と「折り紙の動物」は親子をつなぐ絆であり、ある意味で母親が演出した舞台に乗った息子が、母親の愛に気付く瞬間が用意されていた、と考えることができます。
この解釈は母親の愛情の深さが無限であり、その愛に気付けなかった息子の悲しみが際立つものだと思います。
これはこれで説得力はありますが、実は私は違う解釈をしています。
目立たないのですが、作中に幼少期の主人公が、つぶれて動けなくなった折り紙の水牛に息を吹き込んで復活させるシーンがあるからです。(新☆ハヤカワ・SF・シリーズ版 P.13下段)
つまりこの時点で、主人公にも折り紙の動物を動かす力があることが明記されているわけです。
ただし、母親のように無から有を生み出す力があるかは不明で、弱った折り紙の動物を助けるような補助的な力だった可能性もあります。
とはいえ息子にも「魔法」は伝授されていた、と考える根拠にはなります。この前提で③と④の考察を進めましょう。
③ 主人公は「魔法」を後天的に受け継いでいる
前述したように、主人公は幼少期に折り紙に命を吹き込む行動をしていますし、ラストシーンでも紙の状態だった老虎を復活させています。
老虎の復活については、この日が睛明節なので母親の魂の力が働いているという解釈もできますが、私は、主人公が「魔法」を技術として受け継いでいる解釈を推します。
根拠の一つと考えるのは、母の手紙の中で、故郷の村では折り紙に命を吹き込むことは「実用的な魔法」であり、母親もその母親から教えられたと表現されているからです。(P.26 上段)
この部分では、幼少期の母親が「友だちといっしょに」「赤い紙の龍を折り」「空いっぱいに広がっていく」シーンが描かれています。この表現で、折り紙に命を与える「魔法」は故郷の村では多くの人が日常で何気なく使うものであることがわかります。
つまり、折り紙の動物を動かす魔法は、北斗神拳のように伝授する相手を選ぶ一子相伝の奥義でもなく、水の呼吸 拾ノ型 生生流天のように厳しい訓練や苦心の末に獲得する必殺技でもありません。
むしろ幼少期の母親やその友達が何気なく扱う点から見て、歌や舞のように自然と伝授されていくものだったのではないかと推測できます。
「魔法」につきものの「呪文」はある? 魔法の発動契機を考える
「魔法」には発動のための「呪文」がつきものですが、本作では呪文のような発動契機は描かれていないように見えます。
作中から読み取れるのは、折り紙の動物に命を与える時に行う「息を吹き込む」動作ですが、それだけなら誰でもできますから、物語として面白みがありません。
ここで私が着目したのが「愛」です。
文字で表記するととんでもなく「クサイ」表現になりますが…💦
折り紙に命を与えるのは、「愛」を持って「息を吹き込む」ことではないでしょうか?
ファンタジックでSF的とは言いにくい解釈ですが、この説なら主人公が幼少期に動物を動かせたことも頷けます。彼は幼い時には、母親にも紙の動物にも深い愛情を持っていたからです。
また、この説をさらに推し進めれば、偏見と虚栄心から母親を遠ざける主人公に、母親が不自然なまでに「愛」を強調するシーンが伏線として生きてきます。(P19 上段)
さらに、母の手紙で事実を知った主人公が、手紙に「「愛」の文字をなぞり書きする」シーンが強調されてラストがますます味わい深くなります。(P29 下段)
②の解釈では、老虎をよみがえらせて家路につくラストシーンでは悲しみを帯びて感じられますが、③の解釈をすれば、主人公は母の「愛」に気付いただけでなく、人間としての「愛」を取り戻していることになり、老虎との家路は非常に穏やかなものになっていると感じられます。
つまり、母親は息子に対して全力で愛を注ぐことで「魔法」を伝授しており、既に息子に与えつくしているからこそ、あえて口に出さないし、ラストに明かされる手紙にも書いていないのでしょう。
さらに考えれば、死の間際に折り紙の動物を捨てないように言ったのは、「愛」の無い人生を送るなというメッセージを込めていたとも解釈できます。
こう思うと、母親のキャラクターが「死に際に自分を忘れてほしくないと願う悲しく寂しい人」ではなく、「死に直面してもどこまでも息子の幸せを願う愛情深い母」と思えて、さらに泣けます。
④ 主人公は「魔法」を遺伝的に受け継いでいる?
主人公が「魔法」を受け継いでいるという点で③と似た解釈ですが、遺伝的なものという可能性も存在すると考えて候補に上げました。
この部分の考察は正直言ってかなりオタク的で、あまり本作に関係ないので、スターウォーズに興味がない人はスルー可能です。
( ´∀` )
そうです。私はスターウォーズのオビ=ワンのフィギュアがすごく気になっているのです!
なぜこのシーンが気になるか、それは全体にさほど写実的ではない本作で、なぜかオビ=ワン・ケノービのフィギュアの描写がやけに克明だからです。
中国人に対する差別や、折り紙の動物が主人公と母親以外には無価値なものに見えることを強調する重要な場面ですが、比較対象は「かっこいいフィギュア」程度で十分なはずです。
ところが、「フォースを使え!」と声を発するカラクリまで紹介されているのです。
これはもうオタクとして、このシーンには何らかのメッセージがある! と思うしかないでしょう。
また、あえてオビ=ワンが選ばれた点もナゾです。
スターウォーズをアメリカの象徴として扱い、主人公の出自に関するコンプレックスを示すだけなら、「スターウォーズキャラのフィギュア」という表現で十分です。
さらに、主人公ルーク・スカイウォーカーでも、ダースベイダーでも、アナキン・スカイウォーカーでもなく、あえてオビ=ワンであることこそがメッセージと受け取れます。
オビ=ワンはシリーズを通じて重要なキャラですが、10歳の少年にとって人気なのはやはり主人公ルークや異形のダースベイダーと考えられるからです。
※作中の母親の誕生年と死亡時の年齢、主人公が大学卒業間近なことなどから、オビ=ワンのフィギュア登場シーンは1984年前後と思われます。
するとスターウォーズの公開年から考えてエピソード4~6のルークが主人公の時代と理解でき、アナキンは候補から外れます※
もしかすると、強力な力を持つジェダイ:アナキン(ダースベイダー)の血を引くルークではなく、あえてオビ=ワンを登場させて「血統」、「遺伝」による魔法の伝承を否定した、と考えることはできないでしょうか?
つまり折り紙の動物に命を吹き込む魔法は、母親から息子に遺伝したのではなく、技術として伝承したことをオビ=ワンというキャラに託した、と考えられるわけです!
さらに! オビ=ワンに「フォースを使え!」と語らせることは、母が伝えた「魔法」を使え!と言っているのであり、「愛」を持ち続けろ!と語っている! とは思えませんか?
無理ですかね?… まあ、無理かもしれません💦💦💦
かなりこじつけ感は強いですが、④を考察することで、ますます自説である③の解釈が強化されたと、私は自己満足しています!
グダグダ書きましたが、要は満足できればそれが自分にとっての正解です!(突然暴論)
※著者ケン・リュウ氏は11歳の時に中国からアメリカに移住した事実はあるそうなので、オビ=ワンのシーンも当時の著者の記憶をエピソード化したものかもしれません※
5・まとめ
いろいろ書きましたが、『紙の動物園』は感動できる名作です。
もちろん私の解釈に付き合う必要はありませんが、もし興味があれば、他の解釈をコメントしていただけるととても嬉しいです。
『紙の動物園』は短編集に掲載されており、さっくり読めるのも大きな魅力です。SF・ファンタジー作品として評価が高いですが、人間ドラマがしっかり描かれているので誰にでも読みやすいと思います。
作家になじみが無いので買ってまで読むのはどうだろう? と考える人は、ぜひ図書館での貸し出しを利用してください。
いいなと思ったら応援しよう!

