
<閑話休題>放置主義―レヴィ・ストロースについて―
レヴィ・ストロースは歴史的な名著『野生の思考』において、南太平洋の住民はジャンポール・サルトルの思想に代表されるヨーロッパ人が考えるような野蛮人ではなく、思考を向ける方向性が異なるだけの、知的水準に差がない同じ人類であることを証明してみせた。
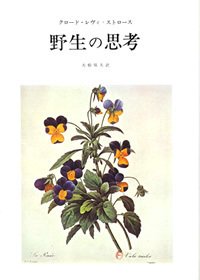
この観点から見れば、現在ではグローバル化、かつては植民地化というヨーロッパ人からの過度の干渉が行われた、特にアフリカや南太平洋の人々にとっては、ヨーロッパ人によって開発(干渉)されないままの方が、つまり放置されていた方が、ずっと幸せだったのではないかと思うのだ。いや、むしろ放置すべきだったのではないか。
つまり、ヨーロッパ人の考える政治理念というのは、ひとえにヨーロッパ社会にのみ通用しかつ有効なものであり、アフリカや南太平洋の人々にはそのまま適用しないものだということだ。彼らには彼らの文化や生活に合った、独自の政治方法や民主主義があって然るべきではないのか、ということである。
また、植民地時代の国境は、そこに住む部族や民族の分布を無視した、帝国主義諸国が勝手に引いたラインを元にしており、独立後もこれを継続することになった。わかりやすい例を挙げれば、アラビア半島からシリアにかけての地域は、古くからベドウィンという遊牧民族が居住しているが、彼らには国境という概念はなく、常に羊の餌となる草を求めながら移動する生活をしていた国境のない地域だった。それが、第一次世界大戦で負けたオスマントルコに対して、戦勝国であるイギリスとフランスが領土の分捕り合戦を行い、それぞれが植民地とした際の国境が、ほぼそのまま現在の国境として残っている。これでは、現実の部族や民族の違いを考慮してないことは明らかだろう。
現在も絶えることのないアフリカの内戦や民族・部族間の争いも、同様の理由から始まっている。ヨーロッパ諸国が現地事情を考慮することなく勝手に植民地としての分割合戦をしたため、民族や部族が混交した状態で国として独立することになり、その結果、国の主導権をめぐって民族・部族間で殺し合いをすることになってしまったのだ。もっと言えば、ヨーロッパ人による文明化がなければ、悲惨な終わりのない争いは起きなかった。アフリカの環境を考慮し、そして生存に適した生活、また古代から満たされていた生活様式を続けていれば、民族・部族同士の共存共栄のみならず、野生動物保護までも実現できたであろう。そこは、地球上でも稀な人と動物が共生する平和な土地になっていた可能性があったのだ。
しかし、アフリカや南太平洋において「ヨーロッパ文明から遅れた生活」をしていることを、否定的にとらえる意見は当然出てくるだろう。「彼らもスマートフォンを使い、インターネットを屈指し、コカ・コーラを飲みたいのだ」と主張する人たちは多くいる。こうした考え方は、グローバリズムに洗脳された、またサルトル的な「野蛮人」思考に毒された考えだと私は認識している。何が幸福かを決められるのは、ヨーロッパ人が勝手に作り上げたグローバリズム等ではなく、そこに大昔から適合して住む住民が、長い年月をかけて築き上げた生活様式による。そこに住んでいる人たちを、自分たちの生活を基準にして不幸だと勝手に決めつけてはならないのだ。
もちろん、そうしたグローバリズムと縁遠い生活を心地良いとは考えずに、ヨーロッパ人のような生活を希望する人も、アフリカや南太平洋などに多くいることだろう。そうした人に対しては、その希望がかなえられる道筋を用意すれば良いわけで、いたずらに猫も杓子もまとめて同じ希望を持つとして開発やグローバル化を強制することは、一方的な思い込み(まさに善意の押し売りだ)であり、全体主義と見なされても仕方ない。
だから、もうアフリカや南太平洋からヨーロッパ人は手を引いて欲しい。ほっといてくれ!と言いたいのだ。しかし、既にヨーロッパ人の手は、アフリカや南太平洋に深く、取り返しのつかないくらいに差し込まれてしまった。一旦グローバル化が進行した後では、元に戻ることはできない。そこに住む人たちは、既にヨーロッパ人のような生活に馴染んでしまっている。
ここで望まれるのは、進化したレヴィ・ストロースの登場だ。「野蛮人ではない」という認識から「ヨーロッパ人でもない」という認識への進化、そして「自然と共生している人々」という新たな思想を創り出す思想家が待たれている。
<私が、アマゾンのキンドル及び紙バージョンで販売している、論考などを集めたものです。>
