
新刊紹介『まだ、法学を知らない君へ』――全講導入文を公開!
有斐閣書籍編集部です!
東京大学にて1・2年生向けに法学の導入科目として開講されている人気の講義「現代と法」を書籍化した『まだ,法学を知らない君へ -- 未来をひらく13講』が7月6日に発売となりました!
◇書籍情報

『まだ、法学を知らない君へ―― 未来をひらく13講』
東京大学法学部「現代と法」委員会/編
2022年07月06日発売
四六判並製カバー付 , 248ページ
定価 1,980円(本体 1,800円)
ISBN 978-4-641-12636-7
まだ,法学を知らない君へ | 有斐閣 (yuhikaku.co.jp)
東京大学法学部の先生方が、自身の専門分野について、今まさに直面している問題を題材として解説しています。タイトルの通り「まだ、法学を知らない」人がいろいろな法律やその社会での働きを学ぶのにぴったりの書籍となっています。
また、いま法律を学んでいる人やすでに法律を学んだ人にも、この本を通して法学が取り組んでいる具体的な問題を知ることで、法学の学習に肉がつき実学としての法学の理解を深めていくことができます。
以下では、13講すべてを各講の導入文と共に紹介していきたいと思います。
第1講 憲法
デジタル社会と憲法
宍戸常寿 先生
2021年,デジタル社会形成基本法が制定された。この法律は,「誰一人取り残さない」「人に優しいデジタル化」という方針で書かれたもので、「デジタル社会の憲法」を目指すものだと言われたこともある。
「デジタル社会」と「憲法」は無縁のように思えるかもしれない。しかし,AI に代表されるデジタル化は,個人の尊重や民主主義をよりよく実現するチャンスを提供している一方で,それらを根底から覆すリスクも高めている。デジタル化と憲法の関係に関心が高まっているのはこのためである。
このような関心から,SNS を含むインターネットを例にして,デジタル化と憲法の関わりについて考えてみたい。
この講では、「デジタル社会」と「憲法」の関係、特に表現の自由、プライバシー等の憲法上の権利とSNS、インターネットとの関わりについて解説がされています。
最近では、SNSにおける偽情報や誹謗中傷などが問題となっていますが、それらの問題点やそれらに対しての立法対応等の取り組みを知ることができます。
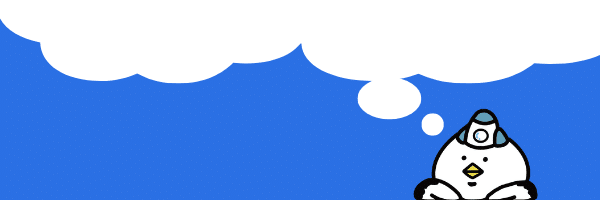
第2講 民法
同性カップルと婚姻
沖野眞已 先生
田中光さんと佐藤玲さんは,大学のサークルで知り合いました。共通の話題で話がはずみ,互いの違いも面白く,2人はサークル外でも一緒に時間を過ごすようになりました。大学卒業後は疎遠になった時期もありましたが,サークルの同窓会での再会の後,2人は互いの距離を縮めていきました。「2 人で家庭を持ちたい,人生をともに過ごしていきたい」と考えるようになった2人は結婚を決意します。
そう,〈2人はごく普通に恋をして,結婚をし……〉とはいきませんでした。田中さんと佐藤さんの婚姻届出は,受理されませんでした。2人がともに女性だったからです。〔これはフィクションです。〕
同性婚については、裁判所が同性婚を現行法で認めないことが憲法14条1項に反するとの判断を示し(札幌地裁令和3年3月17日判決)、同性パートナーがいる社員についても婚姻と等しく扱う「パートナーシップ制度」を企業が導入するなど、近年特に注目が集まってきています。
この講では、札幌地裁の判決を皮切りに、現行の法律婚の制度、そして、同性婚に対応していくならば、どのように現行の法制度を見直していけばよいのかについて、「婚姻」の意義について触れながら、解説がされています。
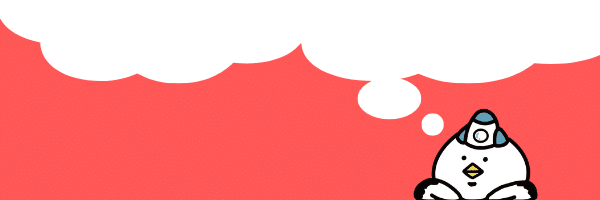
第3講 刑法
刑法は個人の尊厳を守れるか
──性刑法の改正議論を題材に
和田俊憲 先生
ひとりひとりの人を尊厳ある人格的存在として対等に尊重することは憲法的な要請である。刑法の領域でもそれが最大限追求されなければならないことは,いうまでもない。しかし,性犯罪との関係では,それが最も基本的な重大犯罪のひとつであるにもかかわらず,あるいはむしろ,そうであるがゆえに,その要請を徹底することには一定の困難が伴う。性犯罪規定をめぐる最新の改正議論を題材にしながら,性犯罪に対する処罰の最適化を目指すにあたり何が問題となっているのかをみていきたい。単に改革派と守旧派とが対立しているということではないのである。
平成29年に、強姦罪から強制性交罪への拡張をはじめとする「110年ぶりの大改正」と呼ばれる性刑法の改正が行われました。性犯罪によって引き起こされる尊厳侵害は、犯罪それ自体によるものだけではありません。被害者の二次的な尊厳侵害を回避することも重要となっています。この講では、そういった尊厳侵害に配慮をしながら、性犯罪に対してどのような法対応が考えられるか検討をしています。
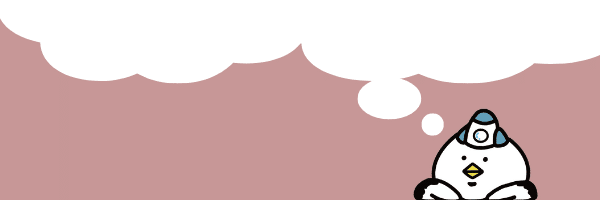
第4講 商法
金融サービス仲介業制度の導入
神作裕之 先生
金融取引の特徴として,需要と供給をマッチングさせることが容易でない点が挙げられる。従来,銀行取引,証券取引や保険取引等を仲介する仕組みは,金融分野ごとにいわば縦割りで構築されていた。新たに導入された金融サービス仲介業制度は,従来の金融仲介制度に加えて,単一の登録によってワンストップで様々な金融商品を分野横断的に仲介することを認める制度である。特に情報通信技術の発展を取り込み,インターネットを用いたサービス提供が期待されている金融サービス仲介業制度の導入の背景と概要等について述べる。
令和3年11月1日に、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、金融サービス仲介業制度が創設されました。これまで、銀行分野、保険分野、証券分野で仲介業をするためには、それぞれの許可や登録が必要でしたが、この新しい金融サービス仲介業制度のもとでは、単一の登録によって様々な金融商品を販売仲介することができるようになりました。この縦割り状態の解消のほか、所属制の不採用など金融サービス仲介業制度の特徴や導入の詳しい背景をこの講で詳しく解説しているので、この講を読んで学んでみてください。

第5講 会社法
役員報酬と法
飯田秀総 先生
会社の経営者はどのような報酬をもらうべきだろうか。あなたが経営者だったとしたら,どのような報酬をもらいたいだろうか。たとえば,会社が成長するかどうかにかかわらず,毎年3000万円もらえれば満足だろうか。あるいは,あなたが立法者だとして,経営者の報酬についてどのような法制度を作ったらよいだろうか。会社の業績が上がれば報酬が増え,会社の業績が下がれば報酬が下がるという,業績連動型報酬を法制度によって義務づけるべきだろうか。本講では,これらの問題について考える手掛かりを提供することとしたい。
会社の経営者は必ずしも株主の利益を追求しているとはかぎりません。この講では、経営者をコントロールする方法として役員報酬に着目し、どのような報酬の設計にすれば経営者が株主利益を追求するようになるのか、具体的な数字を用いながら分析をしています。この分析のほか、日本企業の実際の役員報酬の仕組みや役員報酬に関する法制度についても解説をしています。

第6講 労働法
非正規格差をなくすには
神吉知郁子 先生
パート,有期,派遣……「非正規」とよばれる働き方の低処遇は,固定化されたイメージになっている。正社員との処遇格差は,自由な市場では仕方ないことなのか。それとも,法が積極的に介入して是正すべき問題なのか。この格差問題は,高度経済成長期に確立した日本的雇用慣行と表裏一体でもある。そして,そうした慣行を前提にしてきた労働法自体がいま,根源的な問いを突きつけられている。低成長時代において持続可能な社会を実現していくには,誰をどのように守るべきだろうか?その課題は,自由と保護のバランスにある。
「働き方改革」の実現へ向けた取組みの中に、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」というものがあります。正社員が優遇される日本的な雇用慣行の裏側で、非正規労働者は不安定で不平等な待遇に置かれていました。この講では、格差が生まれた原因から分析し、格差是正のための法規制の対応、そして、今なお残る課題について解説しています。
労働法は、働いている多くの人に関係している身近な法律です。労働法の考え方に触れてみませんか。


第7講 知的財産法
著作権法の過去・現在・未来
田村善之 先生
何が著作権侵害に該当するかを定める日本の著作権法の条文は,かりに条文通りに遵守されてしまうと文化や経済が停滞しかねないほど苛酷なものとなっている。実際には,人々が条文上は著作権の侵害に該当する行為に勤しんでいるために,その種の停滞は耐えがたいほどにはなっていないが,こうした寛容的利用(=寛容されている著作物の利用)は法文に組み入れられていない分,安定的なものとはいいがたく,将来的には著作権法を構造的に変革する必要がある。
デジタル化とインターネットの普及が進んだ現代では、だれもがほかの人の著作物にアクセスしたり、また、自分で発信したりすることが容易にできるようになっています。このような社会の変化に合わせて、著作権法も変化が必要になっています。著作権法はこれまでも社会に合わせて変化をしていて、この講では、著作権法の変遷を解説し、そして、今の社会に合わせてどのような形になるべきなのか示しています。

第8講 競争法
プラットフォーム全盛時代に適正な競争を確保する
白石忠志 先生
私が専門的に研究している競争法の分野は,このところ,特にサイバー空間のプラットフォームをめぐる問題で持ちきりである。この講では,このプラットフォーム全盛時代に適正な競争を確保するという観点から学べる基本的なレッスンを,4つのパートに分けて見ていく。本書では,やはり競争法を専門とするVANDE WALLE 教授も「ビッグテックの台頭──競争法は機能しているか?」を執筆している。2つの講は,大きな意味では重なっているが,切り口は異なる。両方を読むと多角的に理解を深めることができるであろう。
競争法(独占禁止法など)は私たちの生活には、あまり馴染みのない法律かもしれません。しかし、競争法は企業に適正な競争を促し、経済を活性化させる、社会にとってとても重要な法律です。この講では、デジタルプラットフォームに対する競争法上の規制について、主に日本における対応とその展開について解説をしています。競争法についてピンと来ていない人もこの講を読めばそのはたらきをつかむことができます。
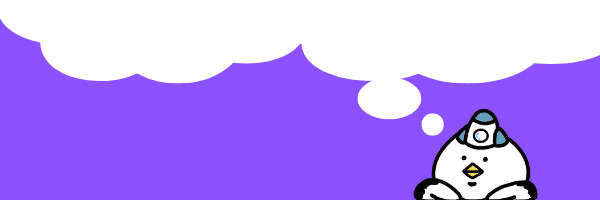
第9講 競争法
ビッグテックの台頭
──競争法は機能しているか?
Simon VANDE WALLE 先生
ビッグテックの力は巨大になり過ぎているのか。そうであるならば,どう対処すればよいのか。これらの疑問は,世界中の政治家,学者,一般市民の間で激論となってきた。競争法は,この議論において中心的な役割を担っている。
この講では,ビッグテックが台頭した様子を簡潔に述べ(Ⅰ),競争法がどのように対応してきたかを説明する(Ⅱ)。次に,これまでの競争法の対応についてどのような批判があるかを紹介し(Ⅲ),今後の方向性を考察する(Ⅳ)。
ビッグテックとは、GAFA(Google、Apple、Facebook〔現在はMeta〕、Amazon)などの巨大IT企業の通称です。この講では、ビッグテックに対する、EU、アメリカ、日本の競争当局の対応について概観し、その対応について、それでよいのかとを考えるとともに、今後の方向性を示しています。なぜビッグテックを規制しなければならないのか、どのような規制が必要なのか、知ることができます。
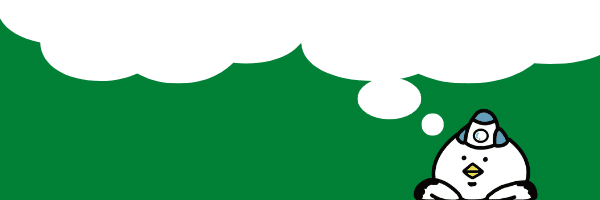
第10講 租税法
GAFA の利益をつかまえる
──経済のデジタル化と国際課税ルール
増井良啓 先生
GAFA をはじめとする多国籍企業は,巨大な利益を稼いでいる。しかし,既存の国際課税ルールの下では,ユーザーの所在地国は法人所得税を課すことができない。この不満を背景に,一方で,英仏をはじめとするかなりの数の国が,一国主義的措置としてデジタルサービス税を導入した。他方で,OECD/G20を中心として,グローバルな国際協調による課税ルールの見直しが進んでいる。はたして,各国課税当局はGAFA の利益をつかまえることができるのであろうか。
これまでの国際課税ルールの下では、GAFAなどの巨大IT企業が自国で得た利益すべてに対して課税をすることができていません。このようなルールでは、デジタル化した社会に適合することができないのではないでしょうか。この講では、GAFAへの課税を取り巻く世界の概況を示し、GAFAに対して一国主義的な措置を取る動きと、国際的な合意に基づいた対応策を模索していく動きを紹介しています。租税法という分野が国内の課税ルールを規定するだけではなく、国家間の利害関係を調整する役割を果たしていることを学べます。
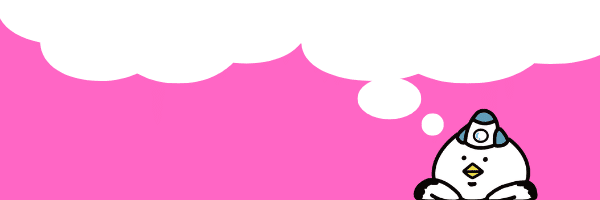
第11講 国際法
国家間のサイバー攻撃をどう規制するか?
──国連におけるICTs 規制論議の経緯・現状・課題
森 肇志 先生
国家によるあるいは国家間のサイバー攻撃が激しさを増している。国連はこうしたサイバー攻撃を規制することができるだろうか? またどのように規制できるだろうか? 国連では2つの組織(GGE とOEWG)がこの課題に取り組んできており,いずれも2021年前半に報告書を作成し,同年12月には,加盟国に対してそれら報告書を指針とするよう要請する総会決議が採択された。本講では,この点に関する国連における議論の経緯・現状・課題について整理するとともに,国際社会における規範形成の一例を示したい。キーワードとなるのは,意見の対立・相違の大きな分野における「共通理解」の形成・強化である。
2021年5月、アメリカの石油パイプラインがサイバー攻撃を受け、ハッカーに対し440万ドルの身代金を支払うという事件がありました(サイバー被害の米パイプライン、身代金4.8億円の支払い認める 米紙報道 - BBCニュース)。この事件が国家によるものとされているわけではありませんが、デジタル化が進んだ現代において、サイバー攻撃は他国を攻撃する手段として非常に有効なものとなっています。
この講では、サイバー攻撃におけるICTs(情報通信技術)利用が国際的にはどのように規制されているのか考えます。国際社会における規範形成には、様々な国の立場や利害が混ざっており、国内の規範形成とは異なる難しさを持っています。この困難な課題に国際社会がどのように取り組んでいるのかを学び、これからの規制論議の進展に注目しましょう。

第12講 英米法
契約とContract
──比較法からパンデミック・オリンピックまで
溜箭将之 先生
2人の人が互いに約束して,これを守ると合意する。これを日本語で「契約」,英語で「Contract」という。契約は法的拘束力をもつから,裁判所で約束違反が認められたら,違反した人は損害を賠償しなければならない。このルールは万国共通だと思われるかもしれない。しかしルールの実際の適用は,国により微妙に異なる。本講のもととなった授業は,新型コロナウイルスが流行し,東京オリンピックの開催が危ぶまれる中で行われた。国際的な契約の定めや,契約に適用されるルールの国ごとの違いは,異例の事態や大きなイベントにおいて,重要な意味をもつ。
この講では、日本法における「契約」に違反があった場合とイギリス法における「Contract」に違反があった場合の適用の違いについて解説し、その上で2021年の東京オリンピックがコロナ禍のなかで中止になっていた場合に日本はIOC(国際オリンピック委員会)から損害賠償請求を受けるのか、オリンピック契約の中身を検討しています。
他の国の法律を学ぶことは、その国で仕事などをするうえでも、もちろん役に立ちますが、日本の法律と比較することで日本法の立ち位置を明確にすることにおいても役に立ちます。
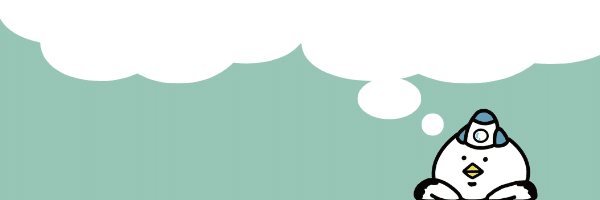
第13講 法哲学
一人一票の原則を疑う
瀧川裕英 先生
だれもが一票を持ち,だれも二票以上持たない。この「一人一票の原則」は選挙に関する基本原則だと考えられている。だが,この原則には疑う余地がある。本講で示していくように,①その原則には重要な例外があるし,②一票の格差を是正するためには,議員について一人一票の原則を解除してしまえばよく,③シルバー民主主義に対処するためには,有権者についても一人一票の原則を解除すべき理由がある。このようにして一人一票の原則を疑うことは,逆に,一人一票の原則が拠って立つ根拠を明らかにするだろう。
法哲学は根本を疑う学問であると聞いたことがあります。この講では、一見すると当たり前のように思える「一人一票の原則」に疑いの目を向け、それに代わる新たな制度を検討しています。「得票数制」、「余命制」、「複数票制」など、それぞれとてもユニークな制度が検討されています。
7月に行われた参議院選挙でも、「一票の格差」が問題となっていました(参院選 「一票の格差」一斉提訴 最大3・03倍、前回からやや拡大(産経新聞) - Yahoo!ニュース)。問題を解決する糸口は、この講のように根本を疑ってみることによってつかむことができるかもしれません。
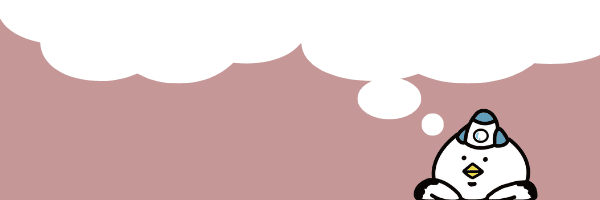
以上13講となっております。
興味のある講を見つけたら、是非手に取ってみてください!
