
快楽のトレッドミル〜どれだけ幸福を追求しても幸せになれないのはなぜなのか #HapHed|進化心理マガジン「HUMATRIX」
" なんでコイツらは十分恵まれてんのにもっといい生活を望んだ? ・・・・俺も同じか ポチタがいりゃあそれでよかったのに もっといい生活を夢に見たんだ そーかみんな夢見ちまうんだなぁ じゃあ悪い事じゃねえ 悪い事じゃねえけど・・・・。"
───『チェンソーマン』/ 藤本タツキ

・#HapHed のテーマソング ▽
# 幸福は、なぜあるのか

#HapHed回では「幸福の生物学/ハピネスバイオロジー」を探求していこう。
まず最初に確認しておきたいのはこれだ;
「快楽」や「幸福」は、その他の基本的な情動と同じように、"生物学的な現象"として発生する。
たとえば「恐怖」という情動。それが発生すると心臓がドキドキし、筋肉がピンと張り詰めて緊張し、目を大きく見開くことになるのは、肉食動物から少しでも逃げやすくするための適応的反応だ。

快楽/pleasureや幸福/happinessは、その逆の効果を及ぼす情動だ。恐怖のように「それから逃げろ!」と警告するのではなく、「それを追い求めろ!」と生物に獲得と達成を望ませる機能がある。
進化論を知らない俗世間の連中は、 "幸せは人それぞれ" と当たり障りのないことを言うかもしれないが、「進化による心の設計」という観点から考えれば、"幸せは人それぞれ" では困る。
恐怖という情動システムは、その存在理由ゆえに"安全なもの"ではなく"危険なもの"から生物を逃さなくてはならないし、幸福という情動システムは、その存在理由ゆえに結果的に"生存と生殖につながるもの"を生物に望ませなくてはならない。
幸福は、「生物学的に適応性のあるもの」を、ヒトという生物に望ませる。

「適応性のあるもの」とは、「遺伝子の生存と効果的な複製につながるもの」だ。最も基本的なレベルでは、食物、住居、安全などがそれに当たる。それがなくては、生物が生存を確保していくのは難しい。
アニメ『チェンソーマン』のホームレス主人公・デンジは、長らく生存ギリギリの生活を強いられてきたためにまさにそれら───食物、住居、安全───を"理想的な幸福の対象"として求めていた。
そしてついにはそれを手にした時、すさまじい幸福を感じていた。

21世紀の恵まれたニッポンに生きるキミたちは、「食べるものがある、寝れる場所がある、殺される心配がない」というだけのことに幸福を感じることなんてあり得るのか────?と、このフィクションの描写に疑問を感じるかもしれないが、幸福の生物学的ロジックによればそれは十分あり得ることだし、実際世界の恵まれない国々ではあり得ていることなのだ。
幸福は、生活レベルに依存する。暮らしむきが裕福になると、そのヒトが内的に認識している〝ハピネススタンダード/幸福基準〟が上昇する。
そうなると、かつて幸せを感じられていたようなささいなことでは、もはや、幸福を幸福として感じられない体質になっていく。

底辺生活のデンジは、ハピネススタンダードが低いため、「朝食のパンに好きなだけジャムを塗って食べられることの幸せ」を思う存分味わうことができる。
だが、ほとんどの現代ニッポン人は、生まれて以来彼よりも生活レベルが高く、そんなことではもう、幸せを味わうことができない。

────なぜ進化は、そんないじわるな設計を心に施したのか? それをこれから説明していく。
ここから先は
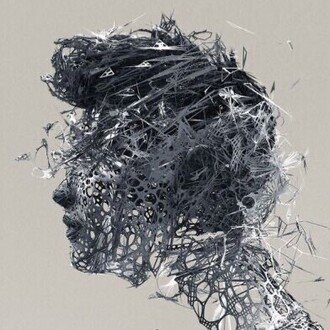
進化心理マガジン「HUMATRIX」
進化心理学(EP)「遺伝子とは、無意識のうちに私たちを動かすものなのだと頭に入れておいてほしい」by ロバート=ライト.心の働きは母なる進…
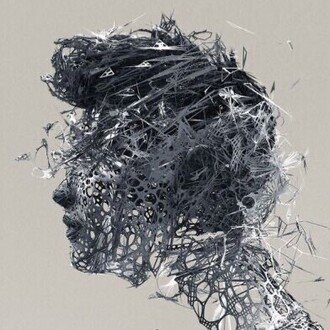
エボサイマガジン|EvoPsy Magazine
【初月無料】月額購読マガジンです。マガジン「HUMATRIX」の内容含め有料記事が全て読み放題になります。毎月計7万字のボリュームで新しい…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
