
裸のサル: 我々人類はなぜ「けもの」ではなくなったのか〜獣の登場から体毛の喪失まで #wayfa|進化心理マガジン『HUMATRIX』
" 進歩を求める中でも、我々の裸のサルとしてのルーツを忘れてはならない。"────デズモンド·モリス『Naked Ape (裸のサル) 』
✔︎獣の登場

「獣(けもの)」という日本語の由来は「毛のもの」。カラダが毛で覆われた哺乳類の特徴を指した言葉だ。
哺乳類の体毛には、体温を維持する役割がある。ファーのコートやモコモコのセーターを持っている人なら、それに保温性があることは実感できるだろう。ふわふわの体毛が生えていることで毛と毛の間に空気の層ができ、暖かさを維持することができるんだ。

哺乳類は体毛を動かしてこの空気の層の厚さを変えることもできる。寒さを感じた哺乳類は毛を逆立てて空気の層を厚くして、熱損失を防ぐためのバリアを強化する。
俺たちサピエンスも外が寒いと思わず鳥肌を立てるけど、これは150万年も前に失った毛皮のコートを拡張しようとする哀れな試みといっていい。
体毛の進化的起源はなんだったんだろう?
現在では、防水のために進化したという「ロウソクの芯」仮説が有力らしい。どういうこと?
すべての生物は水中から進化したので、生きていくためにはカラダの中に一定量の水分を保持しなくちゃいけない設計になっている。
じつはハ虫類のウロコは、陸上に進出したときに乾燥を防ぐために進化的に備わった装備なんだ(たまにそれに失敗してカラカラに干からびたイモリが路上に転がっている)。

一方、俺たちホ乳類の祖先はウロコという乾燥防止・防水装備は持たないけれど、かわりに脂(あぶら)でカラダをコーティングすることで撥水機能を持つようになった(水と油ははじきあうからね)。
スキンケアの基本は化粧水を塗ったあと乳液という脂で蓋をすることだ。あれと同じ理屈で水分を体の中に閉じ込めることができる。
そのあぶらを体内から押し出して皮膚表面に染みわたらせる際に、油を伝わせるロウソクの芯みたいなものがあると便利だ。哺乳類の祖先に生えていた当初の「毛」は、どうやらこの役割を果たしていたんじゃないかと推論されている。*D. Dhouailly (2009)

────ところが、進化とは既存の機構の転用(コオプション)で起こる。
脂性分泌物を皮膚表面に伝わせるために生えていた毛は、やがて断熱・保温のために使われるようになった。もともとある使用用途をもっていたパーツが世代を重ねていくにつれ別の用途のために使われるようになっていく──「何のため?」の目的が変わっていく──というのは進化のお馴染みのやり方だ。
現在の哺乳類の毛には保温という目的/機能に加えて、さらに外傷を防ぐクッションとなる機能、皮膚がじっさいに接触する前に環境を察知する機能(猫のヒゲを思い浮かべてほしい。ヒゲに限らず全身の毛でもそれができる)もつけ加わっている。
これらも機能の転用(コオプション)だろう。

こうして毛の生えたもの-獣-が地球上に現れた。
獣たちにふさふさの毛が生えている最も重要な理由は保温だ。ところでなんで保温しなくちゃいけないんだろう?それは哺乳類が恒温動物だからだ。爬虫類は──日光浴をするトカゲのように──外部の熱源に頼ってカラダを温めるが、哺乳類はみずからの体内で熱を作り出して維持する。
哺乳類の内温性の進化は、幅広い「温度ニッチ」への進出を可能にしたといわれている。自分の体のなかで代謝熱を作り維持するしくみのおかげで、哺乳類は外部温度の支配から脱することができた───ようするに、夜や寒い地域への進出が可能になったんだ。
初期哺乳類はみんな夜行性だった。これはあきらかに、当時の地球上で〈昼の世界〉を支配していた恐竜たちを避けるためだろう。恐竜のような爬虫類は夜は体温が下がって動けなくなる。哺乳類はその隙をついて動き出した。深夜といえば、ネズミたちが屋根裏をイキイキ駆け回り出す時間だ。家にネズミなんて出ないよ!そんな不潔な家に住んでないから!という人でもアニメ・トムとジェリーくらいは見たことがあるだろう。

〝温度〟は生物学的反応の基礎だ。
生物の体内の生理反応は熱がなくちゃなにもはじまらない。すべての生物は化学物質が寄り集まった存在で、酵素によって反応を起こしている。そしてこれらの物質はすべて物理と化学の法則に支配されていて、温度に関するルールにはこういうものがある:「物事の起きるスピードは温度によって決まり、温度が高ければ高いほど速くなる」

そんなわけで体温が高いほど、動物のあらゆる能力は高くなる。* 移動、逃走、捕食、消化、思考、成長、生殖……etc。体温が高いカラダをもつ生物ほど、これらあらゆるシーンすべてで処理スピードが速くなる。すると生存競争で有利になるのは言うまでもない。哺乳類、万歳!!!!
*D. Liam (2019)
とはいえ、生物は無限に体温を高められるわけじゃない。体温が上がると細胞内のミトコンドリアシステムにおいて、電子の漏出によるフリーラジカル発生のリスクが高まる。酸素というのは元々「毒」であっただけあって、非常に取扱注意の物質なんだ。
>フリーラジカルとは?
たぶん、生物がリスクを最小化しメリットを最大化できる限界温度が37℃付近だったんだろう。すべての哺乳類はこの進化的な限界にすでに達していて、だから哺乳類の大半は35-38℃のあいだの一定値に体温を保っている。もちろん、ラクダのように44℃まで体温が上がっても耐えられる仕組みを進化させた特殊なヤツらもいるけれど、そういうときはラクダも熱を引いていて、体は気だるそうで、素早く動けるってわけじゃない。
体内の内部温度を一定の高温で維持することで(温度を一定にするのも化学反応を安定に促進するためには重要なことらしい──パンをオーブンで膨らませているとき、いちいち温度を変えるのは良くない)哺乳類は爆発的に代謝率を高めることができた。哺乳類の基礎代謝率(BMR)は、同じ体重の爬虫類のおよそ10倍だ(すげえ!!!!!!!)。
高い活動性と高い有酸素運動能力を進化させた哺乳類は、やがて爬虫類を圧倒するようになった。イグアナ(体重4kg)は1時間で0.5キロほどしか走れないが、イヌ(体重4kg)は同じ時間で5キロを走破できる(これも10倍だ)。その差は歴然だ。*

*Bennett & Ruben (1979)
とはいっても、運動能力がアップした分、カロリー支出も莫大に増えてしまったという問題もある(これはけっこう大問題)。爬虫類のワニは、川に潜んで水を飲みにくるヌーを一頭でも食べれば、それだけであと一年間(引きこもりニートのように動かずじっとしていればの話だが)何も食べなくても生きられる。だがただ生きるだけでカネ(カロリー)がかかる哺乳類の場合はそうもいかない。日中ただ寝ているだけでとくに何の活動もしていないニートでも真夜中にコソコソと起きてきては家族用の冷凍食品を一人で爆食いしているだろう。哺乳類は生存のための「維持費」が高いんだ。

哺乳類の代謝率の高まりは、ようするに、スローに生きている爬虫類に比べて、人生がファストになったことを意味する。速く走り、速く狩り、速く食べる。そして子どもを速く成長させる。体温が上がると化学反応の速度は上がる。そして子の発生も速くなる。進化は再生産(リプロダクション)が鍵を握っている。
C.ファーマーは、恒温動物の進化の鍵は、親による子育てだったのではないかという説を提唱している。* 胚は温度変化に極めて弱く、体内の温度を一定に保たなければ破壊されたり深刻な障害を引き起こす。だから哺乳類は体温を一定に保つ方向に進化した。また、熱はさまざまな事象を加速させることができる。親が体温を高く保てば胚の発生は速くなる。だから哺乳類は体温を高く保つようになった・・・っていうわけだ。

卵は、恐竜をはじめとする肉食動物の格好の餌食だ。子どもを守るため、哺乳類は体の中で子を育て、生まれたらすぐに立ち上がり自立できるようにした(芋虫みたいな状態な生まれてくるヒトの赤ん坊は例外だ。ウマの出産動画をみよう!哺乳類の赤ん坊はデカく、すぐに立ち上がり、歩き出す!)。体内の熱で発生を加速させ、ある程度成熟した状態で子どもを世に生み出すというのが、一般的な哺乳類の特徴だ。
ほかにも動物界では子の発生を促すために熱を注ぎ込む例は多い。鳥類の抱卵もその一つで、鳥たちが哺乳類同様に体温を高くするという進化を遂げたのもそのため(=子の発生を促すため)だ、とファーマーは論じている。

*C. Farmer (2000)
いずれにせよ、
哺乳類の毛は〈体内の熱を逃さないため〉に備わっているパーツ
なんだ。
✔︎オーバーヒート問題

ここから先は
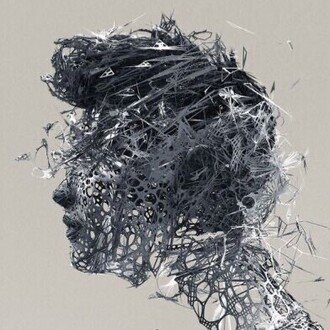
進化心理マガジン「HUMATRIX」
進化心理学(EP)「遺伝子とは、無意識のうちに私たちを動かすものなのだと頭に入れておいてほしい」by ロバート=ライト.心の働きは母なる進…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
