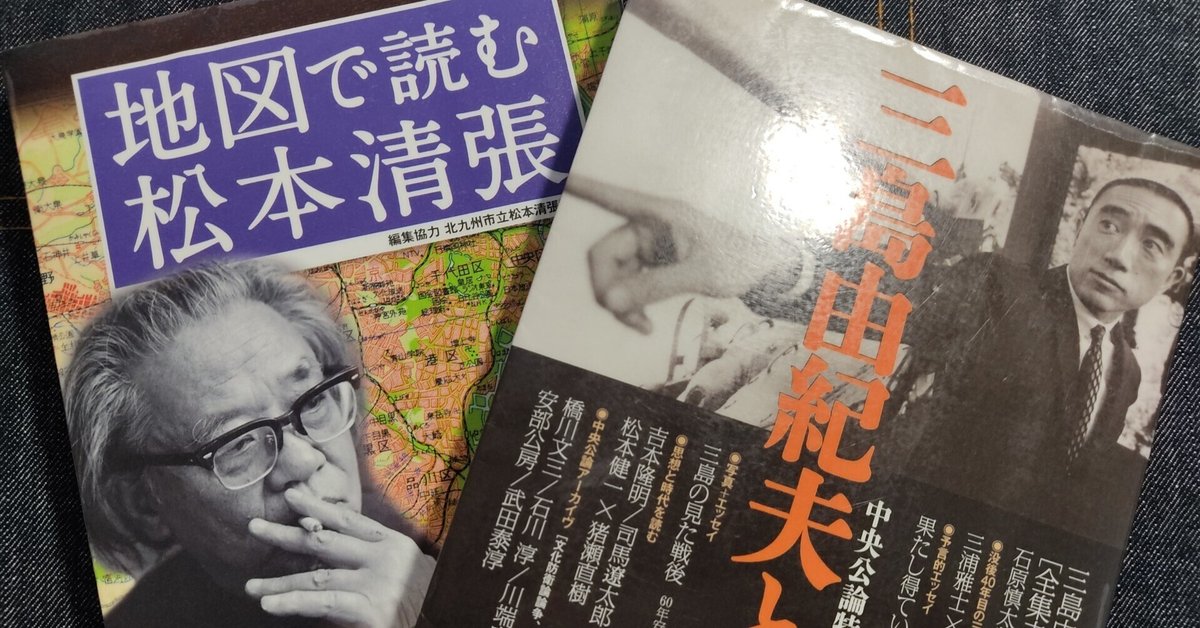
三島由紀夫と松本清張
明日2/2(金)20:00~より、「ことのは」のYouTube にて私のインタビュー後編の配信があります。前編と同じく、最初の1週間のみどなたでも無料で、その後は有料会員限定となります。
前編配信の際に書いた内容の続きで、今回もエッセイを載せておきます。お楽しみくださるなら幸いです。
ーー
三島由紀夫が松本清張を嫌っていた、という有名な話がある。もちろん誰にでも好き嫌いはあるが、『三島由紀夫と戦後』に入っている関川夏央さんの論によると、こんな感じだったらしいから、ちょっと凄まじい。
紛糾したのは〔一九六三年〕七月十七日の第三回である。この日、『日本の文学』に松本清張作品を入れることに三島由紀夫が強硬に反対した。のみならず三島は、松本清張を入れるのなら〔編集〕委員をおりる、『日本の文学』から自分の作品も辞退するとまでいいつのった。
『日本の文学』は中央公論社が企画した全集シリーズで、社長の嶋中鵬二が三島に頭を下げ、続く4回目の編集会議では谷崎潤一郎も清張作品の収録にOKを出したが、最後まで三島が拒絶して不採用になったという。ほとんどイジメというか、今ならパワハラ疑惑で「文春砲」されたかもしれない。
いったい清張のどこを、そこまで三島は嫌ったのだろう。
だいたい三島自身が、風俗小説の『美徳のよろめき』(1957年)で稼いでいたし、『美しい星』(1962年)はSFと呼ばれることもある。直近の選挙を題材に使った『宴のあと』(1960年)に至っては、むしろプライバシー訴訟の判例の方で有名になってしまった。それにはずいぶん、三島も傷ついたらしいけど。
要するに三島本人だって十分、ジャーナリスティックでキッチュな作家だったのだ。だから清張のことを「しょせんはミステリー作家」のように見下していたとは、あまり思いたくない。
関川さんの解釈とは違うのだが、ぼくはむしろ清張が描くミステリーの「解かれ方」に、三島は不満だったのではないかと思っている。
清張作品では、犯人はかなり緻密なアリバイ工作や、証拠隠滅を遂行するのに際し、探偵役の側は驚くほどあっけない「偶然」から、謎解きのヒントを得ることが多い。
たまたま目にした雑誌や新聞の記事や、休息中に小耳に入った周囲の雑談から、「あっ!」と閃いてしまうわけだ。『点と線』(1958年)でも『砂の器』(1961年)でもそうだし、『ゼロの焦点』でも事件の真相を見抜く最大の契機は、ふとスイッチをひねったテレビで流れる番組での会話である。
三島のように、なんというか「宿命や必然」を求めて生きるタイプの人にとって、これはものすごくイラッと来る作風だったんじゃないかと思う。
なにせ本人の主観では日本を「本来あるべき進路」に戻すために、クーデター未遂を伴う拡大自殺を綿密に計画して、最期を遂げる人である。そうした美学からすれば、小説の主人公として英雄的に描かれるのは実存を賭けて犯行に踏み切る側であるべきで、それが「いや〜、でも運が悪くて全部バレるんですよ」なんて、一番あってはいけない結末じゃないだろうか。
かくも傲岸な三島に嫌がらせをされた、被害者の清張の側は相手をどう見ていたのか。
三島が自決した翌日(1970.11.26)の『朝日新聞』で、清張は楯の会が散布した檄文が、2.26事件のコピーにすぎないと暴露している。「三島の文章もアジテーションとなると通俗的で平凡」・「例の文語体系のものだが、高踏的な調子は落ち、安っぽい語いが目につく」・戦前との「一番大きな違いは、三島の行動がつくりごとだったこと」とボロカスな言いようだ。まぁ、たぶん意趣返しなんだろう。
でも、後年に昭和の天皇制の問題に取り組むに際しては、清張は三島の『豊饒の海』を創作ノートに至るまで読み込んだ上でその長短を評価し、自身の鑑としていたらしい(原武史『松本清張の「遺言」』文春文庫、41-45頁)。
戦後という時代を生きた人には、やっぱり「本物」が多かったんだと思う。本物どうしだからこそ、たとえ大嫌いな相手を叩くうえでも、まずは相手の思想に実際に触れて掘り下げ、その本質をしっかり掴もうとしたわけだ。
それに対して、令和に居るのはせいぜいが「ホンモノ」くらいのもので(含む自分)、その条件は本人自身はそうなれないまでも、少なくとも「本物」がかつては存在したことを意識していることだろうか。
一方、ネットでちょっとムカついたらテキトーに検索して因縁をつけ、フォロワーに「さすが○○先生!」とお追従を言ってもらって勝利宣言するのが「ニセモノ」である。そうした事案は第三者委員会のような形で精査し、検証結果をディスクロージャーしてゆかないかぎり、人文学が再び「読む価値がある」と思ってもらえる日は来ないだろう。
P.S.
三島と清張との対比では、(いま手元にないのですが)仲正昌樹『松本清張の現実と虚構』にも、優れた両者の比較論が入っています。
また、昨年夏に司馬遼太郎と対比しながら清張を論じたゲンロンカフェでのイベントは、いよいよ視聴期限が今月末(2/29)まで!
