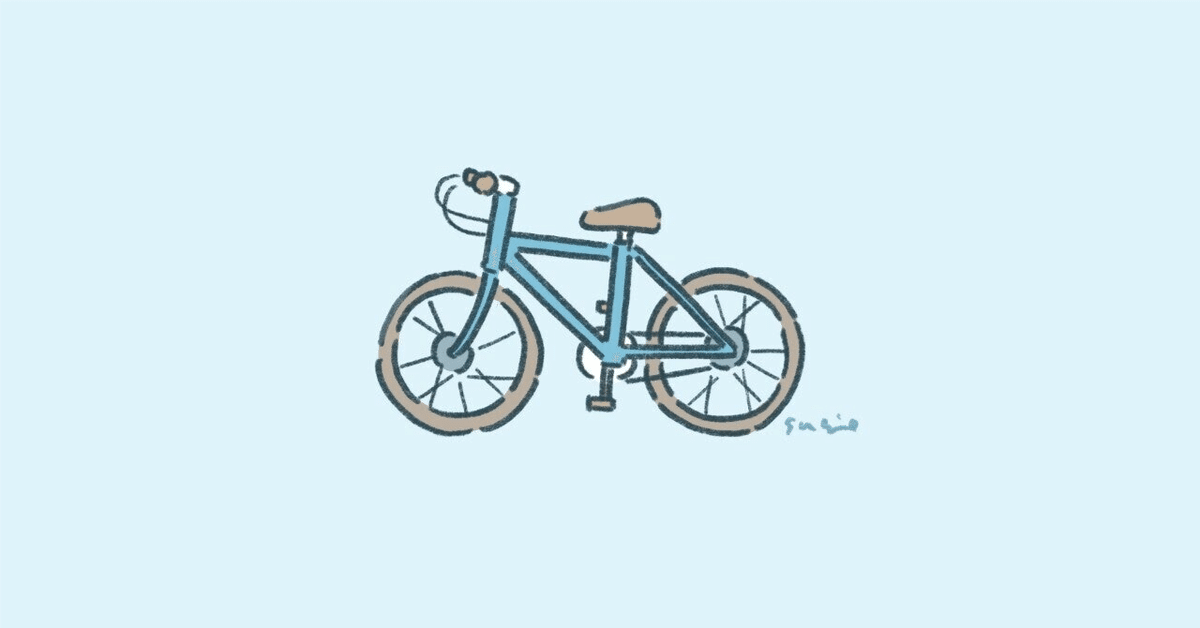
吳明益『自転車泥棒』 世界文学としての台湾文学と人新世[アントロポセン]
大学院の特別講義で、台湾におけるネイチャーライティングの講義があり、その予習として吳明益『自転車泥棒』を読みました。その読書感想文と、講義で感じたことなどをメモしておきます。
呉明益(ウ・ミンイ 繁: 吳明益, ローマ字転写:英: Wu, Ming-yi 1971年6月20日生まれ)は、学際的な台湾の作画家、小説家。輔仁大学文学部マーケティング学科 (今はコミュニケーション学部に所属) 出身、国立東華大学の中国語文学の教授、環境活動家でもある。生態学的な寓話『複眼人(英語版)』(2011年)は2013年に英語版が出版された。チョウのイラストを描き、生態をまとめた著作もある。
感想文
台湾でかつて製造されていた幸福自転車。台湾の複雑な時代背景の中で、自転車をはじめあらゆるの物質や動物が、さまざまな角度で対比され、ストーリーに組み込まれています。
台湾文学の中で切り離せないのが日本統治時代(植民地時代)や戦争の描写。物語の軸となる自転車は、銀輪部隊における兵器として。東南アジアのジャングルに住むゾウも、戦争によって運命を変えられてしまいます。この非人間、ネイチャーライティングの核となる部分の描写は、台湾の日本統治時代を理解するという点においても重要な役割を与えられています。
自転車が主役の物語ですが、印象的だったのは前述のゾウのように、人間によって捕獲され運命を変えられてしまう動物達。ジャングルで無残に死んでゆくゾウ、動物園で処分されゆく動物、多くの動物の死は、植民地支配と資本主義が引き起こした搾取の結果でした。
「でも、ここの動物たちが本当に自分達の時間を過ごしていると、感じますか?」
「時間はたしかに自分のものだと、確信がありますか?」
ムー隊長が、動物園の檻の中で過ごす動物を見て静子に問う言葉です。
動物たちは本来、体に合った空間の中で過ごしており、その空間はまた時間の測り方そのものを規定している。一方人間は時計を発明し、時間の測り方は文化や生活習慣、規則に属するものとなってしまった。
私たちは、動物園の檻の中の動物達ではないだろうか?どれくらいの時間を、身体性を持って過ごせているだろうか?動物の描写を通じて、現代の生活について考えさせられてしまいます。時間が縛られているからこそ、週末自然に触れたくなりますよね。笑 趣味のサーフィン(ボディーボード)は自然と身体性が密接につながるスポーツで、だからこそ面白さや心地よさを感じるのかもしれません。
世界文学としての台湾文学とアントロポセン
先日、台北の台湾文学基地にて、台湾ネイチャーライティングを研究しておられるChang, Ti-Han氏のセッションに参加しました。
人新世(アントロポセン)の定義、そして台湾文学会での試みはかなり実践的だと感じました。私自身、人新世という言葉自体の意味をちゃんと理解できていない状態だったので、そこを文学の表現から実践し定義する試みは非常に興味深く、大変意義のあることだと思いました。
台湾の主なアニマルライティングの著者として、Liu Ke-Hsiang・Liao Hung-chi・Wu Ming-yiの三名を挙げ、オーシャンライティングの著者としてSyaman Rapongan・Liao Hung-chi・Lu Ze-zhiを挙げており、その動物分野と海洋分野の両面からその特徴などを知る事ができました。
Chang, Ti-Han氏の論文を読むと、「自転車泥棒」についてより深まります。
Shaping Taiwan's History through Non-human Agents: Wu Ming-yi and His Postcolonial Ecological Writings
https://clok.uclan.ac.uk/33153/
まとめ
ルポライティングやドキュメンタリーとしてのネイチャーライティングにしか触れてこなかったのですが、今回初めて、小説という形でのネイチャーライティングを読みました。吳明益氏は後記で「小説のかたちにすることで人を理解し、人を思考するために書いている」と言っています。自転車泥棒はじめネイチャーライティングの読書体験を通して私たちも人間の思考を熟考し、今日の環境問題やさまざまな現代問題に対する多角的な思考の取っ掛かりになるのではと思います。さらに翻訳と思えないくらい自然に入ってくる文章だと思うので、是非多くの人に読んでほしいなと思う一冊です。
