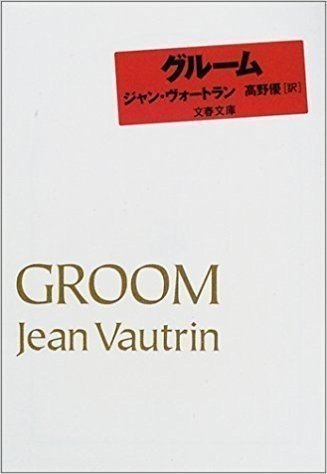闘いの日々に夢見たようなハッピーエンドを――『ディーパンの闘い』
【週報】2017.12.04-11
よう。下品ラビットだ。
年の瀬も押し迫ってきて、いよいよみんな大変そうだな。あんたはどうだい。毎日大変かい。
そうかい。そうだよな。生きていくのは大変だよな。お疲れ様。
おれはインテリの読書家だから、年の瀬というと井原西鶴の『世間胸算用』を思い出す。江戸時代の生活を、大晦日の一日に題材をとって、経済的な側面から描いたオムニバス小説さ。
全二十章の短編は、どれもひとかたならない苦しみとつらさのドラマがあり、しかし、どこかさっぱりとしておおらかだ。それは、どんなにつらかろうが苦しかろうが、生きているものは生きていかなければならないという、生物としての普遍的なありさまが描かれているからだ。それは生き物の形態に関わらず、時代に関わらない。そのありさまが、「金」という流れによって新陳代謝する「都市」という近代的な場でどうなるのか、が『世間胸算用』では描かれている。『世間胸算用』は江戸時代の小説だが、今も昔も、「社会」を動かしている「金」と、それなしに生きられない人間の悲喜こもごもは、変わらないのさ。

『ディーパンの闘い』も、スリランカからフランスに逃れた難民の「ディーパン一家」を、主にその「父」を主軸に描きながら、そうした「生きること」について語る映画だ。
映画の冒頭、軍服姿の「父」は誰ともわからぬ死体を燃やす。「母」はゲットーのようなところで少女を買う。軍服を脱ぎ、「母」と合流した「父」は、少女をつれて闇市へ行き、国外へ脱出するためのパスポートを得る。パスポートの名義は「ディーパン」。そう、彼ら三人はほんとうの家族ではないし、「ディーパン」ですらない。内戦で死んだ「ディーパン一家」のパスポートを得るために、急ごしらえで組み上げられた疑似家族なんだ。

ここでちょっと歴史の講義だ。
スリランカは、1980年代からつい十年ほど前の2009年まで内戦状態にあった。二次大戦前後、イギリス植民地「セイロン」だった時代に、植民者に寄って少数派民族のタミル人が重用さ、その反動で1950年代から、今度は多数派であるシンハラ人に優位な政策がとられるようになった。結果、タミル人はスリランカからの分離独立を目指す「タミルの新しいトラ(TNT)」を組織。そして、その後身である「タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)」が、政府へのテロ活動を行ったことから、内戦状態に突入した。
「ディーパン一家」の「父」は、この「タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)」の兵士として闘った人物だ。彼は内戦で多くの人を殺し、同時に、自分の家族も殺されている。彼が燃やしたのは、そうして彼が殺した敵の死体であるかもしれず、仲間の死体であるかもしれず、家族の死体であるかもしれない。内戦は2009年、LTTE最高指導者の死で集結したが、その直前、LTTEは内戦によって難民となったタミル人を人間の盾に籠城作戦を決行していた。
こうした、地獄のような内戦状態から脱出する三人は、だからなりふり構っていられない。「父」と「母」は、少女を買い、パスポートを買ってまで国外に脱出しようとする。「金」の力は、個人を超えて強い「社会」の力であり、弱い個人は社会に対抗するためにその力を使わなければならない。
しかし、ある社会を逃れて、別の社会に赴いても、個人が個人であることに代わりはない。しかも彼らは不法入国者の難民だ。別天地は、「ここ」という「今いる場所」が絶対的な反証となってはじめて「ここではないどこか」の理想郷となる。別天地を知り、それが「ここ」になってしまえば、そこは理想郷ではなくなってしまうんだ。
だから、彼らが「ディーパン一家」として生活を始めることになったタイミング、すなわちスリランカを脱出したところで、映画のタイトルが画面いっぱいに現れるのは正解だ。彼らの新たな「闘い」はここから始まるんだからな。
しかし、その「闘い」の初陣の、なんと悲壮なことか。闇の中から現れる「父」の姿は、地獄のような内戦を生き抜いた兵士とはあまりにもかけ離れた姿だ。

ぴかぴか光るリボンだかネコミミだかをつけて、観光地で雑貨を売り歩く、憮然とした顔つきのおっさん。
このシーンは、笑っちまうような図ではあるが、それだけに張りつめた緊張感がある。彼がしているのはもちろん違法な商売だが、彼にはそれしか仕事がない。警察に追われながら、故国の戦場にも等しい、夜の町を生き抜かねばならない。
家に帰れば、「母」である見知らぬ女と、「娘」である見知らぬ少女が暮らしている。二人の生活もまた「闘い」だ。自分の生んだ娘でなく、自分を生んだ母でなく、利害関係で結びついただけの他人とともに暮らさなければならないのはサバイバルだよな。いや、たとえ血がつながっていようと、他者とともにあるというのはある種の政治であり、ある種の闘いであるということを、おれたちは容易に忘れてしまう。それは、その種の「真実」を見つめることがキツいからだが、目をそらすには「愛」という前提や「相互理解」という成果が必要だ。それがない彼ら「ディーパン一家」には毎日が内戦状態と言ってもいいだろう。
やがて、彼らはフランス郊外の団地へと引っ越す。「父」がそこで住み込み管理人の仕事を斡旋されたからだ。斡旋したのは、どうやら彼らに先んじてフランスに逃れたらしい男。ということは、この仕事もまた、ある種の違法性をはらんでいる。
彼らが住みついた団地は、さびれ、荒れ果てている。住んでいるのは「ディーパン一家」のような移民や、フランス人の中でも明らかに低所得貧困層とおぼしい人々、そしてチンピラどもだ。これは「バンリュー」と呼ばれる、貧困と犯罪の横行するスラム化した地域の一つだ。
おれはこの団地のロケーションを見て、この小説を思い出した。
(画像クリックでamazonの商品ページに飛びます)
ジャン・ヴォートランのノワール小説『グルーム』は、おれの大好きな文春文庫が、2000年代初頭に海外パルプホラー/ノワールを精力的に翻訳刊行していた、そのうちの一冊として邦訳された作品だ。
パリ郊外の荒涼とした団地を舞台に、「自分はホテルのいけてるベルボーイ少年だ」と思いこむ孤独なひきこもり青年の妄想の世界が、現実世界の過酷さを避けられず、少しずつ崩壊していく過程を語りながら、この小説は世界の歪みを描き出す。主人公は狂人だが、その狂人を閉塞感の中に閉じ込め、押しつぶす世界もまた狂っている。
文春文庫版『グルーム』の訳者・高野優氏による巻末解説から引用するとこうだ。
[前略]四角く、無機質な郊外の団地は、非人間的なものの象徴である。[中略]ヴォートランの登場人物たちはこの非人間的な空間のなかで権力(制度)と戦い、そして破れてきた。
これはまたある人の言うように、団地に象徴される冷たい合理主義と人間が持つ無意識の衝動との戦いでもある。冷たい合理性はいかに巧みに人々を管理しているようでも、時おり暴力となって噴出する人々の無意識の衝動を抑えることはできない。
ここに『ディーパンの闘い』との共通点がある。「冷たい合理主義」の象徴としての「団地」像だ。『グルーム』の原語版が書かれたのは1980年だから、『ディーパンの闘い』の間に約30年の隔たりがあるが、その間に「『冷たい合理主義』が支配する世界」の構造は変わらなかった。「団地」に住む貧困層がチンピラと移民にすり替わっても、「団地」という構造だけがぼろぼろになって残されている。その団地を維持管理[グルーム]するのがスリランカ難民の移民のおっさんだってのが面白いよな。
ということは、『グルーム』との共通点はもう一つあるってことになるよな。そう、閉塞感に捕われ、押しつぶされようとする人物だ。
もちろん、それは「ディーパン一家」のことだ。言葉の通じないフランス人たちに囲まれて働かざるを得ない「父」、「父」以上にフランス語ができないために、仕事がなく、家にいつづけなければならない「母」、そしてふたりよりはフランス語ができるので、「一家」がフランスにいつづける法的な根拠として学校に通うことになるものの、やっぱり移民なのでさっぱり受け入れてもらえず孤立する「娘」のことだ。三人は三人とも、彼らを排除するか、押しつぶそうとする現実の前に鬱屈する。
しかし、彼らは生きていかなければならない、闘わなければならない。
そうした「闘い」を生きるのは彼らだけではない。

このフランス人の男は、ヤクの売人だ。団地にたむろするチンピラに監視され、『グルーム』の主人公が「団地」の一室に引きこもっていたように、「団地」という檻の中にとらわれている。足にGPSをつけられているようだから、もしかしたら帳簿係かなにかかもしれない。売人は、なにやら障害があるらしい叔父と一緒に暮らしている。
ここへ「ディーパン一家」の「母」が、彼の家に家政婦としてやってくることで、物語に登場することになる。「母」はフランス語がしゃべれないが、障害のある叔父の介護には会話は不要なので、この仕事を斡旋された。「母」は売人の叔父のために料理を作り、時折売人や彼の元を訪ねる男たちにも料理を振る舞う。彼女の料理はうまいらしく、売人は「母」に心を開き、フランス語を解さないだろう彼女に孤独を語る。「母」もまた、タミル語を解さない売人に心を開き、身の上話を語る。

面白いのは、このあと。帰宅した「母」は、その晩、帰宅した「父」を誘ってセックスをするんだ。
それまで「スリランカを脱出する」という利害関係だけで同居し、異国での生活の心細さから家庭内内戦状態にあった「偽の夫婦」の二人が、はじめて男女として結ばれる。
彼らの心にあった壁が、いささか唐突に解消されたのはなぜか。理由は二つ考えられる。
一つは、それまで誰にも受け入れられなかった、個人的な悩みを、たとえ言葉は通じなくても誰かに話せたことで、「母」の心が解きほぐされたから。
おれは、人の気持ちというのは、心の中にだけあっては、本人にもしかと把握できないものだと思っている。口に出すか、文章にするか、行動に表すか、いずれにしても「行動」に結びつけることで、人は自身の感情を外在化し、確認することができる。逆を言うと、それをしなければ、自分がどういう気持ちを持っているか、人は我がことながら知ることはできないんだ。「母」は売人に自分の苦しみや不満や悔恨を語ることで、自分の中のもやもやに形を与えられた。だからすっきりして、一人の人間として「父」と向き合えたんじゃないか。
そしてもう一つ、おれはこれが強いと思っているんだが、売人が「父」と同じものだからだ。売人に心を開くことは、「父」を受け入れることになるんだ。
売人は、彼が売人であるというのと同じくらい、障害を持つ叔父のために、チンピラの巣である「団地」に縛り付けられている。そういう自分を知って、できることとできないことを切り分けた上で、やるべきことをしているんだ。それは「父」も同じだ。彼は故国にあっては兵士として、家族とともにある「生活」のために闘い、故国を脱してまでたどり着いた、フランスという「団地」の中でもまた、「家族」とともにある「生活」のために管理人として戦っている。

生きるために苦境に立ち、望まぬながらもやるべきことをやり、戦っている人として、「父」と売人は同じものなんだ。
おれが後者を強い理由と思うのは、映画の結末と結びついていると感じるからだ。
「父」と「母」のセックスと前後して、中盤徐々に打ち解けていった「ディーパン一家」は、しかし売人を擁する「団地」のチンピラたちが、別なチンピラに襲撃された事件を境に、再びぎくしゃくしはじめる。父は石灰ライン引きを自作してまで、「団地」の中庭に白線を引き、非武装地帯を宣言したり、普段チンピラたちがたむろしているロビーを占拠して、同じスリランカ難民と思しい男たちとたむろするようになる。その姿に、「母」はスリランカ時代を思い出す。どうして平穏に暮らせないかと嘆く「母」と、生活を守るためだとしか言わない「父」は平行線を辿り、最終的に「父」は管理人室に引きこもるようになる。家庭内内戦状態の再開だ。
ここで、「父」が、ずっと財布の中にしまっていた「ほんとうの」家族の写真を見るところがグッときた。彼の「ほんとうの妻子」は内戦で死んでいる。彼は扉付き飾り枠を自作して、写真を大事に収める。過去を大切に振り返る勇気を持てたことと、過去を封印して未来を見ようとすることが重ね合わされているように思えるんだ。
そこへ、「母」から電話がかかってくる。「母」はチンピラによる売人の襲撃現場に居合わせてしまったんだ。売人の叔父はサブマシンガンで蜂の巣にされ、売人も重傷だ。その売人が、逃げようとする「母」を離してくれない。銃を突きつけて助け出してくれと懇願する。
電話を受けた父は、マチェーテとドライバーで武装し、襲撃犯のチンピラを殺して銃を奪う。

「父」は頭部に被弾しながらも、車で売人のいる棟に突っ込み、階段を上りながら襲撃犯を次々と倒していく。その姿は、「タミル・イーラム解放のトラ」が甦ったかのようだ。
このシーンは、映画に対して使う言葉じゃないが、まさしく「映画的な」シーンで興奮したぜ。階段を上りながらマチェーテと拳銃で次々襲撃犯を倒していく「父」はアクション映画のヒーローそのものだし、そのときの「父」の顔を映さないことで、「父」の内面を想像させて引き込まれる。
最終的に「父」は「母」の元へたどり着く。結局売人は死んでいたが、彼は「母」を救出した。そしてイギリスへ逃れた「ディーパン一家」を映して映画は終わる。

彼らはいつまでも幸せに暮らしました。
ほんとうにそうだろうか。
このラストは明らかにちぐはぐだ。最後だけいきなりアクション映画のようになって、なだれ込むようにハッピーエンドじゃ、それまでの「どこまで続くかわからない生=『闘い』」のトーンとズレまくっている。
だが、これを「ごほうび」だと考えれば納得できる。そう、これは「闘い」が終わった「父」の見る夢だ。辛く苦しい生が報われて、もう守るために、奪われないために、なにもしなくて良くなった夢。
これは死んだ売人の見ている夢でもあるだろう。だからこそ、彼らは同一人物でなければならない。
そして、それは、スクリーンや画面のこちらがわにいる、おれたちの夢でもある。
おとぎ話が麗しいのは、それが夢だからだ。現実に憂いた魂を優しく包み込むことができるのは、現実ではない。だからおれたちは映画を見るし、小説やマンガを読む。ここではないどこかの物語に耽溺する。
だが、それは、生きている限り、ひとときの夢でしかない。そうであるべきなんだ。
なぜなら、現実はつらく苦しいばかりではないからだ。現実には現実の喜びがあり、楽しみがある。現実のつらさを否定することは、現実の喜びを否定することにもなりかねない。物語だって、そうした現実の喜びの一つじゃないか。
だが、物語への過度の耽溺は禁物だ。まして、「いつまでも幸せに暮らしました」なんて夢に溺れては、「いつまでも」と「幸せに暮らしました」の間に、あまりにもあたりまえなこととして省略されたことばを、なかったことにしてしまう。「いつまでも」と「幸せに暮らしました」を直結してもいいのは、生きるという闘いの終わったときだけなのさ。
あまりにもあたりまえすぎて省略されたことばとはなにか。それに答えるのが、『ディーパンの闘い』という映画だ。
といったところで、今回は終わろう。この週報が、おれの2017年最後の週報になる。
付き合ってくれてありがとうな。
来年は来年で、また新しい闘いが始まる。おれにも、あんたにも。そして、それは、今年がそうであったように、なにも辛いことばかりでもないはずだ。
おれたちには明日があり、友達がいて、そしてまだ見ぬ本や、マンガや、映画があるんだからな。
だから、おれはまだ死なないのだ。
かならず、またお目にかかろう。

(下品ラビット)
いいなと思ったら応援しよう!