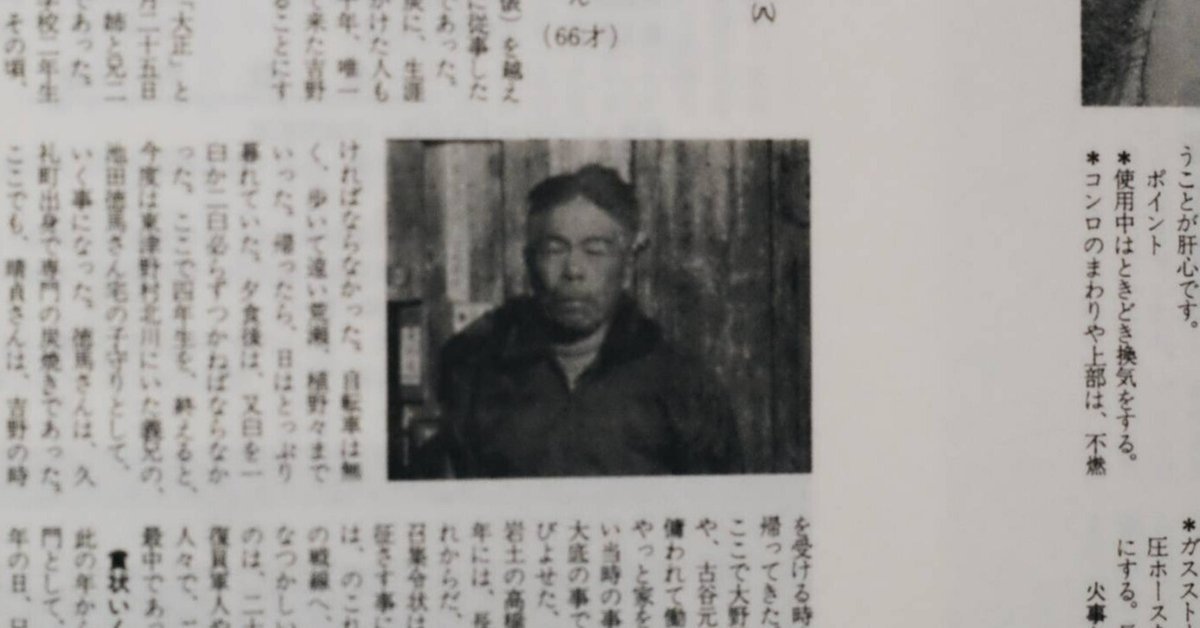
炭焼きという貴族のたしなみ。
これは、今からおよそ100年前に生きた炭焼き職人の話。
昭和53(1978)年の大野見の広報誌に編まれている。
炭焼きの歌
炭焼きは、汗と涙の仕事。山小屋でとまり、夜明けと共に、木をきり、日が暮れてからおく(おく:終わらせる)。そんなに働いても儲からない。 かつてふる里の山あいからは、薄紫の煙が、もうもうとあがっていた、そこには、窯と小屋と炭を焼く、たくましい人々がいた。
雪の日も、風の日も、まっ黒く、 よごれながらも、泣きごとを言わない山の男がいた。火は何時しか、一つ消え、二つ消え、山は元の静けさに帰った。後には、唯天井の落ちた窯だけが残った。もうあの山の賑わいは、帰ってこないだろうか。
暖房用、炊事用として、日本の各家庭で、なくてはならなかった木炭が、ガスや電気や灯油に、かわられて、はや十年以上たった。明治、大正、昭和を通じ、家庭燃料の王座の地位にあった木炭は、今は見る陰も無く、時代の波に、おし流されてしまった。戦後二十年間、木炭は郷土の代表的産業として、ピークの昭和29年には、本村で3000トン(二十万俵)を越える生産高を示し、これに従事した者も200人以上の盛況であった。今消えさらんとする木炭に、生涯の仕事として、青春をかけた人も多い。
今月は、製炭30年、唯一筋に、この仕事に生きて来た吉野の池田晴貞さんを訪ねることにする。
少年は負けず
晴貞さんは、後5日で「大正」と なった明治45年(1912年)7月25日萩中の寺本で生れた。姉と兄2人、弟1人の5人兄弟であった。
明貞さんの苦労は、小学校2年生になった時から始まる。その頃、父親の梅吉さんは、梼原で、梶三椏(かじ・みつまた=どちらも和紙の原料)の商買をしていたが、うまくゆかないままに、ふとした病気がもとで46歳の生涯を閉じたのである。資産とてない一家は、忽ち悲境のどん底に落ちこんだ。現在のように福祉対策の何一つない頃である、晴貞さんは、祖母さんのいる吉野の池田正成さんの所で世話になることになった。きびしい叔母さんのもとで学校から帰ると、中央校下全部へ新聞配達をしなければならなかった。
自転車は無く、歩いて遠い荒瀬、植野々(どちらも吉野から6kmほど)までいった。帰ったら、日はとっぷり暮れていた。夕食後は、又臼を一臼か二臼必らずつかねばならなかった(米の脱穀)。ここで4年生を終えると、今度は東津野村北川(大野見の隣町)にいた義兄の、 池田徳馬さん宅の子守りとして、 いく事になった。
徳馬さんは、久礼町出身(当時は大野見村の隣町。現在は合併して中土佐町になっている。)で専門の炭焼きであった。ここでも、晴貞さんは、吉野の時と同じく、学校から帰ると、子守り、雑用で遊ぶ間とて無い毎日であった。彼にはその少年時代、楽しく遊んだ思い出はない。然し、彼は決して境遇に負けなかった。
へこたれりせず、ひねくれもしなかった。元気一杯、兄の仕事を手伝った。五年生の終りには、炭俵2俵を前後にかたいで山道を運ぶようになっていた。
吉野に帰って
彼は東津野に満20歳、徴兵検査を受ける時までいて、故里吉野に帰ってきた。昭和7年(1932年)であった。
ここで大野民六助さんの移動製材や、古谷元次さん宅の米つきに、傭われて働いた。昭和14年(1939年)には、やっと家を建てた。住宅融資のない当時の事、腕一本での建築は並大抵の事ではなかった。母もよびよせた、昭和16年(1941年)には、船戸岩土(東津野)の高橋福美さんと結婚し、翌年には長男が生まれた。さあ、これからだ、という時、一枚の赤い召集令状は、彼を一兵として、出征さす事にしたのである。後に心は、のこれども、やがて大陸中心の戦線、そこで終戦。
懐かしい妻子の所に帰りついたのは、昭和21年(1946年)の2月で、故里は復員軍人や、戦災を受けて帰った人でごったがえしをしている最中であった。
賞状いく度
此の年から晴貞さんは、炭焼き専門として、一筋に取り組んだ。少年の日、兄の所で習ったのが、この仕事に入る動機であった。この仕事は、きびしく大かたが、山小屋で泊りこみ、時には夜通し、休むこともできないときもある。少年の日からどんなに苦しくとも、弱音をあげず、真面目に元気で生きぬいてきた晴貞さんの根性は、変わることはなかった。
いい木炭は、経験と研究によって、出来上がるが、彼は色々と研究をこらし、遂に「池田流」と称する方法を案した。
今、晴貞さんの居間には十に近い症状がずらりと並び、かつての熱意をうかがわせる。
中でも昭和21年には、時の田村村長より「不断の技術錬磨によって品質改善に寄与した功績」により表彰されたのと、35年、梼原、東津野、大野見三村連合の本品評会において、最高の知事賞を受けているのは、晴貞さんならではの感を深くするのである。
然し巨大な力による燃料革命によって木炭製造は、今や過去の産業となり、多くの業者は、古き者より、長く伝わってきたその職を放棄せざるを得なくなってしまった。晴貞さんもその一人であり彼が燃やし続けてきた炭焼きの火を消したのは、昭和46年(1971年)のことである。
晴貞さんも今年は67歳(1978年当時)。今も山の仕事に精出す毎日である。家庭的にも恵まれ、三人の子供は、それぞれ成長し、孫も5人となった。こうした暮らしができるのも子やらいができたのも炭焼きをしたお陰ですと、にこにこ笑いながら話す晴貞さんである。
まだまだこれからである。然しあの「池田流」の腕をふるう日は、もう再びはこないかもしれない。
【出典】
1978年2月 第143号 広報 大野見
(発行 大野見教育委員会/編集 大野見村広報委員会)
【考察】それでも心は動かない
たしかに晴貞さんの一生は、1940年に木炭国内生産量がピークを迎え、1962年の原油輸入自由化をきっかけに生産量が減少していった世の中の動向を映し出している。

「池田流」どころか、炭焼きという職業もろとも殆ど山に埋もれてしまった現代の暮らしにおいて、炭の存在感はないに等しい。
自由競争による淘汰の果て、備長炭などの炭が高級品としてある種の貴族文化に昇華されたように思える。
平凡な冬の昼下がり、近所で炭焼きをしているおんちゃんが炭窯から炭を出していた。自家用で作る炭はもっぱら調理で利用しているらしい。

炭には樫の木がいいとか、椿や椎の木はだめだとか、この割れ目が肝心だとか、「貴族文化」には似つかわしくないおんちゃんが熱弁を振るう。
かつて汗と涙で賑わった成長産業が、斜陽期をへて、炭焼き職人すら絶滅危惧種と成り果て、今や炭は嗜好品や娯楽の領域に達している。
残念ながら、わたしは普段の暮らしにおいて炭がなくて困ったことが一度もない。おんちゃんの熱弁を聞きながら、炭焼きが辿ってきた趨勢をただ咀嚼しようと努めることしかできなかった。
