
『武士たち』を鼓舞し続ける!フルリモで連続達成を叶えたマネジメント実践記録
はじめに
成果:急遽担当したマネジメントで2ヶ月連続の目標達成!
緊急プロジェクトとして2024年11月から12月にかけて、セールス部の中で最も売上規模が大きなチームのマネジメントを担当し、四半期目標と月間目標を連続達成!セールス部全体の成果にも大きく貢献することができました。
ほぼ全員がフルリモートという少し特殊な環境の中で、この結果はとても意味のあることだと思っています。
(緊急プロジェクト発動の背景は代表の福島のnoteに詳細👇)
キャリア背景:17年の営業経験と新たな挑戦
2007年に新卒で営業職に就いてから、約1年の育休を除きずっと営業に関わる仕事をしてきました。LayerXには2022年5月にフィールドセールスとして入社し、他部署を経て(👇など色々やりました)、2024年4月からはセールス部に戻り営業企画チームに配属。
新人メンバーのオンボーディングや案件支援を通してセールス部全体の成果を支える役割に挑戦してきました。
8月以降は「達成マネジメント」という緊急ミッションとして、既存メンバーの売上底上げに取り組むように。そして11月・12月の正念場では、売上規模が最大のチームを担当し、2ヶ月連続の目標達成を実現しました。
このnoteでは、フルリモート環境でのマネジメントの難しさをどう乗り越えたのか、また実際に行った取り組みや工夫をご紹介します。「武士たち」を鼓舞し続けた自分なりの経験が、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです!
1.フルリモートならではの難しさ
フルリモートの難しさとマネジメント課題
LayerXではフルリモートが選べる柔軟な働き方が続いており、地方で子育てをしながら働く私にとって、とてもありがたい環境です。その一方で、フルリモートならではの難しさもあります。
例えば、雑談の機会が少ない、気軽に質問しづらいといったコミュニケーション面の課題がありました。商談が続き、気がつけば「雑談ゼロで1日終わった」というメンバーも珍しくありません。また、目標達成に向けて「自分の数字」への責任が大きい環境では、チームとしてのつながりが弱くなりがちでした。そのため、「個人目標」から「チーム目標」へ意識を切り替えることが必要だと感じました。
さらに、進捗や数字の見える化も大きな課題でした。オフィスで顔を合わせていれば自然に共有できる情報も、リモート環境では意識的な工夫が求められます。こうした課題を抱えながら、みんなのモチベーションをどう維持するかは、最も重要なテーマのひとつでした。
2. アプローチ:今日から「武士」です
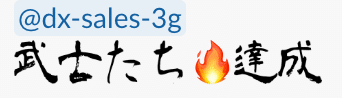
注力したのは、大きく2つです。1つ目は、オンラインで一体感を生み出す働きかけ。そして2つ目は、案件にディープダイブし、目標達成を推進する取り組みです。
(1)オンラインで一体感を生み出す働きかけ
メンバー構成は東海、北関東、九州など全国各地に住む全員男性。バラバラの場所で働いているからこそ、まずは個々の想いを受け止めることから始めました。着任直後に、案件管理とは別でコミュニケーションを目的とした1on1を実施し、ざっくばらんに話し合いました。
どんな想いで働いているか
何を頑張っているか
何に困っているか
どんなチームにしたいか
この1on1を通じて、「チームでもっと連携したい」という声が多数。これを受け、Slackを活用したコミュニケーションを重視して以下を実行しました。
命名「武士たち」
フルリモートの少し孤独な環境で、目標達成に向けて真摯に戦い続けるメンバーを「武士」と称し、呼びかけました。この名前がチームの結束を高めるちょっとしたきっかけ(?)に。

大袈裟なくらいのSlackでのスタンプリアクションの推進
フルリモート環境では感情を共有しづらいので、積極的にスタンプで反応を示そう!と呼びかけました。(これを、スタンプ鬼盛りの強要と人は言います)ちょっと楽しいキーワードを見つけては、すぐにSlackの絵文字を作りました。「え、いつのまに絵文字作ったの?」というザワメキが大好物です。

毎朝の「闘魂注入」投稿
個人ではなくチームを意識するために、そして前向きに一日をスタートするために、毎朝Slackのチームチャンネルに下記を投稿していました!目標と実績
前日からの差分
案件進捗サマリー(ポジ・ネガ両方)
一言
週に1回は雑談をするだけのショート朝会
「15分〜20分間で、その日のお題にあわせて発表する」という業務に全く関係ない雑談時間です。
例えば、「よく見るYoutubeチャンネル」「おすすめのふるさと納税」「お気に入りの映画」など。雑談から親近感・共通点をたくさん再発見しました!
営業日数に応じて必要がない場合はスキップし、柔軟な運営を意識しました。「気兼ねなく雑談できるチャネル」も作成し、心理的安全性を高めました。

「全員の個人目標達成による、チーム目標達成」を絶対に諦めない
チーム数字さえ達成すれば良い、ではなく最後の最後まで全員が個人目標達成するためのプランを考え続けました。これは大切にしている想いです。「誰も置いて行かない、諦めない、期待し続ける」ことも同じく大事にしています。
(2)案件にディープダイブし、目標達成を推進する取り組み
チーム全体の目標達成に向けては、案件進捗に深く入り込み、メンバーと伴走しながら成果を引き出すことを徹底。また、メンバーが商談活動に専念できるよう、準備や社内業務の負担を減らす運用を心がけました。
個人案件の詳細を把握し、チームの達成プランを作成
案件進捗の状況は、個人とのミーティングを通じて深く把握し、チーム全体で共有しやすい形に整理しました。
個人案件ミーティング(週2〜4回)
各メンバーとのミーティングで具体的な案件について深掘りし、課題や次のアクションをすり合わせ。
Salesforce(SF)の個人レポートをカスタマイズして、「これだけを更新すればいい、これだけみれば分かる」状態にしオペレーションを極力シンプルにしました。
未更新の情報があっても咎めずに、ミーティング中に一緒に更新しながら進捗を整理しました。(更新を「やらない」のではなく「やる時間がない」くらい頑張っているのを知っているため)
とはいえ、徐々に更新してくれるようになった…気がします(たぶん)
チームの達成プラン共有会(週1回)
チーム全体で目標や進捗を共有し、士気を高める会議を実施しました。この際、以下の工夫を取り入れました。手ぶら参加の仕組み:事前準備の負担を減らし、メンバーには参加するだけでOKな形式に。個人ミーティングで話した内容をもとに、私がスライドを作成して着地予測とチームとしての達成プランを提示。
1人1分のチェックイン:最初に1人1分ずつのチェックインを導入。簡単な雑談から始めて笑顔で会議をスタートするためです!
目的は共有と相談に絞る:会議内では、個々人と日々確認している個人状況を踏まえて、チームの着地の見立てを共有し、必要に応じて達成のためのリカバリープランを2〜3案提示。
「チーム会で1人ずつの個人の進捗を確認」することは、時間の使い方として勿体ないです。時間が余れば相談タイム。ただ、みんな全員の時間を使うことにまだ遠慮があったので、ここは今後も(もっと相談しやすくなるように)改善の余地ありです!
商談前後の業務負荷軽減のためのサポート
案件によっては商談準備からサポートを開始しました。以下のような対応を行い、メンバーが顧客対応に集中できる環境を整えました。
商談の経緯を整理し、打ち合わせ資料のアジェンダやスライド作成をサポート。
プロダクトのトライアル検証を行っている顧客には、非同期でやりとりができる質問票を作成し、毎日チェック&回答を記入。これにより、リードタイム短縮化を実現しました。(一番多い時で毎日十数社の対応)
必要に応じて、上申資料の草案作成を代行。(同席の有無に関わらず)
メンバーの事務作業の負担を軽減するため、可能な限り巻き取る姿勢を徹底しました。
同席の意識改革
同席に対して「査定されている」と感じるメンバーの心理を変えるため、「同席=助けてもらえる」と思ってもらえるように実利の提供を重視しました。
「上司」とは名乗らないという前提を設け、「操作サポート」や「営業サポート」として同席しました。
「上司」は最後の切り札です、最終局面や交渉・調整時こそ必要なもの。私は案件によってはかなり序盤からの同席もあったので「最初から上司を連れてくる=営業担当が未熟」と捉えられることを避けたい気持ちもありました。自分の位置付けを「サポート」とすることで営業担当が主役となり、お客様との信頼関係を崩さず進行できるように意識しました。
商談中も議事録を取る、商談後に実務を進めるなど、メンバーに対して手を動かし続けることで、同席のメリットを感じてもらえるよう工夫しました。徐々に同席は「頼れるサポート」として捉えられるようになりました。
同席は大切です。マネジメントにとっての具体の案件の解像度が上がり、より適切な支援ができるようになります。
社内連携の架け橋になる
フルリモート環境では、チーム内のコミュニケーションをスムーズにするだけでも意識的な取り組みが必要ですが、チーム外、他部署との連携になるとさらにハードルが高まります。案件ミーティングや同席の中で連携の必要性が発生したら、即座に「社内の架け橋」として動き、他部署との円滑な連携ができるように努めました🤝
他部署との連携例
上長(部長)への交渉関連の相談
BizOps部への契約や請求に関する質問
ドメインエキスパートへの複雑な運用の相談
Dev(開発チーム)への新機能や開発予定に関する質問・確認
パートナーアライアンス部やエンタープライズ部との情報共有 など
「この質問は誰に聞けばいいかわからない」といった場合でも、すぐに適切な人に繋ぐことで、やりとりが滞らないようサポートしました。
設定したNAを実行しているか、ではなく適切なNAを設定できているかを”一緒に”考える
注力案件では、特に「次のアクション:Next Action(NA)」の質を重視しました。ただ行動を「やった or やっていない」と確認すること自体に意味はないと思っています。(レポート上のNAの項目が0になったからといって、達成するわけではありません)その行動自体が適切かどうかこそ重要です。
組織図を可視化して整理
誰が意思決定を行うのか、どのステークホルダーが関わるのかを明確にすることで、空中戦を防ぎました。「誰が何を言っていたのか?」という事実を整理しつつ、漏れがないか別の視点から問いかけることで、リスクヘッジを実現。これにより、シナリオを再設計するきっかけにもなりました。
具体的な問いかけで目線を合わせる
メンバーからの報告を鵜呑みにせず、一緒に作成したパワーチャート(意思決定に関わる組織図の可視化)をもとに「意思決定にはこの部署の役員や部長は関わる可能性は」「例えば、こういう想定される懸念はないか」「ここに新たなアプローチは考えられるか」といった、より具体的な視点で対話を重ねることで、的確なNAを設定できるようサポートしました。
3. 成果
連続達成!!
冒頭でも触れたように、11月・12月ともに目標を達成することができました!
1件あたりのMRRが大きいため、決まれば達成、逆に外せば未達というギリギリの状況が続く、毎月最終日まで結果が読めない展開。今でこそ打ち明けますが、(特に11月は)達成できるか不安な気持ちもありました。全員が最後まで諦めずに走り切った、誇らしい結果です。
意識が変わった
はじめは、自分の目標達成に集中することが優先されていましたが、次第に「チーム全体での達成」を意識するようになった気がします。
「自分の役割を全うする」という姿勢からさらに一歩進み、チーム全体が目標を達成するために、最後の1件まで一緒に追い続けるメンバーもいました。
雰囲気が変わった
Slackだけでなく、チーム会の雰囲気にも変化が出てきました。最初の頃はやや硬い空気が流れることもありましたが、回数を重ねるうちに少しずつ柔らかくなり、自然なコミュニケーションが増えていきました。
特に、雑談を取り入れたチェックインや、会議後に笑顔が見られる瞬間が増えてきたのは印象的でした。気づけば「ちょっとずつチームらしくなってきたな」と感じる場面が増え、個々が安心して話しやすい空気が作れてきたように思います。

まとめ
やっぱり対面のコミュニケーションは大事
フルリモートで仕事をする中で、私なりにいろいろと試行錯誤を重ねてきましたが、やっぱり「顔を合わせること」には特別な価値があると感じています。
仕事の進めやすさや心理的安全性を考えても、気軽に対面で話せる環境に勝るものはないなと改めて実感しました。
頻繁には難しいかもしれませんが、達成会や決起会など、節目ごとに対面で集まれる機会を設けることで、フルリモートでも働きやすさがさらに向上すると思います!
「マネジメント対象」ではなく「協業者」として向き合う
これは、ずっと心がけていることです。メンバーに接するとき、私は「マネジメント対象」としてではなく、「協業者」として向き合うよう意識してきました。相手を変えようとするのではなく、同じ方向を向き、一緒に目の前の案件を受注するというスタンスで関わっていました。
「どうやったらお客様にバクラクを導入していただけるか」を軸に据え、指導や指摘ではなく、サポーターとして一緒に実行し切ることを大切にしていました。

「遊び」を忘れない
これはSlackでのコミュニケーションにも通じるのですが、やっぱり仕事には「遊び心」も必要だと思っています。少しでも笑顔になれるよう、細かな仕掛けを散りばめながらチームの雰囲気づくりをしてきました。

実は、20代のころから私は「山根、お前は遊びがない」と上司によく言われていました(笑)。当時はどれだけ正論を言っても、どれだけストイックに頑張っても、人が動いてくれないことに悩んだことが何度もありました。その失敗や挫折を重ねる中で、「どうしたらみんなが前向きに動いてくれるのか」を考えるようになり、今のスタイルにたどり着いたのかもしれません。
だからこそ、どんなに忙しくても「楽しい瞬間」や「笑える時間」を大事にしたいと思っています。やっぱり人の心が動くのは、ちょっとした「遊び」があるときなんですよね!

以上が、2ヶ月間の緊急ミッションで心がけていたことや、実行してきた内容です🫡
今月からは、新しいミッションがスタートしました!次の役割は、受注単価向上に向けて、セールス部の中で、より大きな企業規模のお客様を対応できるメンバーの育成です。これまでとはまた違うチャレンジになりますが、引き続き試行錯誤しながら頑張っていきます!
バクラク事業部では、一緒に働く仲間を募集中です。興味ある方、お話ししましょう〜🫶
