
「触れて、感じて、学ぶ」小学6年生の地層学習
「触れて、感じて、学ぶ」小学6年生の地層学習
今日の6年生理科は「地層の学習」3時間目。教室で行う地層観察、一見矛盾しているようですが、工夫次第で充実した学びになることを実感した1時間でした。
1. 実際の地層がない環境で、、
私の学校周辺には、残念ながら実際の地層が露出している場所がありません。遠足で見学に行くのも難しい状況。でも、だからこそ創意工夫が必要です。
まず、教科書で地層の観察ポイントを丁寧に学習。その後、実際に触れる体験学習へと移行しました。準備したのは、砂と泥のサンプル。

2.「百聞は一見にしかず」ならぬ「百見は一触にしかず」
写真や文字での学習と、実際に触れる体験の違いは歴然。最初、乾いた砂と泥を触った時は「どちらもざらざらしている」と言っていた子どもたち。しかし、水を加えた泥の「ぬるぬる」感触に、みんなの目が輝き始めました。
「先生、全然違う!」
「砂はまだざらざらしてる!」
「泥はつるつるする!」
楽しそうな子どもたちの声があちこちの班で飛び交います。粒の大きさの違いを、まさに肌で感じ取っている瞬間でした。
3.体験を言葉に、画像に
授業の最後には、miroボード(オンラインホワイトボード)を使って学んだことを整理。写真と言葉で自分たちの体験をまとめ、振り返りを書きました。デジタルツールを使うことで、個々の気づきを共有し、学びを深めることができます。
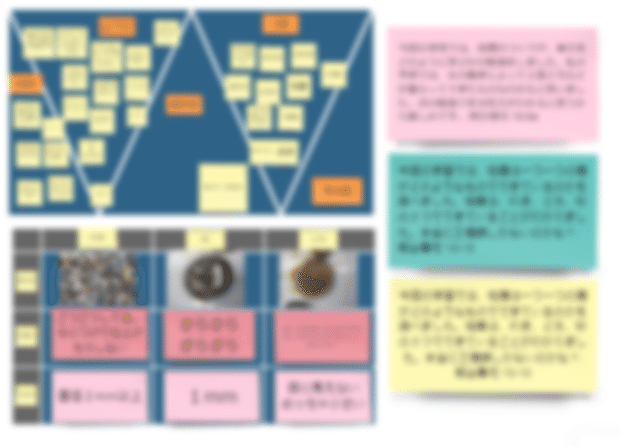

4.教師としての気づき
この授業を通じて、改めて「体験」の大切さを実感しました。教科書や写真だけでは伝わりにくい微妙な違いも、実際に触れることで鮮明に理解できる。そして、その理解が子どもたちの目の輝きや言葉になって表れる瞬間こそ、教師冥利に尽きるのだと思います。
限られた環境や資源の中でも、工夫次第で豊かな学びの場を作れることを、私自身も学んだ1時間でした。これからも、子どもたちが「わかった!」「面白い!」と感じられる授業づくりに励んでいきたいと思います。
