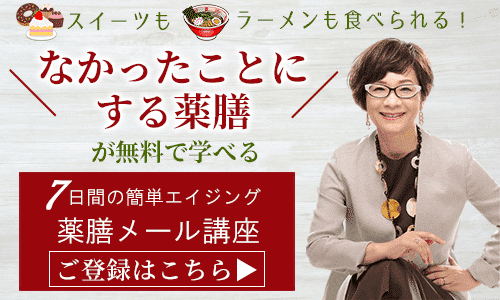薬膳を受け入れてもらうために薬膳講師がしたことと後悔
初めて薬膳に触れてからちょうど10年経ちました。
今薬膳を学んでいて、家族のために良かれと食材を選びメニューを考えているのに、なかなか受け入れてもらえない、逆に反発されるという事を悩んでいる方がいます。
今、わが家の食事はその日の天気や体調に合わせた薬膳ですが家族は何も言わずに食べています。
そして、私も家族も体調を崩す事がここ何年もありません。
10年経ったところでここまでどのように家族が薬膳を受け入れるようになったのか?
どんな工夫をして来たのかを思い出してみます。
これを読まれた「薬膳を家族に反発される方」のヒントになれば幸いです。
薬膳との出会い
初めて薬膳に出会ったのは10年前の52歳。
確か閉経したのは50歳。更年期真っただ中で体調不良にさいなまれていた時期です。
中学2年生、思春期の一人娘の一挙手一投足にイラつき、相手からの容赦ない言葉ですぐにケンカになる毎日でした。
家庭崩壊も時間の問題というほど家族の関係性が最悪の時に、この体調が良くなればこのイライラもおさまるかもしれないと、様々な健康法の本を読んだりトライしている最中に出会ったのが「おうち薬膳」~はじめの第一歩~という講座でした。

この部分はホームページのプロフィールに詳しく書いているので、良かったらお読みください。
薬膳を学ぶためにはベースとなる考えを知る必要があります。
それが「中医学」中国伝統医学です。
一般的にいわゆる「東洋医学」と認識されていますね。
代替療法という位置づけにされることが多いですが、2千年、3千年前から脈々と続いている医学なので、系統立てて理論的にまとめられています。
生まれた時から親から言われて来たのは西洋医学に基づくことや栄養学で言われる炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミンをバランスよく食べるという事だったので、中医学の「一人一人体質に合わせて合う食べ物が違う」という事に衝撃を受けました。
それまで自分の体質や周りと同じものを食べても自分だけが体調を崩す事をコンプレックスに感じていたので、なぜそうなるのかがわかった時は目の前がパッと明るくなったのを覚えています。
もう夢中になって学びました。
生きている自分自身が実験台です。
実践しているうちに体が変わり、体調を崩す事がどんどん減って行きました。
こうなると自分だけではなく家族も薬膳で病気をしないようにしたいという欲が出て来ます。
けれどこれは一筋縄では行きませんでした。
今までなかった考え方への反発
薬膳の基本の考え方が中医学だと書きました。
この考え方は日本にも中国から入って来ていたのです。
遣隋使や遣唐使、鑑真和上等先人が他の学びと共に日本に持ち込んで来たものに中医学の考えや薬草などもありました。
戦国時代の大名では徳川家康の健康オタクぶりが有名ですが、当時50歳くらいが日本人の寿命だった頃に長生きした北条早雲なども独自の健康法をしており、その基本は中医学だったのではと考えます。
このように日本にも浸透していた中医学は江戸時代の鎖国で日本独自に進化発展します。
これが漢方(日本漢方・和漢方とも呼ばれる)でオリジナルの中医学とは少し違って日本に馴染みのあるようにアレンジされています。
煎じ薬に使う植物も中国から入って来なくなれば日本にある植物で代用しなければなりませんものね。
やがて明治維新となり欧米諸国に追いつくために医学も西洋医学が国の定めた医学になりました。
食べ物の栄養の考え方も炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル類という栄養学の考え方で考えられるように。
私自身も中医学に最初に触れた時は戸惑い、混乱しました。
栄養学の考え方は食材が中心。
あるものには炭水化物が豊富だからこれを食べるとエネルギーになる、なので必要。
ビタミンAは粘膜や皮膚の健康を保つために必要。
足して行く考え方です。
ところが、薬膳はその人その人の体のバランスを見るため、一つの食材でも多く摂りすぎてはいけない人もいれば、多めに摂った方が良い人もいる。
つまり人が中心です。
多すぎれば、出すための食材を選ぶ必要があるし足りていないものがあるならそれを他の人より意識して多めに食べる。
後者は一般的に得意かと。
栄養になるものを足して行くのではなく必要なものは補うしすでに体にあるもので多すぎるならそれを出す。
足して行くのではなくバランスを見ながら調整する感じです。
そして目指すのはプラスでもなくマイナスでもないニュートラルな状態。
これを「中庸」と言って、この状態が健康の基準です。
家族にもこれをやって貰ったら体調は整います。
一緒に暮らしていれば日々の体調は自分の体の次にわかるので。
中医学、薬膳と出会った頃は夫や娘にもわかって欲しくて、あれはダメとかこれはやめてこっちを食べて等と習ったことを押し付けていたのです。
それは確かに正しかったけれど、それまでの概念になかったことを急に100%変えられないのは当たり前。
講師になって薬膳を知らない方の相談を受けるようになってから身に染みました。
「腸活のためにヨーグルトを毎朝食べています。」
森澤「お腹が冷えますよね。代謝が悪くなっているし、便秘が解決できていないならそれは合っていないと思いますよ。」
「毎朝、朝食はスムージーです。酵素も繊維質も摂れるから」
森澤「お昼までにお腹が空いて午前中にお菓子を食べていますよね。お腹のもちが良くないから食べてしまっていませんか?」
こんな会話が行き来します。
わが家の家族とも「一回食べなかったくらいで変わる訳がない。」などさんざん言われました。
それで、一切押し付けるのを止めました。
押し付けていないのに家族の体調が変わって来た
漢方薬の材料になるものを生薬(または中薬)と言います。
時々使うことはありましたが、基本は一般に売られている肉や野菜や魚介や海藻、きのこなど。
見たことも無いものを最初から食べてもらうのはなかなか難しいです。
特に男性は食事については保守的な方が多い。
わが家の夫もその一人です。
そこで、嫌だと言われる食材でも天気や体調的に食べた方がいい場合は、ひっそり忍ばせたり、煮物やスープの出汁に使いテーブルに料理として出す時は、一切見えないようにしました。
ある時は、トマトソースを作る時になつめやクコの実を入れたり、カレールーを使わずにとろみをつける時やポタージュの滑らかさを出すために白きくらげを入れたり。
または、ハンバーグや餃子を作る時にみじん切りにして他のものと一緒に入れてしまったり。
いつしかスープや出汁にエキスが出ているからそのもの自体は食べなくても良いとざっくりした考えになって来ました。
こうしているうちに、生理痛が酷かった娘の生理痛が無くなり頭痛のために鎮痛剤が手放せなかった夫の頭痛も無くなりました。
わが家は鎮痛剤を常備していたのに買わなくなりました。
念のために買ってあったものが殆ど飲まずに期限切になって処分するほどです。
この頃から、料理の説明をするようになりました。
きっかけは夫が質問を始めたから。
この料理に入っているこれにはどんな効能があるの?というような単純なものです。
聞かれた時だけ説明していましたが、質問されることが多くなり食材の効能だけでなく、なぜそれを使うのかというもう少し根拠の説明もするようになっていました。
こうなるとシメタものです。
体調管理には食事が重要、食事で健康が保てるという事を夫も身をもって実感し興味がわいてきたのです。
娘は高校を卒業して大学時代から家を出ました。
最初の頃は「口内炎ができたんだけど、何を食べたら良い?」とか「急にニキビがたくさんできたんだけど何を食べたら良い?」というようによく質問して来ました。
社会人になってからは忙しく自炊もままならないことがあり、体調を崩す事が一年目にはありました。
直ぐに熱を下げて出社しようとしますが、熱が上り切っていない時に解熱剤で下げてもまたすぐに上がるので、私に連絡して来ました。
そこでアドバイスをしたところ復活。
家族が薬膳で体調が変わることを実感し行動が変わってきたのです。
人は頭で理解して実体験しないと行動変化にはならない
家族の変化を見ていると、まずは理解してもらうこと。
頭で理解したうえで、自分の体の変化を実体験しないと行動変化にはならないというのが結論です。
今、この記事を読んでいる方の中には、薬膳を学んで色々分かって来ているので、自分の体調管理のために食事に気をつけるようになっている方もいると思います。
この段階は、家族の食生活がとても気になる時期。
その体調の原因は出かけた先で食べたあれだろうとか、食事の時に良かれと出しているあれを残すからだとか・・・
気になって仕方がなくなります。
薬膳は大切な人を思って作る愛情表現の一つ。
体を良くしようと思って作るもの。
そもそも「食」という字は「人」の下に「良」と書きます。
人を良くさせるのが「食」つまり健康になるのが目的です。
私のように押し付けると反発されて余計にイライラしてしまうので、スープや出汁にエキスが出ているからそれさえ飲んでくれたらいいと気楽に構えるのが良いと思います。
体調が変わった実感があれば素直に聞いてくれるし、今まで反抗していた食材でもトライしてみようと変わって来ると思うのです。
ただ一つの後悔
家族、特に娘にはもっと早いうちに薬膳の食の知識が伝えられていたらと少し後悔しています。
私が薬膳を始めたのが思春期のもうすでに自我がしっかり確立している頃だったので。
お弁当はすべて娘の体調と食材の効能で作っていたので、みんなと同じように冷凍グラタンなどを入れて欲しいと言われたこともありました。
娘の体質的には、グラタンなどはあまり食べない方が良かったので入れていなかったのですが。
そして、きちんと伝えられないうちに一人暮らしになってしまいました。
小学校低学年くらいのお子さんまでなら、素直だし親の言うこともよく聞いてくれるので、もっとスムーズだと思います。
仕事に育児に家事と忙しい毎日ですが、子供が体調を崩すとすべての予定が狂ってしまいます。小さいお子さんがいらっしゃるなら少しでも早く伝えておかれることをお勧めします。
子供のうちから自分の体調でどんな時にどんなものが必要かがわかるように育てておくことが食育の一つだと思います。
反抗されたからこその実感。
薬膳を学んで家族にも良くなって欲しいのになかなかうまくかない方のご参考になれば幸いです。
【関連マガジン】
森澤孝美公式サイト
ご提供中のメニュー
お問合せ
通常メルマガ『モーリーの簡単エイジングケア薬膳』お申込みは下のバナーをクリックしてください▼

食べたいものをストイックに我慢するのではなく「なかったことにする薬膳」のメソッドでプラマイゼロにする方法を無料で学べる7日間のメール講座です。お申込みはこちら▼