太宰作品に対する所感
※2023/10/16執筆
2023年の3月頃から、なんだか突然太宰治にハマってしまった。
ハマってからひとしきりあれこれ見て、先日遺作「グッド・バイ」を読み終えたところで、一度これまでの経緯と、現時点での、太宰治に対する総合的な所感を記し残したい。ひとまず作品から。
読了済み書籍、映画、演劇【読了順】※2023年10時点
- 富嶽百景(教科書)
- 人間失格(新潮社)
- 走れメロス(講談社)2022年8月 ※ここで太宰・・・という感情になる
- 斜陽(新潮社)2022年1月
- 井伏鱒二「太宰治」※ここで想いが溢れる
ーー三鷹散策ーー
- 人間失格 太宰治と3人の女たち(映画)
- 津島美智子「回想の太宰治」
- 晩年(新潮社)
- 坂口安吾「不良少年とキリスト」
- 女生徒(青空文庫)
- 新ハムレット(青空文庫/演劇)
- チェーホフ「桜の園」(青空文庫/演劇)
- チェーホフ「三人姉妹」(演劇)
- 津軽(新潮社)
ーー津軽旅行ーー
- 津軽通信(新潮社)
- お伽草紙(新潮社)
- もの思う葦(新潮社)
- グッド・バイ(新潮社)
- 太宰治物語(映画)
経緯
文が書きたいという気持ちが数年前からふんわりと起こり始めた。
その頃翻訳文学だとか新書だとかしか読んでおらず、よく本を読んでいた幼少期は主にミステリばかり読んでいたもので、文章そのもののお手本となるような、何か理想の文章が欲しかった。そもそも、自分がどんな文章が好きで、そして何なら書けるのかを考えるため、とりあえず思いつく日本人の作家の本が読みたい。
そこで思い出したのが、高校の教科書に載っていた、『富嶽百景』。
授業中に読みながら、あの穏やかな空気感が印象的で、なんだかいつまでも忘れられないようなちょうどいいあたたかさが好きだった。
そうか、あの話は太宰治だったか。『人間失格』のイメージがあったが、そういえば、走れメロスも太宰なのか。何か手掛かりになるかもしれないからとりあえず富嶽百景を再読してみようと、表紙が可愛い講談社の『走れメロス』の短編集を買った。
あんまり当時のことは覚えていないが、読んで第一声がこれだったらしい。
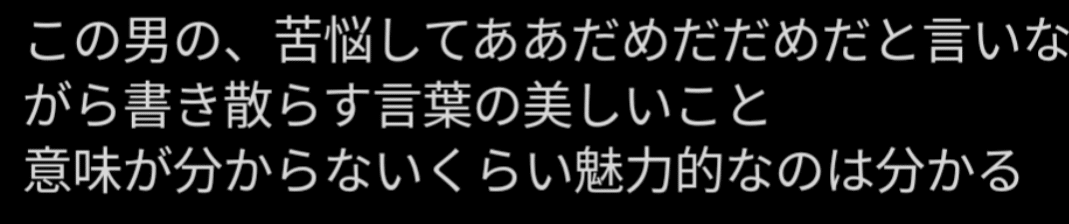
作品について(言葉)
1. やさしくて、かなしくて、おかしくて、気高い
やさしくて、かなしくて、おかしくて、気高くて、他に何が要るのでしょう
という言葉を見つけたが、これこそ太宰文学そのものだなと。やさしくて、かなしくて、おかしくて、気高い。それが太宰治の文章の魅力。こうとしか言いようがない。これに尽きる。
太宰の文を読んでいると、
己を愛するが如く汝の隣人を愛せよ
という聖書の言葉が頻繁にでてくる。キリストに対するただならぬ共感があったように思う。
自分の弱さを徹底的にさらけだしているからこそ、人の弱さにも優しい。そういったやさしさが全作品にある。(ただし無学と老大家に死ぬほどきびしい)
2.本質をそのまま映し出す力
巻末の解説で、「太宰の文学は批評家的であり、その批評精神が自分自身に向いている」と書かれており、これだと思った。太宰の文章はするどく、本質をそのまま映し出すのが上手い。
自分の感じたことを嘘偽りなく印象そのまま書くというのは、思った以上に難しいことだと思う。どこか格好つけてしまったり、なんとなく思ってもないそれっぽいことを書いてしまったり。写実的にあったことをそのまま書けばそれが現実という訳でもなし。
よく、太宰は嘘ばかり小説に書くと言われるが、それは単に「現実ではこんなこと言ってない」だとか「こんなことありえない」といっただけで、彼は自分の感じた印象そのままを書き写しただけなのだと思う。写実的な絵と抽象画の違いのようなものかな。印象派……(たぶん)
現実と違くて、矛盾だらけで、おかしいとしても、それが彼にとっての真実なように思わされるし、また、大体の人間がそうなんだろう。
こんなことを言っている。
主観的たれ!強い一つの主観を持って進め。単純な眼を持て。
人間の正直な言葉ほど、滑稽で、とぎれとぎれで、出鱈目に聞こえるものがない、と思えば、なんだか無性に悲しくなります。
無闇に字面を飾り、ことさらに漢字を避けたり、不要の風景の描写をしたり、みだりに花の名を記したりする事は厳に慎み、ただ実直に、印象の正確を期する事一つに、努力してみてください。
本当に、ハッとさせられる言葉がたくさんある。太宰の小説は「心尽くし」だと本人が言っているが、その通りだと思う。結末を知りたくて読むんじゃなくて、一文字一文字を味わうように読んでいる自分がいる。
3. こちらに話しかけてくる
これはそう感じるとかそういう話ではなく、本当に、話しかけてくる。
こちらが本にツッコミを入れながら読んでいたりすると、うっかり会話が成立してしまう時があって怖い。ここまで読者と会話するのがうまい人がいるのか。実際、彼はいつもファンに読まれることを意識して書いていたようだから、そうなるのも致し方なし。
私は決して嘘をついているのではない。まあ、おしまいまで読み給え
上記のような、本当に話しかけてくるパターンがなくても、太宰文学のほとんどは作者と読者が一対一で対峙しているような気持ちにさせられるのだが、この現象を専門家は「潜在的二人称」と名付けているらしい。
作品について(時代別)
太宰治の作品を大きく分けるとざっくり3期に分かれる。
前期:暗い。「晩年」
中期(戦中):穏やか。「富嶽百景」「走れメロス」
後期(戦後):鬱。「斜陽」「人間失格」
前期
実は、まだあまり深ぼれていない。
でも処女短編集が「晩年」とかいうのが、全くもって太宰らしい走りだし。
これを出す前の太宰の人生はハチャメチャの滅茶苦茶で、自殺未遂(いつもの)、共産主義への傾倒、留年、入水(いつもの)、勘当、薬中(いつもの)、精神病院への入院という散々な具合。そう思うと「晩年」というタイトルにしたくなる気持ちもわかる。
この時期の出来事が一生太宰に「人間失格」だという気持ちを持たせた。
死ぬ前に、最後に自分のことを書いておこうと思って一作書いたら、なんだか満足がいかなくてもう一作書いて、もう一作書いて、そうして溜まった短編を袋につめこんで、「晩年」と書いて置いていたんだとか。
中期
私が特に好きなのは中期で、この頃は妻の美知子さんと暮らし始めて一番心穏やかな時期だったから、それが作品にも現れている。太宰から鬱とか自殺とかそういうのを取り除くと、びっくりするほどただの文才のある男になるのかという感じで、これは本当にみんなに知って欲しいと思っている。
おすすめなのが
富嶽百景
駈込み訴え
女生徒
御伽草紙
特に太宰は既存の話を元に自分の解釈を入れて別の話をつくるのが天才的に上手いと言われていて、その最たる作品が「駈込み訴え」「お伽草紙」の2つ(と私は思っている。)走れメロスもここに該当する。
爽やかで穏やかでユーモアがある最高な作品が「富嶽百景」。
女の心情を書かせたら太宰の右に出る者はいないと思うが、それが「女生徒」。
ぽかんと花を眺めながら、人間も、本当によいところがある、と思った。花の美しさを見つけたのは、人間だし、花を愛するのも人間だもの。
年月は、人間の救いである。忘却は、人間の救いである。
そして、この中期にあたる時期はちょうど戦争が激化した時期をふくむ。言論統制におびえて他の作家たちが何もできないときに、太宰だけはずっと作品を出し続けたというのが、格好いいなぁと素直に思う。
太宰は肺が悪かったから徴兵はされなかったが、それがずっと後ろめたかったよう。死にたいが、戦地に行って連絡が途絶えてしまった友がいるなかで、自分がここで死ぬことはできない、と思っていたよう。戦争がかえって太宰作品をのびやかに生み出し、太宰を家庭に、この世につなぎとめていたというのは、皮肉なことである。
後期
ここが超有名。
斜陽
人間失格
斜陽は、当時斜陽族とかいう言葉が生まれるほどめちゃくちゃに流行った。人間失格は言わずもがなの代表作。全体的にこの時期のものは緊迫感がある。
この時期は大体戦後にあたる。太宰にとって戦後というのはたった3年しかないのだが、戦後になっても何も変わらなかったという日本に対する絶望があちこちに漂う。それだけ、戦争が終わったら何かが変わるといった期待も大きかったのかもしれない。こうした戦後日本に対する絶望感は、「冬の花火」「春の枯葉」という2つの戯曲によくあらわれている。ここあたり、もう少し深掘りたい気持ち。
冬の花火、冬の花火、ばからしくて間が抜けて、清蔵さん、あなたもあたしも、いいえ、日本の人全部が、こんな、冬の花火みたいなものだわ。
永い冬の間、昼も夜も、雪の下積になって我慢して、いったい何を待っていたのだろう。ぞっとするね。雪が消えて、こんなきたならしい姿をあらわしたところで、生きかえるわけはないんだし、これは、このまま腐って行くだけなんだ。めぐり来たれる春も、このくたびれ切った枯葉たちは、無意味だ。
遺作
そしてラストのラストで未完で終わってしまった遺作がある、それが「グッド・バイ」。タイトルからしてさぞ暗いのかと思ったら、これが今までにないくらい拍子抜けするほどのドタバタコメディだった。確かに新しい作風が始まりかけていたのに、太宰はこれを完成させることなく死んでしまった。とっても惜しいものである・・
なんだか笑いながら手を振り、おどけて、そのまま舞台からさっていくような、そんな遺作だった。
「ありがとう!」ヤケみたいにわめいて、階段を降り、途中、階段を踏みはずして、また、ぎゃっと言った。
それにしても、処女作が「晩年」で遺作が「グッド・バイ」。どこまでも太宰っぽいなという感。
好きな作品
ただの備忘録だが、現時点で私の好きだった話を列挙。それこそ好きな作品を列挙するのは宝石を並べるみたいでいいなあ。
富嶽百景:穏やかでユーモアのある大好きな話
駆込み訴え:愛憎というか、真に迫る想い
女生徒:思春期の気だるい切なさのような何か
お伽草紙(浦島さん):幻想的で、そして優しく救いのある素敵な話
竹青:作品としてのレベルがかなり高い。美しい。
一燈:穏やかでどこかさみしい。戦時下における芸術家宣言。
未帰還の友に:還らぬ友を想う
海:SSとして珠玉
春:SS として珠玉
フォレスフォレッセンス:彼にとっては夢も現も同じ。どこまでも一元的なひと。
グッド・バイ:ぶっちぎりに明るい
芸術ぎらい:ハッとする言葉が多い
冬の花火:戦後日本に対するやり切れなさが出ている戯曲
春の枯葉:戦後日本に対するやり切れなさが出ている戯曲
井伏鱒二選集 後期:井伏先生の作品は「宝石」だとか
薄明:子煩悩な父の姿
鴎:「誰にも自信がないのかなあ」
