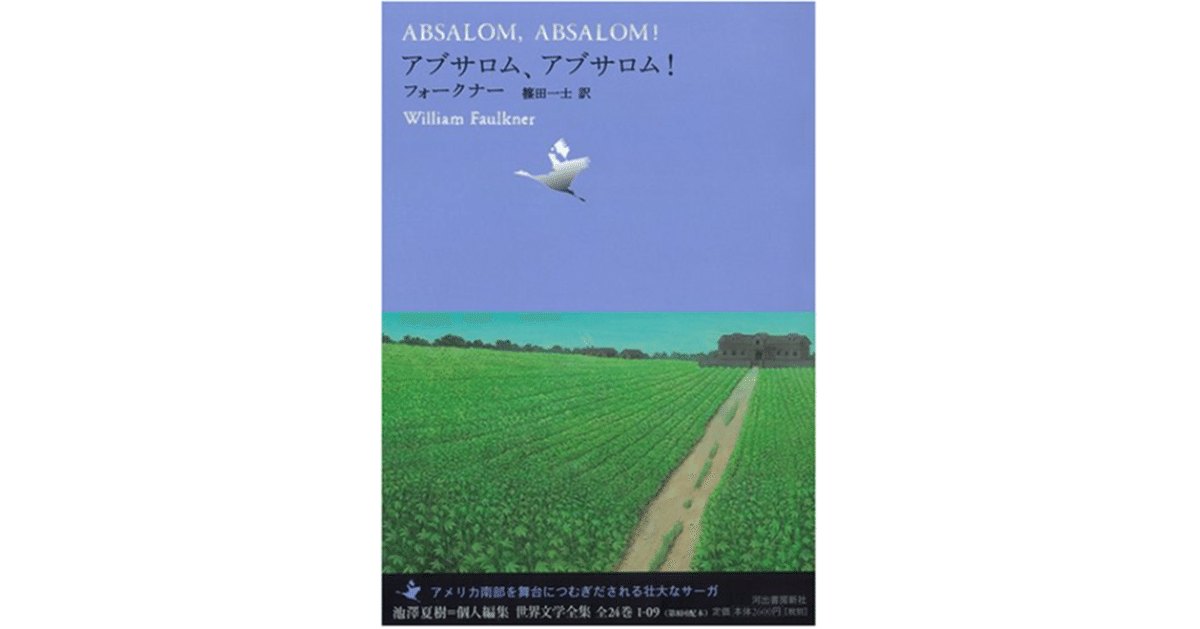
『アブサロム、アブサロム!』ウィリアム フォークナー (著), 篠田 一士 (訳) アメリカという国の、その根底にある狂気について。資本主義の根っこにある狂気について。考えてしまった。
『アブサロム、アブサロム!』 (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 1-9
Amazon内容紹介
南部の差別と人間の苦悩を描く
ノーベル賞作家の代表作
アメリカ南部の田舎町に姿を現した男サトペンが、巨大な屋敷と荘園を建設し、自らの家系を築きあげる。南北戦争をはさんで展開される繁栄と没落の物語。重層的な語りの中に、呪われた血の歴史が浮かびあがる壮大なサーガ。
〈ぼくがこの作品を選んだ理由 池澤夏樹〉
フォークナーは密度が高い。人と人の距離が近く、愛も憎悪も野心も欲望も強烈。登場人物の人柄はどれも忘れがたい。ぼくにとって『アブサロム、アブサロム!』を精読した記憶は、どこかの町で一年暮らしたのと同じくらいの重さがある。
本の帯・裏
呪われた血に翻弄される一族の物語
静かな雷鳴のなかから、悪鬼のごとき形相の男サトペンがアメリカ南部の田舎町ジェファソンに姿を現す。カリブの黒人奴隷を引きつれた彼は、先住民から騙しとった広大な土地に屋敷を建て、自らの血脈を築き上げようとするが、やがて呪われた血の復讐を受けることになる。__重層的な語りとともに展開されるいくつもの家系の物語。すべての作品に通底する暴力の匂い。ガルシア=マルケスを始めとするラテンアメリカ文学ブームの世代を準備し、トマス・ピンチョン、中上健次など、20世紀後半の世界の文学に大きな影響を与えた作家が生涯かけて築きあげた、架空の土地ヨクナパートファをめぐるサーガの最高峰。
ここから僕の感想
フォークナーを読むのは『野生の棕櫚』に次いで二冊目で、あちらの感想文で「アメリカでかすぎて人間がおかしくなる話」と書いたのだが。
この小説もアメリカという国が、なにか根本的に日本人には分からない狂気の上にできあがっていること、その分からなさのもとの狂気が濃密に描きこまれている。
南北戦争前後、金持ちになろうとして巨大な土地を手に入れて、屋敷と農園を築き、そして没落していく男サトペンとその一族の物語である。サトペンが生まれたのは1808年くらい(定かではない)。生まれ育ちは南部といっても、ウェストバージニアのすごい山の中の貧しい丸木小屋。スコットランドからの移民の子どもである。そこにいた有色人種はインディアンだけで、普通に南部といって想像される、広大な農園、農園主の白人が黒人奴隷を使って贅沢な暮らしをしている、そんな人たちがいるなどということもまるで知らずに育った。ちょっと引用する。
そんな所だから、きちんと区分された土地があって、それが、自分ではなにもせずに他人に働かせておいて立派な馬に乗ってそこを見まわったり立派な服を着て大邸宅のヴェランダに坐っているような地主たちによって所有されているということは、彼は聞いたこともなかったし想像したこともなかった。当時の彼としてはそんな生活、そんな生活への欲求があるということ、あるいはそんな欲求の対象になるようなものが存在しているということ、あるいはそういうものを所有している人が所有していない人をひどく見くだすことができるばかりでなく、そうして見くだしていながら同じくそうしたものを所有している他人からばかりでなくそうして見くだされている持たざる人びと、自分たちがけっして持てるものにはならないだろうとわかっている持たざる人びとによってさえもそのことを認められている、などということは、想像もつかなかった。なぜなら彼が住んでいた所では土地はみんなのものだったからだ。だからわざわざその土地の一部を囲って「ここはわたしのものだ」というひとがいたら、それは無茶な話だ。それは品物についても同じことで、だれかがひとより多く持つということはなく、だれもが自分の力に応じて持てるものを持ち、自分が食べたり火薬やウイスキーと交換するに足るもの以上に取ったり欲しがったりするのは正気の沙汰ではなかった。だから彼はすっかり区画されてきちんと分割されている土地があって、そこに住むひとも皮膚の色がどうとか生活手段がどうとかいったことで截然と区別されているとは知らなかった。そういう所では、ある少数の者が他人の生殺与奪や物々交換や売買の権利をにぎっているばかりでなく、蜿蜒反復される個人的な仕事、たとえば瓶からウイスキーを注いでそのグラスを手渡してくれるとか、長靴をぬがしてベッドへ寝かしてくれるといったような、だれでも生まれてから死ぬまでやらなければならないような、だれでもやりたいと思わなかったし今後もやりたいと思わないような、しかし彼が噛んだり嚥んだり呼吸したりする務めをいやがらないのと同じようにだれもそれを怠ろうと思ったことがないような、そんなことをやってくれる生身の人間をも所有していたのだ。
一家が山の上の生活からヴァージニアの町に降りて行ったあと、彼は父に何か用事を頼まれて金持ちの家におつかいにいくが、表門に出てきた黒人に「裏口にまわれ」と追い返されるという体験をする。その屈辱体験からサトペンは「金持ちになる」ことを決心する。しかしもう開拓の時代はかなり進んでしまっていて、いわば遅れてきた貧しい白人の彼は、金持ちになるための道筋はよく分からない。定かではない人の話を頼りに、まずはカリブ海の島、ハイチに渡り、その後波乱万丈・紆余曲折を経て、本書冒頭、ジェファソンの町の郊外に、広大な土地を(不法にのようだが)手に入れ、カリブから黒人奴隷を連れてやってくるのである。
遅れてきた人間ほど、無理な,不法な、暴力的な手段を取らないと金持ちにはなれない。サトペンはそうやって手に入れた広大な土地に豪邸を建て、それを継がせる家族、子孫を作ろうとする。
ところに南北戦争が起きて、南部流の方法で手にしたいろいろを、すべて失っていく、という話である。南部の白人の持つ、南北戦争前後の体験の受け止め方、鬱屈、そういうものが描かれる。
この前、黒人奴隷側を主人公として同じ時期を描いた『ウォーター・ダンサー』タナハシ・コーツ著を読んだ。つい最近の作品である。最近の小説も映画も、南部黒人奴隷制周辺をテーマにしたものは、黒人側の視点からの悲劇の歴史を描くものがほとんどで、そこに登場する南部白人は(特に良心的例外的な人物を除いては)人種差別をする極悪人のように描かれがちである。現代の価値観の中ではそうなるのはまあ当然だ。が、当時の白人の人たちが何をどう感じていたのかは、よく分からない。南部の没落しつつある白人農園主も貧しい白人も、黒人に対してより過酷になっていくのである。
ここで論じたいのは「人種差別」問題ではない。この小説の主題もそこにはない。もうすこし根源的な、アメリカ固有の社会の成り立ちの根幹にある狂気や暴力についてである。暴力というのは人に対して振るわれるだけではない。
あちらの小説の作者タナハシ・コーツも、黒人の肉体というものを最大の資産としてアメリカの資本主義は成立していたし、黒人の肉体を白人が自由に収奪していいという考えはいまもアメリカで続いているということをいろいろなところで書いている。
アメリカという国が生み出す、明らかに過剰な富の発生には、それを求める人の価値観と行動原理がある。その動力の根源にある狂気についてである。黒人奴隷制とその差別はその一部である。それ以前にネイティブアメリカンを暴力とだまし討ちにする形での土地を取り上げるという暴力があり、そうして獲得した自然・国土・資源を根こそぎ強欲に収奪しまくることを当然とする心性がある。そしてそれを自らの一族で独占継承しようという思いがあり、そうであれば一族を継承させようという血族の論理があり、そこにまた人種差別の意識が絡んでくるのである。
あちらの小説でもこちらの小説でも、白人農園主が奴隷である黒人に産ませた子どもの問題、白人の子供と混血の子供、両方が子どもの頃は一緒に育てられながら、ある年齢になり立場の違いに気づくという関係性が描かれる。そのことを当時の、そして現在に続くアメリカ人がどう考えるか、感じるかというのが、小説を理解するのにすごく重要になる。(そこが分からないと、小説の肝心のところがよく分からなくなる。)
「アメリカという国、ないしは今につながるアメリカの資本主義の、世界をわがものにしたいという欲望と行動の原型の狂気」。それをそのまま物語にしたような、そういう小説として、僕は読んだのである。
アメリカの、というより資本主義を生み出したアングロサクソンの思考、はじめの「囲い込み」、誰のものでもなかったものを「俺のものだ」と宣言して、そこから人を追い出し、そこにあった自然をまるごと収奪破壊しつくし、ということの、「誰のものでもなかった場所を俺のものだと宣言し自然を収奪しきる」。
イギリスではじまったそういう動きが、その舞台をアメリカに移したところ、その自然のスケールがあまりにデカかったので、そこに入って行った人間が全員頭がおかしくなる、というのがどうもアメリカという国の起源のように思われる。ネイティブアメリカンを追い出したことと黒人奴隷制がそこに加わるのである。
ちょっと脱線するが、
※貧困から抜け出すために、広大な土地を、その権利もろもろを取得してそこで富を築こうという、そのスケールの大きさを読んで、(この小説でサトペンが手に入れたのは100平方マイル=一辺16キロメートルの正方形の面積である。)、『資源地図』ダニエル・ヤーギン著の第一章で紹介される、シェールガス開発の先駆者ジョージ・ミッチェルのことを思い出した。父親はギリシャ出身の非常に貧しい移民(1901年に渡米する)で、その貧困から抜け出そうしたジョージが紆余曲折を経て採掘の権利を得た試験エリアは1万6000平方キロ(つまり一辺400キロメートルの正方形)である。貧しい移民の子が貧困から抜け出すためにとんでもない土地を手に入れようとするという「アメリカでの成功の形」が相似形である。
話は戻って
「みんなのものの自然から、必要な分だけ何がしかをもらって、そこそこ満足しながら暮らす」という知恵を、もともとアメリカに住んでいたネイティブアメリカンは持っていた。そして主人公サトペンがウェストバージニアの山間部の貧しい白人の子供として育った時は、白人移民だけれど、そういう価値観で暮らしていたことが先に引用した部分でわかる。幼いサトペンからすれば、資本主義というものは土地を囲って自分のものだと主張することも、自分で消費できる以上のものを欲しがることも、「狂気の沙汰」だ。その狂気の欲望側に人生の目標を置いた瞬間からサトペンの破滅は始まるのである。
その前提として、国というのは、そういう「誰のものでもなかったところを占有してしまう」という狂気の沙汰にお墨付きを与える仕組みとして存在する。
今の世界がなんかおかしい、頭のおかしい理屈を信じた人たちによって成立していて、その中心にアメリカという国の狂気があって、それをなんとかしないと地球全体がおかしくなるよということに気づかないとダメなんだよな、と、そんなことまで考えながら読んだ。
ひとつ、よく分からないのは、そうした狂気のありようが、南部と北部で、南北戦争でどのような対立があり、(黒人奴隷制に対する、というより深い所で)、負けた南軍側の人間はどういう鬱屈を抱え込んだのか。そのことがこの小説で、確かに書かれているのだが。書かれてはいても、それはこういうことだ、こういう感情だ、とうまく言葉にできない。
この小説の一番最後、その感情の叫びで終わるのだが。
※ 今回、「池澤夏樹個人編集 世界文学全集」で読んでよかったのは、池澤夏樹氏の巻末解説が素晴らしかったこと。フォークナーの個人としての評伝と、それとの対比でのヨクナパトーファという架空の郡を舞台にした連作を生涯書き続けた、その架空の世界を生き続けた、その二重の人生としてフォークナーの人と作品世界を解説してくれている。主要作品のそのサーガの中での位置づけを解説してくれている。そう知った上でなら、フォークナーの他作品を読んでいけそうだと、そういう気持ちにもなった。
