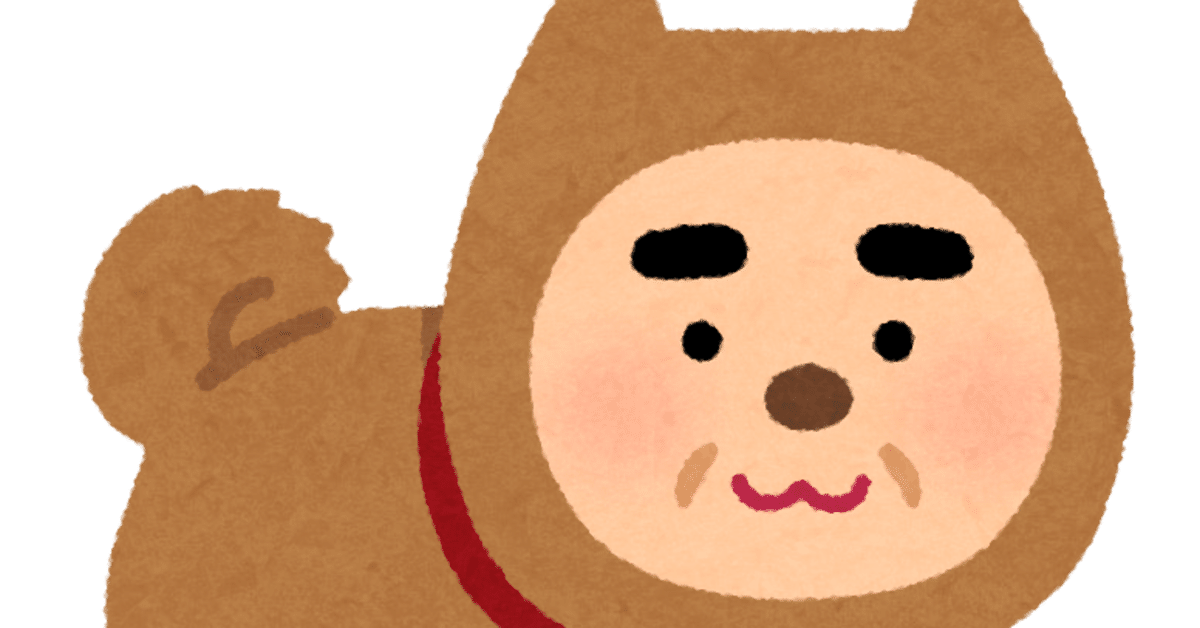
こんな世の中だからブルガーコフを読もう-『犬の心臓・運命の卵』【ロシア語文学】
ミハイル・ブルガーコフ『犬の心臓・運命の卵』新潮文庫版
ミハイル・ブルガーコフは、1981年、キーフ(キエフ)に生まれた作家である。もともとは医師であったが、ロシア内戦後、小説を発表し高い評価を受け作家となった。しかし、その風刺的な作風が当局に問題視され、わりかし不遇な人生を送り、20世紀最高のロシア語文学などと世界的な評価が高まったのは死後のことである。
ブルガーコフは、SF的な手法を用いつつ、ロシア革命後間もないソビエトの社会を風刺するような作品を書いた。本書に収録されている1924年に発表された『運命の卵』、1925年に発表された『犬の心臓』は、わりとモロにそのようなテイストの作品だ。当然、当時は当局に目をつけられており、『運命の卵』は出版できたものの、『犬の心臓』は家宅捜索の際に原稿が押収されてしまい、しばらく出版できなかったという。
訳者のあとがきによると、そのような体制側からすると危険な作家とみられていたブルガーコフであるが、案外スターリンはお気に入りだったようで、何度もブルガーコフに便宜を図ってやったらしい。そのおかげで、1930年代にはいくつかの劇場で仕事を得ることができ、スターリンは、お忍びで彼の作品を観劇しにいったという。しかし、当局との確執は結局埋まらず、自由な作品の発表がかなわないまま、1940年に没している。
まあ、当局に睨まれるのも無理もない感じもあって、例えば『犬の心臓』では、ヒトの脳下垂体を移植され、知能が発達した犬が描かれるのだが、そのある意味啓蒙された犬人は、人格者とはほど遠い、下品なプロレタリアート的存在になってしまう、という具合だ。物語の舞台である社会についても、かつての善きものが失われ、混乱し、荒廃している、といったタッチで描かれる。つまり、革命によってもたらされた、解放された労働者中心の社会が必ずしも掲げた理想のようにはなってないじゃないか、ということである。それは睨まれるだろう。
しかし、同時に、そういった社会の風潮の中で、犬人「コロフ(原文ではシャリコフ)」を生み出してしまうような、マッドサイエンティストめいた医師についても、やや浮世離れしたブルジョワといった雰囲気で描かれているようにも感じられる。ちょっとアレな金持ちの医者が、自ら生み出してしまったプロレタリアートっぽい犬に徹底的に困らされる、という話でもあるわけだ。エリート層の驕りのようなものの滑稽さ、みたいなものも感じられる作品なのである。
そういう両面を考慮に入れて作品全体を眺めると、必ずしも徹底して反革命を主張した作品という感じでもない。ただ「社会のリアル」みたいなものを、ユーモラスに皮肉って見せた、そんな程度のものなんじゃないかとも思う。それが体制側から厳しい目を向けられ続けるということは、やはり、洋の東西、時代を問わず、本当のことというのは言ってはいけないものなのだろう。「リアル」はいつも、誰かにとって不都合なのだ。
現代でも、主に居酒屋などで繰り広げられる、社会や、その一部である組織みたいなものに対する愚痴大会というのは、我々プロレタリアートにとっては重要な娯楽の一つである。しかし、そういう、どうでもいい愚痴みたいなものは、世間では無駄な時間として批判されがちなものでもある。それもわからないではないところがあって、多くの居酒屋談義みたいなものは、単純に「こんな世の中」的題材をただ消費してそれで終わってしまいがちなところがある。世の中や他人の人生を動かしたりはしないのだ。
風刺作品というものも、なんというか、うがった見方をすれば、問題提起にはなるかもしれないが、必ずしも建設的なものだとも言えないという、単なる愚痴に似たところがあるようにも思う。しかし、その一方で、時代を超えて人々に愛されるレベルの作品というのは確かに存在している。
ブルガーコフの語る物語は、辛辣で若干グロテスクでもあるが、どこかユーモラスなところがある。いつ粛清されてもおかしくないような厳しい環境におかれながらも、面白おかしく社会をdisり続けるというのは、並み大抵のことではない。そういう点では、やはりどこかぶっ飛んだところがあったんじゃないかな、という気がしてくる。結局は、人間としての面白さみたいなものが、作品に反映されたりするものなのかも知れない。
自分も、どうせ文句を言うなら、せめてそれを聞く人たちを楽しませられるようにありたいものだ。
いいなと思ったら応援しよう!

