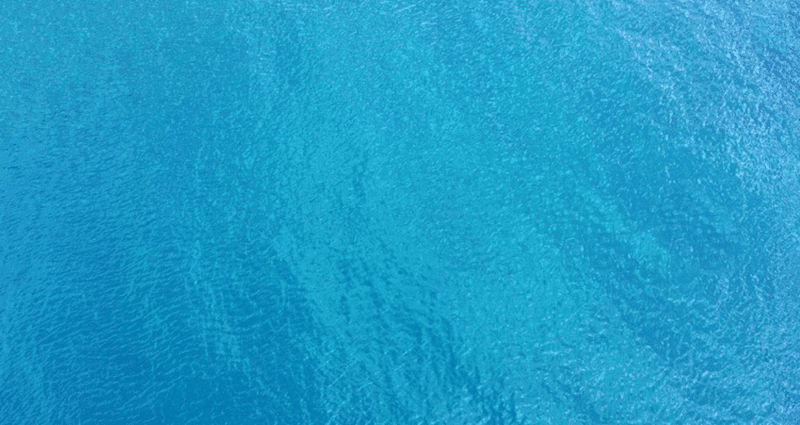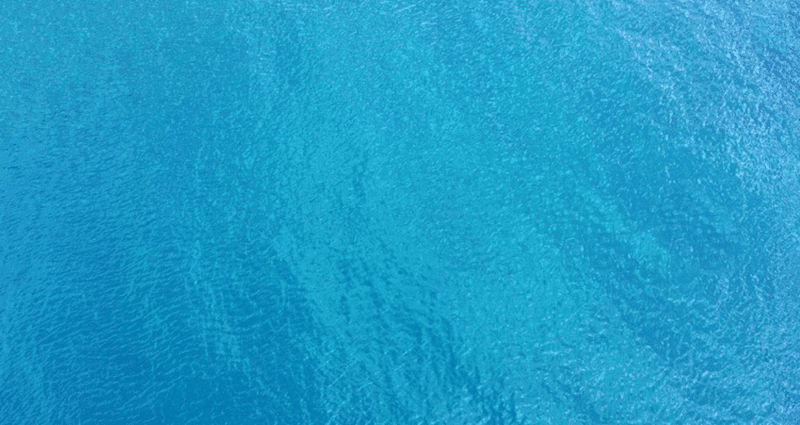SNS社会運動が承認の快楽を得る上で「コスパが良すぎることの功罪」をどう考えるか
投票が迫ってきたので、もう一回くらい都知事選について書こうかと思う。選挙そのものへの分析も、今後の論点の提示ももうしたので、少しメタ的に問題の本質について考えてみたいと思う。
ここ数回の大きな国政選挙も含め、注目度の高い選挙のたびにカルト的な市民運動ーーそれもインターネットを主戦場としたーーものが、そのカンフル剤としてパフォーマンス的に出馬する、という現象が常態化している。そして端的に述べれば、これは言論の敗北なのだと僕は思う。つまり、言論レベルで政治的なものに可能な限り慎