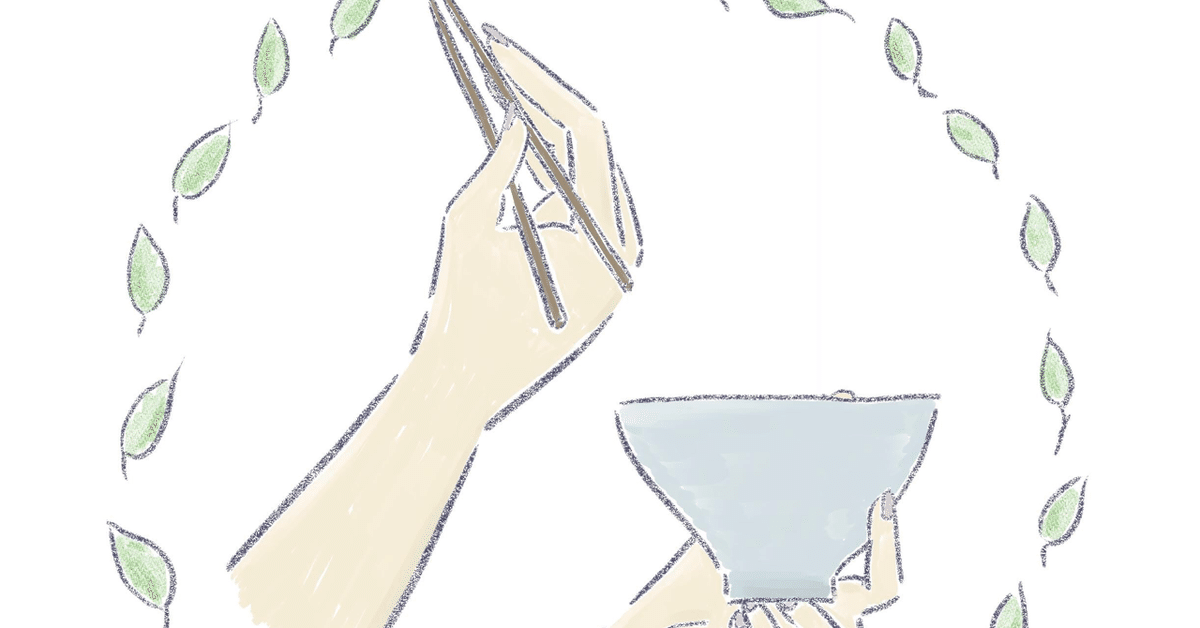
これまで以上に食べる時間を大事にしたい
巷の大学院生です。こんばんは。
今日は学部ゼミにTAとして入っておりました。
学部生同士のディスカッションがとてもよくできていて、私いらないのでは・・?と嬉しくもあり寂しい気持ちになっています。でも私にできることがあると信じてサポートしたいですね・・複雑な気持ちです・・。
さて、今日は最近読んだ本の話。
ここ最近は、自分の専門から離れた書籍を読みたいなあと心がけたりなんかしています。
最近読んだのは、藤原辰史さんの「食べること考えること」です。
この本では、世界の食の歴史、例えばナチスの政策(哲学)における食の考え方について触れたり、科学技術の発展と矛盾する形での農作業や家事労働の重労働化などについても述べられていました。
食の歴史の中でも、乳製品の普及などについて、これまでになかった視座が得られました。
もともと科学技術の発展と、そこで起きてくる倫理観(生命観)の危機のようなものに関心があった...関心...というか不安?恐れ?みたいなものがあったので、小さな、かつたくさんの気づきがありました。
小さな、というのは、この本がコラム集のような形でまとめられていたからです。
あと、最後の方で、石田徹也さんについて知ることができたのもよかったです。
「燃料補給のような食事」
この絵について。知っていますか?
私はこの方の名前を見て、この絵の名前が紹介されているのをみて、インターネットで調べて初めてこの絵をみました。
いろんな感情が沸き起こりました。
科学技術が発展していくように、何かをよりよくしていくプロセスの中に、効率化を求めすぎたり、少しそちらに偏りすぎたりすると、大事なものがいつの間にか失われていく、そしてそれに気づくことすらできず、知らないうちに疲弊していく...
そんなようなことを考えました。
ふと自分が研究室でどうやってご飯を食べているのかとかを振り返ってみました。
PCをみながら、あたかも
忙しいからゆっくり食べる時間ないや
みたいな気持ちになって、食べ物を胃に入れるようなことをしていることに気づきました。
あとは食品添加物がたくさん入っているような手軽な食べ物を食べるときには、あえて味わわないように意識していることもありました。
寂しいですね。
単純だけど、こんなふうに、これまでの食に対する考え方を、見直しました。
他にも藤原さんの書籍、いくつもあるのでまた読んでみたいなと思います。
短いですが今日はこの辺で。みなさま良い夜を〜!
いいなと思ったら応援しよう!

