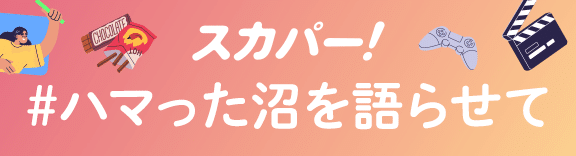旅に取り憑かれて家庭を崩壊させた男
質問が来た。
さて、少しある男の昔話をしようか。
男は、旅に取り憑かれていた。
ひとりきりで乗り込む深夜の列車、どこか知らない街の冷えた風、名前も知らない誰かと交わすたわいない会話。
行く先々で切り取る景色は、家で繰り返す日常よりも、よほど鮮やかに見えた。
旅に出れば出るほどに、肥大化する好奇心。
もっと見たことのない景色が見たい。
知らない文化に触れたい。
現地人しか知らないモノを食べたい。
「ちょっと温泉場に行ってくる」
「週末だけ、山の中で過ごしてくる」
そんな言い訳を重ねていたころは、まだ戻る場所があった。
愛想をつかしながらも、妻は夕飯を用意してくれていたし、息子は小さな手で「おかえり」と出迎えてくれた。
だが、旅は一度深みにはまると抜け出せない。
初めは数日だった。
次は数週間、そして数ヶ月……。
気づけば、男は行き先も告げず「帰らない男」になっていた。
行く先々で出会う連中は、決まって言った。
「自由でいいな」「羨ましい人生だ」
笑える。自由? それは表の顔だ。裏には空っぽの男がいるだけだ。
家に残してきたものがある。
それは、ある意味彼のすべてだった。
妻の笑顔。
息子の寝顔。
「パパ、どこいくの?」と無邪気に聞いてきた、あの小さな声。
それらを捨ててまで、男は旅に没頭した。
なぜか?
家に居ると、自分が「しょぼい男」だと突きつけられるからだ。
仕事はうまくいかず、家族サービスもうまくできない。
だから、彼は「旅人」になった。
「父親」でも「夫」でもない、誰でもない自分になりたかった。
―そして、ある日、妻からの一通のメッセージで全てが終わった。
「もう帰らないでいいですよ。息子は私が育てます」
指が震えた。
スマホがやけに重く感じた。
心臓が鈍く、深く痛んだ。
ああ、ついにすべてを失ったんだな。
もう「ただいま」と言う場所はない。
もう「おかえり」と言う声もない。
それでも、男は旅をやめられなかった。
どれだけ歩いても、どれだけ車を走らせても、追いつけない。
―あの日、あの家にいた「父親だった俺」には。
夜、名前も知らない駅、場末のバーで飲めないウイスキーをあおる。
ガラス越しに見える街灯はぼんやり滲んでいる。酔っているのか、泣いているのか、自分でもわからない。
「結局、お前は何が欲しかったんだ?」
グラスに写った男に問いかけても、答えは返ってこない。
わかってるさ。
旅は「帰る場所」があってこそ、美しいんだ。
―男はそのことに、あまりに遅く気づいただけだった。
荷物は軽い。心は重い。
彼の旅は、きっとどこへも辿り着かない。
……だけど、今夜も歩く。
この虚しさの中でしか、生きている実感がないからだ。
……。
ピピース