
究極の自由と責任 - フランクル
「自尊心=自己効力感+自己肯定感」の、続きです。今回は自尊心の二番目の構成要素、”できてもできなくても”自分は素晴らしいと思える命そのものの自信、自己肯定感について書きます。(前のコラムを読んでない方は、1.スーパー、2.バンデューラ もあわせてどうぞ)
”自己肯定”は生命原理
人間はそんなに簡単には、命を放棄しません。
みんな、事業に失敗して数千万の借金を背負おうと、私利私欲の企みがバレてカッコ悪く職場を追われようと、脇の甘いSNS発言で大炎上の的になろうと、全身全霊をかけた恋に破れて空っぽになろうと。
死にたいほど傷ついても、なかなか死ねません。簡単には止まらぬ鼓動と血潮に動かされ、自分の強さに辟易しながらも生きてしまうのが人間です。
「自己肯定感」から”自己肯定”だけを取り出せば、本来それは、自覚のあるなしに関わらずその人の中に内在する生命原理なのですが、問題はそれを「感じられるかどうか」。これが感じられないと、辛いのです。
器用な人は”自己効力感”に流されがち
しかしまた、人間は社会的な生き物として、外からのノイズに影響を受けます。誰に何を言われたという現前の事実がなくても、生きるために内在化してきた他者の声「~すべきである」「~してはならない」という、必ずしも合理的とはいえないビリーフもあります。
それらに従うことに常日頃慣れすぎてしまっていると、割と簡単に、本来の自分の生きる力が見えない・感じられない状態に陥ってしまいます。
そこで社会適応力が高い器用な人が陥りがちなのは、自分のやりたいことが曖昧なままに(自己肯定感が不在のままに)自分のできることに流されてしまう(自己効力感に従って進んでしまう)というパターンです。
傍から見ると何の不自由もなく成功しているのに、本人は虚しいという、今時の問題を抱えたエリートはこうやって生まれます。要領よく生きることを助けてくれる優秀な意識の機能が、極まったところで生きやすさの邪魔をするのです。
私の”自己肯定感”を支えてくれた読書癖
自分の中にある、その本来の(時とともに変わるものでもあるが)色や形に気づいて直視することでしかつかめないのが、命そのものへの自信、「自己肯定感」なのです。
それは万人から見て分かりやすく輝くものではないかもしれない。言語化すると路傍の石のようなさりげないものかも。途方もない形をしているかも。
でも、それは無視すると具合が悪くなり、直視するとスッキリします。
そしてその独自性・唯一性が、個人の存在に意味を与えます。
ここで突然告白になるけど、わたし自身はかなり頑丈な「自己肯定感」の持ち主です。「自己効力感」のほうは、あったりなかったりですが。
自分が傷つき、回復した経験から癒す側になるケースが多いセラピストとして、まあまあ強い自尊心とともにここまで生きてきて「我こそは深く傷つき、のりこえた」と語れるすごい話を持たないというのは…どうなんだろうと、時々自問することもあります。でも、何回スキャンしてもわたしはわたしなんですよね。
で、その鉄のメンタルはどこから来たのと聞かれたら「子供のころから、ちょっとおかしいレベルの本好きだったから」という答えになるかなあと思います。(社会的応力が低い不器用な子供だったからとも言えます。)
読書とは、活字とは、限りあるひとりの命では賄えぬほどの幅広い情動を、安全なところに身を置いたまま体験して内在化させる(バンデューラ的に言えばモデリング学習できる)人類の至宝です。
「夜と霧」に見る自己肯定感
というわけで、今回、自己肯定感に関連して紹介したいキャリコン学者は、ヴィクトール・フランクル。オーストリア出身の神経科医で心理学者。
ホロコーストからの生還実録「夜と霧」の筆者といえば、知っている人も多いかもしれません。
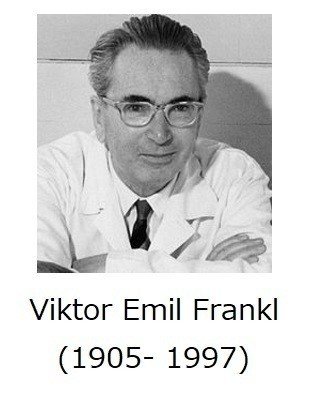
「夜と霧」には、色々な現物証拠があると知っていてもなお、これが実際にあったとは信じられないような人類の黒歴史がつづられています。しかし同時に「自己肯定感」とはなんぞやについての学びとなる名言の宝庫です。
そのフランクルが提唱した心理療法・ロゴテラピー(Logotherapy)は「いかなる状況下でも、生きる価値を追求する自由と責任を持つ存在」として人間を捉えます。苦痛の軽減でも快楽の探求でもなく、自分の人生の意味を探すことこそが人間が生きるモチベーションになるというのです。
これは、彼がアウシュビッツの極限を経験して開眼したものかと思いきや、「夜と霧」を読むと分かりますが、実は逆なんです。ナチに捕らわれる前にすでに理論の骨格を完成させていて、その基本姿勢があったからこそ、フランクルはホロコーストを生き延びることができたと言っています。
10代の半ばに一度読んだときには精神的にダメージを受けた記憶しかなかったのですが、最近読み返して、潜在意識の裡に残る彼の言葉がわたしの自己肯定感を底支えしてくれていたようにも感じました。楽しく読める本ではありませんが、やはり読む価値のある一冊です。自己肯定感がつかめないという人への、推薦図書です。
どなたさまも、ハッピーなライフ・キャリアを。
本コラムを投稿した翌朝にタイムリーな記事が目にはいりました。ハーバードのキャリア相談室で「自分が何をやりたいか分からない」と言って泣くエリートが多いという話です、ご興味があればどうぞ。
