
お持ち帰られ喫茶店❼|めぐみとめぐり、ぐるりとめぐる。

夏休みになった後、こどもが忘れものを学校へ取りに行くように、秋になった後、夏が忘れものを取りに行くことがある。残暑、と呼ぶには幾分遅すぎる時期である。ふたつの気圧がぶつかり、秋雨が熱を覚まして行く。
秋が深まる。
虫の三重奏の調べに乗って、金木犀が空気を彩り、香る。そんな秋の空気に包まれると、おもいだすことがある。
めぐりとめぐりあった日のことを。

タイトルから続く言葉遊びに、ちょっと何言ってるかわからない人は、このまま読み進めていただきたい。さて、ゆくか。
全国五十万人(出口調査速報値)の『お持ち帰られ喫茶店』ファンのみなさん!
お待たせしました! 続篇、出来上がりました!
(歓喜の声)
(歓喜の歌)
(恍惚の顔)
(口元の涎)
うーん、揃いも揃っていっちゃてる!
ありがとう。
あなたも、ありがとう。
そこのきみ、ありがとう。
てなわけで、今回も、ひとつ、ご贔屓に。
この『お持ち帰られ喫茶店』は、いつも、こんな風にはじまる。

わたしは珈琲が好きだ。
だから上京後は喫茶店で働いた。
こうして物語の舞台が整った。

ひとりの少女から物語は始まる。
彼女の名を、めぐみ、と呼ぼう。
めぐみが引き合わせたのがめぐり、だ。
めぐみとめぐりは同郷から上京した同級生だった。
めぐみは、構成作家になる夢を抱いて上京して専門学校に通っていた。
めぐりは、いずれ地元へ戻り自分の喫茶店を持つことを夢見る女子大生だった。オザケンとサニーデイ・サービスとフィッシュマンズが好きなおんなのこ。いわゆる渋谷系というやつだ。
このふたりによる、わたしの周波数帯への干渉が、運命線と世界線を交差させることになる。本来ならば、決して交差することのなかったはずの、わたしとめぐりの移動曲線を。

小さな橙色の花の香りが影を潜めだした夜に、めぐみは専門学校の同輩数名と当店に来店した。化粧気はないが、そばかすがチャーミングで、よく喋り、よく笑う子だった。幾分、痩せ過ぎてはいたが、彼女の周りには、秋だというのに夏の花が咲き誇る雰囲気が、いつでも漂っていた。
週末の夜に店は賑わいを見せていた。
カフェインの効用が広く周知されても、夜間に珈琲を好む者は多い。店としては書き入れ時だ。一杯一杯、丁寧にドリップした珈琲を提供する当店は、回転率を上げることには限界がある。だから、混雑時には、注文を受けてから待たせてしまうことは避けられない。
「店員さん、ぶどうのジュースまだですか?」
めぐみがよく通る声をあげる。
「お待たせしてますね。なにせ珈琲専門店ですので、いま、農園まで新鮮なぶとうを獲りに走らせてるところです。もうすこしだけお待ちください。」
わたしは咄嗟に弁明する。
「えっ?そうなの?」
「いや、冗談です。」
「ぷ、ぷははははっ。お兄さん、面白い!」
「では、もう少しお待ちいただけますか?」
「良いですよ、獲れたての期待してます。」
「ありがとうございます。お客さまが違いのわかる男でしたら、ご堪能いただけるでしょう。」
「え、わたし、女なんですけど。」
「ええ、ボケのサービスです。もちろん、お代は結構です。・クドナルドのスマイルと同じシステムです。」
「ぷははははーっ。なになに?ひょっとして、お兄さん、芸人とか目指してます?」
「まさか。お客さま、わたしは『おまえのギャグで笑ったことはない・ベスト・オブ・高校時代』の受賞歴ある男ですから。」
めぐみの笑い声に釣られるように、連れ合いの知人もゲラゲラと笑う。どうやら苦情回避の呪文が効いたようだと、わたしは胸を撫でおろす。
この日の営業も無事に終わる。
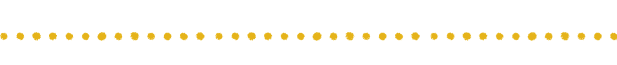
その後も、めぐみは何度か来店してはわたしに絡み、わたしの『ベスト・オブ・高校時代』級のくだらない冗談にゲラゲラと笑うことが続いた。わたしはわたしで、この子、お笑い偏差値低めと疑う日々が続いた。並木道を歩くと、街路樹の落ち葉がパリパリと乾いた音を立て始めた。
誰も彼もの影法師が背丈を伸ばした頃、めぐみは、めぐりを連れて来店した。めぐりは、誰もがはっと息をのむ美少女だった。男性客の目が釘付けになるという瞬間を目撃した瞬間だった。陶器のような白い肌。頬から顎にかけた美しい稜線の小顔には潤んだ大きな垂れ目とうすい唇が完璧なバランスで造形されている。小さく華奢ながらもバランスの取れた女性的な曲線の体躯をした彼女を振り向かずにいる者の方が不自然なほどだった。わたしは、不自然な方であった。
「いらっしゃいませ。」
「こんちゃです。」
めぐみはいつものテーブル席には座らず、珍しくカウンター席に座る。わたしの目の前だ。
「きょうは友達を連れて来たよ。」
「ひとりできたことありましたっけ?」
「あれは、学校の友達。こっちは地元の友達。」
「ん?遊びに来てる?」
「違うよ。一緒に上京して◯女に通ってる子。」
「ああ、そういうことですか。」
「そういうこと。ちょっと、お兄さんに会わせたくて。」
「ここは見世物小屋ではありませんよ。」
「ね、めぐり、言った通りでしょ?」
と、めぐみは隣に座る美少女に声を掛ける。
「うん、うん。のっけからだね。」
と、美少女は楽しそうに言葉を返す。
「あたしの目に狂いは無かったよ。」と、めぐみ。
「さすが、めぐみ。お目が高い!」と、美少女。
「お楽しみのところ何ですが、ご注文はお決まりでしょうか?」
わたしは店員として売上をがっぽりするために、ふたりの会話に割って入る。
「えー、じゃあ、きまぐれで!」と、めぐみ。
「うちはイタリアンレストランじゃありまへん。シェフのきまぐれサラダ的なメニューはやってまへん。」と、わたし。
「ほら、ほら、めぐり、変な人でしょー?」と、めぐみはめぐりに言う。
「うわー、ほんとだー、まじかー。」と、めぐりはわたしを見ながら答える。
「めぐみさんが来ると大変なんだよなぁ。はぁー。」と、わたしは大袈裟にため息を吐く。
「ちょっと、お兄さん、そんなこと言わないでよ。きょうは楽しみにしてたんだから。ね?」と、めぐり。
「うん、すごい、すごい、楽しみにしてた。」と、めぐり。
「ワタシ、オマエラノ注文ナンダ、キイテイル!」
と、わたし。
めぐみとめぐりは顔を見合わせた後、堪えきれないといった感じで声を出して笑う。
「「あははははーっ!」」
いや、笑いたいのこっちなんだが。しかも、苦笑い。最悪じゃ。貴様ら、美少女だからと言って、拙者が許すとでもおもうたら大間違いじゃ。いっそ、斬り捨ててやるかと心のなかで「キェーッ!」と雄叫びを上げながらも、ふたりに微笑む。仕事だから。でも、頬がピクピクしている。
「では、他の者に変わりますので、それまでに考えておいてくださいね。」
ふたりにそう告げ、カウンターを去ろうとした時、めぐみが忙しなく弁解する。
「ごめんなさい。本当に。あの、お兄さんのおすすめの珈琲が飲みたいです、本当の本当に。ね、ね、めぐり、飲みたいよね?」
「うん、うん、おすすめが飲みたい!本当の本当に。」
「……本当に?」
と、わたしは薄い目をして疑いの目を向ける。
「「本当に!」」
ふたりが息ぴったりのユニゾンで答える。「おまいら、ゆずか!」と心の中でつっこみつつも、倍々で力強いじゃないか。嫌いではないぞ。
「わかりました。では、それぞれ味の好みを教えてください。大体でいいから。」
と、わたしはふたりに問いかける。
「えっと、わたしは、いつもブレンドばかり飲んでいるから、たまには単品のコーヒー飲んでみたい。味はコクがあって濃いめが好き。こんな感じでいい?」
「大丈夫ですよ。ちなみに、めぐみさん、チョコレートとキャラメルはどっちが好きですか?」
「チョコレートが好き!」
「オーケーです。では、めぐりさんは?」
「うんと、わたしは苦いの苦手です。普段は、コーヒーよりも紅茶が好きなんだ。でも、今日はここのコーヒーを飲んでみたくて。わたしでも飲めるコーヒーってありますか?」
「うん、大丈夫。じゃあ、めぐりさんは、フルーツティーとか好きですか?」
「大好き!いつもカレルチャペックでストロベリーのとかピーチの買います。あと、アールグレイも大好き。え、こんなんですけど大丈夫かなー」
「大丈夫。フルーティで華やかなのがお好みなんですね。かしこまりました。」
「ええー、すごい!どんなのが出てくるんんだろう?」
「おまかせください。」
ふたりのオーダーを確認し、わたしはそれぞれに合うシングルオリジンの珈琲豆を、いくつかピックアップし、香りを確認する。ふたりの顔を見て、その印象に近い珈琲豆をひとつずつ選ぶ。各々のまめに合ったメッシュで豆を挽き、丁寧にドリップする。わたしは、この時間が無性に好きだ。先程まで饒舌だっためぐみとめぐりも黙ってわたしの所作を見守っている。つつつと、コーヒーの美味しいエキスが含まれた液体がサーバーに落ちて行く。出来上がったコーヒーをふたりに提供する。
「めぐみさんのは、これ。ホンジュラスの農園で採れたコーヒー。ビターチョコレートの香りとオレンジのような柑橘系のさわやかな香りが特徴ね。飲んだらバニラのような甘味が広がって、それからビターチョコレートの風味と、あと、すこしだけ柘榴のような酸味を感じられるとおもう。ご賞味あれ。」
「めぐりさんのは、エチオピアの変わり種。苺の風味に、ブルーベリージャムのような甘酸っぱい果実味とラベンダーのようなアロマを感じられるコーヒーね。明るい酸味だから紅茶好きなめぐりさんには合うとおもうよ。はい、どうぞ。」
きょとんとするふたりの顔を一瞥して頭を下げる。めぐみがコーヒーをひとくち口に含む。
「うっま!何これー!ふぁっ、バニラ、チョコレートみたい!え?これ、チョコレート入れたの?」
「ううん、珈琲豆だけですよ。柔軟剤変えただろみたいなこと言われてもね。」
「ええー、信じられないくらい美味しいんだけど!」
「お口に合ったようで良かった。」
「すごく合う!めぐりのはどう?」
めぐみに促されためぐりも出されたコーヒーをひと口啜る。
「わわわー!い、い、苺がいる!大変だ!鼻から苺の花が咲くよ!わわわ、おいしい!これ、コーヒー?コーヒーだよね?」
「コーヒー。種も仕掛けもない。美味しくなるように魔法の呪文は掛けておきましたよ。あー、ついでに、また来店したくなる呪文も。」
「もう、次いつ来ようか考えてるよ、これも魔法?(笑)」
「めぐりさんは魔法に掛かりやすい星めぐりですね、名前の通り。」
「ふぁー。」
混雑時間に入り店内が賑わい始める。わたしは他の来店客の対応に追われる。めぐみとめぐりは、ケラケラと笑い合いながら、時折、わたしに話し掛けては一言二言を交わして時を過ごす。帰り際に、めぐりがわたしに尋ねる。
「Uさんて、シフトとか決まってる?」
「シフト?ええ、決まってますよ。」
「いつなの?」
「水金土です。イレギュラーもあるけど。どうして?」
「だって、魔法掛けたんだよね?」
「ああ、そうそう、また来たくなる魔法ね。まだ効いてます?」
「効いてる!だから、解けなかったら責任とってね(笑)」
「オーケーです。コーヒー、一杯で手を打ちます。」
「お金取るの⁈」
「これがうちの商いでんな。」
「確かにー。じゃあ、また来る!ぜったい!」
めぐりはそう言い笑顔で手を振る。その笑顔で魔法に掛けられたのは、男性客だけではなかったようだ。自覚はしてなかったのだけれど。恋の魔法というものは、実際、音もなく掛けられることを、後に知る。

大学からの帰り道ということもあり、めぐりは頻繁に来店するようになった。席は必ずわたしの目の前のカウンター席と決まっていた。至近距離で接客をしていると、アイドルのような容姿にも耐性ができるものだ。毎度騒つく他の男性客の視線もさして気にならず、めぐりと話すことも日常となった。
「ねー、Uさん。」
「なに?」
「Uさんって、変だよね?」
「…そろそろお会計で宜しいですか?」
「ややや、そうゆうの!」
「ヘエ。」
「まじめに聞いて!」
「はい、聞きます。」
「いつも思うんだけど、お客さんのクレームになりそうな言葉に変わった返し?するよね?あれ、マニュアル対応してみたいのがあるの?」
「そんなもんない。」
「じゃあ、何?」
「テキトウ。」
「てきとー?」
「そう、てきとー。」
「てきとーで、あんな上手い返しができる…のか⁈」
「上手いかどうかは分からんけど、火に油を注がないようにはしてる。」
「ほー、じゃあ、例えば『コーヒーまだですか?』とか言われたら?」
「只今、お客さまのためにだけに焙煎している最中です、とか。」
「ほー、じゃあじゃあ、『ワイン頼んだんですけど、まだ?』は?」
「空輸されたばかりの樽から瓶詰めしているところです、とか。」
「ほわぁ、『ミルク来てないんですけど?』」
「裏の牧場に搾りに行かせてます。」
「天才か、天性の詐欺師!」
「…そろそろお会計で宜しいですか?」
「天才の方にします!」
「ヘエ。」
「あのね、Uさんの言葉って、飽きないの。あのね、なんかね、なんだろ?」
「頭、空っぽなんだよ、だから、何かの言葉が入れば風が吹いて言の葉が揺れるんじゃない?それを口にしてる感じ。」
「それ、お店の外でも聞きたい!」
「ん?」
「付き合って!」
「ん?」
「付き合って!」
「ん?」
「みんな見ているよ!」
「アリさんの声でお願いします。」
(あのね、付き合って、と言ってる。)
と、アリさんで声のめぐりが言う。
(どこへですか?、と聞いている。)
と、アリさんの声でわたしは返す。
「鈍感!」と、めぐり。
「大胆!」と、わたし。
「作戦を変える!」と、めぐり。
「対策を講じる!」と、わたし。
「喫茶店巡りに付き合って!」
「喫茶店巡り?」
「そう、わたしは色々な喫茶店巡って探ってるの。これはわたしにとって大事ことなの!」
「めぐりさんにとって大事なこと。」
「そう!」
「なにを探ってるんですか?」
「それは…企業秘密だよ。付き合ってくれたら教える!」
「別に知らなくて…」
下唇をきゅと甘噛みして、わたしをジロリと睨むめぐりの瞳は涙目になっている。数秒の沈黙。わたしが口を開く。
「オーケー、付き合う、付き合うよ。喫茶店巡り。」
「詐欺師の方じゃない?」
「じゃない。」
「信じるか。」
「信じなさい。」
「うん!」
めぐりの顔に、ぱぁと笑顔が広がる。アイドル顔のしかめ面からの笑顔、その衝撃エネルギーはチクシュルーブ・クレーターを彷彿とさせる。「これ、全人類の半分滅亡するやつやん」と心のなかで嘯くわたしは笑顔でめぐりに頷き返す。翌週から、めぐりに引き連れられて、都内の喫茶店をぐるぐるぐるりと巡る運びとなった。

喫茶店巡りをして分かったことが二つある。一つは、めぐりは割とまじめに喫茶店を研究しているということだ。初めての喫茶店に行く度にメニューや味を確かめることはもちろん、動線や内装などもチェックして、ノートに記している。見開き2ページで一店舗、しかも、味のあるイラスト付き。ふーむ。侮っていた自分を反省する。
もう一つは、めぐりは、もちもちした食べ物に目がないということ。街中を歩いている際、めぐりはあざとくもちもち食品を探知し、隙あらば、口にはむはむする。それが、また、彼女の持つ可愛さを危険なほどに増加させるのだ。さしずめ、もちもちかわゆさブースターと言ったところか。イコール、それは、行き交う男の視線を釘付けにすることになる。めぐりと街を歩くと、彼女だけでなく、隣に居るわたしも何人もの視線に晒されることになる。苦痛だ。わたしは、極力、目立ちたくない。できれば陰日向でひっそりしていたい。おいしい珈琲が飲めれば満足なのに…
人の気持ちも知らずに、もちもちをはむはむしながらめぐりは言う。
「Uって呼んでいい?」
「なんじゃ、いきなり。」
「そろそろ良いかなって。」
「別にいいけども。」
「U!」
「へい。」
「Uくん!」
「ん?」
「Uさん!」
「ふむ。」
「Uちゃん!」
「はひ。」
「Uたん♡」
「あぷぅ。」
「反射神経すご!」
「遊ぶなよ。」
「ねえ、U。」
「なに?」
「うん、やっぱ、Uがいい。」
「へいへい。」
「へいは一回!」
「キョーシか!」
「Uのあいぼーだよ。」
「へいへい。」
「わかれるよ!」
「成田離婚やん。」
「次、どこ行こう?」
「どこへでもお供しやす。」
「言ったね?」
「線路が続く範囲で。」
「引くも兵法よ。」
「むむ、おぬし、できるな。」
「空者とは、わたしのことよ。」
「…それ、使い方違うぜよ。」
「え?」
「え?」
「うそー。」
「ほんと。」
「やけ食いじゃあ。」
「自腹でどうぞ。」
知らぬ間に、わたしはめぐりと『都内の喫茶店を制覇する同盟』を組むことになっていた。これ、どいういう同盟だ、誰か教えてくれ。友達以上恋人未満なんて言われ方をする時代の関係性を象徴していた。いや、めぐりの気持ちには気づいていたが、わたしの気持ちが追いついていなかっただけなのかもしれない。

その日、わたしたちはオムレツを使ったバーガーが人気の喫茶店の調査に来ていた。無論、わたしはコーヒーのチェックに余念ない。真摯にa cup of coffee(ケインコスギで再生)と向き合っていた。茶の湯の心境。さあ、お点前拝見と心を鎮む。と、そこへ問答無用に押し入るめぐり。御用である!
「このポテト、ケチャップついてない!」
「これ塩味で十分、んまい。」
「味変が出来ないではないか!」
「おま、声でかいて。」
「だって、わたしはこの為に朝ごはん抜いて、万全のコンディションで来たのに…うぅ。」
「オムバーガーが今日のメインディッシュだろ?」
「でも、でも、味変も含めて、それではじめてこの店のポテンシャルがわかるの!」
「ポテトだけに?」
「こらぁー!わたし真剣だぞ!」
「さいません。」
「むー。」
「ときに、あきらめも肝心よ。」
「殺生なぁ…」
「おれは珈琲飲めればいいし。」
わたしをジロリと睨むめぐり。いちいち可愛いのが腹立つ。意地悪したくなるこの気持ちは、恋なのかねぇと独りごちる。店員や周囲の客の視線を感じる。めぐりは無自覚なのがいかん。女子大生の傍らで雑誌のモデルをしているらしいが、詳しいことは聞いたことがなかったが、もしかしたら、それなりに名前を知られていたのかもしれない。
「チューしてくれたらゆるす!」
「なぜ、そうなる?」
「してくれよーぅ。」
「できるか!」
「殺生なぁ…」
「おまいは、なにしに来とるだ?」
「Uは、わたしに興味ないの?」
「ポテトどこ行った?」
「それどころじゃない!」
「急展開やな。ドラマも終盤やん。」
「わたしたちの問題のが大事!」
「いつからおれらの問題になった?」
「わかってない!ぷんだ、ぷんだぞ!」
「なんだよ、急に。」
「Uは、ぜんっぜん、分かってない!」
「ま、まあ、いったん落ち着こね。」
「きょうは帰らない!」
「ん?」
「もうここで暮らす!毎日、ポテトと珈琲を飲んで、わたしは、ここで老いて行くんだ!ひ、と、り、さみしくね。」
「妄想族になってるぞ。」
「ふんだっ!」
「お店だって困るよ、みんな、家庭があるんだから。このままだと、警ら隊が出動して、確保されるよ?めぐり、故郷のお父さんお母さんが泣くよ?いいの?」
「良くないよ!」
「だろ?」
「うん…それはよくないよ…」
「そうそう。」
「…だから、Uがうちに来て。」
「ん?はなし飛んだ??」
「きょうは家まで送ってって、と言っているよ、わたし。」
「うーん。」
「Uは、この店に迷惑かけても平気なの?」
「おれが迷惑かけてんの⁈」
「故郷のお父さんとお母さんを泣かせてもいいの⁈」
「それは、めぐりの話でしょーが。」
「素直に送るか、この店に顔写真貼られて出禁になって法外な料金請求されても送らないか、どっち⁈」
「……送ります。」
「え、いいの?」
「え、送らない選択肢あり?」
「それは、なしだよ。」
「送る一択じゃんか。」
「嫌ならいいもん。」
「嫌…ではないよ。」
「いまは天才か詐欺師どっち?」
「天才の方で。」
「なら、わたしの気持ち、わかるはず!」
「わかる………よ。」
「直球でゆっても受け取ってくれないなら、こうするしかないんだもん!」
「うけとるよ。」
「え?」
「うけとるよ。ちゃんと。」
「ほんと⁈」
「ほんと。」
「ほんとのほんと⁈」
「ほんとのほんと。」
「ほんとのほんとのほんとの…⁈」
「ほんとだっつうのよ。」
「武士に二言はないな?」
「武士じゃないが二言はない。」
「記念日だ!」
「なんの?」
「恋人記念日に決まってるでしょーが!」
「父さん、北の国みたいになってますやん。」
「恋人だもん!」
「恋人かぁ。」
「恋人なるなる詐欺か⁈」
「詐欺ちゃうわ。」
「じゃあ、記念日!」
「パチパチパチパチ。」
「じゃあ、チューして。」
「振り出しに戻ってどーする!」
「してくれよーぅ。」
「…………あとでな。」
「きゃー。U、えちえちだ!」
「こいつ…してやらんぞ。」
「殺生なぁ…」
「我慢しろ。」
「…がまん、できるもん。」
「よしよし。」
店員とほかの来店客に見守られながら、最後はフラッシュモブよろしく総出のハッピーエンドの演出となる訳はなく、わたしたちは店を出た。外は日が落ち、宵の明星の横に一番星が寄り添っていた。もちもちに目が無いめぐりは家へと帰ると一本道の途中のコンビニで、白いぬくい中華まんをひとつ買った。
「はい、ほんぶんこ。」
「いっこ食えばいい。」
「はんぶんこがいいの!」
「なんでよ。」
「記念日だから。」
「だから、はんぶんこ?」
「Uと、はじめてのはんぶんこ。」
「まあ、そうだな。」
「これ、わすれないはんぶんこ。」
「うん、わかった。」
「もしね、もしもだよ?これは、地球が爆発するよりも可能性の低いもしもの話ね。」
「ほぼ、0パーセントじゃん。」
「うん、そう、ほぼ0パーセントのもしも。たけど、もしもね、わたしとUが恋人じゃなくなったとしてもね…このはんぶんこのことは忘れないでね………ぐすん…くぅん…」
言い終わるか終らないうちに、めぐりの瞳にはみるみる涙が溢れ、次々と頬を伝わり流れ落ちていく。両の鼻の下にも鼻水が垂れて、街灯の光を受けてきらきら輝いている。わたしは、お世辞にも可愛いと言えない不細工なめぐりの顔を見た瞬間、恋に落ちた。チクシュルーブ・クレーター級の小惑星が、わたしの心の海に衝突したのだ。いや、もしかしたら、鼻水が発動条件の恋の魔法にかけられていたのかもしれない(なんだ、それ)。鼻水垂らした泣き顔で恋に落ちるやつなど、後にも先にもわたしくらいなものだろう。わたしは、思わず、めぐりを腕の中へ引き寄せた。そして、強く、強く、抱きしめた。
「わわわ…」
と、驚きの声をあげながらもめぐりはしっかりとわたしの背中に手を回して、しがみ付いた。
「涙がついちゃうよ…」
「もれなく鼻水もついてくるやつ。」
「いじわるだ…」
「もれなくめぐりもついてくるだろ?」
「うん…」
「じゃあ、かまわん。」
「ねえ、U…」
「ん?」
「…チューして。」
「また言ってる。」
「…だめ?」
「家帰ったらな。」
「してくれる?」
「ん。」
「何回してくれる?」
「何回でも。」
「ずっと我慢したんだから100回じゃ足りないよ。」
「100回でも200回でもしてやる。」
「詐欺師じゃない?」
「じゃない。」
「ねえ、U。」
「ん?」
「はやく帰ろっ!」
めぐりはわたしの手を引き、走りだす。涙と鼻水をわたしの服で拭った太々しいめぐりは、きっと、今、東京中で一番眩しいに違いないし、たぶん、世界中で一番可愛いに違いない、そんなこと思わずにいられないほどの最高の笑顔を見せていた。
めぐりの手がわたしの手を握る。
わたしはめぐりの手を握り返す。
しっかりと、決して、離れないように。
たとえ、今、地球が爆発するほどの爆風に見舞われても離れないくらいに、しっかりと。
ただの天体に過ぎない星々だが、運命のような星めぐりはあるのだ。わたしとめぐりは、数多な星と喫茶店が存在する星雲の中で再接近し、互いの軌道をぐるりとめぐることになった。
こうして、わたしは、めぐりにぐるりとお持ち帰られた。
その後、ふたりが何回キスをしたかは、ご想像にお任せすることにする。ただし、翌朝、もちもちだっためぐりの唇は、乾燥地帯の大地のように見事なカサカサ地帯となっていたことを付け加えておく。
ーおしまいー
お持ち帰られ喫茶店❼|めぐみとめぐり、ぐるりとめぐる。


