
追憶の防波堤
右手首だけを掴まれて、私の身体は防波堤から投げ出されている。
「…お願いやめて。」
恐怖と怒りの度合いを示す針はもう振り切れて、壊れていた。必死に絞り出した言葉も波の音に消されていく。無抵抗な私を…というか、抵抗してもどうにもならないことを悟って抵抗するのをやめただけの私を、右手首だけで繋ぎ止めて薄ら笑っているこの男は、一体私をどうしたいというのだろうか。朦朧とした頭でぼんやりと考えていた。
高校に入学して同じクラスになった彼は、とても明るくて話しやすい人という印象で、人見知りの激しい私でもすぐに打ち解けて仲良くなることができた。一学期が終わる頃、付き合って欲しいと言われたけど、その時は、正直そういう気持ちにはなれなかった。しかしその後も彼は、顔を合わせる度に好きだ好きだと言って私の側を離れなかった。そのうちなんだか、自分も彼のことが好きなのではないか?という感覚に陥り、きっと彼は一途でいい人だから…と自分で自分を錯覚させてしまった。そして彼を受け入れた。それが悪夢の始まり。その結果がこれ。このありさま。深く考えもせず受け入れた私が悪いのだけど。こんなことをする彼の意図がまったくわからなかった。
初めて暴力をふるわれた日。
別れたいと言ったら殴られた。一度殴ると、それは当たり前のように繰り返される。
「今度、別れたいとか言ったら殺すからな。」
そう言って顔を殴られ、お腹のあたりを蹴られた。何度も。それでも気がすまない彼は、自分の拳で壁や地面を殴った。彼の拳は痛みと怒りで震えている。第二関節のあたりには血が滲んでいた。そして最後は、汚い言葉で私を罵った。私はうずくまり耳を塞ぐ。頭のてっぺんから浴びせられる暴言を聞くのは暴力よりも苦痛だった。身体の痛みはほとんど感じなくなっていたけど、紺色のブレザーには、くっきりと彼の靴の跡が残っていて、私はぼんやりと絶望の淵を彷徨っていた。
付き合ってすぐに激しい束縛が始まった。他の男としゃべるな。目を合わせるな。毎日電話しろ。手紙を書け。学校にいる間、私はずっと監視されている状態だった。彼はいつも睨みつけるように私を見ていて。束縛はどんどんエスカレートしていき、女友達ともしゃべってはいけない。遊んでもいけない。仲良くしていた友達も、静かに離れていった。私の心は、ざりざりと削られていく。
早く別れたかった。普通の学校生活を取り戻すために。別れることがこんなにも難しいことだったなんて。どうしたら終わらせることができるのか、どうしたら彼と離れられるのか、その手段が見つからなかった。どうすることもできなかった。
_ そして私は今、誰もいない防波堤で制服のまま宙に浮いている。小柄な私は、彼にとってただのおもちゃの人形だった。いとも簡単に宙吊りにされてしまうのだから。懲りずに別れたいと口にする私を許せないらしい。もうどうでもよかった。今、私が必死にしがみついている左手を放してしまえば、このまま落下して、数メートル下に見える消波ブロックに頭か顔を強打して血だらけになって意識を失うかもしれない。そうすればもう、彼とは離れられるだろう。きっと。
だんだんと視界が歪んでいく。空が今、何色なのかさえもわからない。もうどうでもよかった。とにかく楽になりたかった。私は目を閉じ、全身の力を抜いて、ふわりと落下していく自分の姿を想像した。
しかしその瞬間、信じられないほどの強い力で手首を引っ張られた。
「てめぇ、ふざけんなよ。死にたいのか?俺が手放したら死ぬよ?もっと耐えろよ。」
そう叫ぶ彼の声は、小刻みに震えながら笑っている。そうか、この人は私を虐めて楽しんでいるのだ。そしてそれを愛だと勘違いしている。私の右手首はもう捻じ切れてしまいそうだった。
一体私が何をしたと言うのだろう。
私はもう何も考えることができなかった。魂さえもどこかへ逃げてしまって、私の中身は空っぽだった。力を失った私は、怒り狂った男に引きずられるように防波堤を歩き、バス通りまで出てから、小さなバス待合所に放り込まれた。もうあたりは暗くなっていて、行き交う車のヘッドライトが充血した目にジリジリと染みて痛い。帰り際、彼は乱暴に唇を押しつけてきたが、私は歯を食いしばって抵抗する。彼は、暴力を振るった後には必ず、愛していると囁くのだ。その度に私は、激しい吐き気に襲われた。
「まっすぐ帰れよ。夜、電話するからな。」
そう言い残して彼は去っていった。
私はバスに乗り、一番後ろの空いている席に鉛のような身体を沈める。手首がズキズキと痛む。窓の外は暗闇だった。ボロボロに千切れた夜があちらこちらに落ちている。私はそれをぼんやり数えていた。月の姿はどこにも見当たらない。遠くには私が落ちて血に染めるはずだった消波ブロックが並んでいて、ずっしりと鎮座するその姿は、力強く私を見つめ返しているようだった。
「自分が変わらなければ、何も変わらない。」
あの大きな塊に、そう言われているような気がして、悔しくて、情けなくて、涙が止まらなかった。私は何度も自分の中で、彼を殺した。呪い殺せるものならと。でもそう思えば思うほど、彼の暴力は激しくなっていった。
_ とうとう私は、限界の日を迎えた。人は結局ひとりでは生きてはいけないことを知る。だれかを頼り、だれかに助けてもらわなければ生きてなどいけない。まして私はなんの力もない子供だったから。
私は担任に理由も言わず、学校を辞めたいと申し出た。私の家族は崩壊していて、両親とは一緒に暮らしていなかったから、当時預けられていた叔父と叔母にすべてを話した。叔父に、なんで今まで黙っていたんだと怒鳴られた。でも、もっと早く言っていたら、もっと違う未来があったのだろうか。私はただただ、ごめんなさいと謝り続けるしかなかった。とにかくもう学校へは行けないと。
私は一週間ほど学校を休み、その間に彼の両親と私の叔父と叔母、担任とで話し合いが設けられたが、彼側は一切暴力を認めなかったという。私が単に彼と別れたくて嘘をついているのだと。しかし、私は気づいていた。彼の母親は、私が彼から暴力を受けていることを知っていたのだ。何度もその現場を見ているのだから。それなのに。
いつか彼自身が言っていた。親父も母親を殴っていると。そしてそれは愛情なのだと。
そんなことも、もうどうでもよかった。彼も、彼の家族も、そして私自身もどうかしている。何もかもどうでもいいから、とにかく彼とはもう二度と関わりたくないとそれだけを訴えた。
自主退学は受理されず、私は卒業まで彼と同じ学校に通い続けることになったが、別れることはできた。卒業まで、彼とは一言も話さず、目も合わせることもなく、ただそこに在る日々を淡々と過ごした。まるで私達の間には何もなかったかのように。
「ツキノ…ごめんね。助けてあげられなくて。苦しんでるの見てたのに、アイツに睨まれるのが怖くて何もできなかった。ほんとにごめん…」
そう言って、ミオリは崩れるように私の前に座り込んだ。ちらちらと様子を伺っていたクラスの子達が集まってくる。
「大丈夫だよ、気にしないで。私だって逆の立場だったら何もできないよ。またこうして友達に戻ってくれるだけで…嬉しいよ。」
そう言って微笑むと、ミオリは教室の真ん中で声をあげて泣いた。私は何度も「泣かないで」と繰り返しながら、上下するミオリの背中を撫で続けていた。しかし心の中では、どうして助けてくれなかったの?というドロドロとした気持ちが氾濫していた。心から人を信頼するという気持ちは、その時にすべて失ったような気がしている。
その後の高校生活は平穏に過ぎていった。
_ 昨年、祖母が旅立ち、十八年ぶりに帰省した。そしてあの防波堤の近くを通りかかったが、不思議なことに、あの時、確かにそこにあったはずの防波堤がどこにも見当たらない。この場所ではなかったのだろうか。記憶は曖昧だった。でもあんな巨大なものが消えてしまうことなんてありえない。それともあれは悪夢だったのか。そんなはずはないと思いながら、あったはずの景色を思い浮かべた。もしかしたらあの日の私は、この世界から切り取られてしまったのかもしれない。どうせ消えるなら、この記憶ごと海の底に沈んでしまえばよかったのに。
それでも私は、生きている。
今日も私を、生きようとしている。
すべて自分で選んできた人生だから。
あの日、失いかけた命を守ることができた自分を褒めてあげたい。満ち足りた絶望の中で、生きている神秘を味わっている。
追憶のような潮風が通り過ぎていく。一瞬、右手首がズキンと疼いたような気がした。
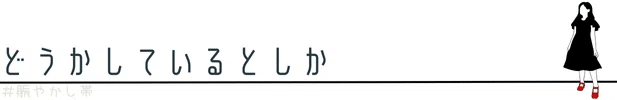
思い切って出してみました。
記憶の整理、心の断捨離です。年末だしね。
