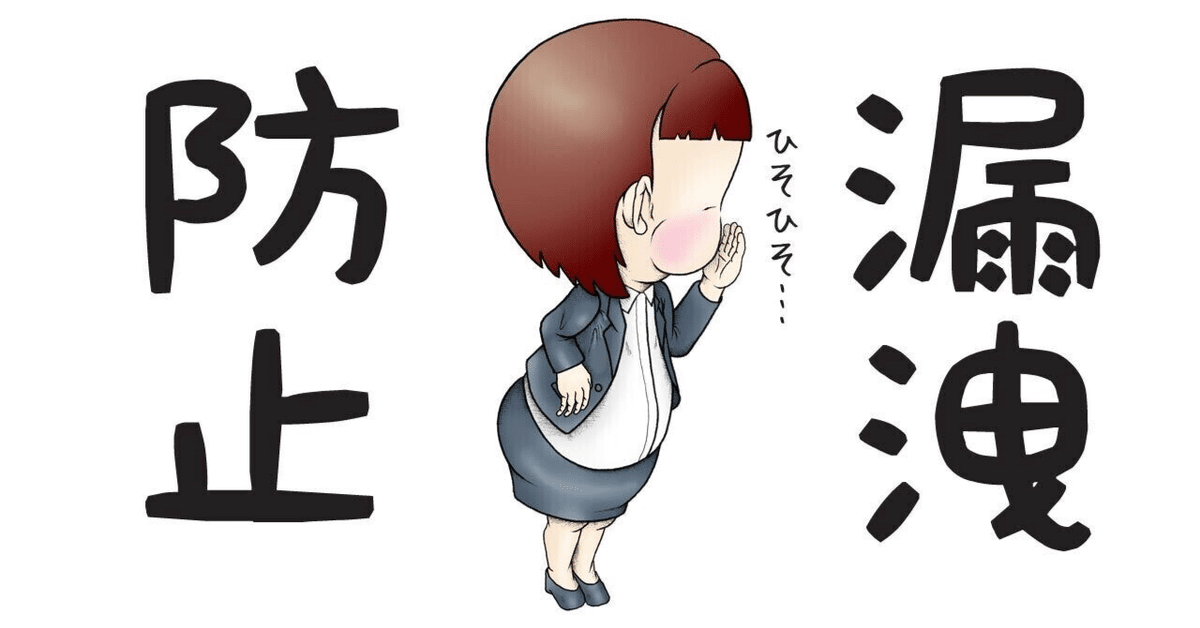
政治(特許・商標)講座ⅴ1115「また、中国のパクリ?」
ペロブスカイト太陽電池は日本人研究者が開発した。
似たような曲げられる中国が開発したとされる太陽電池の報道があった。最初、パクリかな?と思ったが、やはり、似て非なるものである。発電効率など性能では日本に軍配が下る。今回は以前掲載した記事を比較の為に掲載し中国の開発技術と比べられたい。
翻って、日本酒の詳しいひとなら「南部美人」という日本酒をご存じであろう。この「南部美人」を中国では先に商標登録しているので中国の不正商標登録の取消の訴えを粘り強く交渉し,不正登録を取消してもらった事例もある。漢字文化圏であるから容易く起こり得ることであり、中国の商標登録に関して、十分に注意して監視していないと、被害にあう場合も起こり得る。
皇紀2683年5月28日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
紙のように曲げられる太陽電池を中国が開発―中国メディア
Record China によるストーリー • 3 時間前

超薄型で曲げることができる太陽電池がこのほど出来上がった。中国の科学研究者はエッジスムージング処理技術を開発し、同技術をベースに研究開発されたフレキシブル単結晶シリコン太陽電池は紙のように薄く、厚さは60マイクロメートルとなっている。しかも紙のように曲げたり、折りたたんだりすることができる。この太陽電池に関連する研究成果は24日に「ネイチャー」にオンライン掲載され、巻頭記事を飾った。科技日報が伝えた。
単結晶シリコン太陽電池は現在、主に分散型太陽光発電所と地上太陽光発電所に用いられている。これを曲げることができるフレキシブル太陽電池にすれば、建築物やバックパック、テント、自動車、帆船、さらには航空機にまで広く応用することができるようになり、家屋や各種携帯型電子製品および通信設備、交通機関などに軽くて便利なクリーンエネルギーを提供できるようになる。

論文の共同連絡著者で、中国科学院ミクロシステム・情報技術研究所の劉正新研究員は、「今回の研究はシンプルな製法処理によりフレキシブル単結晶シリコン太陽電池の製造を実現するとともに、量産化ラインで量産化の実現性を検証し、軽量でフレキシブルな単結晶シリコン太陽電池の発展に実行可能な技術的な道筋を提供している。同時に研究チームが開発した大面積フレキシブル太陽電池モジュールはすでに近宇宙飛行機、建築物・太陽光発電一体化、車載太陽光発電などの分野で導入されている」としている。(提供/人民網日本語版・編集/YF)
薄くて軽い、次世代太陽電池 下水処理施設で国内最大規模の実証実験
朝日新聞社 によるストーリー • 1 時間前

下水処理槽の蓋の上に置かれたペロブスカイト太陽電池(手前)と、式典に出席した小池百合子・東京都知事(左端)=2023年5月24日午前11時13分、東京都大田区、太田原奈都乃撮影© 朝日新聞社
軽量で生産コストも安い次世代太陽電池の実用化に向けた国内最大規模の実証実験が、東京都内の下水処理施設で始まった。都と、開発した積水化学工業による共同研究。2025年12月まで発電効率や耐久性を調べる。
実験するのはフィルム型の「ペロブスカイト太陽電池」。重さは現在主流のシリコン型太陽電池の10分の1ほどで、薄く、曲げることもできる。ビルの壁や工場の屋根、柱の側面などにも設置でき、弱い光でも発電する。
実験では、森ケ崎水再生センター(大田区)内にある下水処理槽のふたの上に、大きさの異なる電池3枚(計約9平方メートル、出力計約1キロワット)を置いた。これまでの実験にない大きさで、下水処理施設への設置も国内初という。都によると、置き場所を確保しやすい同センターで、下水から発生する硫化水素や海風に対する耐久性も調べるという。
ペロブスカイト太陽電池は、国も開発を後押ししており、岸田文雄首相は4月、当初の目標だった30年を待たずに実用化を目指すという方針を打ち出した。
24日にあった実験の開始式で、小池百合子知事は「エネルギー情勢が厳しく、気候変動で脱炭素などの課題がある中、このイノベーションが日本の技術として羽ばたく手伝いをしたい」と話した。(太田原奈都乃)
ペロブスカイト太陽電池 実用化への道!薄くて軽くて雨でも発電!?
NHK 2022年9月20日 午後2:00 公開
人類が直面しているエネルギー問題を解決し、脱炭素社会を実現するため、再生可能エネルギーの活用が加速しています。その中で大きな期待を集める「太陽電池」ですが、従来型の太陽電池は、発電効率が天候に大きく左右され、曇りや雨の日だと発電量が大幅に落ちるという弱点がありました。その弱点を克服しようと、今、世界中が「次世代型太陽電池」の開発に注力しています。
その中で、最も注目されているのが、「ペロブスカイト太陽電池」です。曇りや雨の日、さらに室内の弱い光でも発電することができることに加え、薄くて軽いため様々な場所に設置することが可能で、世界中の企業が実用化に向けた開発にしのぎを削っています。
実は、このペロブスカイト太陽電池は日本人研究者が開発したもので、そのきっかけは学生からの相談という意外なものでした。“ノーベル賞候補”とも言われるほどの画期的な太陽電池の開発秘話と可能性に迫ります。
世界が注目! ペロブスカイト太陽電池の実力
地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを全て電気に変換できれば、世界中で使うエネルギーをまかなえるほどのポテンシャルがある「太陽光発電」ですが、現在の主流となっている「シリコン」を用いた太陽電池は、寿命が長くて、発電効率が高いという利点がある一方、天候によって発電効率が大幅に落ちるという弱点を抱えていました。
その弱点を克服しようと開発が進められているのが「次世代型太陽電池」です。その市場規模は、2035年には現在の10倍以上、年間8,300億円にまで成長すると予測されています。そして、その大部分を占めると考えられているのが「ペロブスカイト」を用いた太陽電池です。
ペロブスカイトというのは、もともと自然界にある鉱石です。その結晶構造に特徴があり、利用価値が高いため、人工的に作ったものが超電導やLEDの材料などに使われています。
この人工的に作ったペロブスカイトの結晶を太陽電池の素材に使うと、曇りや雨の日、さらに室内の照明でも発電できることが発見され、次世代型太陽電池の最有力候補となったのです。そして、弱い光での発電を実現させているのが、ペロブスカイト太陽電池のもう一つの特徴である“薄さ”です。
「薄さ」のおかげで曇りでも発電可能
太陽電池は、材料に半導体が使われています。半導体は光を吸収すると、電子(マイナスの電荷を帯びている)と正孔(プラスの電荷を帯びている)がセットで生まれ、それらが別々の電極に移動していくことで電流が流れて発電する、という仕組みです。このとき、電子や正孔の移動距離が長ければ長いほど、それらが電極まで到達できずに損失となります。
従来型のシリコンの場合、太陽電池パネルを薄くすることに限界があるため、光を吸収して生じた電子や正孔が電極まで非常に長い距離を移動しなければなりません。強い太陽光が当たっていると問題なく発電できますが、曇りなどで光が弱くなると、生じる電子や正孔が少なくなるため、影響が大きくなります。
一方、ペロブスカイト太陽電池は光を吸収する力が強く、非常に薄い0.1マイクロメートルでも電池として使えるため、電子や正孔の移動距離が短く、ロスがほとんどなく電極に到達できます。そのため、太陽光の500分の1程度の強さの光である室内の照明でも発電ができるのです。
また、ペロブスカイト太陽電池が非常に薄いことは、弱い光で発電できること以外にも大きなメリットがあります。フィルム状の曲げられる太陽電池も作ることができるため、様々な場所に使うことができるのです。
自動車メーカーでは車体に貼り付けてソーラーバッテリーに使うアイデアや、家電メーカーでは室内のIoT機器の電源に使うというアイデア、建築分野では建物全体に貼り付けて発電するアイデアが提案されるなど、様々な業界でペロブスカイト太陽電池を使う構想が練られています。
開発のきっかけとなった“学生の声”
この画期的な太陽電池の生みの親は、桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授です。宮坂さんがペロブスカイトと出会ったのは、今から17年前のことでした。当時、ペロブスカイトは超電導やLEDの材料などには使われていましたが、太陽電池の世界ではほとんど知られていませんでした。
「開発する前はペロブスカイトという物質に私はあまりなじみがありませんでしたが、私の研究室に来た大学院生が突然『ペロブスカイトによる太陽電池をやってみたい』と言いだしたのです」(宮坂さん)
当時、大学院生だった小島陽広さんは、もともとペロブスカイトの特性を調べる研究をしていましたが、その光を吸収する性質に注目し、もしかしたら光を電気に変える性質を持っているのではないかと考え、宮坂さんに相談を持ちかけたのです。
「私は基本的には学生がやりたいと言ったことは『まずは試してみるべき』という考えでしたので、軽い気持ちで『じゃあ、やってみたら』と言いました。しばらく実験をした後、小島さんから『光を当ててみたら微弱な電流が生じた』という報告を受けたのです」(宮坂さん)
それまで太陽電池の素材としては注目されていなかったペロブスカイトが、発電すると分かった瞬間でした。しかし、いざ本格的に太陽電池の研究開発に着手したところ、すぐに大きな壁にぶつかったといいます。
「本腰を入れて太陽電池を作ったのですが、なんせ安定性が悪く、しばらく光を当てると発電しなくなるんです。しかも効率も低くて、正直、これはダメかなと思っていました」(宮坂さん)
実際、2009年に発表した論文は、光を電気に変える効率(光電変換効率)が低いために、世界の研究者からの反応はほとんどありませんでした。
転機が訪れたのは2012年のことでした。ペロブスカイト太陽電池に関心を持った海外の研究者が、「発生した電気を電極に運ぶ部分を液体から固体に変える」という研究を始めたのです。これにより光電変換効率を3%から10%を超えるレベルにまで上げることに成功しました。その成果を『サイエンス』誌に発表したところ、世界中の研究者の目に留まり、ペロブスカイト太陽電池は一気に注目される存在となったのです。
そして、世界中で研究が重ねられた結果、変換効率は飛躍的に向上し、従来の太陽電池に匹敵する25%を超えるまでになったのです。今や世界中で推定3万人ほどの研究者がペロブスカイト太陽電池の研究開発に参入し、実用化に向けた開発競争が激化しています。
宮坂さんは、ペロブスカイト太陽電池がこれほど世界から注目される存在になったことに驚きながら、こう振り返ります。
「ペロブスカイトは化学と物理という異分野が交わっているテーマです。私たちは化学が専門ですが、物理にも手を出す。不得意でも試してみるというチャレンジ精神が非常に大切だと思ったからです。難しいとは思っていましたが、誰もやっていなかったことだからこそ、チャレンジしがいがあると思ってやりました。やってみてよかったですね」(宮坂さん)
実用化に向けた開発競争の今
宮坂さんは、ペロブスカイト太陽電池は“実用化の入り口”に入ったと考えていますが、実用化のためには大きな課題が残っています。それは「大型化」と「耐久性」です。
日本のある化学メーカーでは、2025年までに実用化することを見据え、大型化を実現しようと研究開発を急ピッチで進めています。大型化が難しいのは、安定して高い効率で発電するために、太陽電池の面に均一にペロブスカイトの結晶を並べる必要があるからです。面積が小さい場合は均一に並べることができても、面積が大きくなるにつれ結晶にばらつきが発生し、効率が落ちてしまうのです。
このメーカーでは均一に作る技術を磨き、30センチ角であれば結晶のばらつきを抑えて十分に高い効率で発電できる太陽電池を作る方法を確立しました。そして、これを組み合わせることで1メートル角以上の大型の電池の実用化を進めようと考えています。
また、ペロブスカイト太陽電池は、物質としての安定性が低く、劣化が早いため耐久性に課題がありました。この課題を解決する方法として、このメーカーでは、耐久性が高いシリコンの太陽電池にペロブスカイト太陽電池を重ねるという「タンデム型」の太陽電池の開発も行っています。
このタンデム型にはもう一つ大きなメリットがあります。ペロブスカイトとシリコンとでは、それぞれ吸収する光の波長帯が異なるため、二つを組み合わせることで、より広い範囲の波長の光を無駄なく使え、変換効率を高めることができるのです。
このメーカーでは、タンデム型はバルコニーや壁面に設置し、ペロブスカイト太陽電池は透明タイプで窓ガラスに貼り付けるなどして、太陽電池を建物のさまざまな場所に張り巡らせたいと考え、開発を続けています。
宮坂さんは、シリコンとペロブスカイトの太陽電池がこれから共存していく将来を考えています。
「晴れた日にはシリコンを使って、曇った日はペロブスカイトが補助する。また、シリコンが使えない窓や壁などはペロブスカイトを使っていくと。両方が共存していくことで、総エネルギー量を高めていくというのが今後の方向性だと思います。実用化される未来はそんなに遠くないと思います。場合によっては、数年先には商品化が始まると思っています」(宮坂さん)
一人の大学院生のアイデアとそれを尊重する宮坂さんのチャレンジ精神によって誕生した次世代型太陽電池が、実用化への課題を克服し、地球のエネルギー問題を救う日が来るかもしれません。日本生まれの画期的な新技術の今後に期待が高まります。
薄くて軽くて曲がるフィルム型の次世代太陽電池 都と企業が実証実験を開始
ABEMA TIMES によるストーリー • 昨日 18:42

東京都は、積水化学工業と共同でフィルム型の次世代太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」の実証実験を始めました。
ペロブスカイト太陽電池は日本で開発された技術で、従来のシリコン製の太陽電池と比べて重さは約10分の1と軽く、薄さは1mm程度です。また、柔軟性があり湾曲した場所にも設置が可能です。
都はより過酷な環境下での耐久性を調べるため、潮風やガスなどの影響を受ける下水道施設での実験を決めました。視察した小池都知事は、新たな再生可能エネルギーに期待を寄せました。
「薄くて軽くて曲がるという利点を有効に活用する。また原材料が我が国が世界の3割を占めるヨウ素を活用する点でも、有効なツールになっていく」(小池都知事)
実験は2025年12月までで、実用化に向けてさまざまな実験を行うとしています。(ANNニュース)
中国、日本企業と酷似の会社罰金 社名やロゴ「違法」
共同通信社 によるストーリー • 昨日 19:15

【上海共同】業務用厨房機器大手ホシザキ(愛知県豊明市)と酷似した企業名やマークを使って製氷機を販売し、中国の商標法や反不正競争法に違反したとして、江蘇省南通市当局が市内の中国企業に約11万5千元(約230万円)の罰金を科したことが27日、関係者への取材で分かった。
日本企業の訴えに応じ、知的財産権侵害への対応強化をアピールした形。中国は商標権侵害のほか、偽ブランド品や海外コンテンツの海賊版サイトが横行し、知財権保護の対策が甘いと非難されてきた。
処罰されたのは2020年に設立した「星崎冷熱科技(南通)有限公司」。1998年に中国に進出したホシザキとは無関係だ。南通市海門区市場監督管理局が出した今年2月8日付の行政処罰決定書は、企業名が似ていることについて「ホシザキと混同させる目的」と認定した。
冷熱科技はホシザキが中国で商標登録した「HOSHIZAKI」と似た「HOSYINGKI」のロゴやペンギンの絵柄を、別会社を通じて商標登録。正当に登録したことを示す「Rマーク」も付けていた。
中国 海外の商標保護強化 不正登録 取消しやすく
「・・・10年前,中国向けに酒の輸出をはじめたとき全く関係の無い個人が商標登録をしていたことが判明。当初は,中国当局に取消を求めて申立てたが,棄却された。14年に中国企業が少なくとも3年間商標を全く使わなかったことを理由に改めて申立て,当局に認めてもらった。・・・不正な商標登録であれ,同じ商標を使うとトラブルになりかねない。中国の商標局のサイトでは現地の商標登録の状況などを確認することができるため,・・・日本貿易振興機構(ジェトロ)は日本企業にチェックの徹底を呼びかけている。・・・酒造会社「南部美人」の久慈浩介社長(45)は『同じ商品名の日本酒を海外で勝手に販売されるとブランドに傷が付く。粘り強く権利を訴えることが大事だ』と強調する。」読売新聞2017/11/19(日曜日)より一部抜粋。
私の好きな日本酒の「中国の商標登録」 | Orange Law Office Blog Ò オレンジ法律事務所
参考文献・参考資料
紙のように曲げられる太陽電池を中国が開発―中国メディア (msn.com)
政治(産業)講座ⅴ1107「物資は有限、知恵は無限」|tsukasa_tamura (note.com)
ペロブスカイト太陽電池 実用化への道!薄くて軽くて雨でも発電!? - サイエンスZERO - NHK
薄くて軽くて曲がるフィルム型の次世代太陽電池 都と企業が実証実験を開始 (msn.com)
薄くて軽い、次世代太陽電池 下水処理施設で国内最大規模の実証実験 (msn.com)
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

