
タイピングからタイポグラフィへ
書き手がWordにタイピングしたテキストを「すっぴん」の状態と捉える。「すっぴん」のテキストはそのままでは見るに耐えないので、デザイナーがそれをIllustratorのテキストボックスに流し込み、書体、文字サイズ、行間、その他あらゆる設定を決め、紙面に配置することで美しく仕上げる。これがタイポグラフィという行為の一般的なイメージである。
このイメージに疑問を呈するのが本記事の趣旨であるということをあらかじめ伝えたうえで、まずはタイピングからタイポグラフィへと至る事例をいくつか紹介したい。
流し込むのではなく組む
ブックデザイナーとして知られる鈴木一誌さんの著書、『ページと力―手わざ、そしてデジタル・デザイン』にこんな図版が掲載されている。
図版のそばには「タイトルを組むのにこれだけの手間がかかる」というキャプションが添えられており、20字の短いコピーに施されたいくつものデザイン処理が解説される。この図版から読み取れるのは、テキストを単純に「流し込む」ことと、「組む」ことの間にある美意識の差。

❶ヒラギノ角ゴシック体1のカギかっこを使用。
❷見出しの1文字目なので1pt大きくした。
❸左右幅を90%に変形。
❹24ptヒラギノ角ゴシック体8を使用。
❺ヒラギノ角ゴシック体3を使用。
❻改行の位置に注意。
❼カナ同士なので行間を4ptせまくした。
❽あたま揃えにした。スペースを入れてマイナスのカーニングを入れた。
❾44pt FrutigerBoldを使用し、マイナス2ptのベースラインシフトをかけた。
➓文節の切れ目なので、ほかよりも10em分字間をあけた。
⓫50pt Bodoni Bookを使用し、マイナス2ptのベースラインシフトをかけた。
⓬見かけの頭揃えを実施する。
⓭いわゆるよりひき。1pt下げた。
⓮ルビを7ptヒラギノ角ゴシック体3を使用し別のボックスで入れた。
(『ページと力―手わざ、そしてデジタル・デザイン』より引用)
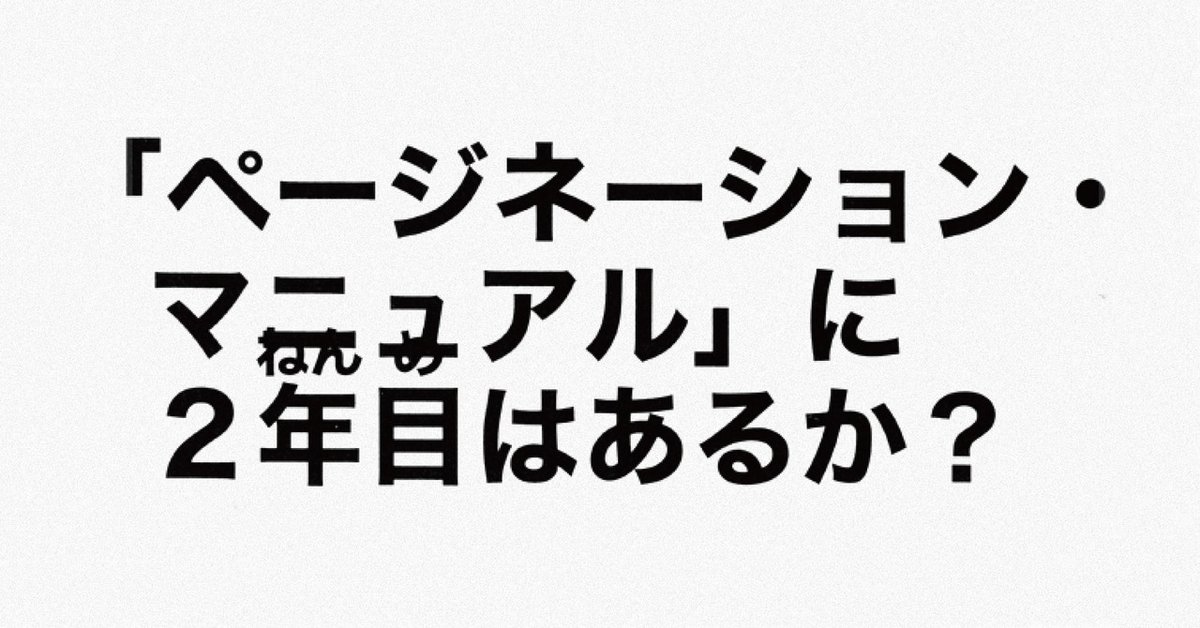
手間をかけないとこうなる可能性がある(『ページと力―手わざ、そしてデジタル・デザイン』より引用)
今時ここまで調整する変態的なデザイナーはあまりいない。というのも、このようなテクニックは元々、手動写植のプロによるもの。写植の時代を通過してきた鈴木さんだからこそ、グラフィックデザイナーがレイアウトから組版までこなすDTPの環境においてもここまでやるのだろう。ただ、平成生まれ、デジタルネイティブな私の目から見ても、文字を大きく扱う場合にデフォルトの音引きって長すぎるし、拗促音や中黒は大きすぎると感じる。それにほとんどの和文書体の従属欧文は、野暮ったい。印刷技術が変わっても受け継がれる普遍的な文字の美意識は尊い。
鈴木さんは前述した著書の巻末に収録している「ページネーションのための基本マニュアル」のPDFを無償で公開している。これは本を編集するためのあらゆる知識が集約された文書で、デザイナーのみならず、デザイナーと組んで仕事をする人なら一度読んでも損はない。そのなかから、書くこととデザインすることの関係性について書かれた一節を抜粋する。
これまで、編集者によるブラックボックス的な作業であった原稿整理にまで言及した。編集者がデザイン的センスを、デザイナーが編集的センスをもたなければならない時代だろう。編集とデザインの境界線を滲ませようともくろんだ。(『[新版]ページネーションのための基本マニュアル』より引用)
書き手がデザインに干渉するのはあたりまえのことだが、美しさと読みやすさを追求するにはデザイナーがテキストに干渉することも、もっとあっていいはずだ。私たちはデザインすることと書くことを切り離しすぎてはいなかったか。
「書く脳」と「デザインする脳」
日本デザインセンターが2017年にリリースしたテキスト編集アプリ「stone」は、文字が入力されると同時に組版におけるさまざまな処理を自動でおこなう。たとえば、stoneにおいて行中の句読点の後は基本的に二分のアキが挿入されるのだが、行末になるとアキなしとなる(Wordの場合一律で二分アキ)。また、いかなる状況においても句読点をぶら下げない。つまりstoneの組版設定は、テキストボックスの両端をピッタリ揃えようとする方針のもとに設計されている。
これが本文組の唯一の答えというわけではない。行末の句読点の後に二分のアキを挿入したり、ぶら下げることで、ベタ組みをできるだけキープする、つまり行ごとの濃度をできるだけ均一にするという方針の組み方もある。

stoneの組版はテキストボックスの両端がきれいに揃う。その代わり、赤いマークの行の字間が他の行と比べて詰まったり、あいたりしてしまっている。

ガイドを入れた。左の組版ではベタ組が完璧にキープされていることがわかる。つまりどの行も濃度がほぼ均一に保たれている。
通常、テキストの内容によって適切な組版は決定される。そして、耳をすませなければ聞こえてこないようなノイズさえも消し去ることをめざして、デザイナーは頭を悩ませる。
そんなわけで、私が以前stoneを用いて執筆を試みたとき、テキストを入力すると同時に行われる処理を見ていて「書く脳」と「デザインする脳」が交錯し、ショートしてしまった。書くことに不慣れな私の場合、執筆しながら組版のことまで考える余裕がない。
京極夏彦さんの追求
京極夏彦さんの書く小説は、ページや見開きの終わりで文章が必ず終わるようになっている。つまり、文章がページやノドをまたがない。本記事を書くにあたり、『豆腐小僧双六道中ふりだし』を購入したのだが、とにかく読みやすい。見た目にも美しい。小説の見開きをここに載せるわけにもいかないので、ぜひ実物を手にとって読んでみてほしい。

購入した2冊。出版社も、担当デザイナーも、判型も、書体も、文字サイズも、行間もまったく違うけれど、京極式組版ルールは共通している。
これはデザイン上の処理だけで実現できることではない。京極さんは、原稿を執筆する時点で文字数を調整しながら書いているのだ。
さらに驚くべきは、文庫版でもノベルスと同様にページや見開きの終わりで文章が必ず終わるということ。文庫とノベルスでは判型も文字サイズも、版面の形も違う。信じがたいことだが、文庫版でも組版の質を保つために原稿を調整しているという。
下に実際の文章を引用する。言い回しや読点の使い方を変えることで、文字数を調整しているのがわかる。
世間様のレヴェルの方が下がっちまったのじゃあないかと思われるようなことも多々ございますですな。(ノベルス版)
世間様のレヴェルの方が下がっちまったのじゃあないのかいと思われるようなことも、多々ございますですな。(文庫版)
これ以外にも、作品によって漢字とかなの割合を意識的に変えたり(そうすることで対象年齢だけでなく、版面の見た目も変わる)、ルビの振り方についての独自のルール「京極ルビ基準」を定めるなど、読みやすさを追求するための工夫は挙げだすとキリがない。
元々グラフィックデザイナーであった京極夏彦さんにとって、書くことと組むことは一体なのだ。
「書く」と「組む」が融けあう
書き手とデザイナーが分業する通常のワークフローにおいて、ここまでの精度を求めるのは難しい。雑誌のライターが書いた文章ならまだしも、作家の文章をデザインのためにリライトすることなどありえない。だから、冒頭で述べたように支給されたテキストに化粧を施すのがデザインだと思われてしまう。
けれど、形と内容が相互に影響しあい化学反応を起こす瞬間を、私たちは幾度となく目の当たりにしてきたはず。書くことと組むことを切り分けるのではなく、両者を融けあわせることができないだろうか。その先に、豊かな読書体験があると信じて。
twitterにて更新のお知らせをしておりますので、よかったらフォローお願いします! https://twitter.com/tsugumiarai
