
【まとめ】NHKスペシャル 東洋医学を"科学"する 〜鍼灸(しんきゅう)・漢方薬の新たな世界〜を鍼灸学生の視点で綴ります。
先日、NHKにて東洋医学についての番組があり、クラス内でもにわかに盛り上がっていました(特に先生)。見逃した方も多かったようなので、ざっくりとではありますが内容をシェアさせていただきます。
鍼灸や漢方薬など「東洋医学」のメカニズムの科学的解明が進んでいる。東洋医学は全身の体調を整えることに主眼が置かれ、深刻な病気になる前=「未病」のときに取り入れることで、健康維持につながると西洋医学の世界でも期待を集める。モデル・冨永愛さんが専門家に体調や体質を見てもらいながら東洋医学を体感。世界の最新研究や臨床現場のドキュメントから、西洋医学と東洋医学の融合で広がる新たな医療の可能性に迫っていく。
ナビゲーターはモデルの冨永愛さん。彼女の目標は生涯現役で仕事(モデル)を続けること。そのために興味を持っているのが鍼や灸、漢方薬といった東洋医学なのだそうです。実際心身のケアに取り入れているのだとか。
鍼灸・漢方の新たな世界
呼吸を楽にするための鍼
大学病院の集中治療室。重度の肺炎で治療を受ける患者さんに「呼吸を楽にすることを目的に、胸のところに鍼を打ちます」

鍼といってもシールタイプの鍼で、本当にペタッと表面に貼るだけ。イエローの円皮鍼(パイオネックス・セイリン)のようでしたので、鍼の長さは0.6mmです。
貼付したのは胸郷(きょうきょう)あたりでしょうか。足の太陰脾経の経穴(ツボ)で、呼吸器疾患全般に用いられます。患者さんも鍼が全く痛くないとのこと。医師も「これで呼吸がもっと楽になる」と一声かけています。
転倒による痛みを抑える漢方薬
救急車で運ばれたのは転倒して足の筋肉を痛めた高齢女性。飲んでいるのは越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)という漢方薬。炎症や痛みを抑える漢方なのだとか。
総じて、東洋医学を現代医療に取り入れることにより、より早く症状の改善が見込めるのだそうです。
世界で注目される東洋医学
鍼灸は世界で注目されており、その証左として鍼灸の論文数はこの20年で6倍以上になっているのだとか。鍼灸の効果が科学的に明らかになってきており、病気を防ぐための仕組みがわかりつつあるのだそうです。
また、漢方薬は腸内細菌との関連性が注目されています。腸内細菌が漢方薬の効果を引き出しているのだそうです。
鍼灸・ツボの効果とは
足のツボで身体全体をあたためる
続いて冨永さんが訪れたのは女性鍼灸師の安野先生。訴えたのは首や肩のこり、胃腸の調子がよくないということでした。首元や肩を抑えると硬くて痛そうだったり、オエッと吐きそうな様子も。
そのまま首肩の治療を始めるのではなく、身体全体をチェックする先生。そこで足先の冷えが見つかりました。冷えが身体全体の血流を悪くし肩こりにも影響を及ぼすことから、冷え改善のツボとして「三陰交(さんいんこう)」をチョイス。肩とは全く関係ない場所にあるツボです。
台座灸であたためると、身体全体がじんわりあたたかくなってきたと冨永さん。

ちなみに三陰交は足の内くるぶし(内果)から3寸(親指を除いた指4本分)上、足の骨(脛骨)の際にあるツボです。女性の美と健康のツボとして知られています。
世界が注目する鍼灸・ツボの効果とは

話は変わって南アフリカ。この地でもお灸が治療として役立っています。日本やイギリスの方々がお灸によるセルフケアの普及活動(moxa Africa)を行っています。

ちなみにお灸を据えているのは「足三里(あしさんり)」。右手の親指を右足の膝のお皿の骨の上部(膝蓋骨底)、それから膝蓋骨の外側に親指側の手掌を合わせます。そのまままっすぐ下に人差し指を伸ばし、指先が触れるところにあるツボです。左足も左右対で同様にして取ります。
足三里は体質改善や病気の予防、長寿にも有効とされています。西洋医学の治療だけではよくならない、不眠や倦怠感の改善のため役立っているのだそうです。
結核とエイズ(AIDS)を患う男性は、息苦しさからくる咳や不眠を訴えています。その方が、こんなに効果がある治療法は初めてだと喜んでいます。
鍼やお灸が症状を改善するメカニズム
続いてはメキシコ、オアハカ。ここでは敗血症についてフューチャーされています。敗血症とは、細菌やウイルス感染が原因で、全身に炎症が広がる病気です。
番組では、敗血症の機序についてもう少し詳しく説明されています。
本来、身体を守るためのはずの免疫細胞が暴走し、炎症物質を大量に投与してしまいます。すると血管や臓器を破壊してしまうのです。重症になると、1/3が死に至る治療が困難な病気です。
敗血症の治療に有効だと期待されているのが足三里。40匹毎2グループの排血病に犯されたマウス実験。敗血症のマウスの足三里に鍼で刺激を与えたところ、半数が生存したのだそうです。もうひとグループのマウスは全てが死んでいます。
ここから、足三里には炎症を抑える強力な効果が確認され、また組織を修復する効果も確認されたのだそうです。
また、足三里への鍼刺激により、迷走神経への働きが確認されたのだそうです。迷走神経とは12ある脳神経のうち10番目の神経で、心臓や各臓器に繋がっています。
足三里から神経回路を介し脳に到達したシグナルをもとに、最終的に腎臓の上部にある副腎に辿り着きます。すると副腎からドーパミン(ホルモン)を放出し、全身に巡っていきます。
ドーパミンは脳に意欲や幸福感をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれていますが、その実、免疫にも関与しているのです。
敗血症に話を戻すと、炎症の原因になるのは暴走した免疫細胞。この免疫細胞にドーパミンが結合することで過剰な炎症物質の放出がストップし、免疫機能が回復し、炎症反応が治まるのだそうです。
前述した南アフリカでのお灸についても同様の効果があることがわかっています。
鍼灸で炎症を抑えることができれば、さまざまな病気の治療に役立ちます。鍼灸はもはや「東洋の神秘」ではありません。科学的な裏付けをもつ治療法なのです。
"心と身体のつながり"に迫る

「ツボにお灸や鍼をすると、他にはどんなことが改善されるのですか?」
「東洋医学では心身一如という考え方があります。つまり心と身体はひとつであり、身体の不調は心の不調につながり逆も然りという考え方です」
東洋医学がはるか昔から大切にしてきたのが、心と身体のつながり。こちらも最新の研究で解明されてきているとのことで、番組はアメリカ、ハーバード大学へ。
ここでは、鍼治療が脳の痛みの調節システムにどのように作用するのか研究しています。番組では、腰痛等の慢性痛を取り上げています。
そもそも、痛みは脳で感じています。例えば、腰の骨や筋肉に問題があった時も、その信号が脳に伝わることではじめて痛みとして認識されます。
しかし、慢性痛になると脳に異変が生じます。痛みを過剰に感じることがあるのだそうです。脳の働き、つまり心の問題に関係していることが最新の研究で明らかになっています。
脳内にある痛みを抑える中枢PAG。慢性痛を抱える患者さんに鍼治療を受けていただき4週間追ったところ、痛みを調節する脳機能が大きく改善されたのだそうです。つまり、鍼により脳の機能を回復させ、慢性的な腰痛を緩和させたのです。
現に、アメリカでは慢性腰痛への鍼治療が公的な医療保険の対象になっているそうです。鍼治療はアメリカの医療システムの一翼を担っているのです。
続いてはイギリス、ヨーク。ここではうつ病の治療が紹介されています。
合谷、内関、百会などへの鍼により、低下した脳の働きを改善しているのだそうです。
750人のうつ病患者への鍼治療の効果を検証した研究によると、薬などの通常治療に加え鍼治療を加えたグループでは改善効果が高くなることがわかったのだそうです。
6年間うつ病に悩まされてきた男性は、3ヶ月の鍼治療を経て症状が大きく改善されたのだとか。
「鍼治療が薬のように効果があるなんて馬鹿げていると思っていました。でも、やってみたら前向きな考えで満たされ信じられないくらいリラックスできました。鍼のおかげで自分を取り戻すことができたのです。」
なぜ東洋医学なのか
鎮痛薬の依存性
今、アメリカでは西洋医学を補う役割で東洋医学を取り入れることが進んでいるのだそう。理由のひとつがオピオイド鎮痛薬の乱用。この薬には強い依存性があり、中毒患者が多くいて、毎年数万人の死者が出るほどの社会問題になっているのだそうです。そこで、国や自治体が薬を用いない鍼治療などの導入を推進していることが紹介されています。
災害地治療で採用された耳鍼

また、米軍では耳への鍼治療が正式採用され慢性痛などの改善に役立っていること、大地震等の災害地医療においても多くの被災者を救っています。
鍼はポケットに入れて大量に運べるので多くの人を助けることができます。患者や家族も方法を学んで治療できるなど鍼には多くの利点があるのです。
慢性疾患と鍼治療
一方、日本でも西洋医学では改善が難しい慢性の病気を中心に東洋医学の導入が進んでいます。そのひとつとして、慢性閉塞性肺疾患(COPD)における診療ガイドラインに鍼治療が掲載されています。西洋医学で改善がみられない患者にとって、鍼治療の選択肢になっているのだそうです。
西洋医学と東洋医学、お互いの利点を活かしよりよい医療を目指す動きが広がっているのです。
「西洋医学だけで治療できれば他のことはあえてする必要はないのですが、実際の現場ではそうはいかない患者が多くて非常に困っている人が多いです。西洋医学と東洋医学、それぞれの治療の利点を生かして患者を早く治して健康の増進に役立てる。というのが非常に良いと思います。
漢方薬の最前線

東洋医学の診察方法
続いては漢方薬の最前線。漢方薬が身近に感じられるという方も多いのではないでしょうか。漢方専門医の先生を訪れた冨永さんからは「市販でも売られている漢方薬だが、どのように選んでいいかわからない」という疑問が。
これに対し「自分がどういう性質なのかまず知る必要がある」と先生。症状について答えたのは
手足の冷え
胃腸が弱い
耳鳴りでキーンとする
この問診から、耳鳴りについて「水の異常」だと仰り、東洋医学の診断方法のひとつである舌診をします。舌診では、舌の色や形などから身体の状態を見極めます。ここで舌の浮腫みがあり、やはり水のバランスが不安定であることを示唆。
さらに、内臓から身体の状態をみる腹診を行います。おなかの右寄りに手で圧を加えると、ハリがあることがわかりました。ここにハリがあるのは便が柔らかい方に多いです。その他、脈診をする様子もありました。
総じて「気の異常」により、胃の調子が悪いし、腸も少し弱いのだと判断しました。
東洋医学では、エネルギーである「気」、血液などをあらわす「血」、血液以外の水分である「水」。この3つの要素で状態を見極めるものだと番組内で説明しています。
その結果処方された漢方が半夏白朮天麻湯(ハンゲビャクジュツテンマトウ)。この漢方には以下の生薬が組み合わされています。
半夏……胃腸を整える
白朮……水のバランスを改善
天麻……めまい、耳鳴りの改善
ところで、この漢方にはどのようなメカニズムがあるのでしょうか。
腸内細菌との関わり
近年の研究で漢方には腸内細菌が深く関わっていることが明らかとなってきました。その一端を解き明かしたのは外科医の先生。
「漢方薬というと内科というイメージがありますが、外科の世界でも結構 漢方薬が使われています。」
漢方薬を用いるケースのひとつが「胆管癌」です。胆管とは、胆汁の通り道のことで、その管にできる癌を指します。胆管がつまり、本来全身に送り届けるはずの胆汁が肝臓に蓄積してしまいます。すると黄疸になり、肝臓の機能が損なわれるのです。
「黄疸(の数値)が下がらないと最終的に(胆管がん)の手術をすることができません」
そこで黄疸の改善に用いられる漢方が茵蔯蒿湯(いんちんこうとう)なのだそうです。
「茵蔯蒿湯を投与して胆汁の流れが良くなる患者さんは2〜3日で良くなりますが、なかなか(胆汁の)流れが良くならない患者さんがいます」
なぜ同じ症状の患者さんでも効果に違いが出るのでしょうか。
その謎を解く鍵になったのが腸内細菌。漢方薬が腸に入ると腸内細菌が集まり、漢方薬を分解する酵素を出します。その酵素にジェニポシド(漢方薬の成分)が近づくと、黄疸を改善する薬効成分(ジェニピン)が分泌されるのだそうです。すなわち、腸内細菌が漢方薬の効果を引き出してくれているのです。
そして、薬効成分の産生能力が高かったのは善玉菌が多い方だったそうです。つまり、漢方に対する反応にバラつきがあるのは、腸内細菌が影響を及ぼしてるとのこと。
他にも腸内細菌に関連する漢方として
甘草(カンゾウ)……免疫調節作用
人参(ニンジン)……疲労改善
柴胡(サイコ)………抗炎症
が紹介されていました。「腸内細菌を改善することで漢方薬の効果をより引き出せる可能性がある」と先生。
これらが明らかになってきた背景として「科学の進歩が伝統的な医学の叡智に追いついてきた」とも。
新たな免疫メカニズム
その他、新たな免疫メカニズムとして大建中湯(だいけんちゅうとう)が紹介されていました。マウス実験にて腸炎のマウスに大建中湯を投与したところ、わずか5日で腸炎が改善されたのだそうです。
これは新たな免疫細胞「3型自然リンパ球」。病原体から身体を守る、腸の「粘膜バリア」維持に深く関わっているのだそうです。
機序としては、まず腸内に降りてきた漢方を食べた腸内細菌がプロピオン酸を産生し、3型自然リンパ球がキャッチ。「バリア機能を高めて」と指令を出し、腸の細胞が粘膜を生産しバリア機能を強化するのだそうです。
番組内では、これらを「医食同源」そして「養生」という言葉で締めくくっています。病気になる前(未病)に養生(セルフケア)をしていきましょうということですね。この考え方を取り入れることにより、病院や病気との付き合い方も変わってくるのではないでしょうか。
最新研究が切り開く東洋医学の未来
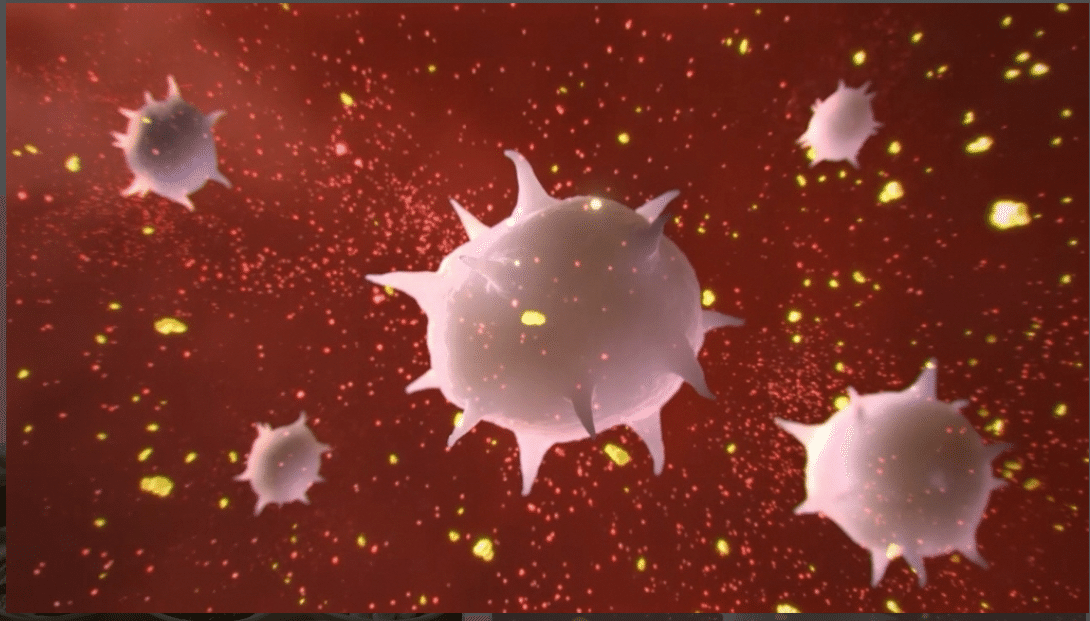
「最近、さまざまな神経科学・神経生理の研究から、鍼灸の治療メカニズムのひとつは「ニューロモデュレーション」であると分かってきました」
ニューロモデュレーションとは、電気や磁気などで神経を刺激し働きを調節する治療法です。このニューロモデュレーションによりさまざまな病気の原因となる炎症を防ぐことができるのではと、世界中で開発が進められています。
通常、病原菌等が体内に侵入し感染した場合、免疫の炎症反応により病気を治す仕組みが備わっています。ところが、心理的ストレスや光などの環境要因により体内に微小な炎症が起こっているのだそう(ゲートウェイ反射)。
次にゲートウェイ反射について説明されています。
ストレス等が加わると、特定の神経回路から伝達物質が血管に分泌されることにより、血管壁にゲートがつくられます。すると、本来血管内にいるはずの病原性T細胞が組織内に侵入。周囲の組織を攻撃し、病気のタネとなる微小な炎症が起こるのだそうです。
これらが原因であると分かってきている病気として
関節リウマチ
動脈硬化
糖尿病
認知症
が挙げられていました。
その対策として経皮的耳介迷走神経刺激(taVNS)が紹介されました。耳に分布する迷走神経へ電気刺激により働きかけ、脾臓から神経伝達物質が分泌されます。最終的に免疫細胞に作用し、暴走を鎮めて炎症を抑制するのだそうです。番組内では間質性肺炎の患者さんに用いる様子が検証されていました。
まとめ
最後に冨永さんのナレーション。
「いつまでも健康でいるために。東洋医学には、わたしたちの生活を支えてくれる大きな可能性が秘められているのです」 〜Fin〜
※いち鍼灸学生が番組を授業内容と紐付けながらまとめてみたものです。もしかすると内容に齟齬等あるかもしれません。特に漢方薬については専門外です。
見逃してしまった方や興味を持っていただいた方のお役に立てれば幸いです。
また、このnoteでは鍼やお灸について、学生目線でシェアしております。例えばこんな記事。こちらもよろしければご覧ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
