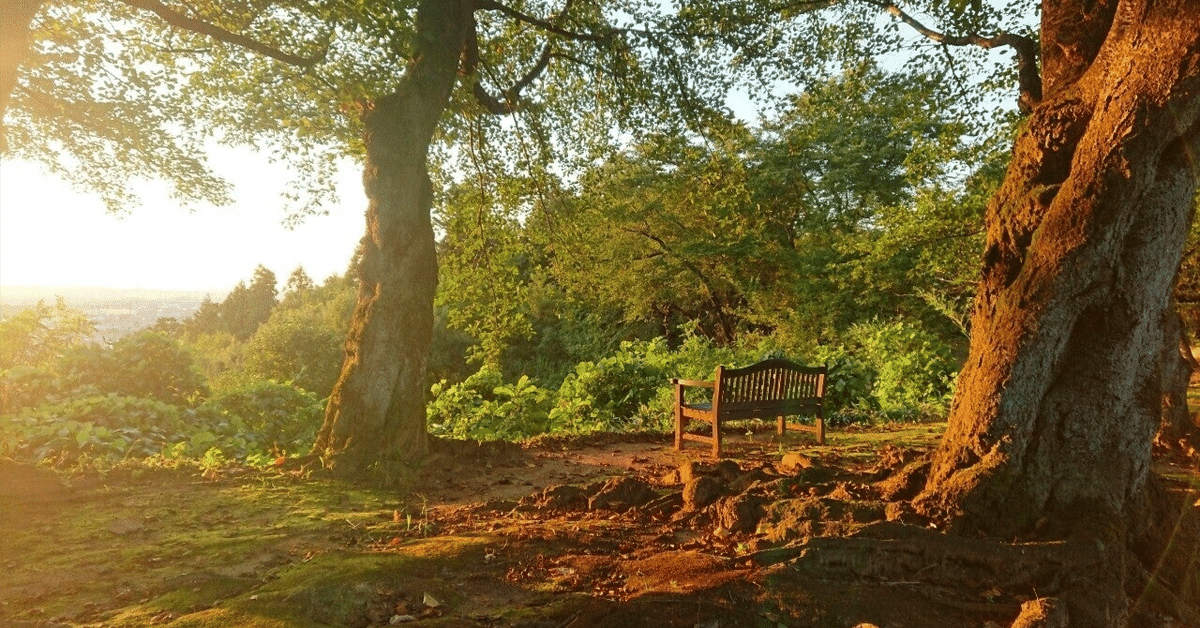
#167|事実をありのままに|解釈は手放し|望む未来を選択する
葛藤が多い今日このごろ。こういう時に私が気をつけていることを記事にした。ちなみにこれは私独自の考え方なので、「心理学的に間違っている」などはあると思う。その辺りは踏まえていただいて、もし活用できるところは活用いただけると嬉しい。note365日連続投稿チャレンジ167日目。
①事実をありのままに受け入れる
たとえば人とのコミュニケーションの上で、自分にとってつらい出来事があったとしよう。
自分からするとそれは「ひどい!」と思えるような対応を受けたとして。その対応に、悲しみや怒りがわいたとする。
それは、全然OKだ。大いに悲しみ。大いに怒ろう。そこはけっして否定しないで、認めてあげるといい。自分を否定しない、責めない。まるまる受容して上げることが大切だ。
その対応を受けて、自分は「悲しいと思っている」「怒っている」「がっかりした」「みじめな気持ちだ」。どんな感情も抱きしめてあげる。
どんな感情であっても、どんなに非論理的であっても、生まれたものは絶対的に正しい。そう考えることが愛だと私は思っている。
②解釈を手放す
そこから、次に自然に考えが移行していくであろう「解釈」が重要になる。
自分が悲しかったという「事実」から、だから相手はひどいことをした(相手にひどいことをされた)、といったような「解釈」に、移行しないように気をつける。
受けた対応と、そこから悲しいという感情が起こったことは事実だが、だからといって相手がひどいことをしたのか?はわからない場合の方が多いし、たとえそうだとしてもその解釈は自分を幸せにはしない。
自分だけの視点でなく、相手の視点、社会の視点、など、多様な視点があり、多様な立場がある。そこから「善悪を決めようとする」ような、「私が悪い or 相手が悪い」ことをハッキリさせようというような、二元論的な思考が始まった場合、人生の無駄使いがスタートする。
そのような思考モードに入った上で、「相手が何を思ってこんな対応をしてきたのか?」という原因探しや、「今後どうすればこのようなことにならないだろうか?」といった改善案を考えることは、残念ながら無駄になる。
その思考モードとは「ジャッジ」のモードであり、「誰が本当に悪者なのか」を探しているような状態だからだ。その土台に立って考える内容は、最終的に「自分の正しさの証明」か「自分の愚かさの証明」にしか行き着かない。実際に裁判が起こっているのでない限り(自分の身の潔白を確定させる必要のある場ではない限り)、それを証明すること自体が不要なのだ。こだわりがあるためにハッキリさせたいだけだ。それをハッキリさせたところで、そのあと起こるのは「分離」である。敵と味方に分かれる。争いが始まる。
自分が正しかったなら相手を責めていいのか?自分が愚かだったなら、自分を罰するべきか?どちらも不要な行為だ。「よりよく生きたい」のであれば。
③望む未来を選択する
事実を受け入れたあとは、「どのような解釈もしない」のが望ましい。加害者にも被害者にもならない。相手も私も悪くない。ただ「こういうことがあって」「私は傷ついた」それだけでいい。
そうして次に、どう在りたいか?を「選択」する。「事実」の受容から「解釈」の罠を超えて「選択」にまで至れば、自分の力は復活する。
最終的に、どんなことがあっても、「で、私はこれからどうしたい?」これだけだからだ。自分がどんな間違いをおかしていたとしても。相手がどれだけひどい人であっても。けっきょく「今ここ」でどのような私で在りたいか?「今ここから」どのように生きていきたいか?
事実を踏まえて、自分を受け入れて、他者や出来事を許して(手放して)、希望を選ぶこと。そうすれば、どんな苦しい状況でも、ふたたび自分の人生に戻ることができる。
スケール(物差し)を持つこと
これを私は「フェーズ1(事実)」「フェーズ2(解釈)」「フェーズ3(選択)」として識別している。
感情がネガティブに揺らぐ事態が起こった際、気をつけていないと簡単にフェーズ2でループが起こるのだが、こういった「自分の心理状況を識別できる物差し」を持っておくと、何かと心が揺れた時には対応がしやすい。
これはビジネス用語では「情報の『空・雨・傘』」と言われるものが近い(というか一緒だが、こちらは「感情に対する物差し」に特化した使い方)
特に気をつけていたいのは、「自分は悪くない」と考えて「相手の間違いを証明しようとする行動に移っていく」ような流れだ。
これは「フェーズ3が2に乗っ取られて暴走している」ようなイメージがある。しかし、その行動をいくらやったところで、未来に得られるものはない。
もしかしたら、白黒ついてスッキリはするかもしれない。何かへの勝利はあるかもしれない。相手に復讐はできるかもしれない。仮にそれで何かを得たとしても、断言できるが「豊かさ」は生まれない。
なぜなら、そういう動きは「癖となり繰り返される」からだ。それは「ネガティブな感情を感じたら、相手(あるいは自分)を攻撃する」というパターンを持って生きていく、ということだからだ。
その生き方では、他者と共に持続的な豊かさを築いてはいけない。一時期は手を取り合えたとしても、何かのきっかけで離れることになる。
しかし人は皆、永続的な豊かさがほしいはずだ。そのためには、善悪の二元を超えられることは必須要素だと思う。敵を作り出すことで自分の痛みから目を背けることをやめること。痛みは感じ尽くす。そうしてこそ人に優しくなれる。そして、希望を持って選択する。そうして強くあれる。
つらいことを人に話して"活きる"ケースと"活きない"ケース
こうしたネガティブな出来事を誰かに話す際には、フェーズ1、2、3のどれを話したくなるかで、自分の状態をチェックできるし、それを話すことによって前向きに働くか、ネガティブに働くかは変わる。
たとえば。
A.「こんなことがあったんだよ」「とてもつらかったんだ」「ひどいと思わない?」という展開なら、フェーズ2にいる。「ひどい」かどうかはわからないことだし、仮にそれが本当に「ひどい」ことだとしても、そこを話す理由は自己の正当化や相手への間接的な攻撃だ。
B.「こんなことがあったんだよ」「とてもつらかったんだ」というだけならばフェーズ1だ。ここを話せる相手というのは、自分にとって大切な存在かもしれない。安心がないと話せない。この話であれば、「自己を癒やす」効果があり、「聞いてもらえた」ことが力になる。
C.「こんなことがあったんだよ」「とてもつらかったんだ」「これからはこうしようと思う」ということであればフェーズ3。これは事実の上で理想や目標や自身の在り方を話すという構造だ。それを聞いてもらうというのは、「宣言効果」になり、その行為が自分の背中を押してくれることになる。
こうして、この物差しを使って自分の状態を整え、よりよい未来に向かうために他者と共有することができる。
逆に使えば、たとえば「愚痴を聞く」という行為が、聞く側にとって本当に負担になるか、相手の力になれたと感じられるよい時間になるかの違いもここにある。「一緒に相手をバッシングする」ために聞かされる愚痴は、聞き手をもネガティブなエネルギーに引き込むが、自分の弱さをありのままにさらけ出したり、前向きな想いのシェアであれば、親近感が増したり応援したいと思える。
フェーズ1への処方箋
「事実から生まれた感情はどんなものであれ正しい」「それを受け止めてあげる」ということを書いたが、しかし、いちいちネガティブな気持ちになっていたくもない。
生まれ出た「ネガティブな気持ち」を否定することはまったくおすすめしないが、生まれないようにはしたいハズだ。
そのための試行錯誤は有効だ。
フェーズ1にアプローチするのは、感じ尽くしたあとの仕事だ。「その起こった出来事」から、なぜ私は「その感情」が生まれたのか?を見ていく。
「相手に無視されてとても腹が立つ」なら、その怒りは認めてあげて感じ尽くす、そのあと。(正確には「無視された」はフェース2の解釈が入っていて、事実としては「声をかけたけど返事がなかった」だ。)
そのあと、なぜ私は「とても腹が立つ」のか?ここには、メモ書きも大いに活躍するし、内観や過去を振り返ること等々のいろんなものが使えるハズだ。
そうして、「子供の頃、無視されたことからいじめが始まってとてもつらい3年間をすごしたから」そこへの防御反応として生まれているのかもしれない。といった理由が見つかる。そこをまた癒やしてあげたり、解釈を更新していく。たとえば「子供の頃は学校が全てだったから舐められてはいけなかった。でも今はもう、どこへでも行ける」といったように。
そうしてうまく消化できると、次に「返事がなかった」としてもべつに「腹が立ち」はしない。こうして人生の「ひっかかりポイント」を解消していくと、何かの出来事に対してわざわざフェーズ1が発動しなくなるので、人生において望まない事態が生まれる回数が減っていく。
自分が健やかに生きていくためにも、他者と豊かさを築いていくためにも、こうした自分の心のかさぶたみたいなものはどんどん体験して→消化していくのがいい。
そういう目線で見れば、「ネガティブになるような出来事」は自分を成長させてくれる最高の贈り物になる。そうして今日より明日がよりよくなる、そんな生き方を私は選ぶ。
p.s.
生きていれば「自分には理解不能な対応を受ける」こともある。しかし、そんな時に思うのは「自分も誰かにとっては理解不能な対応をしている」んだろうなということ。
そうして、「理解不能なものに対する理解」を試みるが、その時にフェーズ2に入っているままだと解釈が歪むので気をつけたい。
まったく話は変わるが、昨日の記事↓で書き出しの一文目を盛大に誤字っていて、修正する前に読んでくれた人は意味がわからなかっただろうなと思う。
こちらで、正しくは
>「自分は人にどう思われているだろうか?」
と書きたかったところを、
>「自分は人にどう思っているだろうか?」
と書いていた。笑
これではまったく伝わる意味が違う。誤字脱字にしても、こういうところは注意したい。昨夜は眠すぎて半分寝ながら書いた記事だったから、という言い訳で〆
✑77分|4300文字
