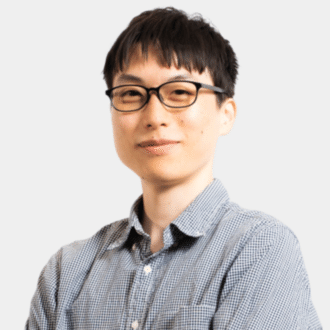5/12木:溢れるアイディアには水底から湧き上がるエネルギーを。
昨日の夜、30分ほどはある研究室からの帰り道を歩く間にずっと考えごとをしていたら、気づいたら家に着いていた。普段はイヤホンでYouTubeを聞き流したりしているのだが、そのときはあまりにも多くの情報が自分の頭の中を駆け巡っていて、処理しきれなかったのだ。
「今自分が所属している子育て団体の活動内容を、どうすればもっと豊かなものにできるのか?」
「活動している会員が、どうすればもっと主体的に参加したいと思えるようになるか?」
「まだこの活動を知らない人たちに、どうすればもっとその魅力を伝えることができるのか?」
「皆が生きやすい集団や組織とは、一体どういうものなのか?」
「もし自分が、自分自身の生きやすい、自分らしくいられる集団・組織・コミュニティを、自分自身の手で作るとしたらどうするか?」
様々な仮説やアイディアが、水底から湧き上がるあぶくのように浮かんでは、別のアイディアによってかき消され、それが繰り返された。
そうして家に着いたとき、あぁ、自分の本当の興味の対象はやっぱりこういうことなのだろう、と思った。この感覚こそが、自分が立てた仮説を検証したいと思う研究者の感覚なのだ。
そして同時に、私はやはり研究テーマを変えた方がいい、と思った。
今の研究を続けながら、それに関連する組織に入ってキャリアを積み、さらに大きく社会的にインパクトのある仕事をすることが、本当の自分の幸せに繋がるのかと言われると、疑問符がつく。
人間は、せんじつめれば皆研究者と言えるのかもしれない。それは、自分自身という存在が満足できる生き方を求めて、仮説と検証を繰り返す存在でもあるからだ。
歩きながら考えたことが、果たして本当に実現できるかどうかなどわからない。それでも、研究者として生きる(飯を食う)だけでないく、広義の意味で研究者として生きる(自分自身の探究をし続ける)ことはし続けていたい、とも思うのだ。
昨日お会いした方とのやり取りの中で、私の話からは水の底から静かに湧き上がるようなエネルギーを感じた、という言葉を頂いた。
私は情熱的に何かに取り組むことができないことがコンプレックスだった。
しかしこの言葉からは、自分自身の持てるエネルギーの質が、情熱とは異なる形で存在することに気づかせてくれた。
水の底から湧き上がる仮説やアイディアを、水の底から湧き上がるエネルギーで形にしていくことができたら、自分の性質を利用して何かすごいことができるのではないか、という気がしてきた。
いいなと思ったら応援しよう!