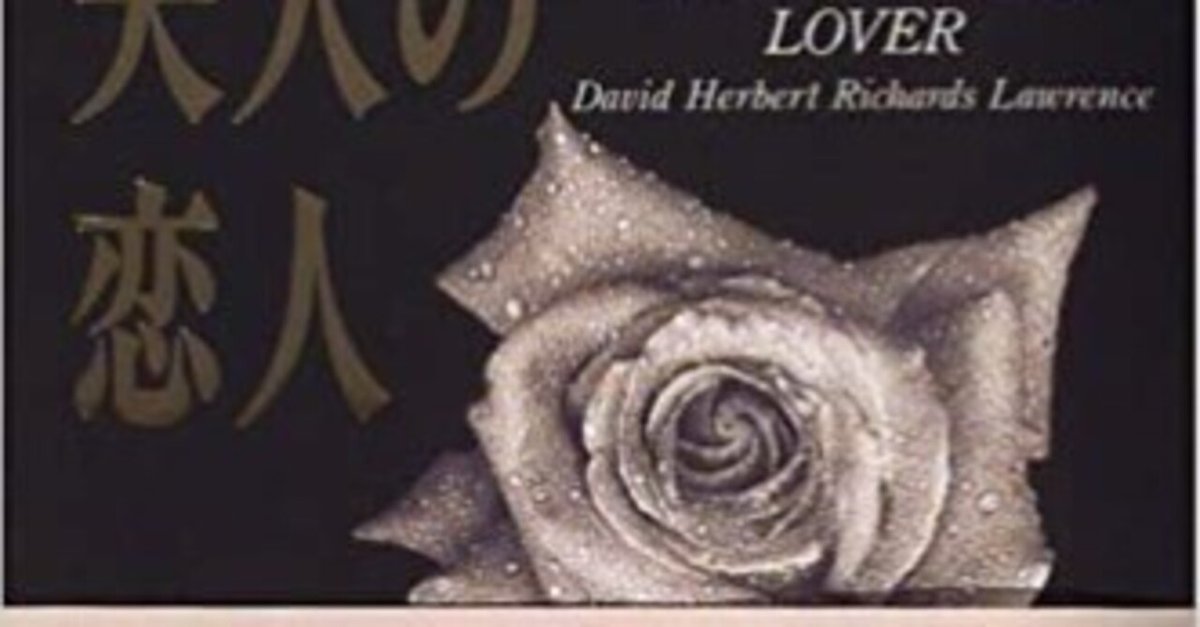
題:D.H.ロレンス 伊藤整訳「チャタレイ夫人の恋人」
ずっと前から読もうと思っていて、やっと読むことができた。最初は古臭くてあたりまえの文章で、あまり気乗りがしなかったが、チャタレイ夫人なるコニーと、その恋人の森番メラーズの恋の進展が気になり最後まで読むことができた。コニーは戦争で負傷し下半身不能で、車椅子生活を送る夫のクリフォードと共に暮らしている。従って、稀に夫の友人たちと肉体的な関係も持つ。でも、性的に満足できない。そして、ある時森番メラーズの上半身の美しさに見とれる。望む通りに彼女は彼と性的な関係を持つことができるのである。コニーは周りの人間たちには慎重に逢引を繰り返しながらも、クリフォードの世話をするボルトン夫人に二人の関係性を見抜かれている。
夫クリフォードは自分の子でなくとも子が欲しいと望んでいる。コニーはメラーズの子供を宿すけれど、言い訳が立つというより、森番メラーズの子を欲しいのである。彼は昔上官に気に入られて中尉まで昇進するが、上流階級の人間ではない。そのため、妊娠は非難を受ける覚悟がいる。彼女は姉と旅行に出かけることにする、旅先で恋をして妊娠する物語を作り出すことができるためである。でも、彼女は父にはありのままに告げる。もはや二人は結婚する約束をしているのだ。例え夫クリフォードが離婚に反対しようとも、メラーズの横暴な妻が長年の別居生活を止めて押し掛けて来ようとも、メラーズも妻との離婚を決意している。コニーの妊娠はこの妻によってこの地に広められて、もはや二人は去るしかない。新たに農場を作ることを夢見て、二人は長く住んだこの地を離れる、ハッピイな終わり方である。
本書は猥褻本として裁判沙汰になっている。その辺りは伊藤整が「あとがき」で書いているが、割愛する。ただ、本書が完訳本であることは言っておきたい。後で、こうしたフランス文学の恋愛ものを比較するが、決して猥褻小説ではない。むしろ文章および作家の洞察力には高貴さがある。現代の文明論に向けての示唆に富んだ提示が含まれている。猥雑さは、エロさと言い換えると、裸体にて雨降る中を、飛び跳ね踊る二人のさまはエロさ以上に、感嘆する美しい動画である。本書は性行為そのものも露骨な描写よりも心理的な感傷と鑑賞、それに感嘆すべき肉体と精神に対する発見がある。D・H・ロレンスの確かで緻密さに満ちた文章があり、男女の心理が彩られている。なお、性的な描写は「O嬢の物語」のようなリアルなマゾ的肉体と行為の描写や「ファニー・ヒル」のような生殖器や性行為の緻密な描写はない。けれど、「ボバリー婦人」のような大胆な心理描写だけではない、露出された性の心理と行為は含まれている。ただ、どれもが高貴な小説の中に入り込んでいる必要不可欠な自然な描写である。
さて、本書では何を描いているのか。決してエロさではない。後でドゥルーズ「千の文学」で、福山智が記述した「生の作家」なるロレンス論を簡単に紹介している。従って、ここでは本書の中に書かれていた言葉「存在の核心」について少し意見を述べたい。恋愛小説等の簡単な他者構造論の紹介でもある。この「存在の核心」とは自己と他者で成り立つ心理の込み入った関係性を指し示している。我とは他者で成り立つ者である。レヴィナス流で言うなら「他者の顔」の中に自らを見出すのである。そして、他者に対して責任を取らなければならない。サルトルの思想を我流で言えば、自らの見るものなる「対自」から、他者から見られる自らなる「対他」へと視線は変わる。恋人を見詰めた視線は、逆に恋人の視線に見られる。心理的にも相手を思っていると、その思いが逆に相手からの思いとなって伝わってくる。こうした思いを受けて、相手の心と体を思いやる自らへと逆変換する「即自」的な存在がいるのである。
こうした他者との関係性は二人だけの関係性ではない。それぞれの夫や妻に、親兄弟の親族に、メイドに、友人たちに及んでこの世界を構築している視線と心理を暴いてくれるのである。そして未来へと自らを進ませることができる。「即自」的な、即ち自己充足している森番メラーズが相手の思いを気に掛ける「対他」的な存在に、また自らの思いに信を置く「対自」的なコニーが、やはり相手の思いを気に掛ける「対他」的な存在に変わってくる。そしてこれらの思いの関係性が見えない紐となって繋ぎ合わさり、更に多数の人を巻き込んで繋ぎ合わせて世界は構築されているのである。そして、彼らは「対自」の思いの充足を図るべく、未来の世界へと自らを投企するのである。
本書のもう一つ重要な点は、社会的な視点からの描写を行っていることである。象徴的なの言葉が「石炭」である。クリフォードは石炭を掘り出す鉱山を持っている。坑夫の住む町のうねうねした道や線路に、轟音や煙、作者はこうした描写を文明への批判として記述している。この批判の正体は丁寧に読破しないと見つからないだろう。現代では、石炭や石油を使わずに脱炭素を求めていながら、戦争の犯罪者から購入を拒否したエネルギー源の代わりに、逆に使用すべき貴重な燃料として石炭の輸入量を増やしている。都合よく物事は変わるのであり、人間の心理は混在した価値判断の中で苦悩する。苦悩は葛藤へと結びつかずに、解決されるべき概念は生み出されない。ただ、生命だけが、現実を生き延びるようとする生存だけが価値を持ち、その価値が傍らでは一方的に破壊されている。そうした文明への批判や諭評は、再度言うが本書では細かく読まないと真相は見えてこない。
今まで読んだ古典的なロマンもしくは不倫小説と比べてみたい。すべての小説が、その他の同類の小説も含めて、既に感想文として記述され掲載している。これを「チャタレイ夫人の恋人」も含めて引用したい。
―――――
1)クレーヴの奥方 ラファイエット夫人作 1678年 不倫な感情を夫に告白をするクレーヴの奥方と相手のヌムール公を通じて恋愛心理を描く初めての本格的な小説作品である。ヌムール公に口説かれるクレーヴの奥方はどう行動するのか、心理は行動にどう擦り込まれていくのか。クレーヴの奥方の切なさが心に沁みてくる作品である。
2)危険な関係 コデルロス・ド・ラクロ作 1741年 法院長夫人を姦淫へと誘う心理的な罠など、性に放縦なバルモン子爵とメルトイユ夫人を主人公にして、封書のやり取りなる書簡体で記述した作品である。子爵はメルトイユ夫人と共に少年少女を淫らな世界へと引き擦り込もうとする。そして、バルモン子爵の罠は手が込んでいて、法院長夫人への思いを必ず遂げようとする。
3)谷間の百合 バルザック作 1835年 フェッリクスなる青年が恋愛を通じて成長していく話である。舞踏会でフェッリクスはモロゾフ侯爵夫人に出会い、谷間の百合にある邸宅に足繁く通い、夫も含めて家族と付き合い始める。主テーマはモロソフ侯爵夫人のフェッリクスを愛する心と欲望との相克を描いている。初め舞踏会で出会った時、肩に口付けをされたモロゾフ侯爵夫人は、その後、この感触が忘れられなかったことを最後に手紙に綴っている。
4)赤と黒 スタンダール作 1830年 ジュリアン・ソレルなる青年の青春恋愛を通じて成長していく様を、法や軍など政治的状況も含めて描いている作品である。確か、手の甲に接吻する。手の内側は許されないのである。
5)ボバリー婦人 フローベール作 1856年 奔放なボバリー婦人が性遍歴を通じて破滅していく過程を、繊細で美しい文章により描かれている。ボバリー婦人はかっては貞淑な娘であった。だが、医者と結婚後、夫の退屈さから、誘惑もあって不倫を行ってしまう。こうして禁断の愛の味を知った夫人は、別の青年とも危険な逢瀬を繰り返して、結局は破産してしまうのである。
6)チャタレイ夫人の恋人 D・H・ロレンス作 1928年 性的不能な夫を持つコニーなる貴婦人が木こりと肉体関係を持ち、互いが互いを必要とする。もはや未来に向けて共に生活することを誓う。
こうしてみると、小説も変化していくのだろうか、それほど違いがあるとも思われないが、純朴さが放蕩な行為を重ね合わせてくる。「危険な関係」だけは、異端とも思われる冒涜な行為を描いている。無論、もっと毒々しい小説はたくさんある。大雑把に言うと、これらの小説は、心理そのものが肉体とせめぎ合っていたが、心理は肉体と離反せずに、むしろ肉体が優位性を保ち心理を従えて作品が展開されているのである。「谷間の百合」は逆に心理が幾分優位性を保っているため心理小説である。心理と肉体の相克は、時代的な変化が多少あっても、どの時代においてもきっと主要なテーマとなっているのだろう。近代の日本の小説にも心理と肉体の相克を描く小説はあったが、最近の小説においてあるのだろうか。禁忌・禁断の垣根がとても低くなっていることが、この種のテーマを取り扱う小説を描くことの難しさを感じさせる。
-―――――
さて「谷間の百合」での壮大で描写力豊かな文章は、当時の人間社会の基盤そのものにも及んでいて描く範囲が広がっている。このためか、女性心理は良く書かれているけれど、やはり男性が描いている文章との思いが強い。きっと「クレーヴの奥方」が、素朴な純粋さを持った文章であるために、一層そのように感じるのであろう。この「谷間の百合」は確かに良い作品であるけれど、どこかあざとい。これも、この作品の出だしが実は手紙となっている。この相手先の夫人の皮肉とも嘲笑の思いから来ていると思われる。やはり面白いのは「ボバリー婦人」の心理と肉体の破滅小説や「危険な関係」なる悪徳な小説である。人間の欲望が実現した時にどうなるのか描かれているというより、悪徳や退廃さが善や健全さを上回って魅力的なためであろう。つまり、小説には適度に悪徳や退廃が含まれている必要があって、この観点からすると「危険な関係」は幾分刺激的である。「ボバリー婦人」が文章の魅力も加わって善悪の釣り合いも取れていて、一番読み良い作品のように思われるが、夫人は結局破滅していくのである。
本小説におけるバルザックの文章は、ロラン・バルトのエクリチュール論から解読していくと面白いと思われる。歴史性と現実を反映して自らの資質と感性を織り込んだエクリチュールなるもの、この研究と解読に値する。無論、他の作品も論じることが可能であるけれど、バルザックの文章はこれらの成分を濃密に含んでいると確信できる。でも、バルザックには「人間喜劇」など他の作品がたくさんあって、これらを読まないと良く分からに違いない。それに、恋愛や不倫小説はまだまだたくさんある。気の遠くなるような話であって、どこかで読むのを打ち切らなければこれらの作品群の全貌は見えてこない、というよりたくさんの小説を追い駆け続けるだけになるのだろうか。と言うより、バルザックの文章を含めてエクリチュール論からの解読は諦めてしまうのか、そんなことは考えずに、まあ、小説は読んで楽しければ良しとすれば良いのだろう。それとも、エクリチュール論とは、きっと読書しながら追求確認し、追い続けるものなのだろう。
さて、ドゥルーズ「千の文学」では、福山智が「生の作家」として、ロレンスが書くセザンヌ論を取り上げている。このセザンヌ論が、ドゥルーズが描くベーコン論の視点をセザンヌとの親近性に向かわせているのである。ロレンスの論を次に示す。『「セザンヌ自身が望んでいたのは抽出表現だった」と確信すると述べているが、注意しておきたいのは、ここで言われる「抽出表現」とは単純に対象として描かれるものではないということだ。そうではなく、物体のなかにある、そして身体の中にある「感覚を経験するものとして生きられる限りにおいて」表現するされたものであり、紋切り型との苛烈なまでの格闘に勝利を収めた後に至る境地に他ならない』この抽出表現が、ドゥルーズはベーコンに結び付けて、またロレンスがセザンヌとロレンスを結び付けている役割を果たしていると福山智は述べている。通常の紋切り型との過酷なまでの格闘の結果得られる感覚の鋭利さは、抽出表現によって得られるのである。
ドゥルーズにとってロレンスは真に生の作家の一人としている。こうした論拠はロレンスの「黙示録論」読み解くと分かるのである。ロレンスは次のように述べている。黙示録とは、これを最後に断っておくが、人間のうちにある不滅の権力意志とその成果、その決定的勝利の黙示に他ならない。集団に住み着いている権力への欲望への絶望的な考察であり、それを乗り越え「象徴」そして「コスモス(宇宙への再領土化)」が必要と福山智は述べている。このロレンスの「黙示録論」は既に読んでいて感想文も書いているはずである。可能ならば掲載したい。言い添えたいことは結構あるが、長くなるのでもう止めたい。また、舌足らずな文章を書いていると思われる。ぜひ福山智の『D・H・ロレンス 生の作家』と題した素敵な論評を読んで楽しんで欲しい。
以上
いいなと思ったら応援しよう!

