
朝霧カーニバルボランティア振り返り ~私だからの災害伝承とは~
さてさて。
自己紹介からの投稿から初めての投稿となります。
今回は、以前からお関わりのあるN.Mさんのご連絡より、一般社団法人三陸&東海防災フォーラム伝さんの販売、伝承のお手伝いをさせていただきました。そのポートフォリオとして書かせていただければと思います。
伝承館と違う難しさ
一応伝承館の研修生と言うこともあるので、学びになった部分が多くありました。特に、「幼い子供」に語るといったことは訪問したや実地研修中でも伝承館では少ないように見えました。一番多いと感じるのは、中学生・高校生かな、、、と個人的には感じています。
そこで大きな障壁となるのが、言葉だったりしました。
例えばになりますが。
例:「震災によってインフラが寸断されて、物資を配給できなくなって、ごはんを食べるのが難しくなった。」
これを4~7歳の子供が分かるでしょうか。
「インフラって何ー!?」
「配給って何ー!?」
など言葉の質問をされてしまう、、、
伝承館だとこういった場面を目撃することがなかったので、少し戸惑ってしまいました。当日はスケッチブックだったり、「防災ダック」を用いての

伝承の形でしたので、「これは何を伝えなければならないのか」のゴールを立て、そこに向けて、子供に向けた言葉に置き換えて、進んでいく。
簡単に見えて、意外と大変なんです。
いつも通りのトーンで語りそうになってしまいそうになってしまいますし。
でも、私が伝承館でそういった機会をあまり見たことがないだけで、伝承館にも幼い子供は来る。だから、そういった時、どう接する、伝承するか。今後に繋げていきたい。
子供たちの反応
当日は販売と同時に以下のプログラムを実行しました。
-当日の流れ-
防災ダック(子供たちに「この時どうする~!?」と聞いて考える)
↓
リオン(絵本)での津波の高さを認識
(著作の都合上、帯だけになっていまいますが、、)

↓
スケッチブックでの津波が発生したら、どうするのか。


↓
非常食の紹介
↓
販売コーナーに繋いでいく、、、

といったワークショップというかプログラム形式のような流れでした。
全体的に「この時どうする!?」がメインの形でした。
(クロスロードを小さい子へ向けた形と言った感じでしょうか)
そこで、分かる子もいれば、、、
分からない子は、親御さんに聞いたり、助け船を出してくれたりといった場面が多かったです。質問にはっきりと答えてくれた子も、それに対し、親御さんのリアクションでの関わりもありました。
その様子を見て、私としては、自分事として考えていくためには、私は他者とのコミュニケーションが大切だとつくづく感じています。
その中で気づけることもあるし!!(根拠もない個人的な考えですが)
私に語れること・語れないこと
今回は、私と現地(東海地域)出身の方以外は、福島(いわき)や宮城(仙台)の出身の方だった。半分ぶっつけ本番みたいな形で語りとなっていまったが、その中で気づいたことがある。

被災したから話せることは、私(現地で被災していない)には話せない。
当たり前ではありますがね、、、
ですが、”被災したから話せること”って皆さんはなんだと思いますか。
避難生活だったりが上げられると思います。
半分正解でしょうか。
被災した人はもっと細かな話が出来ます。例えば
被災当時に皿を汚さない方法(サランラップを巻けば洗わずに済む)
ここまで細かなことは私個人話せない。被災した人たちだからこそ、語れることだと思う。宮城(仙台)出身の本社団法人の理事の方も仰っていました。それと同時に思い出したことがある。
佐藤先生の”未来を拓く”話より
1年程前に石巻を訪れた時、
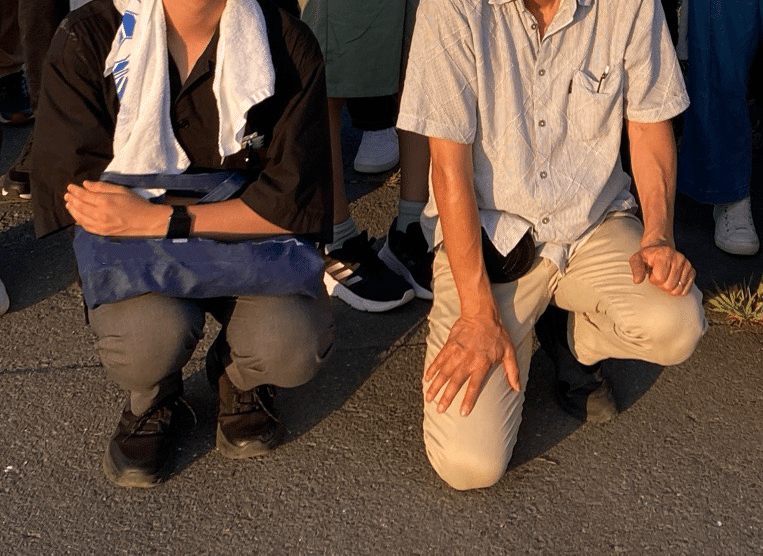
大川伝承の会の佐藤敏郎先生は、以下のようなことを仰っていました。
(概ねになりますが)
”語りたくても語れない人がいるということ。”
現地で被災した人にとって、語ること自体、あの日の記憶を思い出すことになる。中には、壮絶な被災をされた方もいる。それを思い出す辛さで語れない人もいるということ。
現地の人にとっては、内心はつらいことなんだと思う。
私は、つらいという気持ちはない。
現地で被災していない。
身内の誰かが東北地方出身で被災したといったこともない。
だが、伝えたい。自分事として考えてほしい。
と言う気持ちは強い。それは、被災をしていないからこそ他の人よりも強く持ち続けることが出来るのかもしれない。
私は、あの日の細かなことは語ることは出来ない
けど、私のような立場と気持ちだからこそ、語れることがきっとあるんだと思う。
その内容は明確にはなっていない。それは、今後活動を続け、明確にしていきたい。
自分の唯一に近いこの立場の意味とは
しかし、一つなんとなく分かったことはあった。
首都圏や東海だったり、他の地域の人の東日本大震災に対する考え方だったりと言うのは、東北の方より少しなんとなく理解できる。
そりゃ分かりますよ!だって防災やら震災ってなんか堅苦しそうだもん
けど、いつか首都圏、自分が住む神奈川、そして東海にも地震がやってくる。今回一緒に活動をした東海出身の方は、次のように仰っていました。
「ずっと昔から東海大地震来ると言われ続けてきた。
しかし、東北や能登など他の場所で先に起きてしまっている。」
たまたま自分の住んでいる場所じゃなかっただけでいつかはやってくる。
だからこそ、他の地域で起きたことを他人事としてでなく、自分事として考えてもらわなければならない。(ある意味注意喚起のような形とも言っていた。)それが一人でも多くの尊い命を守るために必要だと私は強く考える。
私は宮城でも岩手、福島、ましては東北生まれ育ちでもない。
神奈川生まれ育ちの生粋の関東人だ。
震災(私の場合は東日本大震災が主となってしまうが)などに対する”考え方”や”視点”を”理解できる立場”だからこそ、その人たちに寄り添った語りを行うこと。そして、深い語り(現地の方など)の橋渡しが十分に出来るようにすることが私にとって出来る災害伝承の形の一つなのかもしれない。
来年度実施に向けて
実施後ミーティングでは、来年度に向けての今回の成果と課題が上げられた。来年度に向けての課題は以下があった。
・順路を設けた形にする(語りを来てくれた人に十分に行うため)
・規模次第では、予約制にする
・偏ったのではなく、幅広い年代に向けた災害伝承
・お客様向けアンケート(QRコードでの実施) etc…
(覚えている限りになってしまって申し訳ない、、、)
成果としては、語りとワークショップを融合したプログラム型は未災地の人に対してはとても効果的だったと思う。

これは、今後も続けていきたいかつ、自身の他の活動にも必要に応じて、応用していきたいと感じた。
来年度も実施予定らしいので、ぜひ今後とも協力していきたい。
そして、上記の課題の解決と、自分だけが語れることの内容(概ねでもいいから)をはっきり出来るよう、今後とも活動を続けていきたい。
この度は、このような機会をいただいたN.M様や関係各所に感謝申し上げます。
今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。
*同活動参加者より、許可・確認をいただき、投稿をしております*
関係各所リンク
一般社団法人三陸&東海防災フォーラム伝 様
静岡県立朝霧野外活動センター
(朝霧カーニバル)
減災絵本「リオン」
ぼうさいダック
にーえすもち(投稿者のHPです)
