
#3 ナレッジマネジメントって、そもそもなあに??
こんにちは!てけ王です!🐔🍗
まず私の話の前提に、「ナレッジマネジメントとは?」というところからお話ししますね。
2つの知識
まず知っておいていただきたいのが、暗黙知と形式知というふたつの言葉です。
大まかに、人の「知識」は、この2つに分けられます。
暗黙知とは、学習や経験で身に付けた知識、経験知、人の頭の中だけにある知識です。直感とかひらめきとか、信念・思い・体に染み付いたワザなどなど。そういったところもまとめて暗黙知と呼ばれます。
一方、形式知とは、知識が文書化されていて、他の人に伝承可能な状態になっているものを指します。ネットで検索できる情報は全て形式知ですね。言葉や動画も形式知といえます。
暗黙知と形式知は、氷山の図で例えられることがあります。この水面から上の見えている部分、これが形式知です。そして暗黙知がこの下の部分。モヤモヤしている知識、言葉になっていない知識。

ところで質問です。
人の知識における、暗黙知の割合って、何%位だと思いますか?
………
実は約90%が暗黙知と言われます。
きっと、思うより多かったのではないでしょうか?
よく、「ググったら何でも出てくるじゃん」「ナレッジマネジメントなんてGoogleがあれば解決じゃん」なんて言う人もいますが、ネットで出てくるのは全て形式知ですよね。
それに、もしも自社の暗黙知だと思っていたものが、ググって出てきたら怖いですよね(笑)
翻って、極端な話、会社に必要な知識が全て暗黙知だったらどうでしょうか?
過去に「2007年問題」が社会問題となったことがあります。
これは、団塊の世代と呼ばれた方々が、一斉に退職してしまうことによる問題です。
2007年問題に対して、企業はこぞって再雇用制度を導入しました。でもこれは、問題を先延ばしにしただけでした。のちに、2012年問題として改めて社会問題になりました。
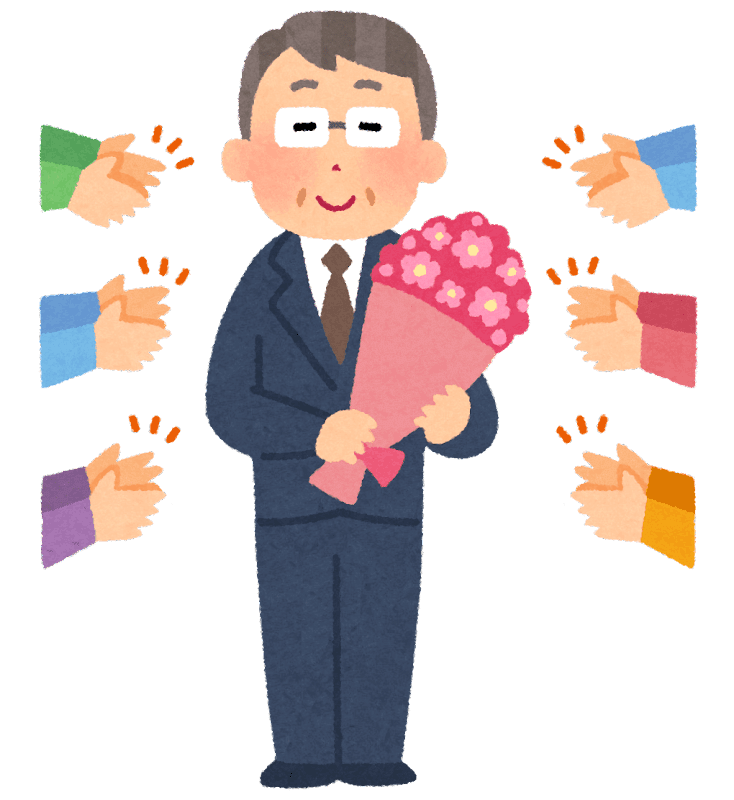
2007年問題で起こったこと
この問題は、単なる「労働力の減少」ではありません。
問題の本質は、組織に大切な「知識」が消滅してしまうことだったのです。
この典型例と言われているのが、当時メガバンクで相次いで起こったシステムトラブルです。
メガバンクで、そのベテランの人しか知り得ていなかった例外処理などがたくさんあり、それが伝承されなかったことで、結果的に大規模なシステムトラブルが起こってしまったという事例です。

またこの頃、「人為的ミスによる工場火災が増えている」というニュースがよくありました。
なんで?と思ってしまいますが、これは危険物を扱う施設で、ベテランが行っていた「特別な知恵やノウハウ」が伝承されていなかったために起こった事故のようです。
死活問題ですね。
例えば、「ボイラーを起動させるために、マニュアルではこのボタンを押して10分で温まると書いてあるけど、実は5分後に温度を下げないと熱くなりすぎてしまうんだ」といったような、ベテランしか知らない暗黙知があったのかもしれませんね。
このように、経営を揺るがすような大問題が起こるリスクがあるのです。マニュアルだけでは不十分なナレッジが、現場にはあります。
私も、以前工場にいましたので、現場の状況はよくわかります。
2007年問題・2012年問題は、ナレッジ伝承の重要性が露呈した問題であったと思います。その時の教訓が、今生きているのでしょうか?
当時はまだ、終身雇用が当たり前の日本でしたから、危機感は感じていなかったのかもしれませんね。
「なんか大変だけど、まあなんとかなるよね」と楽観視していたのでしょう。
でも昨今は、若手も含めた激しい人材流動化が起こっています。
個人知を組織知にする。このことは会社の持続的成長のためにはもはや早急に取り組むべき課題だと思っています。コトが起こってからではもう手遅れなのです。
ベテランが多い一方、30~40代のミドル層が少ない。そんな人員構成になっている会社は多いようです。
一時期、正社員の採用を抑えたしわ寄せが来ている、ということでしょうか。
人材流動化が激しいとどんなことが起こるか
ベテランが定年を迎えたとき、知識を伝承する相手は本来ミドル層だと思います。
しかし、ミドル層が少ない。必然的に、引き継ぐ相手は若手となります。
そのとき若手はどうするか。
きっと、ベテランがいなくなって、「ああ仕事が大変になった。辞めちゃおう」と考える方も多いのではないでしょうかね。
「やりたいことを仕事にする!」そうなりつつある時代ですからね。
ベテランも抜けて若手もいなくなったら会社の持続的成長は望めないですよね。
成長どころか、組織が崩壊します。
会社から人がいなくなってしまうというリスク。
そこは早急にリスクマネジメントしておくべき部分だと思います。
知識の伝承は、一朝一夕に対応できるものではありませんから、今すぐにでも、しっかりと知識を蓄積・共有する仕組みを作り始めることが必要です。
しかしながら、ナレッジマネジメントはシステムさえ導入すればすぐに解決できるものでもありません。
..…と、今回はここまでです!
「スキ」をいただけますと励みになります!!
自己紹介です🐔🍗
フォローしてくださると嬉しいです😊
