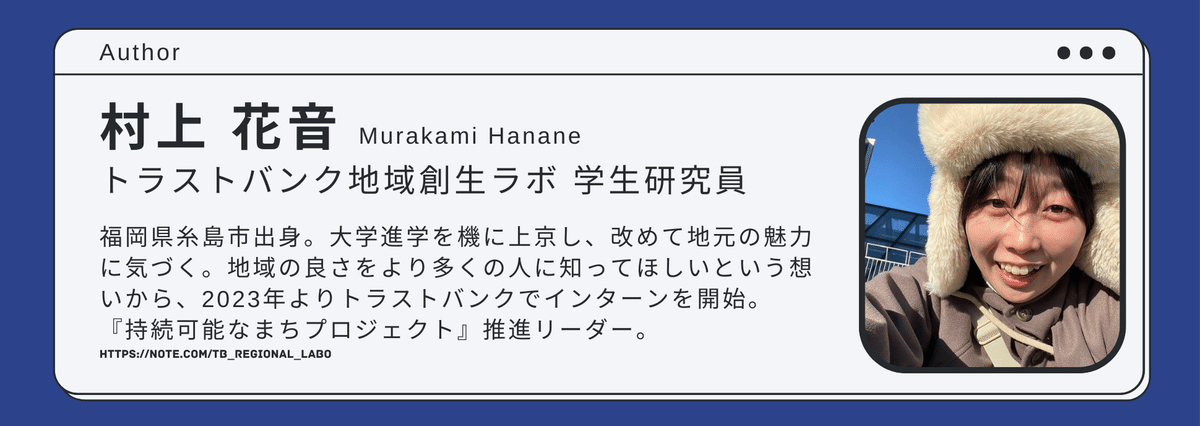持続可能なまちを実現するために~人口編~/『持続可能なまちプロジェクト』進捗レポート
トラストバンク地域創生ラボ 学生研究員の村上です。
学生研究員が中心となり、若者の視点を生かして新たなまちづくりについて考える『持続可能なまちプロジェクト』。
昨年10月に、中間報告を行ってから、約3か月が経ちました。
本記事では、その後の進捗とともに、今後どのようなことを行っていきたいのかについてお伝えします。
これまでのおさらい:人口減少と持続可能なまちづくり
①従来の課題認識
日本の持続可能なまちづくりにおいて、これまで「人口減少」や「人口流出」の問題が中心的な課題として議論されてきました。人口がまちの持続可能性を左右する重要な要素として捉えられ、“人口増加の必要性”が強調されてきたのです。
② なぜ持続可能=人口?
しかし、そもそも持続可能なまちづくりにおいて、なぜ人口が重要視されてきたのでしょうか。
人口がまちに与える具体的な影響について、国土交通省と、人口縮小社会における問題解決のための検討委員会が発表した内容を、以下にまとめました。
【社会における「人口減少」の問題点】

●国内経済の縮小
労働力人口の減少と高齢化が進み、消費市場が縮小します。この経済の縮小は特に地域経済において顕著に現れ、成長の停滞を招く可能性があります。
●人口オーナスの増大
少子化が進む中で、現役世代の負担が増大します。これにより社会保障の不均衡が生じ、生活水準が低下するリスクがあります。発展途上国が人口ボーナス期を迎える中、日本の国際競争力が低下する可能性もあります。
●食糧確保と土地利用への影響
農業従事者の減少や農地面積の縮小が進み、これが土地利用や農業の持続性に影響を与えています。また、過疎化が進行し、限界集落の増加により地域経済の衰退が懸念されています。
●経済社会の破綻
高齢化が進む中で、若年層の生活水準が悪化し、少子化が進行するリスクがあります。社会資源の配分が偏ることで、社会全体の不安定化が進む可能性もあります。
「提言『人口縮小社会』という未来—持続可能な幸福社会をつくる−」(2頁)
これらの影響は、人口縮小が社会のあらゆる規模での縮小と負担増加を引き起こすということを示しています。
③私たちの考える新しいアプローチ方法
上記を調べたうえで、私たちは“人口が増加すればまちが持続可能になる”、というアプローチに疑問を抱きました。それは人口の増減が、まちの持続可能性に直結する、という理由にはならないと感じたからです。
もちろん人口減少の影響は確かに深刻ですが、その対応策がしっかりと講じられれば、持続可能な社会を作り出すことも可能なのではないでしょうか?また、人口増加を目指す政策は、地域間での「人口の奪い合い」を引き起こしかねず、結果として持続可能なまちづくりの実現を困難にする可能性も考えられます。
そこで発想を転換し、「人口減少は避けられない現実」として受け止めた上で、人口が減少する中でも「心豊かに暮らせるまち」を創造する方法を模索することにしました。具体的には、まず「若者の意見を反映させたまちづくり」のビジョンとして「期待が生まれ、ふくらみ、つどい、かなうまち」を掲げました。このビジョンのもと、人口動態と住民の幸福度の両面から持続可能なまちの本質を探り、その実現に必要な考え方や仕組みについて深く検討を進めていくことにしました。
若者の視点から見えた現状と課題
まず我々は、人口にとらわれずに地域を持続可能にするには、住む、訪れるに関係なく、その地域に価値を抱き、関わりたいと思ってくれる人を増やすことが大切だと感じ、「人口減少にとらわれない地域との関わり方」をテーマにした座談会を開催しました。
この座談会によって、「若者の多くが地域との交流やイベント参加に興味を持っているものの、具体的に何を始めたらいいかわかっていない」という課題が浮かび上がりました。
また、トラストバンク地域創生ラボの『若者の地方に対する意識調査 2024』でも、「約4割の若者が地域活動に興味を持ちながらも行動に移せていない」という結果も出ています。これらはどちらも「行動の第一歩目」が明確でないことが一因かもしれません。
この発見を踏まえ、私たちは「知らない地域を知り、好きになってもらう」=「0から1を作る」仕組みではなく、「もともと馴染みのある地域(地元)に戻りたい」と思えるような地元への回帰を促すUターン施策に注力すべきだと考えました。
具体的には、進学や就職で地元を離れた(または離れる可能性のある)若者たちが、地元地域への愛着を育み、将来的に再び住みたいと思えるような施策の提案を目指すようになりました。
Uターンの現状と課題
地方出身者が一度東京圏で勤務した後、地方へ戻って働く「Uターン」には、様々な要因と課題が存在するようです。Uターン者の現状と阻む壁について、内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局の調査結果を基にまとめてみました。
①課題

●働き口の不足
地方には希望する職種や業種が少なく、賃金面でも都市部と比較して大きなギャップがあります。そのため、仕事の選択肢が地方への帰還を妨げる要因となっています。
●生活利便性の低さ
医療や教育、文化的活動など、地方での生活基盤が都市部と比べて充実していないと感じる若者が多い状況です。この差が移住後の生活への不安を生み出しています。
●イメージ不足
地元に戻ることで得られる生活のイメージが具体的でないため、Uターンへの決断が先延ばしになりがちです。地方での生活の魅力を感じられる情報発信や、試しに住む機会が不足しています。
●コミュニティとの距離感
地元に戻っても、すでに形成されたコミュニティに馴染むのが難しいと感じる若者が多く、これが心理的な壁となっています。
「東京圏、地方での暮らしや移住及び地方への関心に関する意識調査」
②課題の背景

これらの課題は、地方と都市部が持つ特性や環境の違いに由来しています。
都市部の多様性や利便性は多くの若者にとって魅力的な選択肢となりますが、それは地方が持つ価値と相反するものではありません。むしろ、地方が持つ豊かな自然環境やゆとりあるライフスタイルが若者にとってどのような価値を持つのかを再認識し、地方ならではの強みを活かした仕組みを作ることが重要です。
若者自身が地元に戻ることの意義や魅力を再発見できれば、Uターンの実現はより現実的なものとなるのではないでしょうか。
課題解決(Uターン促進)に向けた提案
地方へのUターンを促進するには、「都市部で得た経験や学びを地方に還元する」という視点が重要であると考えています。これから私たちは、東京圏を経験や学びが豊富な「インプットの場」の代表地域として、そして、地方圏を、培った経験や学びを活かす「アウトプットの場」として捉え、次のような仕組みづくりを目指します。

●愛着を持続させる仕組み
地元に対する愛着やつながりを保ち続ける仕掛けが必要です。離れていても地元と関わりを持てる環境が、将来的なUターンのきっかけを作ります。
●離れることを否定しない考え方
若者が一度都市に出ることを前提に、その経験を地域で活かせる循環を促します。「出る=悪い」ではなく、「戻る価値」を感じてもらう取り組みが重要です。
実際に進学・就職をきっかけに東京へ移住する若者は少なくありません。そこを否定するのではなく、ゆくゆくはしっかり経済を回す一人として地元に戻ってきてもらうことに意識を置いた方が良いと考えています。
今後の展望
今後、私たちが目指すのは、若者の地元への愛着を育み、その想いがUターンという具体的な行動に結びつく仕組みづくりです。これを実現するためには、地元を離れた若者たちに「戻りたい」と感じさせる魅力的な要因を創出することが不可欠です。
施策のターゲットは、進学や就職を機に地元を離れた若者たちです。彼らが持つ地元への「愛着」をさらに深め、それを継続的に維持できる具体的な仕組みが必要です。私たちは、若者が都市部で経験を積むことをポジティブに捉え、その経験や知見を地域の発展に活かせる「循環型社会」の構築を目指します。この考え方こそが、自然なUターンを促す重要な要素であり、地域活性化への突破口になると確信しています。
今後は、どのようにして愛着を強化し、持続させ、最終的にUターンにつなげるのか、具体的な施策を検討していきます。引き続きお付き合いください!