
【読書感想】内向性の力:内向型のあなたへ贈る生き方のヒント
可能な限り生成AIに関連した記事を書くようにしていましたが、変則的にこういった書評ブログ的なこともやっていこうと思います。
また、記事についてはChatGPTやほか生成AIと絡めつつ展開するように心がけます。
今回ご紹介させていただく本はジル・チャン著の「「静かな人」の戦略書」という本になります。
この本は2022年6月に初版が出され、自分が購入したものは同年11月の7刷であることからも、かなり売れた本であることが見て取れます。
実際、13万部は売り上げたそうで今の時代なかなか凄いことだと思います。
さて、内容については著書名からも分かる通り、内向的な人に向けたものになります。
特に著者が経験してきたことをベースに展開されており、実際に起こりうる場面も多く掲載されていることから、イメージしやすい構成になっています。
主に「仕事」「人間関係」「対人での活かし方」「潜在能力」が主題となって展開されています。
以下いくつかピックアップして、また自分の経験もあわせて本書をご紹介させていただきます。
新しい環境が苦手
新しい環境が苦手というのは多くの内向的な人が共感できることだと思います。人生様々な局面であたらしい人間関係を築かなければならない場面があります。クラス替えや、進学、就職、異動など多岐にわたります。
「新たな仲間を作るのが難しい」というセクションについては、内向的な人は外見を覚えるのが苦手と書かれていますが、全くその通りです。
名前と人の顔が覚えられない。自分は、小、中、高とクラス全員の名前を覚えたことは一度も無いかも知れません。
社会に出てからもせいぜい周囲数人しか覚えていない気がします。職にもよりますし、実際そんなものかもしれませんが。
そういった事への対策として3つのことを本書ではあげています。
馴染むために必要な3つのこととして、「仲間を見つける」「仕事の能力を誇示」「明確な結果を出す」というのがあげられています。
具体的には1対1の場面で接点を作る。ちょっとしたことでも誰かに聞いてみれば、それだけで接点は作れます。
また、内向的である強みを活かして、徹底的に考えて先手を打つことも有用であると書かれています。
このようなことをコツコツとやって信頼を積み重ねることの重要性が説かれています。
自分は本書を読む前から、意図的にちょっとしたことを聞いては「ありがとうございます」と返して接点を作るようにしていたので、ある一定効果はあると実感できています。
しかしこれは相手にもよります。性格やシチュエーションは千差万別ですので、それこそ内向的な人が持っている洞察力を活かして、取り組むことが求められるかもしれません。
また、本書とは関係無いですが、相手の性格を類推して効果的に接触する方法もこの記事の後半に軽く書かせて頂きます。
まとめ
自分自身、内向的な人間だと考えています。人前で目立つことが苦手で、今もそうです。そのため、本書の内容は非常に共感できるものでした。
特に、日頃から内向的な性格で悩んでいる人には本書が非常に役立つと思います。
本書では、内向性の持つ強みがいくつか紹介されています。それは自分の経験からも納得できるものでした。
例えば、「内向型の人は長期的に深い関係を築くことが得意」とありますが、相手の理解を得られたときの関係の持続性は、私も実感しています。
また、「文章を書くのが得意」とも述べられています。面白いか、面白くないかは置いておくとして、確かに文章を書くのは苦では無いので、それはおそらく正しいでしょう。
また、本書は静かな人、内向的な人に向いている本ですが、外交的だと思っている人にも有用だと思います。
職場や知人との人間関係において、内向的な人を理解する一助となるでしょう。
最後に強いて批判的なことを言えば、本書は学術的な本では無いため、エビデンスの提示が一部不足しているかと思います。
最も、何にでもソースを併記すれば良いわけではなく、読みやすさや著者の経験がベースとなっているため仕方が無いところではあります。
例えば「内向的な人は他人の感情に影響されやすい」や、「内向型の怒りの表現は露骨では無く、目立たないだけ」等は、確かに頷けることではありますが、誰しもにあてはまるものなのでしょうか。
その後の論理展開としてやむを得ない書き方ではありますし、そこまでやり玉にあげるようなことではないですが、あくまで多くは、一般的には、といった副詞が先頭につくことを意識した方が良いかも知れません。
ただ、無理矢理ひねり出した問題点がそれくらいなので、普通に読むにはかなり有益だと思います。
余談:性格分類と体癖論
自分自身を理解する上で性格診断を行ってみることも有益です。
本書でも簡単に内向的か、外交的かを判断するテストがありますし、MBTI(マイヤーズ・ブリッグス・タイプ・インジケーター)についても触れられていますが、改めて以下にまとめます。
性格診断は、個人の性格特性を理解し、その特性が行動や対人関係にどのように影響を与えるかを評価するためのさまざまな方法があります。以下にいくつかの一般的な性格診断手法を示します:
MMPI(ミネソタ多面体パーソナリティーインベントリ): MMPIは、精神疾患の診断と評価に広く使用される心理測定ツールで、特定のパーソナリティ特性や精神疾患の有無を測定します。
MBTI(マイヤーズ・ブリッグス・タイプ・インジケーター): MBTIは16種類の性格タイプに分けて個人の性格を評価します。エネルギーの源、情報の収集方法、意思決定、生活スタイルの4つのカテゴリに基づいて分類します。
ビッグファイブ(Big Five): このモデルでは、性格は開放性、誠実性、外向性、友好性、神経症傾向の5つの主要な特性によって評価されます。
DISC: このモデルは、Dominance(支配性)、Influence(影響力)、Steadiness(安定性)、Conscientiousness(誠実性)の4つの特性に基づいています。
エニアグラム: 9つの異なる性格タイプに基づいて個人を評価するシステムで、それぞれのタイプは特定の欲求と恐怖によって動機付けられています。
これらの手法は、自己理解、自己啓発、チームビルディング、リーダーシップ開発、キャリア計画など、さまざまな目的で使用されます。それぞれの手法には独自の強みと制限があるため、特定の目的や状況に最適なものを選択することが重要です。
ただし、これらの性格診断が科学的に正確な「真実」を必ずしも提供するわけではないことに注意が必要です。それらは個々の性格特性をよりよく理解し、人間関係や職業生活におけるそれらの影響を考察するためのツールと考えるべきです。
主にこういったものは、自分自身を理解する手助けとなるツールですが、実際のところ相手を理解しなければならないことが多いのでは無いでしょうか。
そうしたとき「体癖論」と呼ばれるツールも役に立ちます。
「体癖論」については主旨と逸れるのでどこかで自分の実体験とあわせて記事にしようと考えていますが、端的に言ってその人の骨格、顔つき、体系から性格を類推するものとなります。
全部で10種(12種)あって、これを軽くでも理解しておけば、初対面でどう対応すればよいか、どう付き合っていけば良いかの道しるべにもなります。
例えば、この人は典型的な3種だなと思えば、その人が昼飯を食べ終わってちょっとした後にネガティブな報告に行くであったり、食への感謝が尋常ではないので、お菓子を持って行くなど対策が取りやすくなります。
あと最近面白かったのは、典型的な7種だなと思っていた人と初めて会話をする機会があり、その第一声に「大学は何処を出たの?」だったので本当に面白いなと思いました。(7種8種は世界のありとあらゆるものを勝負ごとと考えがち。7種は勝つこと、8種は負けないことにこだわる。)
本題に戻りますが、他人を理解することは、自己理解にもつながりますし、それこそ内向的な人が得意とすることではないでしょうか。
内向的な人が難しいと感じる状況は、特に人間関係においてでしょう。そんなとき、「体癖論」を軽く触れると、あるいは今回の記事では取り上げていませんが、「アドラー心理学」について学ぶことも、その問題解決の一助になるかもしれません。
もし興味がありましたら、ぜひ書籍等で調べてみてください。
おまけ
ChatGPTとのやりとり
記事作成にあたって以下の通りChatGPTに添削等をお願いしています。
やりとり全量です。
サムネイルの素材
以下はBing Chat(に搭載のAI、生成に関してはDALL-E)で作成したものです。
著作権はフリーなのでご自由にどうぞ。


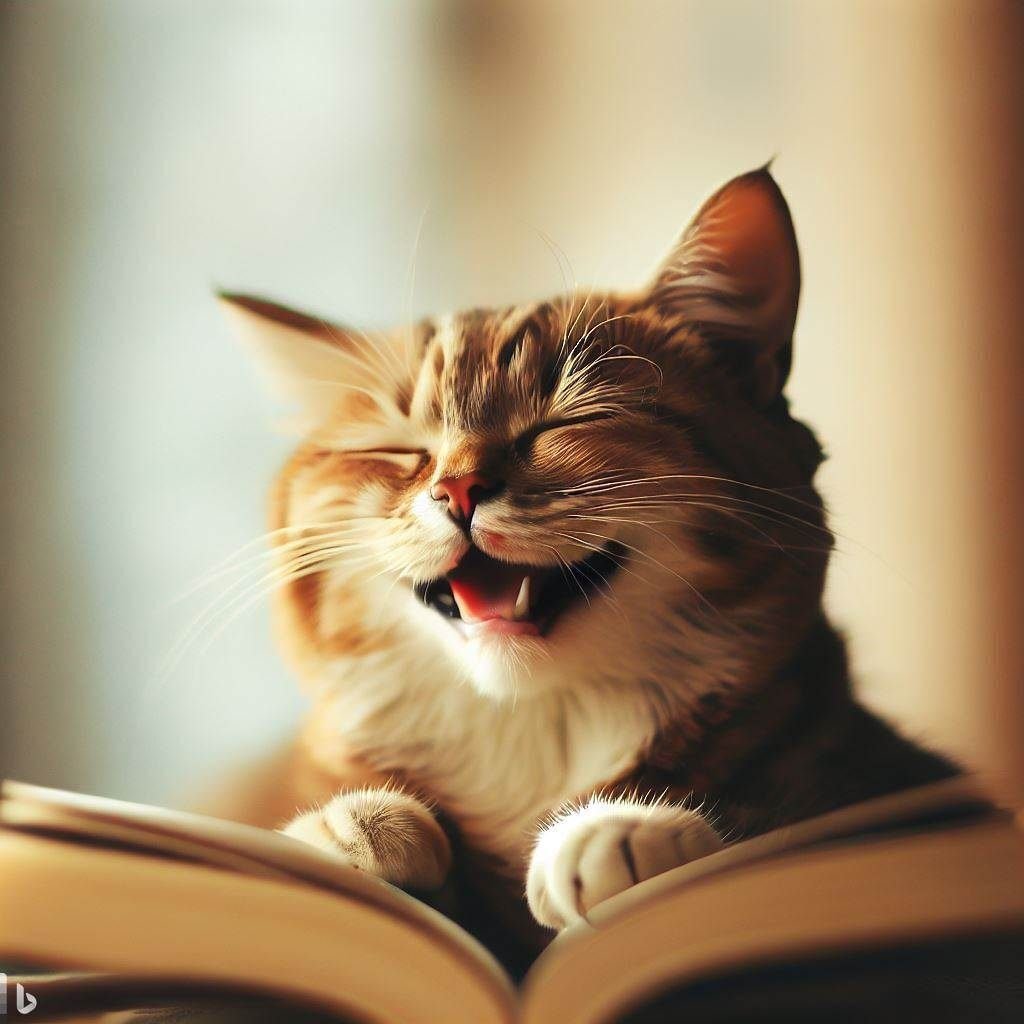
Amazonリンク
アフィリンクです。
