
Weekly自分_221024-221030_ゆらりゆらゆらへらりへらへら
はじめに
このnoteの無料部分では、僕が日々なんとなくやっている『糸井重里さんの「今日のダーリン」を読んだ感想文』が見れます。
また、有料部分は今週気になった情報のリンク集になっています。
特に気になったものは所見みたいなものも書いてあるので気になる人はぜひ購読してください。
今週の雑感
全然更新が間に合っていません!
というのも、僕は今、香川県と愛媛県の間にある三豊市という場所にいるからです。
友人の一世一代をお手伝いするために来ているのですが、僕はなんとなくアイドルタイムに堤防のへりに寝っ転がって流れて形が変わっていく雲をぼんやり眺めたりしています。
ここでの体験や学び、またシェアしたいなぁと思ったりしていますのでお楽しみに!
今週の「今日のダーリン」を読んで
10月24日
『人がひとつところにたくさん集まってるからといって、みんなの気持ちがひとつだなんて思いすぎないほうがいい』
『人は、じぶんがなにかを真剣にやろうとすると、どうしても、みんなにも真剣になってほしいと願う』
『みんながばらばらはまずは前提で、 その上で、なにが、どこがひとつになれるのか?なにでひとつになったら、うれしいのか?とても少ないことで、手をつなぐくらいがちょうどいい。』
『「ばらばらだけど、それぞれが親切」なんてのは、最高』
という言葉を拾いました。
今日の「みんなの気持ちがひとつだなんて思いすぎないほうがいい」という言葉が最近の僕の中の気づきと一緒でとても興味深かったです。
ついつい自分の声がでかいもの故に全体の方向性を決めてしまったりグルーヴ感のようなものを作ってしまって「えいや!」としてしまうのですが、いざやってみて俯瞰して見てみると「あれ?ちょっとみんなしっくり来てない気がするぞ?」と思うことが最近あったのでした。
みんなそれぞれたぶん思い思いの形でその場に存在したり参加したりしているので、良くも悪くも「全体としての意思」みたいなものは存在していないのかもしれないなぁと思います。
そういう状況の場で本当に必要とされていることは「ほんの少しの団結点」みたいなものなのかもしれないなぁと思ったりしています。
この「ほんの少しの団結点」をどうやって作るか?みたいなところのノウハウをいろいろ考えたり直観でやってみたりしてトライ&エラーを繰り返しながら掴んでいけたらいいなぁと思いました。
まずやってみたので、次はちゃんと振り返ってみよう
10月25日
『もしかしたら時代背景のようなもの』
『進学のために生まれた土地を離れた人たちって、10年ちょっとくらいしか故郷にいなかったということか』
『若いころのじぶんと、一度じっくり話してみたい』
僕は生まれ育った街から成人するまで出ることはありませんでした。
僕の地元というか、小学校区はわりと同じように生まれ育った街から出ていく人の方が少ないように感じます。
僕の地元は良くも悪くも何もない街で、僕はよく「何でもあるけどなんにもない街」という風に形容しています。
社会人になった時から僕は表現の世界と市場を繋ぐような仕事をしているのですが、もしかすると僕が生まれ育った街になかったものを心のどこかで求めていたり、憧れがあったからなのかもしれません。
コンプレックスでも別に欠如したものを埋めようとするわけでもなく、ほんの少しばかりの背伸び、みたいなものな気がしています。
10月26日
『糸井重里さんは、昔を懐かしむみたいなことが好きじゃない』
『「死期が近いんじゃないか、おい」とも思えてくる』
『どっちつかずの立ち位置、黄昏』
『どうしたって、やがては自然と夜になる』
今回の「今日のダーリン」は「旅の効力」のような話をしているニュアンスを受けました。
僕も昨日から旅をしていて、ひさしぶりにひたすら動きに身を任せているのですが本当に楽しいです。
インターネットや仕事からある程度強制的に距離を取るような生活になっていて、おのずと目の前にある情報に集中するということが当たり前になってきているように感じます。
ついつい僕たちは「僕たち」という言葉を拡大解釈してしまいがちで、「人間であれば僕たちである」みたいな感じで世の中の色々なことを捉えてしまいがちな気がしています。
いったいどこからどこまでが「僕たち」なんでしょうね~
10月27日
『「寂れる(さびれる)」と「古くなる」は違う』
『どうせ、もう古くなっているからと思って、それについて考えることもしなくなると、寂れる。』
『衰えているなりに、力を失っているなりに、洗ったり磨いたりを続けていると、輝く。』
『手を入れるとか、手をかける、目に入れる、目をかける。これって、お金のあるなし、時間のあるなしとはほとんど関係ないんじゃないだろうか』
『人が、じぶんに手をかけるって、どういうことだろう。』
「それなり」という事なのだろうなぁと思いました。
そして、よくよく考えてみると「それなり」という言葉の語源がわからないなぁと思ったので調べてみました。
すると、「その状態のまま」という意味と「それ相応」という意味が出てきました。
僕たちが普段よく使う用法としては後者の意味を使いがちだなと思うのですが、「ありのまま」のような意味もあったのだなと思うとなかなか興味深いなと思います。
そう考えてみると寂れるではなく古くなることで出る味みたいなものが生まれる条件みたいなものがなんとなく見えてきそうな感覚があります。
寂れてしまうのは文字通り寂しいですが、古くなっても手が入れられてメンテナンスされることで出る味ってたしかにあるなぁと思います。
「人がじぶんに手をかける」とはどういうことか?
10月28日
『ビジョンが現実に近づくほど、気持ちも現実的になり、細かいことが気になったり心配になったりする』
『しっかりするな!』
『どうやら、今日までに集まった本が2万5千冊ほど』
『集まった本を地域通貨のようなものでやりとりするのは世知辛い』
すぐ色々な要素を絡めようとしてしまいがちな性格をしています。
「せっかくなら」とあれもこれもと狙ってしまうのです。
そんな性格なので、たまに自分だけがものすごく得をしてしまうことがあって、少し心苦しくなってしまうときもありました。
この感覚をもしかすると「世知辛い」と呼ぶのかもしれません。
最近は少しコツを掴んできて、自分であれこれつまみ食いできるように段取りをせずに、同行者であったり、他の人のアイディアをまずは求めてみてその中から決めてみるようにしています。
自分だけで考えているとついつい自分の世界の中での最適解を選ぼうとしてしまいがちなので、もっとランダムな要素というか、他の世界と接続されることでの化学変化みたいなものを楽しんでもいいのかな?と思っています。
とある場所では「誤配」と呼ばれてたりなかったり
10月29日
『(前橋BOOKFESが気になり)「頼む!」みたいな気持ちでしばらく生きてきた』
『本はある。ともだちは来てくれる。申し分ないよね。』
最近、「メインとサブ」みたいなことを意識するようにしています。
理由としては、昨日の分に書いた「あれもこれも癖」を弱めたいなということと、きちんと何がメインで何がサブかを決めた方がメリハリが出るなと思ったからです。
実際、そういう風にメインとサブを分けていろいろと行動することで、端的に余白のようなものが生まれたように感じますし、万が一取り逃してしまったときの「あちゃ~感」みたいなものが軽くなるように感じます。
みんなが主役でみんながかっこいいのももちろん面白いと思うのですが、本当にみんながみんな主役を演じれなかった場合に主役の中での差生まれたりしてしまうので、サブというか下支えする役割に意味が出たりするのかなぁと思います。
いろいろなことにメインとサブがあることにはちゃんと意味があるものなんですね。
10月30日
『「前橋BOOK FES」の第一日ははじまってみれば大盛況だった。』
『「このお祭りには、お客さまはいません」という言葉の真意は、「消費者」でなく「参加者」なので、他の「参加者」を幸福にすることが仕事であり、じぶんが満足することを願ってこの場にいる、という事だった』
『やりたい人がたくさん出てくるのは、絶対にいいこと』
前橋BOOK FESに行ってみたい人生であった。
同じ時間、僕は香川県の三豊市というところにいて、友人のスパイス料理人がイベントに呼ばれ、これまでの集大成のような料理を振る舞うことをサポートしていたからです。
この時ほど身体が二つあったらよかったと思ったときはなかったね
はじめてみるまではこわいけど、いざはじめてみれば思いのほか反応を頂けることは意外にあるように思っています。
そして、そういうことほど自分よりも周りを勇気づけることに繋がったりするなぁと思います。
ファーストペンギンという言葉を使うのは安易な気がしますが、誰の足跡もない場所に初めて足跡を付けるのには勇気と思いっきりが必要だと思います。
大人になればなるほど前提知識が増えるのでなおさら。
よ~かったぁ~
以下有料部分
さて、ここから下は購入者限定になります。
内容は今週の気になるトピックに関してだったり、ネットサーフィンしてて有用だなと思ったリンク集になります。
気になる人は100円で僕が飽きて更新を止めるまでは新しいものも見放題なので買ってみてね!
ここから先は
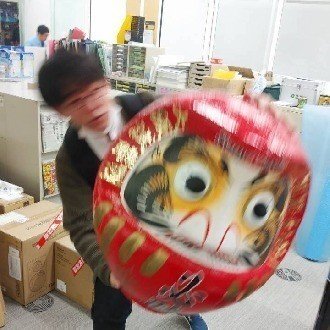
更新終了-有益なことは書かない日記
備忘録代わりに日記を書いています。
この記事が参加している募集
大阪で音楽関係の仕事をしています。 アニメや漫画、TVゲームからボードゲームまで広く遊びが好きです。
